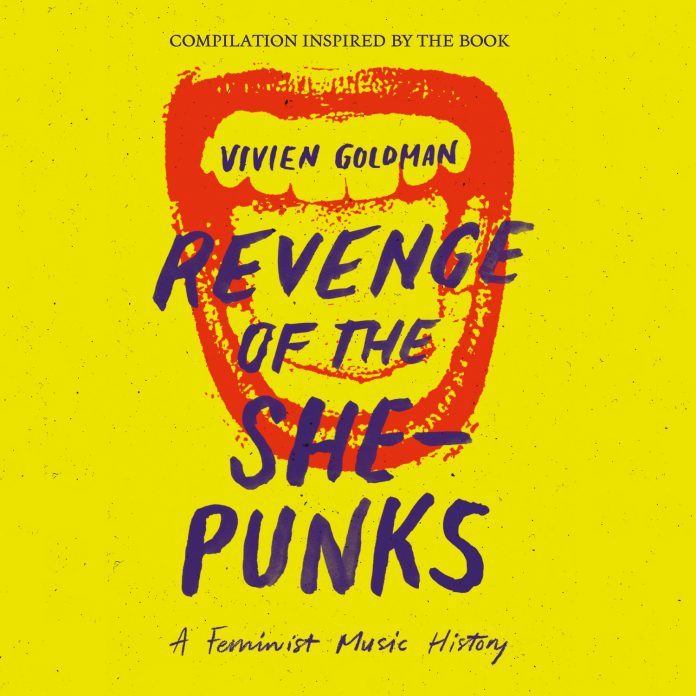ドラムとベースのコレオソ兄弟を中心に、ジョー・アーモン・ジョーンズも名を連ねるロンドンの五人組、エズラ・コレクティヴの新作『Where I'm Meant To Be』が11月4日にリリースされる。ファースト『You Can't Steal My Joy』から3年ぶりのアルバムだ。サンパ・ザ・グレイト、コージー・ラディカルといったゲストも参加。楽しみに待っていよう。
ジャズと様々なジャンルをシームレスに融合させたサウンドでシーンをリードするUKのクインテット、エズラ・コレクティヴ。名門パルチザン・レコードより、待望のセカンド・アルバム『ホェア・アイム・メント・トゥ・ビー』をリリース。
●ゲスト:サンパ・ザ・グレイト、コージー・ラディカル、エミリー・サンデー、ネイオ
アルバムより、「Life Goes On (Feat. Sampa the Great)」のビデオを公開。
★Ezra Collective - Life Goes On (Feat. Sampa the Great) (Official Video)
https://youtu.be/9sS-QEyLycs

2022.11.4 ON SALE[世界同時発売]
アーティスト:EZRA COLLECTIVE(エズラ・コレクティヴ)
タイトル:WHERE I'M MEANT TO BE(ホェア・アイム・メント・トゥ・ビー)
品番:PTKF3020-2J[CD/国内流通仕様]
定価:未定
その他:世界同時発売、解説付
発売元:ビッグ・ナッシング/ウルトラ・ヴァイヴ
収録曲目:
01. Life Goes On (feat. Sampa the Great)
02. Victory Dance
03. No Confusion (feat. Kojey Radical)
04. Welcome To My World
05. Togetherness
06. Ego Killah
07. Smile
08. Live Strong
09. Siesta (feat. Emeli Sandé)
10. Words by Steve
11. Belonging
12. Never The Same Again
13. Words by TJ
14. Love In Outer Space (feat. Nao)
★Ezra Collective - Victory Dance (Official Video)
https://youtu.be/NiZPsN2pbTM
●Ezra Collectiveは11月4日にPartisan Recordsからニュー・アルバム『Where I'm Meant To Be』をリリースする。『Where I'm Meant To Be』は、Ezra Collectiveのハイブリッド・サウンドと洗練された集団としての個性を昇華させた作品だ。Thelonious Monkの『Underground』をモチーフにしたアルバム・ジャケットをはじめ、楽曲はクールな自信と明るいエネルギーに満ちている。アンサンブル・パート間でのコール・アンド・レスポンスによる会話に満ちたこのアルバムは、長年ステージ上で共にインプロヴィゼーションを行ってきた成果である。Sampa The Great、Kojey Radical、Emile Sande、Nao等も参加したこのアルバムは、汗に満ちたダンス・フロアと夏のディナーのサウンドトラックを等しく明るくする。バンドの2019年デビュー・アルバム『You Can't Steal My Joy』は、ジャズの繊細さとクラシックなサウンドをアフロビート、ヒップホップ、ダンスホールのリズムとシームレスに融合させたサウンドで、イギリスでのジャズ復活の中、彼らを最もエキサイティングなアクトの1つとして確立させた。結果、Rolling Stone、Pigeons & Plane、The New York Times(London)は注目すべき新進バンドのひとつとして、彼らを取り上げた。
●Ezra CollectiveはUKのジャズ・シーンをリードするバンドだ。メンバーはドラムのFemi Koleoso、ベースのTJ Koleoso、キーボードのJoe Armon-Jones、サックスのJames Mollison、トランペットのIfe Ogunjobiの5人。イギリスの音楽教育機関、トゥモローズ・ウォリアーズで出会ったことにより、活動がスタートした。2枚のEPをリリース後、2019年にデビュー・アルバム『You Can't Steal My Joy』をリリース。高い評価を博した。バンドは事実上のスーパーグループで、Ezra Collectiveとしての活動以外でも多忙を極める。ドラマーでバンド・リーダーのFemi Koleosoは今やGorillazのラインナップに欠かせない存在だ。ベースのTJ KoleosoはYazmin Laceyと共演。キーボードのJoe Armon-JonesはMick Jenkinのニュー・アルバムに参加。Nubya Garciaとツアーをおこない、FatimaとのコラボレーションEPをリリースする予定である。サックスのJames MollisonはNala Sinephroのバンドでプレイし、トランペットのIfe OgunjobiはBurna Boyと共に、ソールドアウトのスタジアムでプレイしている。
■More info: https://bignothing.net/ezracollective.html