ジュリアナ・バーウィックは、登場から10年が経とうといういまだにタグ付けの困難なアーティストだ(これまでのレヴュー)。ときどき「歌姫」としてエンヤなどに比較されているのを見かけるが、それはまったくちがう。バーウィックは歌曲を歌うのではないのだから。発声したものをペダルでループさせるだけ。“歌わ”なくていい、演奏しなくていい、つくらなくていい、息をするだけ──そのミニマルなスタイルは、だからこそ消費されてしまうことなく、また、いかなるトレンドにもわずらわされない。
彼女の音楽が、クラシックまがいでもヒーリング・ミュージックの類でもなく、〈デッド・オーシャンズ〉や〈アスマティック・キティ〉のようなエクスペリメンタルなインディ・レーベルからリリースされ、ダーティ・プロジェクターズやスフィアン・スティーヴンスなどに並んでカタログ化されているのは、ひとえにわれわれがそのスタイルに前を向いた自由とインディ精神を感じていたからだ。
バーウィックは、女神の役割を負うことからも負わされることからも自由であり、しかもそれを拳をかざしたり男勝りのスタイルを身につけたりする必要もなく可能にしている。また、高度な音楽教育を受けているとはいえ、彼女の録音スタイルのDIYさ、ライヴ活動の地道さ、飾らなさはわれわれがイメージする通りのUSインディであり、ジュリア・ホルターらと並んで、2010年以降のシーンに爽やかな喜びを与えつづけてきた。バーウィックの自由……それはあの眩しい残響として筆者の心に波打ちつづけている。
さて、今作は「ウィル」と名づけられている。『サングイン』『ザ・マジック・プレイス』『ネーペンテース』といった過去作品に対して、バーウィックにしては強い意味やニュアンスが出たタイトルだ。音楽性が大きく変わったわけではないため、それはなおさら、彼女の中に兆す変化を想像させる。
音の特徴から整理するなら、本作はこれまででもっとも楽器が多用され、「伴奏」のともなったものだと言うことができるだろう。これまでと変わらず、クセのないハイトーンの一節がループされる冒頭の“セント・アポロニア”は、突如加わるチェロとピアノに印象的に縁取られる。つづく“ネビュラ”は頭からシンセサイザーのアルペジオに先導されてはじまり、それは曲中途切れることなくつづく。次の“ビーチド(Beached)”はピアノ伴奏が寄り添う。これらは単に彼女のライヴのスタイルが反映されたものでもあるだろうが、声以外の周波が加わって心地よさが増している。エッジイなイメージは後退し、ほっとするような柔らかさが感じられる。
そんななかではっとするのは“Same”だ。リヴァービーにふくらまされたストリングスやトランペットが曲を先導する……そのようにいくつもの音色を持つのもめずらしいが、この曲にはカナダ出身のアーティスト、トーマス・アーセノールトの歌もフィーチャーされていて、彼の声が入ってきたときに彼女の世界に他の人間の主観と時間が混線してきたような、わずかな違和感が生まれ、驚かされる。深いエコーとループが交差しこだましあう彼女の音楽は、構成要素がほとんど自身の声ということもあり、言葉やメッセージがない場合でも圧倒的に主観的な世界を立ち上げる。彼女の音楽を聴くというのは、彼女の感情の球体、あるいは意識の球体、それに触れているという感覚だ。ここに他者が入り込んでくるというのは、その球体が球ではなくなるということ、破綻のない世界に異物が混じり、これまでに生まれなかったはずの可能性や偶然性が──まるで生命の誕生のように──生じてくるということを予感させる。他人との制作という点では、ヘラド・ネグロとのオンブレ名義での活動があるが、そちらはまさにコラボの体で、互いの協力によって一枚のアルバムを生むべく美しい予定調和が図られていた。しかし、今回そういうものとまったく異なる原理のもとに他者の声、他者の「will」が聴こえてくる。そのあたりに、バーウィックの次を見てしまう。

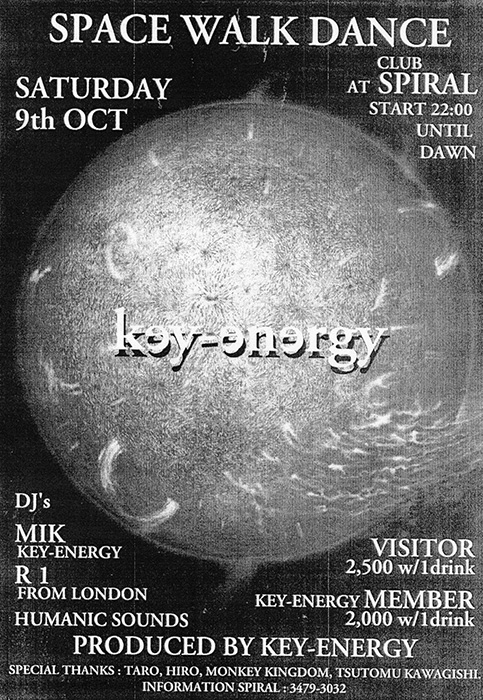
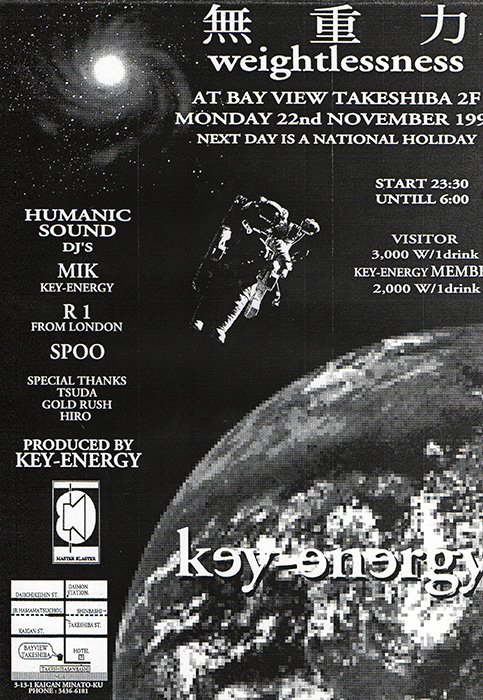











 Artist: Prettybwoy
Artist: Prettybwoy














