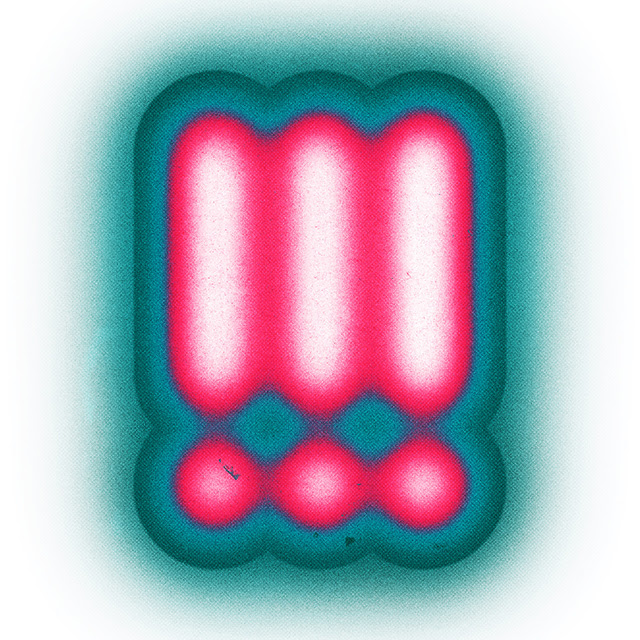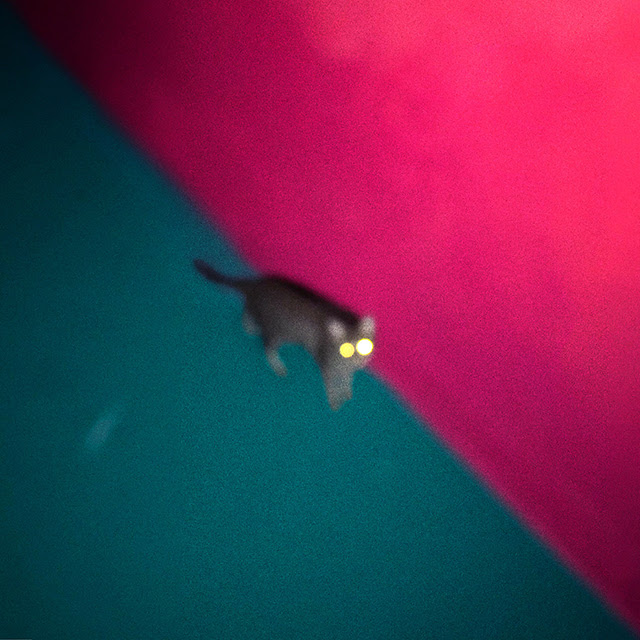言わずもがな、80年代からDJとして活躍し、数々のリミックスやプロダクションで名を馳せ、セイバーズ・オブ・パラダイスやトゥ・ローン・スウォーズメン、ジ・アスフォデルスなど多くのプロジェクトで素晴らしい音楽を生み出し続けてきたヴェテラン、ポスト・パンクとハウスとの間に橋を架けたUKテクノ番長、アンドリュー・ウェザオールが久方ぶりの来日を果たす。表参道のヴェニュー VENT の3周年を祝うパーティ《VENT 3rd Anniversary》の一環として開催される《Day2》への出演で(サークル・オブ・ライヴを迎える《Day1》についてはこちらから)、なんとオープンからクローズまでひとりでロングセットを披露するのだという。と、とんでもない。いま彼がどんな音楽に注目しているのか確かめる絶好の機会でもあるので、8月24日は予定を空けておきましょう。
伝説! Andrew Weatherall が表参道VENTの3周年パーティーDay2で、オープン・トゥ・ラストのロングセットを披露!

国内屈指のサウンドシステムと、こだわり抜いたブッキングで日本のナイトシーンに一石を投じてきた表参道VENT。8月17日と24日に3周年パーティーを開催! 8月24日のDay2には現代のミュージックシーンに計り知れない影響を及ぼしてきたリビングレジェンド、Andrew Weatherall (アンドリュー・ウェザオール)がオープン・トゥ・ラストのロングセットで登場!
Andrew Weatherall ほど多岐にわたる音楽ジャンルに影響を及ぼしてきたアーティストもなかなかいないだろう。10代の頃からポップカルチャー全体に傾倒し、音楽と洋服と本と映画に夢中になっていたという。音楽制作を始めてからは、ずば抜けた才能を発揮し、New Order、My Bloody Valentine、Primal Scream、Paul Weller、Noel Gallagher、Happy Monday などの制作に関わったり、リミックスを提供。デビュー前の The Chemical Brothers や Underworld などの素晴らしい才能をいち早く発掘したのも Andrew Weatherall 達だった。
アナログレコードをこよなく愛し、今でも幅広い音楽ジャンルのDJプレイを披露している。ロカビリーからテクノまでをプレイする、Andrew Weatherall にとっては音楽ジャンルの壁などは無いに等しい。数々の革命を音楽業界に巻き起こしてきた、真のイノベーターと共に迎えるVENTの3周年パーティーに乞うご期待!
更に超豪華特典! VENTの3周年を祝して Andrew Weatherall が、最新の Mix を2本提供してくれました!
・Mix #1はこちらでお楽しみ下さい!
Andrew Weatherall VENT 3rd Anniversary Mix #1
https://soundcloud.com/vent-tokyo/andrew-weatherall-vent-3rd-anniversary-mix-1
・Mix #2はVENTのメールマガジンに登録してくれたお客様にダウンロードリンクをお送り致します。
https://vent-tokyo.net/
こちらのトップページ中段にあるフォームにてご登録下さい。
※ 不定期にVENTの最新情報をお送り致します。

【イベント概要】
- VENT 3nd Anniversary: Day 2 Feat. Andrew Weatherall -
DATE : 8/24 (SAT)
OPEN : 23:00
DOOR : ¥4,500
ADVANCED TICKET : ¥3,800
https://jp.residentadvisor.net/events/1293718
※ 前売り券が完売した場合は当日券の販売はございませんので、お早めのご購入をお勧め致します。When the advance tickets will be sold out, we won’t sell the door tickets.
=Room1=
Andrew Weatherall
And more
VENT:https://vent-tokyo.net/schedule/andrew-weatherall/
Facebookイベントページ:https://www.facebook.com/events/2253976334915551/
※ VENT では、20歳未満の方や、写真付身分証明書をお持ちでない方のご入場はお断りさせて頂いております。ご来場の際は、必ず写真付身分証明書をお持ち下さいます様、宜しくお願い致します。尚、サンダル類でのご入場はお断りさせていただきます。予めご了承下さい。
※ Must be 20 or over with Photo ID to enter. Also, sandals are not accepted in any case. Thank you for your cooperation.
【INFO】
VENT PRESS
MAIL: press@vent-tokyo.net
TEL: 0364389240
ADDRESS: 〒107-0062 東京都港区南青山3-18-19 フェスタ表参道ビルB1F
VENT WEB SITE: https://vent-tokyo.net/
Facebook: https://www.facebook.com/vent.omotesando/
Twiter: https://twitter.com/vent_tokyo/
Instagram: https://www.instagram.com/vent.tokyo/