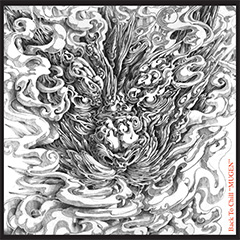私はジョン・ケージが「聴くこと」のみを単純に推奨したとは思えない。どう考えても事態は逆だ。ケージはむしろ「聴こえないこと」の問題を人生かけて追及したのではないか。あの有名な無響室での彼の経験は、聴こえないことの驚きであったはずだ。ケージは音を「生きているもの」「捉えられないもの」として、いわば不確定な運動体として認識していたと思うのだが、無響室においては音が止まっている経験をした(のかもしれない。そんなことは本人しかわからない。だがそれで何が問題あるのか?)。音が聴こえず、真空状態にいること。音が止まっている経験。聴こえるのは体内の音のみ。それは死に限りなく近い体験であったともいえよう。つまり音の極限地点であったのだ。
その意味で「静寂な」エレクトロニカ以降のアンビエント/ドローンやフィールド・レコーディング作品がときにケージの美学を援用するのは、「ジョン・ケージという作曲家のイメージ」を借用・援用したに過ぎない。大谷能生が言うように、「4分33秒」は休符の音楽だし、休符はカウントしなければならないのだから、そのとき演奏者は厳密には世界の音のざわめきなどを聴いて恍惚になっている場合で(暇)はないはずだ。演奏者は自分の/他人の音楽を聴かなければならない(黙々とカウントしている)。
とはいえケージの思想は極端な両義性をもっているからこそ誤読できるし、誤読できるからこそ、普及しやすい。それゆえ誤読の豊かさがあるともいえる。それは事実だ。だが、本当にジョン・ケージは「聴くこと」のみを推奨していたのか。彼の言説にはどこかにトリックがないかともう一度疑ってみるのも悪くはないはずだ。それこそ誤読の可能性として。そもそも「音楽を演奏する」と、「世界の音を聴く」というのは、相反する矛盾を孕んでいないか。
坂本龍一もまた、音楽/ノイズという両義性を生きてきた音楽家だ。坂本は類稀な作曲家でありながらも、同時に、ノイズに対して柔軟かつ鋭敏な感性を持ちつづけているサウンド・アーティストであり、ノイズ・コンポーザーであった。私はこのような両義性こそ、この音楽家の本質ではないかと思っている。たとえば、あのYMOの活動も、坂本にとっては新しい音色の探求と発見という側面も強かったはずである。だからこそ彼は2000年代を通じてカールステン・ニコライ(アルヴァ・ノト)やクリスチャン・フェネスらエレクロトロニカ/電子音響アーティストとのコラボレーションを続けてきたのではないか。そして細野晴巨、高橋幸宏ら「盟友」との再会・再合流もエレクトロニカを介してものではなかったか(90年代には『愛の悪魔』のサントラがある。坂本ノイズを満喫できる傑作だ)。
その音楽/ノイズという両義性は、2009年にリリースされた坂本のソロ・アルバム『アウト・オブ・ノイズ』以降、より随所にあきらかになっている(正確には2004年の『キャズム』をもうひとつの中継点とした00年代全般だが)。彼は作曲家として世界のノイズをリ・コンポジションしようとしている。そこで坂本が取った方法論は何か。私は、即興=インプロヴィゼーションとコンポジションの交錯であったのではないかと思う。さまざまな音への反応によって、世界の音を再構築していく行為だ。彼が2000年代を通じて行ったカールステン・ニコライやクリスチャン・フェネスとの共同作業もインプロヴィゼーションからはじまってコンポジションへと行きつく創作であったはずである。グリッチからアンビエントへ、という変化もこれに呼応している。だが、これは世界的な傾向でもあった。坂本はつねに世界の無意識にアジャストする。
この2015年にNYのレーベル〈12k〉からリリースされた坂本龍一とテイラー・デュプリーとイルハ(コリー・フラーと伊達伯欣)の3組(4人)による『パーペチュアル』がリリースされた。本作もまた、エレクトロニカ以降のインプロヴィゼーションとコンポジションの交錯としてのアンビエントを、より深い次元で実現している傑作であった。
演奏は2013年夏、山口のYCAMで繰り広げられたもの。4人での演奏はこれが初という。もっとも坂本はテイラーと共演経験があり、すでに〈12k〉からデュオ・アルバムを出しているし、イルハも〈12k〉からアンビエント作品をリリースしており、いまや新時代のアンビエント・アーティストと目されている。彼らのファースト・アルバム『shizuku』は、鎮静と静寂を与えてくれる傑作だ。もちろんテイラー・デュプリーとの競演の経験もある。
だが、4人という状態になったことで、それぞれの共演とがちがう奇跡が起きたようにも思える。坂本龍一、テイラー・デュプリー、イルハらによる3組4人の演奏は、偶然とコントロールの狭間で揺らめいている。まるで光のように。まるで空気のように。坂本は彼らしいピアノをほとんど演奏していない。そのかわりに叩く、擦る、落とすなどしていてサウンドを生成させている。まさに「アウト・オブ・ノイズ」。
何より、これがインスタレーション的なサウンド・アートではない点が重要だ。彼らはそれぞれの演奏者の音を意識しつつ、ときに受け流し、ときに反応をしている。つまり「音楽を演奏している」のだ(と同時に彼らの音はパフォーマンスである。かつて坂本が影響を受けたナム・ジュン・パイク的な演奏ともいえる)。
朝霧のような持続音からはじまり、まるで明け方から早朝にかけての大気の変化のような1曲め“ムーヴメント1”、繊細な音と微かにプリペアドされた異物感のある音などが蠢く2曲め“ムーヴメント2”、カサカサと鳴る静かなノイズの狭間から、水滴のように美しいピアノが鳴り響く3曲め“ムーヴメント3”まで、まさに光の陰影のような音響/音楽である。
このアルバム(録音)で注目すべき点は何より3人の個が音の空気の中に融解している点だ。反応と生成によって生まれる音響空間は、それぞれ個性的な音楽家の個性を消し去る。音を聴いているかぎりでは3曲めに僅かにあらわれる坂本のピアノなどを除き、どの音を3人が発生させているのかは即座にはわからない(担当楽器のクレジットと照らし合わせ、よく聴けばわかるが)。インプロヴィゼーションからの無の生成。それはけっしてネガティヴな意味ではない。美しい音響の空間の生成のみ貢献しているのだから。個人的には2曲めに突如響くコインが落ちる音のようなサウンドにとても惹かれる。なんという美しい音だろう……!
そうして生まれた美しい音の群れは、私たちの耳を静かに通り過ぎていく。「聴く」という後期の恣意性は宙吊りにさせられ、音の繊細な変化に、ただ耳を傾けることになる。そう、聴き手は音を捕まえることはできない。音響による無の生成。それはアルバム名とおり「永遠」をも意味しているはずだ。永遠=無。この「永遠」の領域においては「聴こえる/聴こえない」の距離は、そう遠くないものとして存在している。「生きること」と「死」が常に隣り合わせのように。動き。持続。変化。永久。無。つまり「音楽」とは生と死の営みなのであり、即興と作曲は人生そのものを刻みつける行為なのだろう。
(追記)
本年2015年に入り、坂本龍一関連のリリースが相次いだ。中でも2005年から2014年までの未発表曲集『イヤー・ブック2014-2015』は非常に重要なアルバムである。2005年以降ということは、坂本流のグリッチ・ミュージックの消化ともいえる『キャズム』以降であり、また、アンビエント/ドローン(およびポスト・クラシカル)の時代を先駆けた2009年の『アウト・オブ・ノイズ』直前と以降を挟んでいる重要な時期に当たる。クリスチャン・フェネスやカールステン・ニコライ、クリストファー・ウィリッツなどと共作を行っていた時期でもあり、どの楽曲も(とくに2011年以前)、彼の音楽のドローン性とそのドローンの内部に運動する微細なサウンドが、静謐な音響の中に生成していくさまが手にとるようにわかってくる。また、2009年以降の音には、来るべきソロ・アルバムの萌芽を聴きとることも可能だろう。美術館やCMなどのために作られた音楽だが2000年代中盤から2010年代初頭の坂本龍一が、いかにサウンド・アーティスト/ノイズ・コンポーザーとして充実していたのかをあらためて知ることができる。このような充実した曲がいままでリリースされなかったことは、彼の現在進行形としての音楽家としての全体像を私たちは捕まえていなかったことになる。まさに発表されなかった幻のソロ・アルバムといっても過言ではない。また、ようやくリリースされた『音楽図鑑 2015エディション』は、本編であるディスク1のリマスターも、いたずらに音量・音圧を上げずに音の解像度を明確するというじつに素晴らしいリマスタリングが行われており必聴だったが、マニアなら未発表曲・テイクのみを収録したディスク2も貴重な音源だ。とくにラストに収録されたアンビエント/ドローンな未発表曲“M33 アンタイトルズ”は、この作曲家にとって音の内部にミクロに動く音の運動がいかに重要なエレメントであるのかわかってくる。坂本本人もインタヴューで語っていたが、たしかに彼の現在の作風に近く、非常にいまを感じる曲だ。