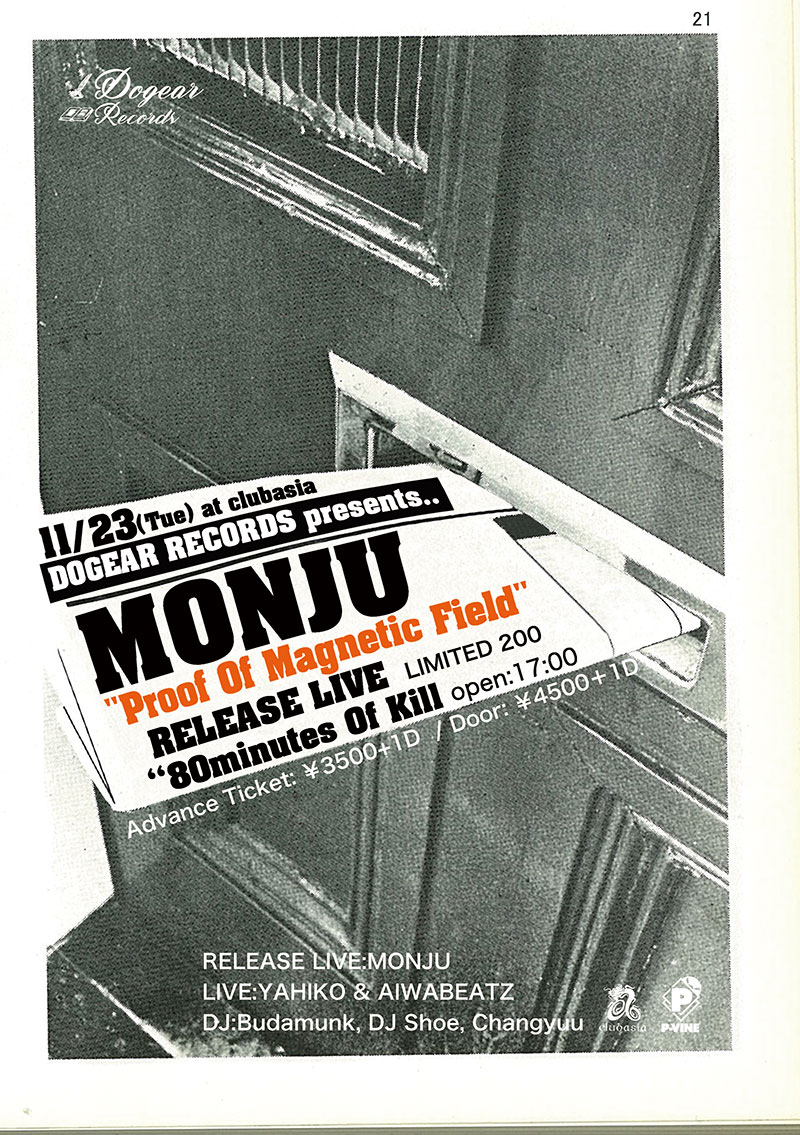これは期待の膨らむコラボだ。アンビエントをはじめ幅広い活動を繰り広げるナカコー、今年〈ハイパーダブ〉から新作を送り出したプロデューサーの食品まつり、大ヴェテラン・ドラマーの沼澤尚(ナカコーとの関係も深い)によるライヴ・セッションが音盤化される。いろんな要素がクロスオーヴァーした音楽に仕上がっているようだが、はてさて、いったいどんなサウンドが鳴り響いているのか……発売は年明け後の1月12日。いまから楽しみです。
ナカコー×食品まつり×沼澤尚!
待望の初音源リリース決定!!
三者三様、独自の音楽観に定評あるクリエーターよる膨大なセッション音源をナカコーがトリートメント! 静寂の中の心地良さにどこか引っ掛かりを残したアンビエント的オルタナティブポップミュージック!
Koji Nakamura (electronics)、食品まつりa.k.a foodman(electronics)、沼澤尚(Dr)がスタジオに入り素材録音ために敢行した即興的なライブセッションをナカコーがトリートメント(Extraction、Edit、Mix)した全7曲のアルバム『Humanity』が2022年1月12日にリリースとなります。
アンビエント、エレクトロポップ、ダンスミュージック、ロックがクロスオーバーした一種のオルタナティブなポップミュージックはニューノーマルな日常にピッタリ寄り添う今日的な録音作品と言えます。
[リリース情報]
アーティスト:Koji Nakamura+食品まつりa.k.a foodman+沼澤尚
タイトル:Humanity
レーベル:felicity / P-VINE
品番:PCD-18891
フォーマット:CD / 配信
価格:¥3,300(税込)(税抜:¥3,000)
発売日:2022年1月12日(水)
[収録曲]
M1. no.1
M2. no.2
M3. no.3
M4. no.4
M5. no.5
M6. no.6
M7. no.7
[プロフィール]
【Koji Nakamura】
1995年地元青森にてバンド「スーパーカー」を結成し2005年解散。その後、ソロ活動をスタート。アーティスト活動他、コンポーザーとしてCMや劇伴、多くの楽曲提供を行う一方、バンド「LAMA」「MUGAMICHILL」としても活動中。また日本のアンビエントを牽引すべく、『HARDCORE AMBIENCE』をduennと共に主宰し、映像やライブを展開中。
【食品まつりa.k.a foodman】
名古屋出身の電子音楽家。2012年にNYの〈Orange Milk〉よりリリースしたデビュー作『Shokuhin』を皮切りに、現在までNY、UK、日本他の様々なレーベルから作品がリリースされている。また、2016年の『Ez Minzoku』は、海外はPitchforkのエクスペリメンタル部門、FACT Magazine, Tiny MixTapesなどの年間ベスト、国内ではMusic Magazineのダンス部門の年間ベストにも選出されてた功績を持つ。
【沼澤 尚】
ドラマー。LAの音楽学校P.I.T.に留学。JOE PORCARO,、PALPH HUMPHREYらに師事し、卒業時に同校講師に迎えられる。2000年までLAに在住し、CHAKA KHAN、BOBBY WOMACK、AL.McKAY&L.A.ALL STARS、NED DOHENY、SHIELA E.などのツアーに参加し、13CATSとして活動。2000年に帰国して以降現在まで、数えきれないアーティストのレコーディングやライブに参加しながらシアターブルック,blues.the-butcher-590213で活動中。