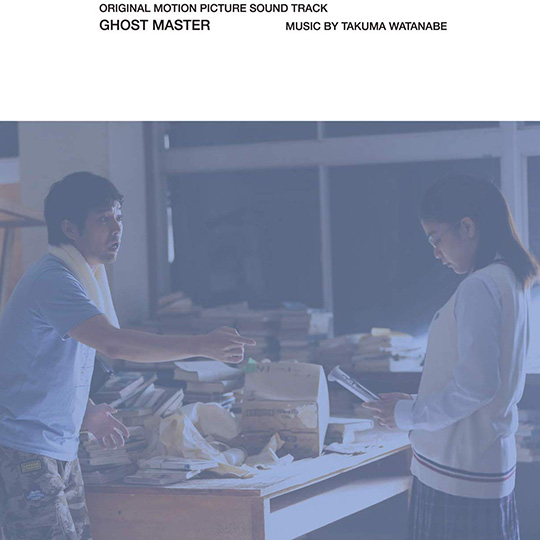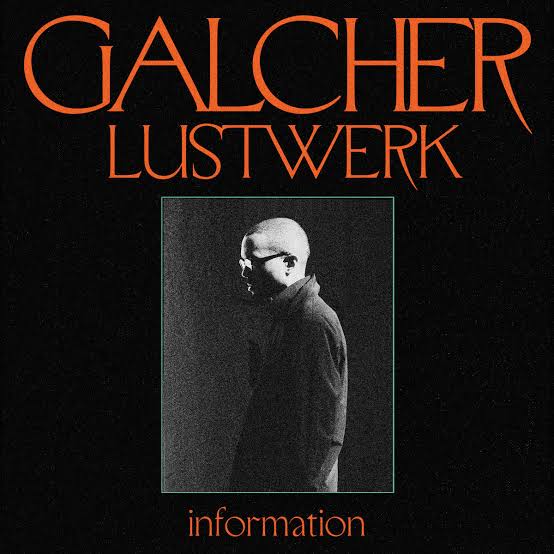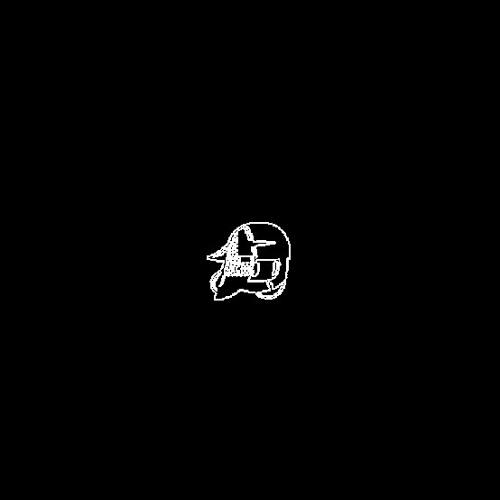来年3月にニュー・オーダーの来日が決定、石野卓球と Stolen が追加出演することも発表された。その噂の Stolen とはいったい何者なのか? というわけで、この秋ベルリンで開催されたニュー・オーダーと Stolen のライヴの模様をレポートします。
世界が音楽に貪欲だった70年代の再来か!? 中国の新世代インディーズ・バンドがニュー・オーダーと共に欧州に君臨、そこで、手にした未来とは!?
現代に残る社会主義国家でありながら、他の資本主義国家よりも圧倒的な経済発展を遂げている中国が閉鎖的であるというイメージはもはや過去の産物ではないだろうか。むしろ、時代を逆行するかのごとく、どんどん自由が制限され、それに気付く余裕さえないほど殺伐とした環境で、ピュアな感性が蝕まれていくように感じる今の日本の方がよほど危機感を覚えるのは筆者だけだろうか。物質的なものでも情報でも、いとも簡単に何でも手に入る環境が決して幸せで良いことであるとは言えないのだ。
これは何も社会的なことに限った話ではない。アンダーグラウンドな音楽シーンにおいても同様に思うのだ。
まだ10月初めだというのに冬物のジャケットが必要なほど冷え込んだ日、ベルリンのコンサートホール「Tempodrom」でヨーロッパ・ツアー真っ最中の New Order のライヴが行われた。そのサポートアクトを務めたのが、中国四川省成都出身の中国人5名、フランス人1名からなる6ピースバンド “Stolen” である。

Photo by Alexander Jung
ヨーロッパでは未だ未知の領域である中国のインディーズ・シーンから、突如テクノの街ベルリンに現れたバンド Stolen とは一体何者なのだろうか? まず、アジア人のコンプレックスを隠そうとするありがちな “Too much なデコラティヴ” は一切なく、むしろ、全身黒の衣装で統一したシンプルなミニマル・スタイルに黒髪の彼らは控えめな若者の集まりと言った印象。
それに反して、ライヴ・パフォーマンスはストイックと完璧主義の塊である。心の奥底に押し込めた欲望やら鬱憤やらをサウンドに打ち付けて、吐き出しているかのように激しく、それでいて荒削りで強引な演奏ではなく、インテリジェンスで完璧なまでのスキルに身震いするほどの衝撃を受けた。
圧倒的な存在感を放つフロントマン Liang Yi による堂々たるナルシシズムを全面に出した独自の世界観に真っ先に引き込まれていく。歌詞はほとんどが英語で歌われており、その時点で中国だけでなく、世界の舞台を見据えているように思えた。そして、彼らの放つサウンドはポップではなく、一貫してダークである。VJ担当の Formol によるアートワークがその世界観をグラフィックと写真のコラージュで実にシュールに表現している。

Photo by Alexander Jung
Kraftwerk や Joy Division に影響を受けているという彼らだが、全員まだ20代である。インターネットが監視下に置かれている中国で、違法ダウンロードによって手にした “外の世界の音” から、自分たちが生まれてもいない70年代のドイツのクラウトロックやイギリスのポストパンク、ニューウェイヴと運命的に出会う。そして、インスパイアされ、独自の解釈によって、ギターと打ち込みが疾走するオリジナリティー溢れる Stolen サウンドとして誕生したのだ。ダークでメランコリックであるが、そこに存在するのは絶望ではなく、暗闇で輝く生粋のアンダーグラウンドである。
自国へ帰ればアルバイトで生活費を稼ぐ日常が待っている労働者階級出身の彼らに、ネット世界ではなく、本物のベルリンを見せ、スポットライトを当てた重要人物がいることを忘れてはいけない。彼らの成功への道は、プロデューサーの Mark Leeder の存在なくしては語れない。1990年、壁崩壊直後の混沌としていたベルリンで、自身のレーベル〈MFS〉を設立し、マイク・ヴァン・ダイクや電気グルーヴといったテクノ・アーティストのリリースを手掛ける傍、世界を飛び回り、アンダーグラウンド・シーンで光る原石を掘り続けてきた伝説のプロデューサーである。90年代から中国の音楽シーンに注目していた彼の目に止まったのが、平成生まれの若き Stolen である。マークは一体彼らにどんな未来を見たのだろうか?
伝説のプロデューサーと言えば、もはや何度観たか分からない筆者の音楽人生のバイブル『24アワー・パーティー・ピープル』の故トニー・ウィルソンが頭に浮かんだが、壁に分断されていた80年代の西ベルリンを描いたドキュメンタリー映画『B-MOVIE』が、Mark Reeder そのものなのだ。彼の半生を描いた同作では、自身がストーリーテラーも務めており、狂乱に満ちた同じ時代を駆け抜けた同士として、当然ながらトニー・ウィルソンとの親交も深かったと言う。

Photo by Alexander Jung
ベルリンは、時代を越えて心底アンダーグラウンド・ミュージックと共存している街であると言える。地下鉄の中やストリートでは日々パフォーマーたちによって様々なジャンルの音楽を耳にし、普通の女の子が Bluetooth スピーカーから爆音でビート・ミュージックを鳴らしながら闊歩する。世界最高峰と呼び名の高い Berghain では毎週末36時間ぶっ通しのパーティーが行われている。そこには年齢も性別も人種も関係ない、心底音楽が好きな人間たちが集まっている、ただ、それだけである。
Joy Division の『Unknown Pleasures』のTシャツに身を包んだ熟練でシビアな New Oeder ファンを前で堂々たるプレイを見せつけ、取り込んだ Stolen は、アジアを代表するバンドとしてここヨーロッパで確固たる地位を築いていくだろう。この日、客席には彼らの楽曲 “Chaos” をミックスした石野卓球の姿があった。Stolen に昔の電気グルーヴの姿を重ねながら、70年代のマンチェスターやベルリンの再来を期待せずにはいられない一夜となった。
New Order (ニュー・オーダー)の来日公演に、ニュー・オーダーのバーナード・サムナー(Vo.)が絶賛する中国のインディーバンド Stolen と石野卓球が追加出演決定!!
1980年代後半から1990年代初頭にかけて起きたマンチェスター・ムーヴメントを描いた映画で2002年に公開され大ヒットした映画「24アワー・パーティー・ピープル』にも登場する、マンチェスター・ムーヴメントの象徴的アーティストで、ロックとダンスを融合させてサウンドが、ブラー、オアシス、レディオヘッドなど、その後のUKロックバンドに多大な影響を与えたイギリス、マンチェスター出身の伝説バンド、New Order (ニュー・オーダー)の来日公演に、中国のインディーバンド、Stolen と石野卓球の追加出演が決定しました。
Stolen はニュー・オーダーのバーナード・サムナー(Vo.)が彼らの音楽に惜しみなく賛辞を贈る、平均年齢26歳の5人の中国人と1人のフランス人による中国のインディーバンドで、10月からスタートしている、ヨーロッパでのニュー・オーダーのライブ・ツアーにスペシャルゲストとして帯同中。
石野卓球は、Stolen の全世界デビュー・アルバムとなる『Fragment (フラグメント)』にリミックスを提供していますが、実はこの3組のアーティストを繋ぐハブとなったのは、マンチェスター出身のプロデューサー、DJ、そしてドイツベルリンの伝説的音楽レーベル〈MFS〉のオーナーでもあるマーク・リーダーです。
マーク・リーダーはニュー・オーダーのバーナード・サムナーにいち早くベルリンのダンスミュージックを体験させた人物で、彼がいなければニュー・オーダーの名曲“Blue Monday”が生まれることはなかったと言われています。
また、電気グルーヴの『虹』を自身のレーベル〈MFS〉からリリースし、電気グルーヴと石野卓球がヨーロッパで活躍するきっかけを作ったのもマーク・リーダー。
そして、Stolenの全世界デビュー・アルバム『Fragment (フラグメント)』をベルリンでレコーディングし、このアルバムに石野卓球のリミックスが収録されることになったのもマーク・リーダーのプロデュースによるものなのです。
国も世代も異なるアーティストたちが、“音楽密輸人”の異名を持つマーク・リーダーを中心に日本公演で貴重な邂逅を果たします。
なお、ゲスト出演決定につき、開場・開演時間が変更になりますので、詳細は以下の情報をご覧ください。
【ライブ情報】
※ゲスト出演決定につき、開場・開演時間を変更させて頂きます。予めご了承ください。
東京 3月3日(火) 新木場 STUDIO COAST / special guest : 石野卓球
東京 3月4日(水) 新木場 STUDIO COAST / special guest : STOLEN / 石野卓球
OPEN 18:30→18:00 / START 19:30→19:00
TICKET スタンディング ¥10,000 指定席 ¥12,000(税込/別途1ドリンク)※未就学児入場不可
一般プレイガイド発売日:発売中 <問>クリエイティブマン 03-3499-6669
大阪 3月6日(金) Zepp Osaka Bayside / special guest : STOLEN
OPEN 18:30→18:00 / START 19:30→19:00
TICKET 1Fスタンディング ¥10,000 2F指定 ¥12,000(税込/別途1ドリンク)※未就学児入場不可 ※別途1ドリンクオーダー
一般プレイガイド発売日:発売中 <問>キョードーインフォメーション 0570-200-888
制作・招聘:クリエイティブマン
協力:Traffic
【ニュー・オーダー】
メンバー:バーナード・サムナー、ジリアン・ギルバート、スティーヴン・モリス、トム・チャップマン、フィル・カニンガム
マンチェスター出身。前身のバンドは、ジョイ・ディヴィジョン。80年、イアン・カーティスの自殺によりジョイ・ディヴィジョンは活動停止を余儀なくされ、バーナード・サムナー、ピーター・フック、スティーヴン・モリスの残された3人のメンバーでニュー・オーダーとして活動を開始。デビュー・アルバム『ムーヴメント』(81年)をリリース。82年、ジリアン・ギルバート加入。83年に2ndアルバム『権力の美学』をリリースし、ダンスとロックを融合させた彼らオリジナルのサウンドを確立した。85年リリースのシングル「ブルー・マンデー」は大ヒットを記録、12”シングルとして世界で最も売れた作品となった。同年初の来日公演を実施。所属レーベルのファクトリー・レコードが地元マンチェスターに設立したクラブ、ハシエンダ発のダンス・カルチャーは、80年代後半にマッド・チェスター、セカンド・サマー・オブ・ラヴといった世界を牽引する音楽シーンを生み出した。その一大カルチャーの中心的存在として、3rdアルバム『ロウ・ライフ』(85年)、4thアルバム『ブラザーフッド』(86年)、5thアルバム『テクニーク』(89年)をリリースし、その評価・人気共にUKユース・カルチャーの象徴となった。93年、ロンドン・レーベル移籍第1弾として、名曲「リグレット」等が収録された6thアルバム『リパブリック』をリリース。7thアルバム『ゲット・レディー』(2001年)と8thアルバム『ウェイティング・フォー・ザ・サイレンズ・コール』(2005年)は、ギター・サウンドに比重を置いたサウンドとなった。2007年、オリジナル・メンバーのピーター・フック(b)がバンドを脱退。2001年と2005年にフジ・ロック・フェスティヴァルに、2012年にサマー・ソニックに出演。2014年、MUTE移籍が発表され、2015年9月23日に9thアルバム『ミュージック・コンプリート』をリリース。2016年、実に29年ぶりの単独来日公園を行う。2017年、ライヴ盤『NOMC15』をリリース。2019年6月、地元マンチェスターの伝説の会場で2017年6月に5夜に渡って行われたライヴを収録した『∑(No,12k,Lg,17Mif)』を発売。
タイトル:∑(No,12k,Lg,17Mif) / ∑(No,12k,Lg,17Mif) New Order + Liam Gillick: So it goes..
品番:TRCP-243~244 / JAN: 4571260589032
定価:2,600円(税抜)*CD:2枚組
【石野卓球】
1989年にピエール瀧らと電気グルーヴを結成。1995年には初のソロアルバム『DOVE LOVES DUB』をリリース、この頃から本格的にDJとしての活動もスタートする。1997年からはヨーロッパを中心とした海外での活動も積極的に行い始め、1998年にはベルリンで行われる世界最大のテクノ・フェスティバル“Love Parade”のFinal Gatheringで150万人の前でプレイした。1999年から2013年までは1万人以上を集める日本最大の大型屋内レイヴ“WIRE”を主宰し、精力的に海外のDJ/アーティストを日本に紹介している。2012年7月には1999年より2011年までにWIRE COMPILATIONに提供した楽曲を集めたDisc1と未発表音源などをコンパイルしたDisc2との2枚組『WIRE TRAX 1999-2012』をリリース。2015年12月には、New Orderのニュー・アルバム『Music Complete』からのシングルカット曲『Tutti Frutti』のリミックスを日本人で唯一担当した。そして2016年8月、前作から6年振りとなるソロアルバム『LUNATIQUE』、12月にはリミックスアルバム『EUQITANUL』をリリース。
2017年12月27日に1年4カ月ぶりの最新ソロアルバム『ACID TEKNO DISKO BEATz』をリリースし、2018年1月24日にはこれまでのソロワークを8枚組にまとめた『Takkyu Ishino Works 1983~2017』リリース。現在、DJ/プロデューサー、リミキサーとして多彩な活動をおこなっている。
www.takkyuishino.com
【STOLEN】
中国で今最も刺激的な音楽シーンになるつつある四川省の省都・成都(せいと)を拠点にする平均年齢26歳の5人の中国人と1人のフランス人で構成される6人組のインディーズバンド「STOLEN(ストールン:秘密行动)」。2011年の結成から7年、謎多き中国のインディーズシーンから全世界デビューアルバムとなる『Fragment(フラグメント)』はドイツベルリンの伝説的レーベル「MFS」のオーナーMark Reederがプロデューサーとなり、成都にある彼らのホームスタジオとベルリンのスタジオでレコーディングされた。テクノやロックといったカルチャーを独自に吸収したそのサウンドやライブステージ、アートワークは、中国の音楽好きな若者から人気を集めるポストロック〜ダークウェイブの旗手として、その注目度は世界中へ拡がっている。
STOLEN
日本デビュー・アルバム『Fragment』発売中
価格:¥2,500+税
商品仕様:CD / 紙ジャケ / リーフレット
品番:UMA-1121
日本特設サイト: https://www.stolen.jp/#vbid-f4774c46-fyjqoota
Weibo: https://www.weibo.com/mimixingdong
Instagram: https://www.instagram.com/stolen_official/
Facebook: https://www.facebook.com/STOLENfromChina