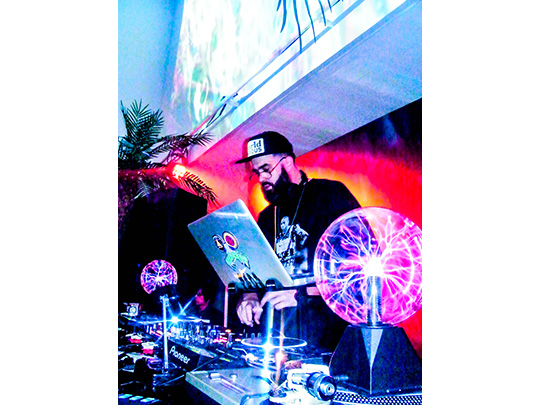奇数月第4金曜"SACRIFICE"@Orbit
毎月第1火曜「旅路」@SHeLTeR
偶数月第3月曜「一夜特濃」@天狗食堂
6月22日 "Life Force Alfrescorial" @Panorama Park Escorial 箱根
https://lifeforce.jp
世界観で選んだ新譜と準新譜 2013.6.12
 1 |
Frieder Butzmann - Wie Zeit Vergeht - Pan https://soundcloud.com/pan_recs/frieder-butzmann-wie-zeit |
|---|---|
 2 |
Dont - AR 005 - Atelier Records https://dtno.net |
 3 |
Stellar OM Source - Image Over Image - No 'Label' https://soundcloud.com/omsource/image-over-image-12 |
 4 |
Yes Wizard - Crowdspacer Presents'Yes Wizard' - Crowdspacer https://soundcloud.com/crwdspcr/sets/yes-wizard-generator2 |
 5 |
Juanpablo - Lost series part 1 - Frigio Records https://soundcloud.com/frigio-records/juanpablo-mick-wills-rmx-ft |
 6 |
Anstam - Stones And Woods - 50Weapons https://www.youtube.com/watch?v=hXuGRvlhbXg |
 7 |
Ruff Cherry - The Section 31 E.P. - Elastic Dreams https://soundcloud.com/elastic-dreams/ruff-cherry-the-empath |
 8 |
SH2000 - Good News - Ethereal Sound https://soundcloud.com/ethereal-sound/sh2000-good-news-forthcoming |
 9 |
Laurel Halo - Hour Logic - Hippos In Tanks https://soundcloud.com/hipposintanks/laurel-halo-aquifer |
 10 |
Scott Walker - Bish Bosch - 4AD https://soundcloud.com/experimedia/scott-walker-bish-bosch-album |