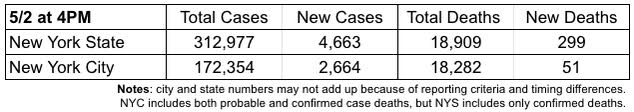アメリカ合衆国ノースカロライナ州出身のサウンド・アーティスト、トーマス・フィリップスの新しい音響作品が、日本・東京を拠点とするサウンド・アート・レーベル〈SAD rec.〉(https://sad-tokyo.com/)からCDリリースされた。 2016年に〈13〉からCDリリース作品『Chuchoter Pas De Mots』と〈LINE〉からデジタルリリース作品『Limit_Fold 』以来なので、約4年ぶりのアルバム・リリースということになる。
本作リリース元の〈SAD rec.〉は2013年の発足以降、 ケネス・カイアーシェナーとの共作『Five Transpositions』、ソロ作品『Two Compositions』のリリースと、この類まれな聴覚/感覚を持っているアーティストの音響作品を送り出してきたが、本作『Pulse Bit Silt』は〈SAD rec.〉/トーマス・フィリップスの協働における最高傑作ではないかと思う。音の質、空間性、コンポジション、ノイズ、音響そのどれもがかつての傑作群よりも一歩も二歩も抜きんでたからである。フランスコ・ロペスのハードコア・フィールドレコーディングに対して、エレガンスなフィールド・レコーディング作品とでも形容すべきか。
これまでのトーマス・フィリップスのリリース作品で印象に残っているアルバムは、〈SAD rec.〉の2作に加え、2006年に〈LINE〉からリリースされた『Intermission / Six Feuilles』、日本・東京の〈ATAK〉から2009年にリリースされたi8u + Tomas Phillips 『Ligne』(i8uはサウンド・アーティストのフランス・ジョビン変名。彼女もまた本年5月に新作を〈Editions Mego〉からリリースしたばかり)などだったが、本作『Pulse Bit Silt』は、どの作品よりもアルバムを通して見事な「流れ」を形成しているように聴こえた。アルバム作品として、より成熟しているのだ。
『Pulse Bit Silt』には計6曲(合計収録時間は46分。昨今のアルバム作品としては比較的長い収録時間といえる)の音響作品が収められているが、どのトラックとトラックもシームレスに連結し、ミニマルにして静謐な音響空間が次第に生成変化するような感覚を得ることができた。グリッチな電子ノイズやアトモスフィアな持続音に加えて、女性のヴォイスやインダストリアルなサウンドが要所に適切にレイヤーされていく。音の粒子が空気中に舞い踊り、音の粒が知覚に浸透するような麗しい音響たちを、その音の一粒、一粒を愛でるように聴取していくと、まるでゴダールやタルコフスキーの映画作品のように、カットとシークエンスが独自の持続感で進行していく総合的な芸術作品にすら思えてくるから不思議だ(彼は作家/小説家としても作品を発表しているらしい。音と言葉の両方から自らの芸術を追求しているのだろう)。
そう、本作はトーマス・フィリップスの新しい代表作にして、いまの時代におけるサウンド・アート作品を象徴するCDではないかと思う。〈SAD rec.〉から同時リリースされたビージェイ・ニルセン(BJ Nilsen)『The Accursed Mountains』、ケン・イケダ、ユキ・アイダ、ケイタ・アサヒ(Ken Ikeda,Yuki Aida,Keita Asahi)『Summer Sessions』を合わせて聴くことで「環境録音、電子音響、ドローンなどのエクスペリンタル・ミュージック」の現在を深いレベル体験/体感できるはず。3作とも高品質/高音質な「CD作品」だ。ぜひとも聴いて頂きたい。