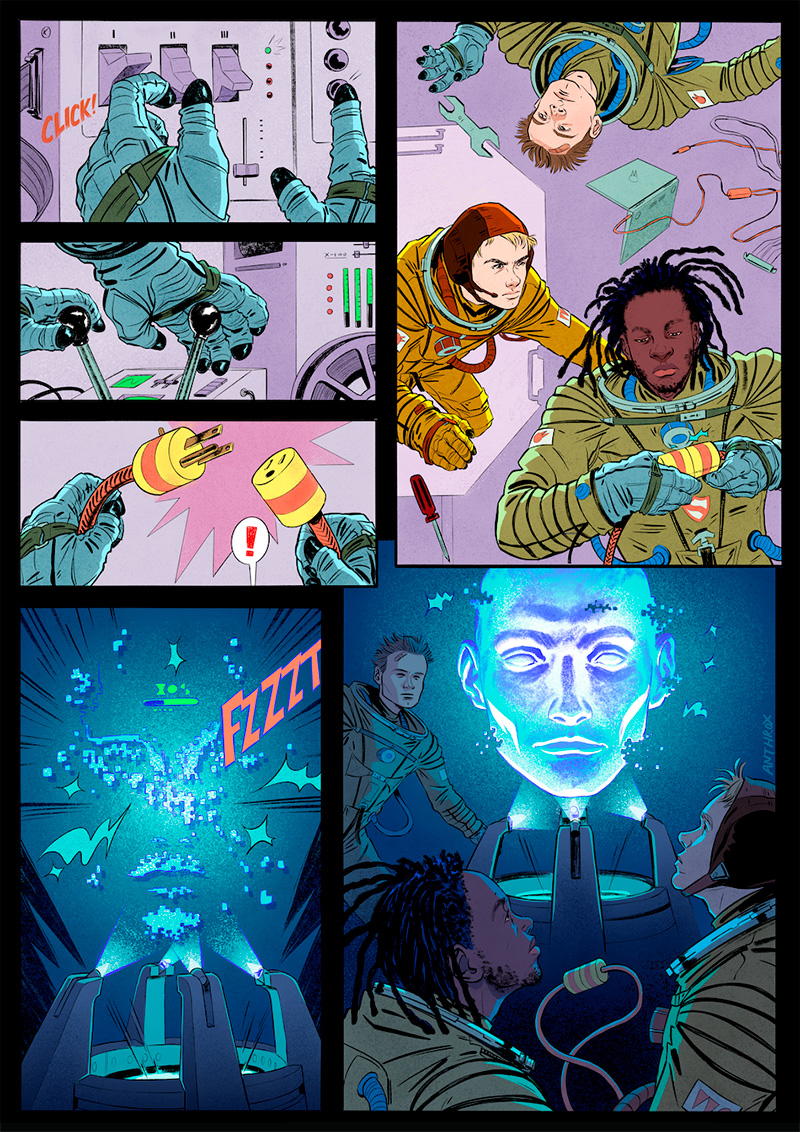幕開けとともに閉塞感が増しつつある2022年の世相を尻目にボリスは加速度を高めていく。起点となったのは2020年の夏あたり、最初の緊急事態宣言が明けたころ、主戦場ともいえるライヴ活動に生じた空白を逆手に、ボリスは音楽プラットフォーム経由で多くの作品を世に問いはじめる。新作はもちろん、旧作の新解釈やデジタル化にリマスター、ライヴやデモなどのオクラだし音源などなど、ザッと見積もって40あまりにおよぶ濃密な作品群は、アンダーグラウンド・シーンの牽引車たる風格にあふれるばかりか、ドゥーム、スラッジ、シューゲイズ・メタルの代表格として各界から引く手あまたな存在感を裏打ちする多様性と、なによりも生成~変化しつづける速度感にみちていた。
なぜにボリスの更新履歴はとどまるところを知らないのか。そのヒントはルーツにある轟音主義に回帰した2020年の『NO』と、対照的な静謐さと覚醒感をもつ2022年の『W』——あわせると「NOW」となる2作をむすぶ階調のどこかにひそんでいる。
取材をおこなったのは旧年12月21日。同月だけで彼らはBandcampにライヴ盤と3枚のEP(「Secrets」「DEAR Extra」「Noël」)をあげており、前月にはフィジカルで「Reincarnation Rose」をリリースしていた。いずれも必聴必携だが、クリスマス・アルバムの泰斗フィル・スペクターが聴いたら拳銃をぶっぱなしかねないドゥーミーな音の壁と化したワム!の「ラスト・クリスマス」(「Noël」収録)と、「Reincarnation Rose」EPの20分弱のカップリング曲「知 You Will Know」の水底からゆっくりと浮上するような音響性が矛盾なく同居する場所こそボリスの独擅場であり、その土壌のゆたかさはおそらく今年30年目を迎える彼らの歴史に由来する。
そのような見立てのもと、最新アルバム『W』が収録する「You Will Know」の別ヴァージョンに耳を傾けると、浄化するようなサウンドと啓示的なタイトルに潜む未来形の視線までもあきらかになる。現在地からその先へ――Atsuo、Takeshi、Wataのボリスの3者に、30年目の現状と展望を訊いた。

スタジオでの作業は日々絵を描きつづけるような、どんどんアップデイトされていくような感じなんです――Atsuo
■ボリスは海外を中心にライヴ活動がさかんですが、このコロナ禍で制約があったのではないかと想像します。実際はどうでしたか?
Atsuo:こんなに(海外に)出ていないのは何年ぶり? という感じだよね。
Takeshi:ぜんぜん行っていなかったのは2006年よりも前だよね。それ以降は毎年かならず行っていたもんね。
■2006年より前というのは、いかに長く海外での活動をされているかということですよね。でも逆に、ライヴ・バンドのメンバーに取材すると、ツアーがなくなって最初は悲しかったけど、ツアーしない時間にいろんな発見があったという意見もありました。
Atsuo:前はツアーをしなければ食べていけないと思っていましたから。コロナに入ってアルバムをすぐに作ってBandcampで2020年の7月に出したんですけど、その反応がすごくよくて世界中のリスナーからガッチリサポートしてもらえたんです。Bandcampの運営とか、楽曲の管理を自分たちでやりはじめたらツアーに出るよりも、経済的によい面もあって、制作にも集中できた。あと、すごく大変なことをしていたんだ、という実感もあります、ツアーに出るということが(笑)。その反面、あらためて再開するのも大変かなと思っています。いちおう今年は米国ツアーを予定してはいるんですけどね。
■アメリカはどこをまわられるんですか?
Takeshi:全米をほぼ1周する感じです。
■「周」という単位を聞くだけでも大変そうですよね。
Atsuo:感覚を戻すのがね。ほんと体力も落ちているんで。コロナ以前の状態まで自分たちのコンディションを戻さなければならないというのはたしかに大変です。
Takeshi:オフ無しで7本連続とかね。
■ツアーと制作中心の生活ではメンタル面での違いはありますか?
Atsuo:スタジオでの作業は日々絵を描きつづけるような感じなんです。そういった生活のほうが個人的には好きなんですけどね。新曲を作ってレコーディングしていると精神的にはめっちゃ安定するんですよ。日々新しい刺激が自分に返ってくると、やっぱりいいなと思います。コロナ禍で気づいたのは、自分の性質が絵描き的というか、描いて作られていく感覚に惹かれるということでした。いわゆるバンドマンとはちょっと違う感覚というか、描き続けていかないと完成しない、その感覚が強いです。
■Wataさんはコロナ禍でご自分の生活や性格の面で新たな気づきはありましたか?
Wata:家にずっといてもけっこう大丈夫でした(笑)。
■意外とインドアだったんですね。Takeshiさんは?
Takeshi:ライヴができなかっただけで、あとはあまり変わらなかったですね。スタジオにもしょっちゅう入っていたし。音楽が生活に占める割合は変わらないどころか、逆に増えた気がします。
Atsuo:制作ペースは上がっているものね。
Wata:スタジオはふつうに使えていたので、思いついたらスタジオに入ってセルフレコーディングして家にもってかえって編集して。
Takeshi:前はその合間にツアーのリハーサルがあったりして、制作に集中できない局面もあったんですけど、コロナ禍では制作に没頭していました。
Atsuo:今回のアルバム『W』はリモート・ミックスなんですね。
■リモート・ミックスとは?
Atsuo:担当していただいたエンジニアが大阪在住で、そこのスタジオの音響を「Audiomovers」というアプリで共有して、オンラインで聴きつつzoomで話し合いながらミックスを進めました。家の環境で聴けるのでかえってジャッジもしやすかったりするんですよね。
■東京で録った素材を大阪に送ってミックスしたということですか?
Atsuo:そうです。今回はBuffalo Daughterのシュガー(吉永)さんに制作に入ってもらったので、シュガーさんに音源をいったんお送りして、シュガーさんからエンジニアさんへ素材が行き、確認しながらミックスという流れです。
■通常のスタジオ・レコーディングとはちょっと違った工程ですね。
Atsuo:僕らはもう20年以上セルフレコーディングなんです。リハスタで下書きしたものを完成品に仕上げていくスタイルです。ミックスだけはエンジニアに手伝ってもらっています。
■その前の曲作りの段階はふだんどのような感じなんですか。
Atsuo:曲はリハスタでインプロした素材をもとに編集して曲の構造を作り、必要であれば肉づけするというプロセスでできあがります。CANと同じです。
Wata:最初は作り込んでいたけどね。
Takeshi:初期のころはわりと普通のバンド的だったね。
Atsuo:うん、リフを作って、何回繰り返したらここでキメが入ってとか決めていたね。セルフレコーディングをはじめたあたりからいまの方法になっていきました。いわゆるレコーディング・スタジオではどうしても「清書」しなければならない状況になると思うんですよ。それが苦痛で(笑)。間違えちゃダメというのがね。でも間違えたり、逸脱することに音楽的なよさがあったりするじゃないですか。だったら自分たちで録れば、たとえ失敗しても問題ない(笑)。そのぶんトライできるというか。
Takeshi:曲を作る工程は、みんながそれぞれ素描をしていて「こんなのが描けたんだけど」と互いに見せ合うような感じです。そこでやり取りしながら色を入れていったり、線が決まっていったり、そういった感じです。
Atsuo:いわゆるバンド的な曲作りだと、下書きみたいなリハーサルを何度も重ねてレコーディングがペン入れみたいなイメージな気がするんですね。清書するというのはそういう意味なんですが、僕らはそうじゃなくて下書きから一緒にドンドン塗り重ねて描き上げていく感じですね。
KiliKIliVillaとはインディペンデントにおける基本理念を共有している感覚があります。KiliKiliVilaの契約は利益が出たら折半なんですね。それは欧米ではごく普通のことなんですが、国内でそれをやっているレーベルはある程度以上の規模では極端に少なくなる。――Atsuo
■プロセスを重視するからなにがあっても失敗ない?
Atsuo:失敗も2回繰り返すと音楽になる。そういう観点から以前はガチガチに決め込んでいた構成も、失敗を受け入れられる意識になり、(演奏の)グリッドも気にならなくなりました。反対に、ポストプロダクション全開な作り方を試した時期もありましたけどね。同期などを使っていた時期です。いまは自分たちにしかできない方向、グリッドレスな方向に行っています。
■方向性の変化はどんなタイミングでおとずれるんですか?
Atsuo:そのときどき好きなことをやっているだけです。これだけ長いあいだやっていると、なにをやっても世間的な評価は変わらないんですよ。であれば好きなことをやったほうが単純に楽しい。それこそカヴァーとかやると、高校のころやっていた楽しい感じを思い出したり。
■若々しいですね(笑)。
Atsuo:(笑)楽しいことをやっていたいとは思いますよ。とくにいまのような状況下では各自の死生観みたいなものも露わになってきますし、楽しいことをしないと意味がないですよね。
■とはいえコロナ禍で音楽をとりまく状況は厳しくなりました。たとえば今後どのようにバンドを運営していくかというような、現実的な話になったりしませんか?
Atsuo:ずっとインディペンデントでやってきてレーベルに所属することもなく、すべてを自分たちで舵取りしてきたんですね。原盤もほとんど自分たちで持っています。コロナ禍では自分たちで判断して行動するという、ずっとやってきたことがあらためて重要な気がしています。
■KiliKIliVillaから出すのでも、いままでと体制は変わらないということですね。
Atsuo:体制は変わりませんが、環境はよくなりましたよ。たまたま知人を介しての紹介だったんですけど、KiliKIliVillaとはインディペンデントにおける基本理念を共有している感覚があります。KiliKiliVilaの契約は利益が出たら折半なんですね。それは欧米ではごく普通のことなんですが、国内でそれをやっているレーベルはある程度以上の規模では極端に少なくなる。レーベルの与田(太郎)さんからそういう契約だと聞いたときも、自分たちには普通のことなので、「はい、お願いします」――だったんですが、いざまわりを見渡すと日本でそれをやっているレーベルはあまりない。インディペンデントにおける価値観もシェアできるし、やりやすいですよね。そういうインディペンデントにおける美意識を共有している方がKiliKiliVillaのまわりにはたくさんいるので、いろいろなことがスムーズですね。
それこそ高校生のころの感じというか、影響を受けたことを直で出してしまうような。――Atsuo
■レコーディング、作品づくりに話を移します。ボリスは2020年夏にアルバム『NO』を出し、2021年はBandcampを中心にデジタル・リリースを含めるとかなりの数の作品を出されています。そして2022年の第一弾アルバムとして『W』が控えています。『W』の制作はいつからはじまったんですか?
Atsuo:『NO』のレコーディングが終わった時点で『W』の方向性が見えてきて、『NO』をリリースする前には『W』のレコーディングは終わっていました。
■『NO』は2020年の7月です。一度目の緊急事態宣言が解除になってしばらくしたころ。
Takeshi:そうですね、その年の6月には終わっていたんですよ。
■同時進行ですか?
Takeshi:『NO』が先に終わって、その後にすぐつづく感じでした。つながっている感じといいますか。
■『NO』が「Interlude」で終わっていたのが不思議でした。
Atsuo:出す時点で『W』が決まっていたので、2枚でひとつという感じでした。
■ということは制作前に2枚にわたる構想をおもちだった?
Atsuo:『NO』の終わりごろにそうなった感じですかね。
■では『NO』はもともとどういう構想のもとにたちあがったのでしょう。
Atsuo:いま思えば現実逃避だったかも(笑)。とりあえずスタジオに入って肉体的にもフルのことをやって、疲れてすぐに寝てしまうような、現実を見なくてすむようにしたいというコンセプトだったかもしれません(笑)。不安な感じやネガティヴなエモーションを音楽でポジティヴな方向に昇華する、それが表現の特性だと思うんですね。無意識にそのことを実践していたのかもしれないです。
■そういうときこそ曲はどんどんできそうですね。
Atsuo:それはもう(笑)。
Takeshi:血と骨に刻み込まれているから(笑)。
Atsuo:それこそ高校生のころの感じというか、影響を受けたことを直で出してしまうような。『NO』のときはわりとTakeshiと僕のルーツにフォーカスしていました。僕がメインのヴォーカルをほとんどとって、曲作りの段階からこれはツアーでやろうともいっていました。僕がヴォーカルでサポート・ドラマーを入れてやるんだという前提があって、いまは実際そういうライヴ活動をしていますからね。そこで僕とTakeshiにフォーカスしたので『W』ではWataの声にピントを当てて――ということですね。
僕も高校のときはパンク、ハードコアの影響をもろに受けていて、『NO』ではノイズコアの方向に突き進んでいきました。Takeshiとそういった部分を共有できるのはソドム。カタカナのソドムのノイズコアな感じが大好きだったんです。――Atsuo
■おふたりのルーツというのはひと言でいうとなんですか?
Takeshi:パンクとハードコア、ニューウェイヴも聴いていて、いちばん衝撃を受けたのはそのあたりの音楽なので、初期衝動とともに、身体に染みこんでいます。そういったものがコロナでグッと閉塞感が高まったたタイミングでウワーッとあふれでてしまった(笑)。
Atsuo:僕も高校のときはパンク、ハードコアの影響をもろに受けていて、『NO』ではノイズコアの方向に突き進んでいきました。Takeshiとそういった部分を共有できるのはソドム。カタカナのソドムのノイズコアな感じが大好きだったんです。『NO』はイタリアのF.O.A.D.というパンク~ハードコアのレーベルにアナログ化してもらったんですけど、そのレーベルがソドムの再発(『聖レクイエム + ADK Omnibus』)をしたんですよ。そういう流れもあってF.O.A.D.に決めたという(笑)。
■高校時代ソドムをカヴァーしていたんですか?
Atsuo:ソドムはやっていなかったですね。『NO』では愚鈍の「Fundamental Error」をカヴァーしています。
■原点回帰的な側面があったんですね。
Atsuo:あとはロック・セラピー。実際僕らは高校時代、そうした激しい音楽を聴いて精神を安定させていたところがあったんですね。
■ことに思春期では激しい音楽が精神安定剤の役割を果たすのは、わが身に置き換えてもそう思います。
Atsuo:ヘヴィメタルが盛んな国は自殺率が低いという話を耳にしたこともある(笑)。精神に安定をもたらすメタルといいますか。それもあって『NO』はエクストリームなんだけどヒーリング・ミュージック的なおとしどころになっていきました。自分たちにとってもそういう効果がありましたし。
■『NO』というと否定のニュアンスが強いですが、『W』と連作を成すことで激しさや衝動に終始しないボリスの現在(NOW)のメッセージを感じますよね。そのためのWataさんの声という気がします。
Atsuo:チルなんだけど逆に覚醒できる感じになっていったんですね。
■『W』にはシュガー吉永さんがサウンド・プロデュースで入られていますが、かかわりはいつからですか?
Wata:EarthQuaker Devicesというアメリカのエフェクターメーカーから「Hizumitas」という私のシグネチャー・モデルのファズが出たんです。そのメーカーの親睦会が2016年にあって、そこで初めてお会いしました。
Atsuo:TOKIEさんもその集まりで初めてしゃべったのかな。そこからシュガーさんがライヴに来てくださったり、だんだんつながりでできていきました。もともとBuffalo Daughter、好きでしたしね。『New Rock』のレコ発とか行きましたもん。
■意外なようなそうでもないような。ともあれ90年代的なお話ですね。
Atsuo:自分のなかではBuffalo Daughterはインディペンデントな位置づけ。ゆらゆら帝国などともに認知度が高かったですし、そういう日本の状況からの影響も当時は受けていました。
■シュガーさんの手が入ったことでもっとも変化したのはどこでしょう?
Atsuo:エレクトロニカというか電子音的なアプローチはシュガーさんの手腕です。ローが利いたキックであるとか。でも聴いてすぐにおわかりになる通り、僕らの演奏にはグリッドがないんですよ。録音はスタジオで適当に録っているのでリズムも揺れまくっているんですが、それを前提にシュガーさんは縦の線をプログラムしてくれてバンドのノリに合うような感じでアレンジを追加してくれました。曲の構造はほぼ決まっていましたが、シュガーさんに、曲の間口を広げてもらったというか、見える、聴けるアングルを増やしていただいたという感じです。サウンド・プロデュースの依頼ではありましたが、曲が並んで、今回の個展はこんなテーマなんだ、というようなものが見えてきたとき、どのようにプレゼンテーションしてもらえるのか? そういった感覚です。
■ちなみにボリスがいままでやってきた外部との協働作業というと――
Atsuo:成田忍さん、石原洋さん、NARASAKIさんにも1曲手がけていただいたことがあります。
Takeshi:あとはコラボレーションが多いですね。
[[SplitPage]]僕らはバンドというものに対するこだわりは強いですよ。だけど、バンドの運営や方法論で音楽の可能性が閉じられるのがイヤなんです――Atsuo
■さきほどAtsuoさんは自分が歌うとき、別のドラマーに叩いてもらっているとおっしゃっていましたが、フォーメーションみたいなもがどんどん変わっていっていいというお気持ちがあるということですか?
Atsuo:僕らはバンドというものにたいするこだわりは強いですよ。だけど、バンドの運営や方法論で音楽の可能性が閉じられるのがイヤなんです。
■でもそれはアンビバレンスですよね?
Atsuo:はい。だから基本この3人で音楽の可能性を広げたい、新しいものを追究して作っていきたいという思いもあって、シュガーさんへサウンド・プロデュースをお願いしたり、新しい血としてサポートのドラマーに入ってもらったり、以前は栗原(ミチオ)さんに入ってもらったこともありました。
■そうでした。最近なにかと栗原さんのお話をしている気もしますが、栗原さんが参加された『Rainbow』がペダル・レコードから出たのが2006年ですね。
Atsuo:その後で正式にサポートで入っていただいて、本格的にツアーをまわるようになったのは2010年から11年あたりでした。
Takeshi:栗原さんはサポートと言うよりも、僕らの認識としては4人目のメンバーだったんですよ。当時新しいアルバムのデモを作っていたときも、栗原さんがいる体でやっていましたから。
Wata:2014年の『Noise』だよね。
Takeshi:曲に必要なギター・パートが1本ではなくて2本、無意識にそうなっていたんですね。ある程度までかたちになってきたときに栗原さんが離脱しなくてはならなくなって、いままで作った曲をどうしよう?ってなったときに、4人のアレンジだったものを3人用にリアレンジをする必要になり、それでWataが死にそうになるという(笑)。
Wata:『Noise』の何曲かは栗原さんの音も入っているんですよ。デモで弾いていたテイクをそのまま使ったりしました。私は栗原さんと同じようには弾けないので、どうしようって(笑)。
Atsuo:3人であらためて完成形を作らなきゃならなかったので、それは大変でした(ため息)。
Wata:すごく助けてもらっていたので、いなくなったときは心細かったです。演奏面ではとくに。
Atsuo:でもあの時期があったのでWataもヴォーカルに集中できるようになった。
■ボリスは3人ともヴォーカルをとるのがいいですよね。
Wata:ヴォーカルというほど歌えているかはわからないですけどね。
Atsuo:さっき言っていたエフェクターメーカーのSNSでWataのことを「ボリスのギター、ヴォーカル」と紹介していたんですが、「いや、ヴォーカリストじゃないし」と本人がつぶやいているのを耳にした憶えがあります(笑)。
Wata:ヴォーカリストというよりは楽器的な感じ、ヴォイスという言い方が近いです。主張とかメッセージを伝える役割ではなくて、楽器の一部として存在している声ですね。
■でも『W』ではメイン・ヴォーカルをとっていますよね。プレッシャーはなかったですか?
Wata:最初から音響的という作品内でのイメージはあったので構えたりはしはなかったです。
■歌メロはWataさんが書かれた?
Wata:メロディはTakeshiです。
Atsuo:ほとんどの手順としては楽曲ができあがって、仮の歌メロをTakeshiがインプロで作って、曲ごとに見えたテーマをもとにふたりで歌詞を書くんですけど、Wataが歌うという前提だと出てくる言葉も違ってきますよね。
Wata:私は歌詞にはタッチしていないですけどね。ふたりが書く詞も、言葉で風景が見えてくるような内容なんですね、主張とかメッセージではなく。
Takeshi:逆に『W』では自分だと歌わないような言葉を歌わせることができたともいえるんです。Wataの口から出てくるであろうと想像した言葉だったり旋律などを使えたりしたので。
Atsuo:歌詞においてはWataの担当は「存在」ですよね。
■歌詞も全員で書いているというイメージなんですね。
Atsuo:その点もKiliKiliと考え方が通じているんですよ。僕らは楽曲の登録も連名なんです。たとえばWataはじっさい歌詞を書いていないけれども作詞者はバンドとして登録しています。それはWataの存在があるからその言葉が生まれてくるという理由です。バンドというのはそういうものだと思うんです。
■それならメンバー同士のエゴがぶつかって権利問題に発展するということもなさそうです。
Atsuo:エゴを聴きたいリスナーもいるとは思うんですよ、誰が曲を担当し、歌詞を書いているのかということですよね。そこをはっきりさせたいリスナーは多い気がします。
■レノン、マッカートニーもそうですし、はっぴいえんどでも細野さんの曲と大瀧さんの曲は違いますから、そういう腑分けの仕方も当然あるとは思うんですが、ボリスの場合みなさんはキャラが立っているのにエゴイスティックな打ちだし方はしていないですよね。
Atsuo:自然とそうなったんですが、共通している考え方は、いちばん大事なのは「ボリス」という存在、バンドということなんですよね。
■そのスタンスをとりながら、今年で――
Atsuo: 30年。
エゴという意識は僕らは薄いと思いますね。自分にとって音楽、曲というのは、言いたいことを言う場ではないんですね。曲のかたちがだんだんできてきて、仮のメロディを乗せたときに、「こういう言葉が乗るよな」と導かれるというか委ねるというか。――Takeshi
■30年といえば、ひとつの歴史ですが、長くつづけてこられた秘訣はなんですか?
Atsuo:さっきも言ったようなエゴとかが音楽の可能性の狭めるのが僕らはイヤなんです。
■そこもCANと同じですね。リーダーがいない、けっして誰かが中心ではない。
Atsuo:傍から見たら僕がリーダーに見えるかもしれませんが、いちばん雑務をしている、ただのアシスタントなんですよ(笑)。
与田(KiliKiliVilla):その考えを持っているだけでバンド内の格差を生まなくなりますよね。イギリスはバンドに権利が帰属することが多いですが、日本だと作詞作曲で個人を登録する習慣があります。そういったことを長いことみてきて、イヤな思いもしてきたから若いバンドにこういう登録の仕方があるから、そうしてみない?とアドバイスすることもけっこうあります。ボリスはそれを自分たちでやっていたという驚きはありましたよね。
■日本の場合芸能界の習慣ともいえますよね。
Atsuo:だからバンドの地位が低いといいますか、フロントマンとバックバンドという序列のヒエラルキーになっていく。そういうビジネスモデルが主体になっている気がします。
Takeshi:エゴという意識は僕らは薄いと思いますね。自分にとって音楽、曲というのは、言いたいことを言う場ではないんですね。曲のかたちがだんだんできてきて、仮のメロディを乗せたときに、「こういう言葉が乗るよな」と導かれるというか委ねるというか。音にしても、僕はほっとけば、ガンガン弾き倒しちゃうんですよ。でも、バンドやとその音楽を主体に考えれば、曲がそうなりたいであろうというコードストロークや弾き方に自然になっていきますよね。楽器をもっているミュージシャンのエゴではなく、楽曲のほうへ自分を寄せていくというか、ボリスで音楽を作っているときはそういう感じになっていますね。
Atsuo:CANとの違いは音楽的な教育を受けているかどうかということかもしれないです。僕らは独学ですからね。外部とは共有できるかはさておき、バンド内での音楽言語はいろいろあるんですけどね。
■とはいえ共演は多いですよね。秋田昌美さん(MERZBOW)、灰野(敬二)さん、エンドン、カルトのイアン・アストベリーなど、ボリスはいろいろなバンドやミュージシャンと共演していますが、他者と同じ場を作るには共通言語を見出す必要があるんじゃないですか?
Atsuo:秋田さんは誰とでもできるし、誰とでもできないと言えますからね。
Takeshi:秋田さんとやるときはおたがい干渉していないよね。
Atsuo:それもエゴがないということなのかもしれないですね。自分たちの曲を放り出していますからね。秋田さんで埋め尽くされてもぜんぜんかまわないというか、それで自分たちの曲が新しく立ち上がる感じを聞きたいというのがまずあるので。シュガーさんにしてもバンドのグリッドレスな感じを尊重してくれたので、『W』ではうまくいったんだと思います。
■ボリスにとって今年はアニバーサリーイアーですが、アメリカ・ツアーのほかに計画していることがあれば教えてください。
Atsuo: 『W』もKiliKiliで30周年記念第1弾アルバムと言っているので、第何弾までいけるか挑戦しようと思っています(笑)。アルバムはだいぶ録り進んでいるし。
■KiliKiliからは昨年暮れに「Reincarnation Rose」が出ていますが、あれを聴くとやりたいことをやったらいいやという感覚を受けますよね。極端なことをいえば、売れなくてもいいやというような。
Atsuo:そもそも売れようと思ったことはないですよ。
■とはいえ「Reincarnation Rose」もメロディはキャッチーじゃないですか。
Atsuo:キャッチーさは大事ですが、売れたいというのは違うんですよね。ヘヴィな曲でもキャッチーかそうでないかという判断基準がある。楽曲の世界観がしっかり確立されたとき、初めてキャッチーと言えるのかもしれないですね。
■さきほどソドムとか栗原さんとかの話が出ましたが、70年代、80年代、90年代とつづく東京のアンダーラウンド・ロックシーンの牽引車は片やボリス、片やゆらゆら帝国というような見え方もあると思うんですよ。このふた組にはアンダーグラウンド、モダーンミュージックのようなセンスをポップアートにしているような側面があると思うんですね。ゆらゆら帝国とボリスはぜんぜん音楽性が違うけど、出てきているところってすごく近いところだったりするじゃないですか?
Atsuo:同じスタジオを使っていたり、近いようで遠い感じですか。いちばんの違いはメタル以降の文脈だと思うんですね。
■ボリスはメタルにもリーチしていますよね。
Atsuo:海外では完全にメタル・バンドあつかいですね。
Takeshi:自分たちでメタルだと言ったことはないんですけどね。でも向こうから手を差しのべてくるんですよ。
■メタルにもいろいろありますが、どのようなメタルですか?
Takeshi:メタル・シーンの裾野が欧米では広いというか、単純に規模が違います。
Atsuo:ドローン・メタルというジャンルがあるんですよね。僕らはそのオリジネイター的な扱いではありますね。SUNN O)))とかですね。あとはシューゲイズ・メタル、シューゲイズ・ブラックという呼び名もあって、そういった風合いも感じさせるようで、総じてポスト・メタル的な言われ方をします。
Takeshi:何かと後ろについてくるんですよ、メタルって(笑)。
Atsuo:日本と海外だとメタルという言葉がカヴァーする領域に差があると思うんですね。向うはものすごく広い。あのスリル・ジョッキーがメタル的な音楽性のバンドをリリースするくらいですから日本とは捉え方が違いますね。
■日本だとどうしても様式的なものというイメージが強いですよね。
Takeshi:いわゆるカタカナの"ヘビメタ"のイメージなんですよね。
Atsuo:僕らは速く弾くよりはシロタマを伸ばしたいほうなので(笑)。もっとオーガニックなんですよね。音を伸ばしてそこでなにが起こってくるかというドローン・ミュージック的な方法を結果的にメタルに取り入れている。
■一方でアメリカには日本のアンダーグラウンド・ロックの熱心なリスナーも多いですよね。
Atsuo:かつては音楽好きが最後のほうにたどりつく辺境という位置づけでしたよね。
■いまではボリスや、それこそメルツバウやボアダムスのような方々の活躍で日本のアンダーグラウンド・シーンは一目置かれている気もします。
Atsuo:でも気をつけておきたいのは、一目を置かれると同時に大目にみられている部分もあるんですよね。日本人だからメチャクチャやっても許されるというか。
■それを期待されているともいえないですか?
Atsuo:並びがボアダムス、ギター・ウルフ、メルト・バナナですよ。ルインズにしても。
■ややフリーキーな音楽性ですが、いい意味で根がないからからフリーキーさなんじゃないですか?
Atsuo:それはそうかもしれない。
■ボリスも、みなさんの佇まいも相俟って欧米の観衆に独特な印象を与えるのではないでしょうか? Wataさんなんかはすでにアイコニックな存在だし。でも「Reincarnation Rose」のMVはもうちょっと説明があってもいいかと思いました。
Wata:私以外のメンバーもあのなかに女装して参加していると思われていますよね。
■そう思いました。検索してはじめて知りましたよ。
Atsuo:けっこうちかしい友だちからもAtsuoとTakeshiはどこにいるの? って訊かれましたもん。
■ついにマリスミゼルみたいになるのか、いまからその展開は逆に攻めているというか、真の実験性とはこういうことをいうのだろうかと、いろいろ考えましたよ。それもアーティスト・エゴの薄さからくる展開なのかもしれないですね。あれは反響も大きかったですよね?
Atsuo:すごかったですよ。最初に写真を公開したときは、「ボリス、ヴィジュアル期に突入」とか書かれました。発表前はコスプレとか言われるかなと思っていましたけどね。
■どなたのアイデアですか?
Atsuo:流れなんですよ。シュガーさんとTOKIEさんにMVに参加してもらうアイデアは最初からあったんです。それだったらドラムもよっちゃん(吉村由加)にお願いしようということになって。衣裳はpays des feesというランドにお願いして、TOKIEさんもWataも一緒にお店に行って衣裳合わせをして、メイクとウイッグに関してはビデオの監督のアイデア。当日ヘアメイクさんとかも入ってできあがったのがあれだったんですが、当日までメンバー自身どうなるかわからなかったです。
Takeshi:自分も知らなかった。PVの撮影だと聞いてスタジオに行ったら、あのメイクを済ませたみなさんがスタンバイしていて「えっ!?」って、なったんですよ。
Atsuo:写真を公開した直後の反応はこっちも不安になるような感じだったんですが、翌日にはMVが出て、音を聴いてもらえればふつうにロックですし、わかっていただけたと思います。
■30年経ってもまだまだノビシロあるな、ボリスと思いました。
Atsuo:(笑)。でもそんなふうにみなさんの頭のなかにいろんな考えが湧き起こっていたのだとしたら、やってよかったと思いますよ。