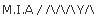the telephones We Love Telephones!!! EMIミュージックジャパン |
海外の新しいムーヴメントから意匠をかっぱらって、それを邦楽のリスナーにアジャストするように意訳、あるいは超訳して音を届けるバンド。いつの時代にもそんなバンドはいて、多くの場合は、洋楽系のリスナーから遠巻きに白い目で見られたりもしてきた。しかし、the telephonesはそんなステレオタイプな洋楽系邦楽バンドの枠組から外れて、新たなムーヴメントをこの国のシーンで巻き起こそうとする強い意志を前面に押し出してきた上昇志向の強いバンドだ。メジャーから2枚目のフルアルバムとなる『We Love Telephones!!!』は、そんなthe telephonesにとって正念場とも言える作品である。
彼らが過去に参照してきたニュー・レイヴやディスコ・パンクといったムーヴメントは、ここ数年で跡形もなく消え去ってしまった。同時に、the telephonesをめぐる状況は次第に熱を帯びていき、同世代のバンドとのイヴェントである〈KINGS〉や、精力的なツアー、フェス出演などを通して、彼らは新しいタイプのロックリスナーを開拓することに成功してきた。その背景には、かつてはこの国の若いリスナーの間でも機能していた、「洋楽に影響を受けた邦楽と出会う→その元にある洋楽を辿っていく」というリスナーの行動原理が働かなくなってしまったことの、幸福な副産物とでも呼ぶべき追い風があったかもしれない。いずれにせよ、the telephonesが現在の邦楽ロックのフロントラインに立っているのは事実だ。"あざとさ"を捨てた丸腰状態のままバンドの本質と向き合ったニュー・アルバム『We
Love Telephones』をたずさえて、彼らはここからどこへ向かっていこうとしているのか? フロントマンの石毛 輝を中心に、本音を交わしてきた。
要はいわゆるニュー・レイヴとかディスコ・パンクっていう流れのなかでやってた僕らが、それが終わったなかで何をやるのかっていうのがすごく大事なことだと思ってたんだけど、そこで開き直ってみたら意外にいい作品ができなって思って。
■まず今年の3月にナカコーのプロデュースによる「A.B.C.D.e.p.」をリリースして、4月に初のセルフプロデュースによる「Oh My Telephones!!!e.p.」をリリースして、今回のアルバム『We Love Telephones!!!』に至るわけですけど、この流れのなかで、the telephonesの音楽はどんどん解放されていったように思います。
石毛(VOX/GUITAR/SYNTHESIZER):曲としては全部同時に作ってたんですよね。「A.B.C.D.e.p.」と「Oh My Telephones!!!」用の曲が10何曲かあって、そこからナカコーさんといっしょに選曲していって、これはナカコーさんにやってもらう、これは自分たちでやるっていう感じで分けていって。
■じゃあ、ナカコーにある程度たくさんの曲を聴いてもらった上で、どの曲だったらいっしょにやると面白いかっていう判断からピックアップしていったのを最初にかたちにしたのが、「A.B.C.D.e.p.」ってことですか?
石毛:そうです。ずっとナカコーさんのファンだったから、純粋に「どれが好きなのかなぁ?」って訊きたい気持ちもあって。まだその時点ではこのアルバムの曲全部はまだ出揃ってなかったんですけど、たとえば"I'll Be There"(『We Love Telephones!!!』収録)なんかはその時点でもうあった曲で、「この曲やりたいな」ってナカコーさんが言ってて。
■「A.B.C.D.e.p.」の時点で、アルバム『We Love Telephones!!!』までの構想はかなり明確にあったんですね。
石毛:そうですね。その時点でアルバムの設計図はあったら、全部が同時進行です。the telephonesのやることは、つねに「確信犯だ」って言われたいんですよね。
■そういう意味では、ナカコーから「盗めるものは盗んでやろう」っていう意図もそこにはあったりした?
石毛:あぁ、それはもう、もちろんありましたよ。去年アルバム『DANCE FLOOR MONSTERS』でメジャー・デビューして、あれはある意味、僕らの勢いだけをパッケージした、いちばん濃い部分だけを絞って出したようなアルバムだったんで、その次に出す作品は、本来の自分たち――もともといろんなタイプの音楽をやりたかったバンドだったから――勢いだけじゃないものがやりたいなと思って。やっぱりiLLの作品を聴いたらわかるけど、ナカコーさんの作品って音がすごくいいじゃないですか。シンセもたくさん使ってるし。だから、これまでの自分たちの作品では作れなかった音像が、ナカコーさんだったたちゃんと作れるんじゃないかなと思って。で、もちろんその過程で、いただける技術は盗んじゃおうと思って(笑)。
■その意図を隠すこともなく?
石毛:そうそう。もちろん、僕も隠さずに「教えてください!」って言うし、ナカコーさんも隠さない、ものすごくオープンな人だから。音楽に限らず、あまり詳しいことは言えないけど(笑)、いろんな動画とかもすぐに焼いてくれたりとか。the telephonesのレコーディング以外でもiLLの現場に行かせてもらって、機材をどうやって使うのか、音をどう作るのかとかも教えてもらって。しっかり盗みましたね。まぁ、盗みきれてないとは思うんですけど、いままでわかんなかったことがわかったのは大きかった。ものすごい勉強になりましたね。
■それは、その次の段階として、「Oh My Telephones!!!」と、『We Love Telephones!!!』収録曲における初のセルフ・プロデュースというチャレンジを見据えてのこと?
石毛:もちろんそれもありますけど、それをそのままナカコーさんからの影響でやったらあまり意味もないと思ってて。あくまでセルフ・プロデュースでやる上での助言というか、アドヴァイザー的な存在として考えてました。あんまりそこに頼っちゃうと、自分たちでやる意味がなくなってしまうから。でもまぁ、ぶっちゃけ、録り終わった後にいっかい聴いてもらって、「大丈夫ですかね?」って相談はさせてもらいましたけど(笑)。
[[SplitPage]]まぁ、タナソーっていうか、そのへんのメディアの人たちやリスナーも含むすべてに対して。でも、そういうネガティヴな感情もつねに持っていたいというか、それがなきゃダメなんですよね。
■あらためて、この『We Love Telephones!!!』をどういう作品にしたいと思ってたのかについて、メンバー全員に訊いていきたいんですけど。
岡本(SYNTHESIZER/COWBELL/CHORUS):まず最初に石毛が曲を持ってきて、それをスタジオで流してっていう作業をこの5年間ずっとやってきた中で、今回はこれまで以上にとにかく曲がいいなっていう印象があって。だから、今まで結構作品ごとにコンセプトがガチガチにあったんですけど、今回は自由に、いい曲はいい曲でどんどん入れていくみたいな感覚でみんなで作っていった感覚ですね。
松本(DRUMS):もちろんそれぞれの曲にはテーマとかもあるんですけど、それを前面に出していくんじゃなくて、まず音楽として楽しくやれたらなって思ったんで。自分たちのスタイルで演奏していったら、それは自然に自分たちだけの音楽になっていくんだなって。それは、作っててそう思ったというより、作品が完成してみて気づかされたことですけど。
■前作の『DANCE FLOOR MONSTERS』はリスナーが求めているところに思いっきり直球を投げた作品だと思うんですけど、そういう意味では、今回は思いっきり自分たちのやりたいものをやりきったってこと?
岡本:そうですね。自分たちがもともともっていたいろんな音楽的な要素を、ただ好きなように表現するっていう、なんだか簡易な話になっちゃいますけど、そういうことだと思うんです。やってみたい音楽っていうのは本当にたくさんあって、たしかに『DANCE FLOOR MONSTERS』みたいなアッパーで単純に踊れるロックっていう部分も僕らのなかにあったものだけど、今作みたいにいろんなサウンドやメロディが混在している方が、より自分たちらしい作品って言えるんじゃないかと思います。
長島(BASS/CHORUS):たぶん、『DANCE FLOOR MONSTERS』のツアーをやってたときに、「ここでもっとこういう曲があったら良かったのにね」っていうことを石毛が言っていて、もしかしたら今作はその欠けたピースを埋めていくものっていうか、いままでライヴやってきてもっとこういうのもやりたいっていう思いが、今回の楽曲たちが繋がったんじゃないかなって思います。だから、今回はプレイしてて楽しい曲が多いし、いい意味で力を抜いてできたんですね。作っていく作業の段階から。みんな楽曲がすごく気に入ってたら、逆にすげぇ気合い入れて作らなきゃっていうよりかは、「おぉー! この曲いいね!」っていう感じで、みんなでワイワイやってるうちにできていったような感じです。
■これまでとは違ったタイプの曲が生まれてきた、その背景にあったのはどういう思いだったんですか?
石毛:さっき宇野さんが言った通り、『DANCE FLOOR MONSTERS』は求められている場所に思いっきりボールを投げた作品だったので、次も勢いだけで作ったら完全にこのバンドは終わるなぁって思ってたんですよ。じゃあ、もともとこのバンドでやりたかったことって何だったんだ?ってことに立ち返った作品をこのセカンドでやろうと思って。具体的には、the telephonesってインチキディスコって自分たちで言ってきたバンドだけど、ちょっとずつ、もうちょっと濃いダンス・ミュージックの要素も入れていこうかなって。でも、同時にポップであること、勢いのあることっていのもthe telephonesの音楽の重要な部分だから、そこに関してはギリギリのところまで詰めていきましたけど。作品を作っていくなかで、迷いがどんどん消えていった感覚がありましたね。
■インディーズ時代のアルバム『JAPAN』は、当時のニュー・レイヴをはじめとする同時代の洋楽とリンクするようなサウンドを無邪気に出していた作品で、『DANCE FLOOR MONSTERS』はメジャーというステージで自分たちがそのタイミングで切れる最も有効なカードを切った作品だったと思うんですけど。
石毛:そうですね。だから、今回は『JAPAN』を作ってた頃の衝動に近いものがあったんですけど、当然、あの頃よりも洗練されてるし、当時は知らないことが多すぎたから。単純に、いま考えるともっと合理的にできるだろってことを悪戦苦闘しながらやったっていう、そういう楽しさが当時はあったんですけど。今回はその頃の無邪気な気持ちのまま、格段にクオリティが上がったものを作れたかなって。それと、あの頃と違って、いまはもう洋楽との同時代性っていうのは、僕はもうぶっちゃけ全然気にしてなくて。というのも、いまは日本でも、自分のまわりにものすごくカッコいいバンドが増えてきて、洋楽に対して変な劣等感を感じなくなってるっていうか。いまの日本の20代でバンドをやってる連中のなかにも、こんなカルチャーがあるんだよっていうのをちゃんと示したほうがカッコイイんじゃないかって思って。迷いが消えたっていうのはそこかもしれないですね。ほんとに胸を張って「日本のバンドです!」って言えるようになった気がする。
■なるほど。それといま、同時代性って言えるほどの音楽性だけでくくれるシーンみたいなものって、海外のロックバンドのなかにもないですよね。いいバンドって、もう、個々がそれぞれ勝手にオリジナルなことをやってるっていう状況で。それはイギリスに限らず、ブルックリン周辺のバンドもそうだし。精神性で繋がってる部分はあるのかもしれないけど。
石毛:うんうん。それはほんとにそうだなぁと思って。だから、要はいわゆるニュー・レイヴとかディスコ・パンクっていう流れのなかでやってた僕らが、それが終わったなかで何をやるのかっていうのがすごく大事なことだと思ってたんだけど、そこで開き直ってみたら意外にいい作品ができなって思って。開き直ったっていうのが、いちばん気持ち的にでかいですね。もうパクらなくていいやっていう(笑)。
■でも、かつてthe telephonesにニュー・レイヴやディスコ・パンクってレッテルが貼られたことは、the telephonesの音楽に対していちぶのリスナーにいろんな先入観を与えることにもなったけど、逆にそこをうまく利用してきたって部分もありますよね。
石毛:うん。それはもちろん自覚してますし、否定するつもりはないです。みんなで蛍光カラーのパーカーを着たりしてね(笑)。
■自分が初めてthe telephonesのライヴを見たのは2年前の2008年でしたけど、そのときに印象的だったのは、他の日本のギター・ロックのバンドのライヴに集まってるオーディエンスとは、全然違うオーディエンスの層をつかんでるんだなってことで。ちゃんと新しい現場を作ってることを実感したんですね。
石毛:いわゆるTシャツとデニムでタオルを首に巻いてるようなロック・キッズ以外の人が、ライヴハウスにたくさんいたっていうことですよね?
■そうそう。かわいくてオシャレな子がライヴハウスにいる! っていう(笑)。
石毛:2008年はそういうムーヴメントを小さいながらも作れて、すごく駆け上がっていった実感を持てた年でしたね。普段は全然音楽を聴かないような若い子達に、そういう文化を少しでも伝えられたっていう実感があった。でも、そんなのはすぐ終わるとも思ったんで。次はどうしようってことばかり考えてましたね。
■そして、メジャーに行くという選択をしたわけですよね。
石毛:うん。そこでとりあえずファッションとしてのニュー・レイヴは捨てようと思って、みんな思い思いの格好をしはじめたんですよね。僕はヒッピー崩れみたいな格好をして髪が伸ばしっぱなしになって、ノブちゃん(岡本)はゲイみたくなって、(長島)涼平は可愛くなって、(松本)誠治くんはラーメン屋みたいになった(笑)。
一同:あははははは!
石毛:ファッションに縛られるバンドじゃマズイだろっていうのと同時に、メジャーシーンでこのまま何年やれるのかっていう不安と期待があって。せっかくだからそこでシーンをひっかきまわすと同時に、ムーヴメントを作れたらいいなって思って。日本独自のシーンっていうのをすごく意識するようになりましたね。その前後に、KINGSというイベントも軌道に乗るようになって。
■興味深いのは、the telephonesを遠目で見ていたような人たちにとっては、「ロックで踊る」っていう〈KINGS〉ってイヴェントのコンセプトって、ニュー・レイヴやディスコ・パンクの延長として見られてた感が強いけど、いっしょに〈KINGS〉をやっているTHE BAWDIESも言ってましたけど、実はそこには90年代末の〈AIR JAM〉がひとつの理想形にあるんですよね。
石毛:うん。時代が時代なら、それこそ〈AIR JAM〉にいたようなキッズたちを、いまの僕たちは巻き込んでるのかもしれないですしね。僕らのライヴでダイヴとかモッシュが多いのも、きっとその時代の名残だと思うし。でも、自分としてはやっぱり、もっとライヴハウスとクラブの現場が――ここでいう現場っていうのはロック系パーティのことだったりするんですけど――混ざって欲しいって思うんですよね。だから、自分も大きなロックフェスとかに出たときに、ステージから「現場に行け!」って言うんですよ。まるで、ワールドカップのデンマーク戦に勝った後の長谷部みたいに(笑)。
■「Jリーグにも足を運んでください!」みたいな?(笑)
石毛:まぁ、そこまではカッコよくないかもしれないけど(笑)、言わなくてもいいのにどうしても言ってしまう。それは、もっと音楽を自由に楽しめる現場を作りたいからなんですよね。〈AIR JAM〉の世代の人たちがモッシュとダイブというのを文化として定着させたわけですけど、僕らの世代はそういう立ノリじゃなくてもっと横ノリの、踊るっていう文化をロックのオーディエンスに広げられないかなって。そうしたら、時代と時代が分断して横軸しかないような日本のロックシーンにも、ちゃんと縦軸のようなものができるのかなって思ってて。
[[SplitPage]]たとえば僕は高校を途中で辞めて死ぬほど退屈だったんですけど、唯一音楽だけはほんとに好きだったからライヴハウスで働き続けて、なんとかここまで生きてきたっていう、本当に音楽に救われたっていう実感を持ってるんですけど。
■たとえば、これはele-kingだから敢えて訊きますけど、the telephonesが歌ってるダンスフロアと、ele-kingの読者がイメージするダンスフロアっていうのは、違うものじゃないですか。
石毛:たぶん、真逆ですね。
■それによって偏見を持たれるのは不本意なことだったりします?
石毛:うーん......。でも、どっちの現場も健全だし、そんなに違うとは思わないんですよね。ドラッグもないし。だから、どっちもあってよくて、それが混ざるのが一番いいと思うんですけど......なかなか水と油だから、どうなんでしょうね。その架け橋的なバンドになればいいなぁとは常々思ってるんですけど。
■今作『We Love Telephones!!!』はいきなり「I Hate DISCOOOOOOO!!!」という怒りを表明した曲で始まるわけですが。この怒りの矛先はいまの音楽シーンに対して? それとも、社会全体に対して?
石毛:全部ですね。たまにすべてのものが嫌いになることあるんですけど、「I Hate DISCOOOOOOO!!!」の"僕を打ちのめしたとこで何の意味がある?""自分じゃできないくせに"というラインは、完全に田中宗一郎に言ってます(笑)。
■(笑)。
石毛:まぁ、タナソーっていうか、そのへんのメディアの人たちやリスナーも含むすべてに対して。でも、そういうネガティヴな感情もつねに持っていたいというか、それがなきゃダメなんですよね。すごく充実して幸せを手に入れると不安になっちゃって、これは全部嘘なんじゃないかと思うような人間なんで。
■いろんな批判もあるんだろうけど、言ってみればthe telephonesって、最初から隙だらけのバンドだと思うんですよ。
石毛:そうそう。ツッコミどころがいっぱいある。こんなに隙だらけなんだから、打ちのめしたところで何の得もないよって言いたい(笑)。
■打ちのめされても、ヘラヘラ笑いながらまた立ち上がってくるような、そういうタフさを持っているバンドだと思うんですけどね。だから標的になりやすいのかな?
石毛:そうですね。そういう部分はタフになったような気がしますね。
■もともとthe telephonesはメディア主導ではなく、現場から火のついたバンドだっていう、そこの自負もあるんじゃないですか?
石毛:それもありますけど、現場から生まれた僕らも、結局はメディア主導のフェスにのっかってるっていう現状もありますからね。それは僕らだけじゃなくて、他のバンドもそうですけど。別にそれが悪いって言いたいわけじゃないけど、もっと〈AIR JAM〉がやったみたいに、自分たちだけで磁場を作れるんじゃないかって思いはあるんですよね。せっかくここまで状況を作ってきたんだから、ついてきてくれるオーディエンスもいるんじゃないかって。そろそろ何かを仕掛けていかなくちゃなって。20代のうちになにかデカいことをやりたいなって思ってます。
■そういうthe telephonesの持ってるカウンター意識って、あまりファンのあいだにも伝わってないような気もするんですけど。
石毛:表現の根本には、いつもラヴがありますからね。すごく理想主義的な部分が大きいから。僕たちって尖ろうとしても、結局は4人の人間性に部分で、どうしてもラヴとかピースな感じになるんですよ。
■今作『We Love Telephones!!!』も、曲によっては"HATE"とか"DIE"とかっていうネガティブなフレーズも耳に残りますけど、基本的にはすごくラヴとピースな作品ですよね。
石毛:そうです。基本的にthe telephonesのテーマは愛と自由だと自分は思ってます。
■愛と自由をこの2010年の日本で歌う意味は、どこにあると思います?
石毛:いま、バンドであんまり愛を歌うバンドっていないと思うんですよね。個人的な内面の葛藤とか、そんなのばかりが幅を利かせていて。自分もそんなにすげぇ考え込んだ上で、「愛と自由」だって思ってるわけじゃないから、ちょっと答えづらいんですけど......やっぱり、まだバンド・シーンは終わってないっていう希望の火をつけたかったっていうのがあって。これから音楽をプレイする若い子にも、音楽でもメシは食えるよっていうのを伝えたいのがある。いまってなんとなく、日本の音楽シーン全体が、メインストリームもアンダーグランドも、どんどんコアなものになっている気がするんですよね。
■CDを買うという行為そのものが、マニアックな行為になってきてますからね。
石毛:でも、そんな時代でも普通の人がバンドをやってもいいんだよ、選ばれた人しか音楽をやっちゃいけないわけじゃなくて、普通の人間でもバンドはできるんだよっていうのを証明するバンドになりたいんですよ。それが結局は、愛と自由に繋がってるんじゃないかな。だから、いまの世界が退屈で死んじゃうよっていうような人たちに自分たちの音楽を届けたい。この気持ちが正確に届くかどうかわかんないですけど、たとえば僕は高校を途中で辞めて死ぬほど退屈だったんですけど、唯一音楽だけはほんとに好きだったからライヴハウスで働き続けて、なんとかここまで生きてきたっていう、本当に音楽に救われたっていう実感を持ってるんですけど。だからいま、学校も仕事も行かずに時間を持て余してるスーパーニートみたいな人がいたら、別に僕らの音楽じゃなくてもいいんだけど、誰かの音楽を聴いてそれに救われるような体験をしてくれればいいなって。まぁ、それが自分たちの音楽だったらいちばん嬉しいんだけど。
[[SplitPage]]だからね、ele-kingを読んでるような音楽をすごくよく知ってるような人たちに、「やっぱthe telephonesってクソだね」って言わせちゃうくらいの、そういうバンドになっていきたいですね。それでも、「あの曲はいいよね」みたいな。
■いまのtelephonesの現場には、ニートっぽい子はたくさんいる?
石毛:いや、全然いない。リア充ばっかだと思う。2ちゃんねるのスレッドとかも大して書き込みもないし(笑)。だからもうちょっと腐ってる奴らがいてもいいなって思うんですけど、逆に言うと、もう腐ってる奴らが聴きたいとは思わない音楽になっちゃったのかもしれないですね。それはたぶん、これまでの僕らのやり方があざとすぎたのかもしれない。でも、そのへんの連中に嫌われてもいっかいちゃんと上に行く必要があったと思うし、まだまだ上に行きたいところはあるんで。それが一段落したら、もういちどそこらへんにいる人たちに問いかけたいって気持ちは強いですね。
■自分で自分のことを「あざとかった」って言うのはそれだけ客観視できてるってことだと思いますけど、あざとさっていうのは、どこかでツケを払う必要があると思うんですよ。そういう意味で、今回の作品はそのツケを払ったような、丸裸の作品になってるのかもしれないですね。
石毛:なってるのかな? 基本的にはツケを払ったつもりではいるんだけど、もっといいツケの払い方もあると思うんですよね。これまで誤解させたきたところをどうやって解いていくか、それは難しいことなんですよね。でも、バンドが上に行くにはそういうこともしなきゃいけない。音楽がカッコよければ売れるっていう時代はやっぱり終わったと思うんで、自分たちがいいと思う音楽をどうやって広げていくか、あらゆる手段を講じるしかないと思うんですよ。で、そういうことに対して自分は積極的な人間だから、何でもやっていこうと思ってます、いまは。それが度を超えると、精神的にはつらくなったりもするんですけど。
■それは、別にこれまでのリスナーを裏切ってきたとか、裏で舌を出していたとか、そういうことじゃなくて、自分たちの音楽を限定した形でしか伝えてこなかったことに対するしんどさですよね?
石毛:そうですね......あぁ、そうかもしれない。うん、そうですよ! そうだわ!
一同:あはははははは!!
石毛:そういう意味で、今回の作品でようやく解放されたのかもしれない。いや、完全に腑に落ちたました(笑)。だからね、ele-kingを読んでるような音楽をすごくよく知ってるような人たちに、「やっぱthe telephonesってクソだね」って言わせちゃうくらいの、そういうバンドになっていきたいですね。それでも、「あの曲はいいよね」みたいな。たぶん、全曲好きになるのは難しいだろうけど、「the telephonesクソだけど、この曲だけはいいよね」っていう、それぐらいの耳のあるリスナーといっしょに走っていきたいですね。つねに時代と同期しながら新しいことをやっていきたいし、なるべくならその最先端を走りたい。基本的に人を引っ張ることは嫌いだけど、いまは引っ張ってもいいよって気分、なんでも背負ってもいいよって気分なんで。いろいろ背負うかわりに、先を走らせてくれっていう感じですね(笑)。