地域密着文化フェスティヴァル、(( ECHO KYOTO ))。6月にジェシー・カンダを迎えて開催された同イベントですが、2回目となる今回は、京都の電子音楽レーベル〈shrine.jp〉の20周年記念企画。しかもスペシャル・ゲストとして、なんと〈Mute〉の創始者であるダニエル・ミラーの参加も決定! これはなんとも気になる組み合わせです。12月3日はぜひとも京都METROまで足を運びましょう。なお、〈shrine.jp〉は20周年を記念した全国ツアーも開催するとのことで、詳細は下記をご覧ください。
[11月29日追記]
本日、(( ECHO KYOTO ))のタイムテーブルが発表されました。こちらからご確認ください。また、イベント直前の12月1日(金)には、ダニエル・ミラーがDOMMUNEに出演することも決定(20:00~21:00)。弊誌編集長の野田努も出演します。お見逃しなく!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(( ECHO KYOTO )) にMUTE創始者ダニエル・ミラーの出演が決定!
shirine.jp 20周年記念 × ダニエル・ミラー(MUTE)
2017.12.3 (Sun) @METRO
特別先行早割チケット、本日23日より発売開始!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(( ECHO KYOTO ))
shirine.jp 20周年記念 × ダニエル・ミラー(MUTE)
12月3日(日)に京都METROで行われる (( ECHO KYOTO )) に、〈MUTE〉レーベル創始者のダニエル・ミラーの追加出演が決定した。なおダニエル・ミラーは、TOKYO DANCE MUSIC EVENT(11月30日~12月2日)にてカンファレンスへの登壇とWOMBでのDJ(12月1日)を行うことが決定している。

電子音楽界のパイオニアにしてゴッドファーザーであり、過去40年の音楽世界史における最重要人物のひとりであるダニエル・ミラーと、糸魚健一主宰の京都を代表する電子音楽レーベル〈shirine.jp〉20周年を記念してレーベルゆかりのアーティストが出演! 京都と世界の電子音楽が会場のMETROから京都盆地にこだまして、脈々と続く京都の電子音楽史にまた新たなページが加わることでしょう!
また本日23日(月)より2週間限定で特別先行早割チケットを発売する。
今年6月に行われた第1回目の (( ECHO KYOTO )) は、ビョーク、Arcaなどのビジュアルを手がけるジェシー・カンダによる「クラブを寺院化する」というコンセプトのインスタレーションが行われ大きな成功を収めた。今回が2回目の開催となる。
■公演概要
(( ECHO KYOTO ))
shrine.jp 20周年記念 × ダニエル・ミラー
2017/12/3 (Sun) @METRO
Open/Start 18:00
ADV ¥3,800 / DOOR ¥4,300 (共にドリンク代別途)
LINEUP:
ダニエル・ミラー (Daniel Miller)
Acryl (dagshenma + Madegg)
Hideo Nakasako
HIRAMATSU TOSHIYUKI
kafuka
Ken'ichi Itoi
masahiko takeda
TOYOMU
*出演者プロフィール詳細 https://trafficjpn.com/news/ek
★2週間限定!特別先行早割チケットを発売!!
¥3,300 ドリンク代別途
[受付期間:10/23 12:00~11/6 09:59] ←枚数限定!
※『特別先行早割お申し込み方法』→タイトルを「12/3 ECHO KYOTO 早割希望」として頂いて、お名前と枚数を明記して
・・・11/6 10:00より発売開始・・・
ローソン Lコード:54946
ぴあ Pコード:348-946
e+ https://eplus.jp/
※前売りメール予約:
上記早割チケット期間以降は、前売予約として、ticket@metro.ne.jpで、前売料金にてのご予約を受け付けています。前日までに、公演日、お名前と枚数を明記してメールして下さい。前売料金で入場頂けます。
==============================================

世界有数の文化都市 京都、その豊かな文化土壌において、真のアーティストによる比類なき地域密着文化フェスティヴァルを開催し、日本国内、そして世界へ発信する。
ECHO/ 廻向(えこう):参加アーティストと地域が作り出す卓越した表現がこだまし、広く人々に廻らし向けられる。
https://www.facebook.com/ECHOKYOTOECHO/
==============================================
「MUTEは偉大なレーベルのひとつだが、その偉業はポップと実験の両立のなかでなしえたもので、ことエレクトロニック・ミュージックの発展においてはもっとも重要な役割を果たしている。1978年に創設されたインディペンデント・レーベルが、いまだに刺激的で、いまだに冒険的で、そして相変わらずポップであるということは、偉業というよりも、もはや奇跡といったほうが適切かもしれないが、しかし、それこそがMUTEというレーベルなのだ」--- 野田努 (ele-king)
https://mute.com/
==============================================
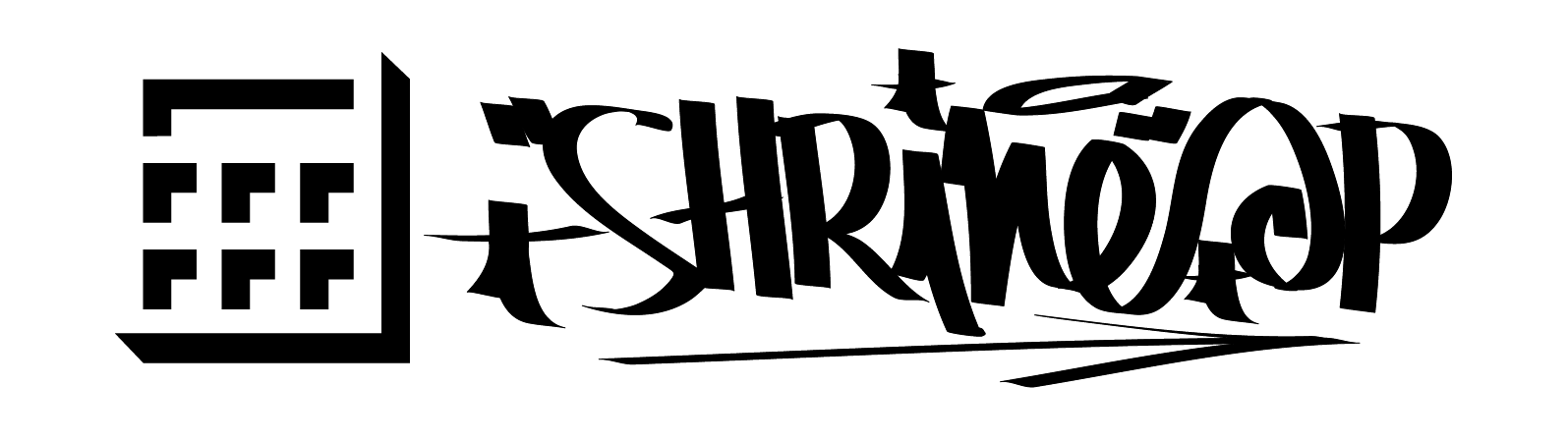
shrine.jp (シュラインドットジェイピー)
shrine.jpは、京都在住の電子音楽家 糸魚健一によるエレクトロニック・エクスペリメンタル・レーベルである。1997年に音楽への可能性への探究心を表現する為に発足された。これまでデザインとプロダクトを利用したメディア実験ともとれるリリースを繰り返してきている。
また、ダンスミュージックに特化するサブレーベルMYTHがある。shrine.jpが社、形あるもの、すなわちコンテンツ(内容)を主体とし、MYTHは話=コンテクスト(文脈)あるいはコンジャクチャ(推測)を示す。
www.shrine.jp
shrine.jpは20周年を記念し全国ツアーを行う。
日程は以下の通り。
shrine.jp 20th Anniversary Tour
12/2 shrine.jp 20th Anniversary Exhibition& Reception Party
@FORUM KYOTO
12/3 shrine.jp 20th Anniversary Tour in Kyoto
meets (( ECHO KYOTO ))
@METRO
12/21 shrine.jp 20th Anniversary Tour in Fukuoka
meets MIND SCAPE
@Kieth Flack
12/24 shrine.jp 20th Anniversary Tour in Sendai
Emotional electronic music for X’mas
@CLUB SHAFT
12/30 shrine.jp 20th Anniversary Tour in Tokyo
Grand Tour Final!
@KAGURANE



 発売日:2017年11月20日(月曜日)
発売日:2017年11月20日(月曜日)




