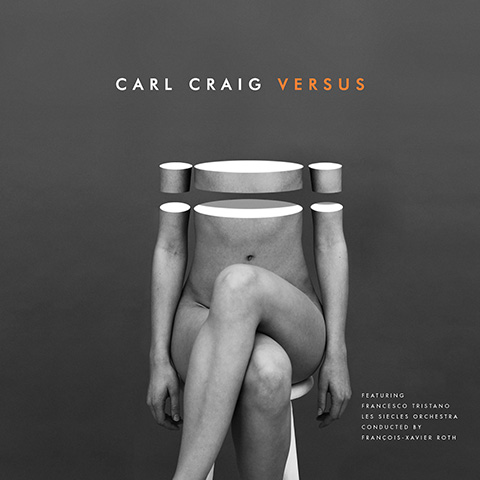『ジャパノイズ』の著者としても知られるアメリカの音楽学者デイヴィッド・ノヴァックはかつて、90年代後半からゼロ年代前半にかけて東京に出来したひとつの音楽シーンを、代々木Off Siteをその象徴として捉えながら日本発祥のまったく新しい即興音楽のジャンルとして「音響(ONKYO)」と呼んだ(1)――もちろんそこで挙げられた数名のミュージシャンたち、たとえば杉本拓、中村としまる、Sachiko M、吉田アミ、秋山徹次、伊東篤宏、宇波拓、そして大友良英らについて(ここに大蔵雅彦やユタカワサキをはじめとしてまだまだ加えるべきシーンの担い手がいたこととは思うが)、その多様な試みと実践を「音響」というただひとつのタームで括ってしまうことなどできないし、ノヴァック自身もおそらく批判を覚悟のうえで戦略的にそうした呼び方を採用しているようにみえる。それにそもそも「音響」と言い出したのはノヴァックが最初ではない。この呼称が日本語の読み方のまま世界的に流通していることからもわかるように、それが認知されるきっかけとなったのは日本語圏ですでにそうした呼び方がなされていたからだ。その起源は虹釜太郎が渋谷に90年代半ばに2年ほど構えていたレコード・ショップ、パリペキンレコーズのコーナーにあった「音響派」という仕切りにあると言われているが(2)、そこで扱われていた音楽は即興音楽シーンに限らずより広範かつ雑多なものだった(3)。だがいずれにしてもこの時期にそれまでの即興音楽とは質を異にしたニューウェーブとも言うべきいくつもの魅力的な試みがおこなわれていたことは事実であり、匿名的で、微弱な音量で、沈黙や間を多用するなどとしばしば言われる(4)ように、それらにゆるやかに共有されていた同時代性のようなものがあったということも指摘できるように思う。そしてそうした動向をリアルタイムで国内外へと発信し続けてきたウェブ媒体として「Improvised Music from Japan」があった。
もともとは「Japanese Free Improvisers」という名称で1996年に英語オンリーで開設されたこのウェブサイトは、その後日英二ヶ国語になり、日本で活躍する外国籍のミュージシャンも紹介するために名称を変え、さらにCDショップ兼レコード・レーベルとしても機能しはじめることとなる。2012年からは水道橋にイベント・スペースとしても利用できる実店舗「Ftarri」を構えることになる、その前身となったサイトである。それを独力で立ち上げ運営してきた鈴木美幸は、それまでジャズ評論家/翻訳家として執筆活動をおこなっていたのだが、この時期に出現したまったくジャズとは接点のない即興演奏を前にして戸惑いと驚きを感じ、そして途方もない魅力を覚え、すぐさま世界に紹介する役割を買って出た(5)。ウェブサイトに記載されるミュージシャンの数は日増しに増えていき(いま現在も増えている)、シンプルなページ・レイアウトも手伝って、膨大なアーカイヴを簡潔に参照することのできる類稀なメディアとして機能していった。そしてこのウェブサイトが日本の同時代的な即興音楽シーンを、殊に海外へと向けて発信していく重要な役割を果たしていったということは改めて述べるまでもない。そこには「音響」として括ることはできないにしても、しかし何らかの新しさはあった。ならばそれはいったいどのような新しさだったのか。
「Improvised Music from Japan」が紙媒体として発行している雑誌がある。2003年にその増刊号として、音楽家/批評家の大谷能生が責任編集を務めたものが出された。新しい世代の即興演奏家を紹介することがテーマになっていたその増刊号では、冒頭に、大谷による「Improv's New Waves ―論考―」(6)と題された文章が掲載されていた。そこでは多くの若手即興演奏家たちに「個人的な好みを排した、匿名的な音の世界」へと足を踏み入れていくことを厭わない傾向がみられるという指摘がなされ、さらにジョン・ケージもデレク・ベイリーも前提していなかっただろうものとして、しかし当時の(おそらくは現在も)先端的な即興音楽シーンの経験の基盤となっているものとして、録音メディアという装置を挙げながら、「これまでの音と音楽との区別がまったく役に立たないこうした世界を一旦受け入れ、そこからまた改めて『音楽』と呼べる体験を作り上げていくこと。即興演奏家とは、『音』と『音楽』とが現実に交錯する『演奏』の現場でそれを実践していくミュージシャンたちのことだ」と述べられ、そして次のように締め括られていた。
先ほど聞こえた音は、一体なんだったのか? 今聴こうとしている音は、一体どのような音なのか? 指先を緊張させながら鼓膜と思考を充分にゆるめる、または、思考を緊張させながら指先は脱力させるという相反する作業をおこなうことによって生まれるこうした問いを繰り返すことによって、即興音楽の演奏者は物質的持続の底の底へと降りていく。リ=プレゼンテーションに伴うすべての喜びと手を切ろうとする、こうした聴覚による世界の描写方法は、これまでのどのような芸術からも得ることのできない、まったく新しい現実との接点をぼくたちに提示してくれるだろう。(「Improv's New Waves ―論考―」)
録音装置というメディアは人間的な価値判断や聴取の可能性を度外視して、あるいはそれらとは無関係に、あくまでも物質の次元で響きを捉え記録するものであり、たとえば自由に織り成されていく即興演奏が、メロディ・ハーモニー・リズムといった西洋音楽を構成する要素を持たずとも、あるいはその他の組織化された音の秩序をあらかじめ備えていなかろうとも、録音されるというそのことが音楽の成立条件となることによって、そうした側面をまるごと預け、繰り返し聴くことのできる音楽として手元に残してしまうことができる。演奏家はそこで出す音の種類や音の出し方に縛られることなく、思い思いにサウンドと関わりを持つことができるようになる。経験の基盤となっている物質的な次元が、意味づけられる前の音響を聴き手としての演奏家に開示してくれるのだ。そこに「聴覚による世界の描写方法」が見出されていく。「まったく新しい現実との接点」が見出されていく。
大谷の論考にいち早く反応したのは音楽批評家の北里義之だった。彼は大谷の論考にいくつかの疑問を提起した(7)。するとそれに対する大谷の返答が「ジョン・ケージは関係ない」(8)という新たな論考としてまとめられ、さらに北里の再反論が「ケージではなく、何が」(9)という文章をも生むこととなり、とりわけ後者の論考は曖昧に乱用され続けてきた「音響」というタームについての再考を促し実相を炙り出そうとする極めて示唆に富んだものなのではあるが、ここではそれらのやり取りに関して深入りしない。一言添えるとしたら、大谷が個人主義を徹底させた先にある「匿名的な音の世界」を見出したことと、北里が「匿名的な音の世界」にモダンの原点そのものへの回帰を見出したことは、同じことがらを別の側面から考察しているに過ぎないということのように思う。だがここでは大谷が描いたシーンの情況について、北里がそれを「即興演奏が徹底して個の音楽であったことに対するアンチテーゼ」(10)だと読み取ったことに着目しておきたい。個人主義が徹底されようと、モダンの原点への回帰であろうと、そこにはそれまでの即興音楽が個と個の衝突やそれを過剰に濃縮することに価値を見出していたこととはまったく別の在り方があった。それはオフサイト周辺のシーンをつぶさに観察してきたイギリスの音楽家/批評家クライヴ・ベルの言を借りるならば、「肉体的なエネルギーや即効性のあるレスポンスよりも、リスニングとサイレンス、そして忍耐力を前面に押し出していた」(11)のである。そして「個の音楽」から離脱していくなかで見出されたのは、共演する際に単に個と個が対峙するだけではなく、「まわりの空間の、ほかのたくさんのものの一部」(12)として捉え返されるような共演者の在り方でもあった。ここに聴取と同様に新たな価値が見出されたことがらとして空間を付け加えることもできる。そこでは「アカデミックな場所にはいないバンドマンたちが、初めて空間を問題にしだした」(13)のである。
あれから14年もの歳月が流れている。その間にも様々な試みがなされてきた。「音響」をジャンルとして忠実になぞる者もいれば、杉本拓のようにそれを「テクスチャーの墓場」(14)と呼んで明確に批判する者もいるし、それでもなお何らかの可能性を模索する者もいれば、そうした問題系とはまったく別の領域で活動をおこなう者もいる。「音響」の行く末として「即興」の原理的な不可能性が提起される(15)一方で、そうした原理論は即興音楽の実際に即していないという意見(16)もある。多様化と細分化を複雑に極めていく現代即興音楽シーンについて、それを一言であらわすのは容易ではない。だがこれだけは言えそうだ。そうした様々な試みが自然と集まってくるような、いわばホットスポットのような場所が各地に点在しているということは。とりわけ水道橋Ftarriに足を運んでみるならば、戸惑いと驚きを覚えるような、そして途方もない魅力に打ちのめされてしまうようなイベントに、なんども出会うことができるのである。それらは「音響」に限らず、たとえばジャパノイズ、サウンド・アート、現代音楽、フリージャズといった既成のジャンルに近接し人脈的な交流を持ちながらも、それらのどのタームでも捉えきれないような魅力を放っている。だから大谷能生の「Improv's New Waves」にまるで呼応するかのようにして、それを呼び覚ますかのようにして、今年のはじめにFtarriの店主・鈴木美幸が「即興音楽の新しい波」(17)というタイトルを冠したイベントをおこなったことを、もう少しよく考えてみたいのである。
確かに2003年には見られなかった新しい試みが、2017年までにはいくつも出てきている。それらが果たしてシーンとしての波を形成するものなのかどうかはまだわからないが、まったくもって無関係な試みがただ単に乱立しているだけというよりも、やはり同時代的であるような響き合いを聴かせてくれるように思うのである。それを考えてみるためにも、ここでは水道橋Ftarriをひとつの窓としながら、そこからどのような光景が見えているのか、あくまでも極私的な体験から得られた見取り図を描いてみることにしたい。そのためにここでは、「ハードウェア・ハッキング」「ライヴ・インスタレーション」「シート・ミュージック」「即響」という4つのテーマを設け、それぞれについて言及していく。ただし、これらは情況を把捉する手段として便宜的に設定されたテーマに過ぎないので、当然のことながらジャンルのようにシーンを四分できるというものではなく、さらにミュージシャンによってはこれらのテーマに跨る試みをおこなっている者もいるだろう。それでもそうした具体的な実践に接近していくための契機になるのではないかとは思う。
註
(1)デイヴィッド・ノヴァック「音、無音、即興のグローバルな価値」(宮脇俊文、細川周平、マイク・モラスキー編著『ニュー・ジャズ・スタディーズ』アルテスパブリッシング、2010年)。なお、こうした動向はすでに90年代からあったとはいえるものの、Off Siteが開店していたのは2000年~2005年の五年間である。ノヴァックの同論文に対しては音楽ジャーナリストの横井一江により複数の誤謬が指摘されており、出版社から正誤表が出されているので、参照する際は注意が必要。
(2)たとえば、臼田勤哉、赤坂宙勇、大和田洋平、大谷能生による音楽批評誌『エスプレッソ』による記事「音響派について」(https://www.tinami.com/x/review/05/)。
(3)虹釜太郎「音響派の再発見」(『別冊ele-king ポストロック・バトルフィールド』Pヴァイン、2015年)。
(4)たとえば、畠中実「音の『無名状況』」(『三太Vol.6』2007年)。ただし同論考では「即興音楽」だけでなくより広く「サウンド・アートおよび実験的音響/音楽作品の分野」が取り上げられている。
(5)鈴木美幸「即興演奏シーン若手世代探訪」(『ジャズ批評No.99』ジャズ批評社、1999年)。
(6)大谷能生「Improv's New Waves ―論考―」(『Improvised Music from Japan EXTRA 2003』IMJ、2003年)。以下の引用も同論考から。なお、同論考は加筆修正を施しタイトルを「Improve New Waves」と改めたものが大谷の第1評論集『貧しい音楽』(月曜社、2007年)にも収録されている。
(7)北里義之「即興と音響の合流点で」(『NEWS OMBAROQUE 62号』2004年1月5日発行)。
(8)大谷能生「ジョン・ケージは関係ない」(『三太Vol.5』2007年)。同論考も『貧しい音楽』に再録。また、見られるように北里の書評から三年を隔てておこなわれた応答は、大谷によればもともとは北里の書評に対する反論を書こうとしていたわけではなく、偶然発見した書評がそのとき書き進めていたテーマに沿うものだったため、「具体的な論争対象」として取り上げることになったのだという。
(9)北里義之『サウンド・アナトミア』(青土社、2007年)。
(10)北里義之「即興と音響の合流点で」(『NEWS OMBAROQUE 62号』2004年1月5日発行)。
(11)クライヴ・ベル「OFF SITE: IMPROVISED MUSIC FROM JAPAN」(https://www.redbullmusicacademy.jp/jp/magazine/off-site-improvised-music-from-japan)。
(12)中村としまるによる発言。デイヴィッド・ノヴァックによる前掲論文から引用。
(13)大友良英『MUSICS』(岩波書店、2008年)。
(14)杉本拓「音響的即興を巡る言説」(『ユリイカ 2007年7月臨時増刊号 総特集=大友良英』青土社、2007年)。
(15)佐々木敦『即興の解体/懐胎』(青土社、2011年)。
(16)北里義之「即興解体論/懐胎論 in progress」(mixi内のエントリー、2008~2010年)。
(17)正式なタイトルは「東京発、即興音楽の新しい波」。出演者は第1セットが竹下勇馬、石原雄治、増渕顕史の3人による浦裕幸の作曲作品の演奏、第2セットがbikiと中村ゆいによる即興セッション、第3セットが池田若菜、内藤彩、山田光、滝沢朋恵による、前三者が持ち寄った作曲作品を組み合わせた演奏、第4セットが大上流一、徳永将豪、Straytoneによる即興セッション。当日はFtarri店主であり企画者でもある鈴木美幸による日英2ヶ国語で書かれた出演者たちの紹介文が配られ、また、国際舞台芸術ミーティングの一環としておこなわれたこともあってか外国人を中心に大勢の観客が詰めかけており、日本のインディペンデントな音楽シーンの一端を海外へと向けてプレゼンテーションするまたとない機会となっていた。出演者のうち、本稿では滝沢朋恵とbikiを取り上げることができなかったが、それは決してこのふたりが魅力に欠けるということではなく、紹介するのに適当なアルバムがなかったということに過ぎない。シンガーソングライターとして共演するだけでなく即興的なコラボレーションもおこなう滝沢の才能には注目すべきものがあるし、ノーインプットのミキシングボードと自作した距離を測る装置を組み合わせて魔術師のような振る舞いで演奏をおこなうbikiは、他方では風船を落としていく音の展示作品を手がけてもいて、ハードウェア・ハッキングとインスタレーションの両方に跨る特異な実践をおこなっている。ふたりのそうした側面を収めたアルバムのリリースが望まれるところである。
1 ハードウェア・ハッキング
ハードウェア・ハッキングというのは字義通り既成の楽器や電子機器を物理的に改変するという意味で、とりわけ実験音楽/電子音楽の世界で著名な作曲家ニコラス・コリンズによって特有の意味合いが付与されて用いられるようになった。コリンズの言わんとするところを簡潔にまとめた金子智太郎による記事(18)から引用すると、ハードウェア・ハッキングとは「電子工学の専門知識を前提としないDIY電子工作」であり、「コリンズがハードウェア・ハッキングの文化的性格として強調するのは、電子音楽における作曲家と技術者の分離の解消や、デジタル化によって減退した直接性と接触性の回復などである」。要するに必ずしも専門的な技術者ではない演奏家が、自らの手を動かし試行錯誤と実験を繰り返しながら、既成の道具に直接的な改変を施していくことによって新たなサウンドを探し出すのである。コリンズ自身が述べるように、それを「その機器の設計者すら予想しなかった結果を、あらゆる可能性に挑戦する極端な実験主義によって生みだすこと」(19)と言い表すこともできるだろう。そこには既に完成された楽器を使うことでは得られない新奇な音色の探求と、さらにそうした楽器を用いた演奏に要請される新たな身体性の獲得、およびそこから導き出される、これまでになかったような時間的/空間的な構造化への可能性が秘められている。

中田粥 - A circuit not turning
きょうRecords (2017)
Amazon
こうした方向性をもっとも過激に推し進めているひとりとして中田粥の名前を挙げることができる。東京都出身で現在は大阪に拠点を移して活動する中田は、既成のキーボードを解体し、内部の基盤を剥き出しにするとともにその回路に手を加え、独自の音響を紡ぎ出す実践をおこなっている。そうして生み出された楽器を彼は「バグシンセサイザー」と名付け、彼自身はハードウェア・ハッキングではなくリード・ガザラが提唱した「サーキット・ベンディング」の手法の応用であると言い、さらにそれをかつてジョン・ケージがピアノの内部の弦に直接ゴムや金属を挟むことでコンパクトな打楽器アンサンブルとしての音響を生み出した「プリペアド・ピアノ」における内部奏法の延長線上にある実践として捉えている。初期のバグシンセサイザーによる演奏では、自主制作したミニ・アルバムに残されているようにプリセットされた音源が断片的にあらわれていく奇妙な具象性を聴かせていたが、現在はより回路の接触から生まれる電子音響ノイズが強調されたサウンドとなっており、それは『A circuit not turning』で全面的に聴くことができる。一方でライヴでは音響を聴かせるだけではなく、小さな基盤のタワーを構築したりするなど、単なるサウンドの愉しみとしてだけでは終わらない、造形的な視覚要素と空間を生かしたインスタレーション的側面を体験することができる。
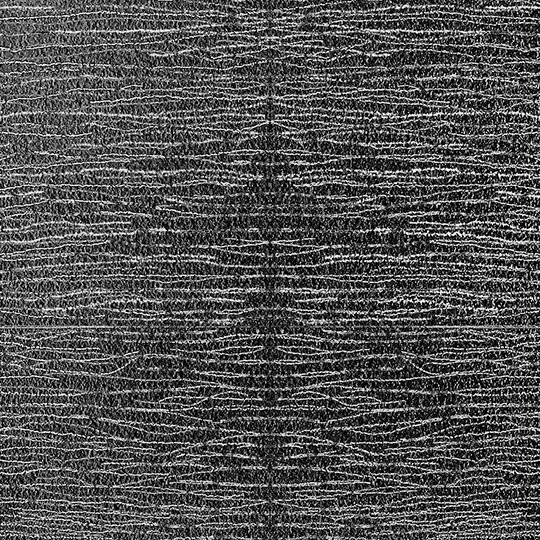
竹下勇馬 - Mechanization
Mignight Circles (2017)
Bandcamp
中田粥とも共演歴が多く、ハッキングという方法論を別の視点から極端に推し進めているもうひとりのミュージシャンとして、竹下勇馬の名前も外せない。中田とふたりで「ZZZT」というデュオ・ユニットを組んでもいる竹下は、エレクトリック・ベースに様々な自作の電子機器を取り付け、自ら「エレクトロベース」と名付けた、これまた奇っ怪な楽器を扱っている。アメリカのトランペット奏者ベン・ニールが「ミュータントランペット」と名付けた改造トランペットを使用していたことを彷彿させるが、ミュータントランペットが既存の音楽を前提とした複数の楽器パートを兼ねる異なる要素の統合を目指すものであったのに対して、エレクトロベースは統合というよりも増殖であり、異なる要素が異物のままに同居することで前提とされる音楽それ自体を問い直しにかけていく。さらにニールがSTEIMという研究所の後ろ盾のもとに楽器を発展させていったことに比すると、あくまでもDIYの精神で改変を施していく竹下の楽器はより自由な音楽へと開かれてもいる。竹下によるベースの改造はいま現在も続いており、一旦でき上がった状態に慣れるとさらにコントロールし難いものへと改変していくというのだからその実験精神は尽きることがない。演奏では通常のベースの弦の響きを織り交ぜ、それを変調するとともに複数の電子音響ノイズを併用するサウンドを生み出しており、『Mechanization』の後半においてその模様を聴くことができる。
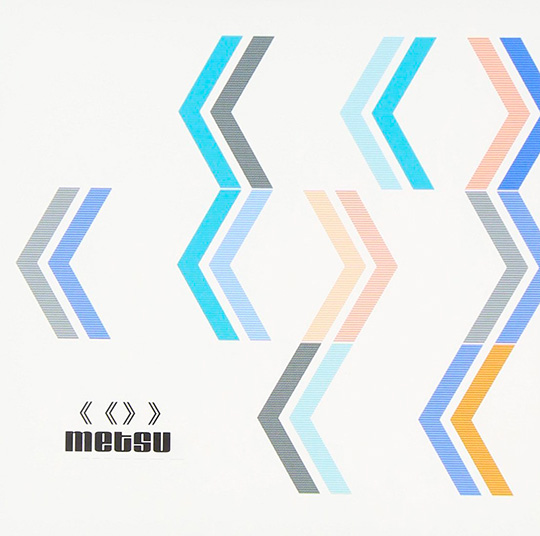
《《》》 - 《《》》
Flood (2015)
Amazon
中田粥と竹下勇馬が、ドラマーの石原雄治、ギタリストの大島輝之とともに結成した《《》》(metsu)によるアルバム『《《》》』では、ハッキングによって生み出されたふたりの楽器が、アコースティックな打楽器とエッジの効いたカッティング・ギターとともに丁々発止のやりとりをする様が収録されている――とはいえハッキングされた楽器から発されるのは肉体的というよりもテクノロジカルなエネルギーであり、レスポンスも即効性があるというよりは不確定的な要素が多く、そこが従来の即興音楽にはない面白さとも言える。このアルバムの3曲めおよび4曲めに参加しているサックス奏者の山田光は、改変こそ施していないものの、マイクロフォンやスピーカーを組み合わせることによって独自の音響をサックスから紡ぎだす演奏を試みてもいる。山田のそうした側面にフォーカスを当てたアルバムはまだ発売されていないものの、ロック・バンド「毛玉」のフロント・マンとしても知られる黒澤勇人とのデュオによる作品が近くリリースされる予定だという。すでにゼロ年代の後半から即興音楽シーンに関わってきた黒澤もまた、集音と増幅を駆使することによって、卓上に寝かせたギターから独自のエレクトロ・アコースティックなサウンドを聴かせる演奏をおこなっている。
このようにハッキングされた楽器からスピーカーを通して発される電子音は、楽器奏者との共演をおこなうことによって、電子音と楽器音が交錯するいわゆるエレクトロ・アコースティック音楽としての様相を呈していく。「エレクトロ・アコースティック」という言葉自体は、狭義には50年代の電子音と具体音を併用したレコード音楽のことを指すが、「音響」のムーヴメントと相俟って90年代以降により広く知られるところとなり、生演奏にエレクトロニクスを取り入れただけの音楽にも適用されるなど、現在では語感の良さも手伝って乱用されているきらいがある。しかし「エレクトロ・アコースティック」という考え方がもたらしたのは単に電子音と生音を併用するということだけではなく、技術の進歩などにより一方にまるで本物の楽器のような音を出す電子音があらわれ、他方には拡張され尽くした特殊奏法――これもひとつの技術革新だ――によってあたかも電子音のようなサウンドを奏でる楽器奏者があらわれ、そうした境界線の曖昧になった電子音/生音が、サウンドの平面上に同等の資格をもって立ちあらわれることによって、電子音や楽器音に歴史的に担わされてきた役割というものを、あらためて問い直す契機になったという点にこそある。そこでは音の発生源がラップトップPCなのかアコースティック楽器なのかといったことよりも、そこに一体どのような音が発生していて、それがどのように聴こえてくるのかということの方に焦点が当てられる。とりわけ「ハードウェア・ハッキング」の流れのなかから導き出されてくるエレクトロ・アコースティック音楽では、電子的なノイズと楽器の非器楽的使用による無形のサウンドが交差する傾向が強く、それを必ずしもハッキングすることのないエレクトロ・アコースティックの実践と関連づけてみることもできるだろう。
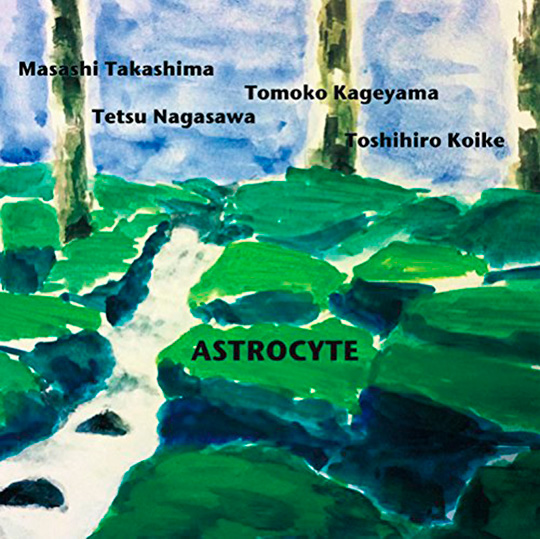
高島正志 / 影山朋子 / 長沢哲 / 古池寿浩
Astrocyte
meenna (2016)
Amazon
山田光のアイデアを取り入れることによって、独自の組み合わせからエレクトロニクス装置を生み出したドラマーの高島正志もまた、サウンドの地平をゆく固有の道を突き進んでいる。「G.I.T.M.」と名付けたその自作装置を取り入れた高島の演奏は、リズムというよりは痙攣するパルスの積み重なりを聴かせ、合奏では往年のスピリチュアル・ジャズのような陶酔感を伴っていく。他方で高島は作曲も手掛けており、そのモチベーションは自由であるはずの即興演奏が陥りがちな定型を脱することという、ギャヴィン・ブライアーズのデレク・ベイリーに対する批判を彷彿させるものがあるが、それでも彼自身はプレイヤーとして即興演奏をおこなう活動を手放してはいない。いわば彼にとっての作曲行為は即興演奏と相互に影響を与え合うような地続きのものとしてあるのだろう。現在は福島県に居住し、アジアン・ミーティング・フェスティバルにも出演したギタリストの荒川淳が郡山市で運営するスペース「studio tissue★box」で主に活動しているものの、都内でライヴをおこなうこともある。先日(5月5日)も高島の作曲作品が、竹下勇馬と石原雄治によるデュオ・ユニット「Tumo」によってリアライズされるライヴがおこなわれるなど、シーンとの交流がみられた。
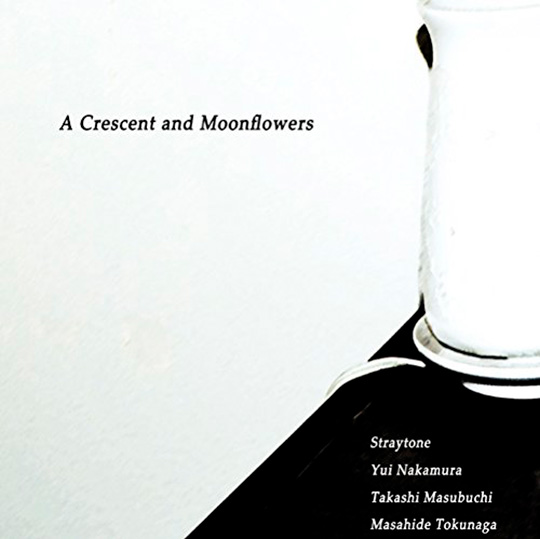
Straytone / 中村ゆい / 増渕顕史 / 徳永将豪
A Crescent and Moonflowers
meenna (2016)
Amazon
エレクトロニクス奏者と楽器奏者の共演から生まれるエレクトロ・アコースティック作品も紹介しておきたい。ミニマル・ドローンな音源の反復から電子音響を変化させていくStraytone、太く豊かな倍音を含んだサウンドを求道的に発し続けるサックス奏者・徳永将豪、12小節という定型を取り外したブルースの音響そのものに焦点を当てるかのようなギターを奏する増渕顕史によるトリオ・セッションと、声というよりも呼吸する気息の物質性をあらわにするヴォイス・パフォーマー中村ゆいが加わったカルテットによるセッションのツー・トラックを収めた『A Crescent and Moonflowers』である。管楽器のようなうねりとプリペアド・ギターのような打楽器的なサウンドを聴かせるStraytoneの演奏は、徳永と増渕による特殊奏法を取り入れた響きと混ざり合い、さらには吉田アミの「ハウリング・ヴォイス」を彷彿させる電子音響的なヴォイスを発する中村ゆいの演奏がそこに重なり合うことで、サウンドそれ自体の地平が開かれていく。そうした音像のなかから、ときおりその楽器の、あるいはその奏者にしか出せない固有の響きが前面に出てくる瞬間に立ち会うとき、サウンドの地平に照準を合わせていた耳に異化作用が施されていくというのも、こうしたセッションならではの愉しみだと言えるだろう。
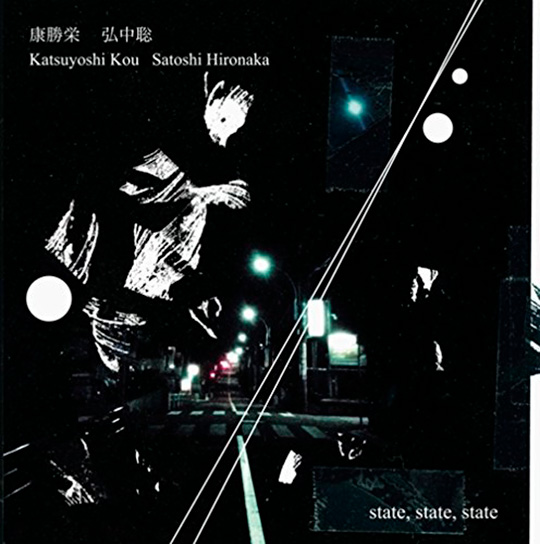
康勝栄 / 弘中聡
state, state, state
ftarri (2012)
Amazon
エレクトロ・アコースティック音楽の可能性を、あくまでも演奏を基礎としながらも、録音芸術として作品化した特筆すべきアルバムとして『state, state, state』も挙げておきたい。MultipleTapを主宰しウェブ雑誌『20hz』を発行するなど、日本のインディペンデントな音楽シーンを精力的に紹介し続け、クライヴ・ベルにも「これらの音楽を取り巻く環境を、特に日本において変えていくという使命を負っている」(20)と評された康勝栄と、変則的で巧妙にデザインされたリズムがラップのフロウを新鮮に聴かせるバンドskillkillsなどで活躍するドラマーの弘中聡によるデュオ作品である。僅かにポスト・プロダクションが施されたデュオ演奏とそれぞれのソロ、そして録音されたままのデュオ演奏が収録された本盤は、エレクトロ・アコースティックという考え方によって演奏をサウンドの地平で捉えられるようになったはずのわたしたちの耳が、それでも音盤上で施される改変によって本来の演奏を想起してしまうということ、しかし手を加えないことが本来の演奏と呼べるものなのかどうかということなどを、スタイリッシュなビートとともに提示している。すでに5年前の作品であり、とりわけ康の現在の活動はギターよりも自作エレクトロニクス装置を用いた演奏をする機会が多くなっているものの、そうした問題提起する射程の深さを伴うこの作品の特異性はまったく古びていない。
註
(18)金子智太郎「ハードウェア・ハッキング」(https://artscape.jp/artword/index.php/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%83%8F%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0)
(19)ニコラス・コリンズ『Handmade Electronic Music』(久保田晃弘監訳、船田巧訳、オライリージャパン、2013年)。厳密には、ここでのコリンズの発言はハッキングの一種である「サーキット・ベンディング」について述べられたもの。
(20)クライヴ・ベル、前掲論文。
2 ライヴ・インスタレーション
かつてデュオ・ライヴをおこなった川口貴大と大城真は、それを観た米国のとあるレーベル・プロデューサーから「これはインスタレーション系だ」と評されたことがあるという。要するに「こんなものは音楽ではない」という否定的なニュアンスが含まれた評価を受けたのだが、むしろそうした評価を、従来の音楽概念では評価しきれないような、しかしあくまでも音を介した新しいパフォーマンスとの出会いから発された言葉として、ポジティヴに受け止めることもできるだろう。今年の春に出版された大友良英による好著『音楽と美術のあいだ』でも提示されていた、音楽とも美術ともつかないそうした新たな表現領域――あるいは領域から逸脱する表現のありよう――を、しかし美術に基軸を置いた音の展示ではなく、あくまでも音楽の現場で「演奏」としてなされている、いわば「ライヴ・インスタレーション」とも言える実践を眺めることから、その実態を探っていきたい。ここで紹介するミュージシャンたちの多くはアート・スペースに設置されるような音の展示作品も制作しており、いわゆるライヴハウスのような音楽のために設けられた場においても、空間と大きく関わるようなリアルタイムの反応と操作をおこないながら、投げ出された音の行方を見守るという非常に独特な「演奏」をおこなっている。こうした動向については、音楽家/評論家のデイヴィッド・トゥープによって「フェノメノロジスト」という呼称が用いられてもいる(21)。

川口貴大 / ユタカワサキ
Amorphous Spores
Erstwhile Records (2015)
Erstwhile Records
川口貴大はもともとフィールド・レコーディング作品の制作からそのキャリアを出発させながらも、ゼロ年代の半ばにはすでに会場内を歩き回りながら自作の音具を設置していくという特異なパフォーマンスをおこなっていた。『n』に結実するそうした方向性は、その後、大城真、矢代諭史とともに結成したグループ「夏の大△」へと受け継がれるとともに、より演奏に比重を置いた新たな表現を開発していった。複数のヤンキーホーンと音叉、さらには臓器のように伸縮する巨大なビニール袋とスマートフォンの光を用いたパフォーマンスでは、演奏の進行と展開を共演者に対する反応ではなくビニール袋の動きに合わせるという、非常に独特な即興演奏の取り組み方をしている。共演者との相互触発から反応の応酬を聴かせるのではなく、もっと人間の世界から離れた物と物の相互作用を提示するかのような川口のパフォーマンスは、その見た目の異様さもさることながら、どこにでもある日用品の匿名性とは裏腹に、彼にしか生み出せない個性的なサウンドを奏でることにも成功している。ユタカワサキとのデュオ・セッションにポスト・プロダクションを施すことで完成した『Amorphous Spores』で聴くことができるのは、人間の身体的な動作からは切り離されたところにある音響に刻まれた、しかし紛れもない彼の個性である。

大城真
Phenomenal World
hitorri (2014)
Amazon
匿名的かつ個性的なサウンドは大城真が自作した通称「カチカチ」からも聴くことができる。かつてはヴィデオ・フィードバック現象を音楽として提示し、その後も「ウネリオン」と名付けた独自のフィードバックを発生させる楽器を自作するなどしてきた大城は、よりコンパクトに持ち運びの出来る形態として手のひらに収まるサイズの「カチカチ」を生み出した。会場内を歩き回るパフォーマンスは、ともに「夏の大△」で活動する川口貴大の初期の試みを彷彿させるところがあるが、至る所に設置された「カチカチ」が生み出す即物的な音響のアンサンブルがサウンドのモアレを形成するところなどは、独自に取り組んできたフィードバック現象の実践からの形跡を感じさせる。ヴィデオ・フィードバック、ウネリオン、「カチカチ」などを全て収録した、大城の活動の集大成ともいうべき作品が『Phenomenal World』である。彼自身の「現象としての音や、その発生の仕組みへの興味」(22)があらわされている本盤のタイトルからは、現象学を出発点に非人間的なオブジェクトに立脚する哲学を構想するという、グレアム・ハーマンの「オブジェクト指向存在論」を連想させるところがある。ただしそうした現代の思想動向の実体化や反映を彼の音楽に見出すことよりも、まずは様々にあらわれるサウンドに対する興味と驚きが根底にあるのだということには注意しなければならないだろう。
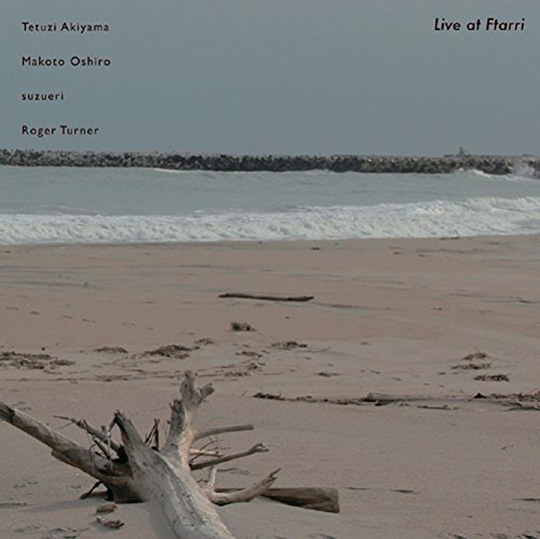
秋山徹次 / 大城真 / すずえり / Roger Turner
Live at Ftarri
meenna (2016)
Amazon
今年の初めにイングランド北西の都市マンチェスターで大城真とともに展示およびライヴをおこなったすずえりの近年の活動にも非常に興味深いものがある。アコースティック・ピアノ、大小のトイピアノ、それにさらに小さな模型のピアノを連結し、「ピアノでピアノを弾く」という実にユニークな展示作品を手掛けるすずえりは、ライヴにおいても複数の「ピアノ」を用いながらそのユニークネスを発揮したパフォーマンスを繰り広げている。会場で何かを制作しようとしているものの、それにしてはあまりにも非合理的で非効率的なプロセスを踏んでいくことが、むしろ自作した音具たちの連関を生み出していくそのパフォーマンスは、従来の演奏概念とはまったく別のところから「即興」の醍醐味を聴かせてくれる。肩肘張らない脱力した佇まいもまた、しかつめらしく状況を見守る即興演奏とは別の緊迫感を生み出していく。残念ながら彼女のこうした側面を捉えた音盤はまだリリースされていないものの――とはいえ、彼女の面白さは音盤にはならないライヴのプロセスにこそあるともいえる。なので反対に、それをどのようにサウンドとして定着するのかは非常に気になるところだ――大城真、秋山徹次、それにロジャー・ターナーとのカルテットによるセッションを収めたアルバム『Live at Ftarri』でその特異な実践を垣間見ることができるだろう。
音盤として残された彼ら/彼女らの実践は、あくまでも変化するサウンドの妙味にその魅力があらわれているわけだが、ライヴや展示においては「装置の実用性や象徴性ではなく、装置同士のネットワークや、物質が人間にもたらす影響」(23)とも言われるような、人間中心主義的な世界を離れた音たちが織り成していく、オブジェクトの相互作用のようなものを形成することの面白味がある。多くの場合ハッキングした自作音具を用いながらも、それをスピーカーから電子音として鳴らすのではなく、あくまでもアコースティックな響きとして空間に配置していくということも、現象する音の環境世界を提示しようとすることと無関係ではないだろう。それは「演奏」というよりも、人間に従属することのない音の発生を、制御不能なままに見届けようとするある種の「聴取」行為とも言える。こうした点から、まったく別の試みであるように思えながらもフィールド・レコーディングという実践との近似性が浮かび上がってくる。フィールド・レコーディングもまた、人間の世界を離れた音の環境を相手取っていく試みだからである。言うまでもなくそれをどのように切り取るのか、すなわち聴取する耳をどこに設定するのかということがフィールド・レコーディングの要であり、それは必ずしも聴くことによって視点を切り取ることが要点ではないインスタレーションの在り方とは異なっている。しかし耳の先で起こる出来事を人間が従属させることはできないのであって、とりわけそうした聴取の実践をライヴ空間でおこなうミュージシャンにあっては、そこでわたしたちが立ち会うこととなるのは出演者たちに同化した耳の視点ではなく、むしろ彼ら/彼女らが聴き、聴こうとし、それでも聴くことの外部へと溢れてしまうような音の生態系であるだろう。

stilllife
archipelago
ftarri (2015)
Amazon
笹島裕樹と津田貴司のふたりによって結成されたstillifeは、フィールド・レコーディングをライヴにおける「演奏」としておこなう非常にユニークなデュオ・ユニットである。彼らのライヴでは、オートハープや木製の笛、音叉、小石、ガラス瓶その他無数の音具と、集音し変調するエレクトロニクス装置などを用いながらも、それらは一般的な音楽の演奏においてホワイト・キャンバスに描かれる絵のようにあるのではなく、むしろその場の環境やライヴをおこなう会場にすでにある様々に彩られたキャンバスを前にして、その背景が決してまっさらな沈黙ではないことを明かすかのように挿入されていく響きとしてある。言うまでもなく、彼らがそこで聴き取ろうとするサウンドは、観客であるわたしたちと同一のものではない。むしろ聴き取ろうとする彼らの「演奏」によって浮かび上がる音の世界が、わたしたちひとりひとりに固有の聴取の位置を与える契機となっていく。しかしだからこそ、彼らの音盤はライヴであらわされる音楽とはまったく別の価値を帯びもする。傑作ファースト・アルバム『夜のカタログ』の翌年にリリースされた『archipelago』では、あたかも電子音楽のような即物性を伴って響く鳥の鳴き声が、最終的にはそれが他ならぬ「鳥の声」という意味にまみれたサウンドでしかなかったということに、思わず気づかせるような工夫が凝らされていて、それは録音作品ならではのstillifeの「耳」の刻みかたとも言えるだろう。
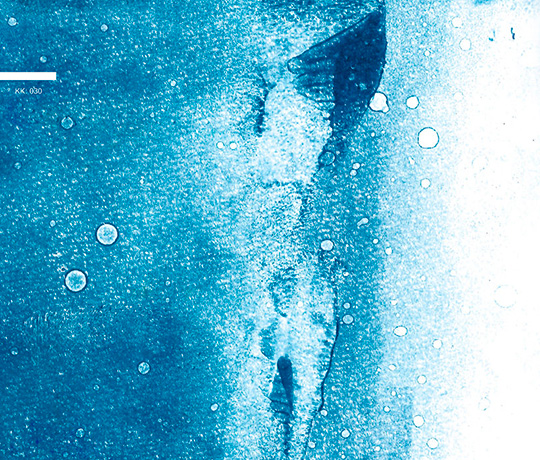
松本一哉
水のかたち
SPEKK (2015)
Amazon
stillifeのメンバーでもある津田貴司と、ベースを用いた特異なドローン/倍音を奏でてきたTAMARUとともに、昨年からは「Les Trois Poires」というグループでも活動をおこないながら、独自のフィールド・レコーディング作品を残しているアーティストとして、打楽器奏者の松本一哉の名前を挙げることもできる。「自分が指揮者になったように音を選んで聴けば、身の回りには常に偶然に作曲された音楽が溢れている」(24)と語る彼が、「偶然のオーケストラに奏者として自分が音を足すことで、全く別の聴き方ができたり、もっと違う楽しみができたり、今まで体感したことのない新しい価値を見出せる」(25)ということを念頭に置いておこなった環境音とのセッションが、『水のかたち』には収められている。全編が「ありのまま」に収録された本盤からは、「波紋音」をはじめとした複数の音具を用いた、水琴窟での数回にわたる演奏から、長野県根羽村に固有の独特な鳴き声を持つ蛙との演奏、梅雨明けに突然訪れるひぐらしとの演奏、あるいは浜辺に打ち寄せる波音との演奏など、水をテーマに様々な場所でおこなわれた「セッション」の記録を聴くことができる。打楽器奏者ならではのリズミカルな演奏もおこなう松本の音楽が、しかしときおり環境音なのか彼の打音なのかわからなくなる瞬間に立ち会うとき、「偶然のオーケストラ」が詩的な方便やケージ主義的な認識論ではなく、極めて具体的なサウンドのありようを指しているのだということがわかる。
註
(21)David Toop “Can SOUND”, The Wire 400, June 2017.
(22)『Phenomenal World』、大城真によるライナーノーツより。
(23)金子智太郎「音の展開2014」(https://artscape.jp/dictionary/newword2014/contents/10101391_18765.html)。なお、同論考では「ハードウェア・ハッキング」がいわゆるサウンド・アートの文脈で取り上げられているものの、本稿では竹下勇馬のようにより演奏の性格が強いアーティストのハッキングの事例を紹介するため、また、川口貴大のようにハッキングをすることはないものの音の展示の性格が強いアーティストを紹介するため、これらを別の項目として立てることにした。
(24)『水のかたち』、松本一哉によるライナーノーツより。
(25)同前。
3 シート・ミュージック
シート・ミュージックとは元来音楽の流通形態のひとつの在り方を指し、とりわけ録音/再生技術が音楽の消費形態として一般化する以前の18世紀末から20世紀初頭にかけて、音楽家が生み出した作品をいつでも再現できるような状態で所有するために売買された楽譜を指すのだが、ここでは大谷能生が『貧しい音楽』のなかで設けた章のタイトルから借用し、即興音楽シーンにおいて新たな表現を求めるために取り交わされているいわゆる「作曲もの」の総称として用いることにしたい。同書のなかで大谷がおこなったインタヴューにおいて、そのころ即興よりも作曲へと活動の比重が増していた杉本拓は、「即興で演奏すると落ち着き先が似てしまう、結局ある磁場の中に収まってしまう。そういった重力から離脱する手段としての作曲」(26)の魅力を語っていた。意味づけられる前の物質的な次元における音響を経験の基盤として分有しているならば、シート・ミュージックの役割もまた、同一の音楽を記号化して保存/伝達することよりも、記号化することから生まれる流動的で一回的な実践のほうに焦点を当ててみることができるようになる。すなわち、紙に書き記したスコアを介して演奏をおこなうことが、単なる伝達の手段やイデアルな領域に作品を保存するのではなく、即興演奏に新たな側面から光を浴びせ、より活動を活発化させるための方途となっていくのである。
(ところで、かつて批評家の佐々木敦は、体験を前提とし聴かれることを目指しているという点においてコンセプチュアル・アートとは異なるものとしながら、「一回性の中に、他の可能性を排除するに足る理由づけ」のないような、「聴かなくても聴いてることと無限に同じになる」ようなものこそが、「即興的な、偶然的な要素を取り入れたヴァンデルヴァイザー以後の作曲の方法論」だと述べていたことがある(27)。いわば充足理由律を否定する思弁的な作曲に可能性を見ていたのであって、それは音をあるがままにするはずのケージ主義的な実験音楽の多くの試みが、しかし音の物的状態ではなく、あくまでも聴くこととの関わりにおいてのみ可能な実践でしかなかったのに対して、聴取および演奏とは区別された作曲それ自体を提起していたジョン・ケージ自身の試みにおいては、「聴取と音の相関」(28)を抜け出す手掛かりをみることができるのであり、その方向性を相関主義の隘路に陥ることなく推し進めたものとして「ヴァンデルヴァイザー以後の作曲の方法論」を捉えることもできる。だが本稿では、あくまでも演奏やパフォーマンスに重心を置いた実践を事例として紹介しているため、こうした「思弁的作曲」を中心的に取り上げることはしない)。

Suidobashi Chamber Ensemble
Suidobashi Chamber Ensemble
meenna (0016)
Amazon
2016年に結成されたSuidobashi Chamber Ensembleは、そのメンバーの多くが即興演奏家としても活躍していながらも、ヨーロッパの現代作曲作品からメンバー自身による豊富なアイデアを取り入れた楽曲、あるいは交流のあるグループ外の音楽家による作曲作品もリアライズしてみるなど、「作曲もの」を活発に実践しているグループである。メンバーを率いるのは吉田ヨウヘイgroupで活動していたフルート奏者の池田若菜で、ほかに即興演奏に果敢に取り組んできたヴィオラの池田陽子、シーンには珍しいファゴットを奏する内藤彩、さらに杉本拓と大蔵雅彦が参加している。前三者はクラシック音楽を素養に持つというところもユニークで、とりわけ内藤彩はこのグループに参加するまでこうしたシーンとはまったく関わりを持っていなかったというところも興味深い。ライヴでは毎回趣向を変え新たな楽曲に取り組んで見せる一方で、決め事なしの集団即興も試みるなど、尽きないアイデアと怖いもの知らずの実験精神にはつねに驚きが満ち溢れている。そうした彼ら/彼女らの魅力をたった1枚のアルバムに集約することなど到底できないが、それでも『Suidobashi Chamber Ensemble』におけるヴァンデルヴァイザー楽派の楽曲を演奏するという試みからは類稀な音楽が生み出されており、ライナーに池田若菜が書き記しているように「構造の理解だけでははかれない何か別の視点から作品を体験すること」(29)の面白さを感じ取ることができるだろう。
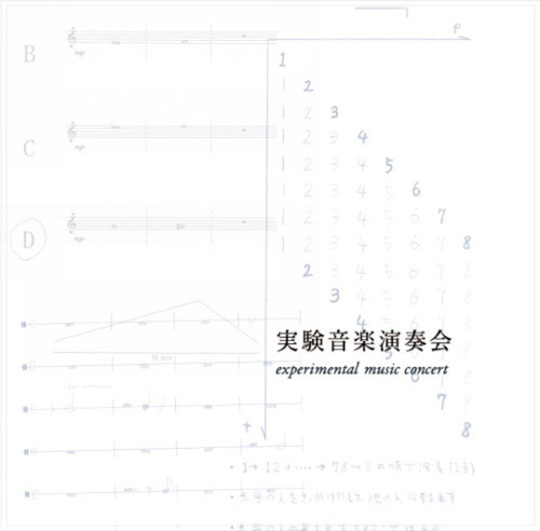
Various Artists
実験音楽演奏会
slubmusic / kenjitzu records / l-e (2015)
実験音楽演奏会
Suidobashi Chamber Ensembleとも交流を持ちながら、主に大崎/戸越銀座のイベント・スペース「l-e」を拠点に活動する実験音楽演奏会(30)も、こうした「作曲もの」で魅力的な活動をおこなっている集団のひとつである。杉本拓が2013年にl-eでおこなっていた「実験音楽スクール」の参加者からなるこの集団には種々様々なメンバーがおり、「なるべく失敗しそうなのを作る」(中条護)という意見から「誰でも参加できる、なるべく簡単なことをやりたい」(高野真幸)という意見まで飛び交う(31)など、一様に括ることのできないバラエティの豊かさがある。だがそれでも、こうした集団として活動をおこなうことが互いに影響を与え合うことによって、また、基本的にはどのような実践も許されるl-eという拠点を持つことによって、様々に新しい試みへと踏み込んでいくことのできる理想的な環境があるとは言えるだろう。『実験音楽演奏会』に収められているのは、五線譜に書き記された作品からテキスト・スコアによるものまで様々であり、たとえば室内の温度を演奏を指示する楽譜に見立てた作品の実演などが収録されている。杉本はかつてこう述べたことがあった――「実験音楽とは、何が音楽であるのか、どのようにある音についてそれが音楽であるかないのかを認識するのか、そういう問題に対して思弁を活性化させ、さらにその思弁に対して実践で答える、そういった精神を持続させていく装置のひとつである」(32)。

浦裕幸 / 金沢健一 / 井上郷子
Scores
meenna (2017)
Amazon
こうした固定メンバーあるいは集団による実践とは異なりながらも、ユニークな作曲作品を生み出している存在として浦裕幸の名前も挙げることができる。2月17日のライヴで初演された「Etude for Composition #1」において、リアライズする即興演奏家の固有のサウンドを扱いながらも、カードを捲る無意識的な動作とそこから生まれる意図されざる響きを露わにしていた浦は、『Scores』においても奏者固有の音響をたゆたわせながらも、二重の無意識的なるものを顕在化させることに成功している。ひとつめはまったく音楽化されることを想定せず、もっぱら造形的な美しさだけを追い求めて制作されていた彫刻作品から、その形象を楽譜に見立てることで生まれる和音とその連なりであり、もうひとつはそれを演奏した10月1日の群馬県立近代美術館に偶然居合わせた子供のはしゃぎ声と基層となる環境の響きである。ポスト・ケージの地平にいるわたしたちにとって、もはや単にステージ上で演奏者がなにもしないというだけでは、意図されざる響きとしての「サイレンス」が立ちあらわれてくることはない。浦自身がどこまでそれに意識的に取り組もうとしているのかは定かではないものの、彼の実践からは、現代の耳に「サイレンス」をいかにして出会わせることができるのか、という挑戦を読み取ることもできるだろう。
註
(26)杉本拓インタビュー(『貧しい音楽』月曜社、2007年)。
(27)佐々木敦『「4分33秒」論』(Pヴァイン、2014年)。
(28)仲山ひふみ「聴くことの絶滅に向かって」(『現代思想』2016年1月号、青土社、2016年)。
(29)『Suidobashi Chamber Ensemble』、池田若菜によるライナーノーツより。
(30)アルバムの参加メンバーは米本篤、小林寿代、高野真幸、山田寛彦、中条護、佐々木伶、平野敏久の計7名。
(31)「座談会 実験音楽演奏会」(『l-eマガジン3号』2015年)
(32)杉本拓「実験音楽入門」(『Loop Line』2010年)
4 「即響」
「即響」という耳慣れない造語は、フランス文学者/音楽評論家の昼間賢による論考「音響音楽論」(33)から借用した言葉である。同論考では、組織化された音楽、あるいはそうした音の連なりにすでにして組み込まれた楽音ではなく、「音響」――とりわけ音の(複製技術というよりも)保存手段としての録音を介したものとしての――を起点に据えて音楽の再構築を図る試みについて、それを喉歌、ブルガリアン・ヴォイス、クロード・ドビュッシー、ジミ・ヘンドリクス、フィールド・レコーディングといった多岐にわたる事例を辿りながら論述していくという内容になっている。その最終章「究極のローカル(二)――楽器に徹した即興演奏=即響の現在」において、昼間は現代即興音楽シーンについて触れながら、その特徴を「音の過剰や極端な欠如によって音楽の根幹を揺るがすのではなく、特異な響きを最大限にいかしつつ、通常の音楽とは別の音響を、あくまでも楽器によって、すなわち人間の身体を介したかたちで演出する音楽」として「即響」と呼ぶことにしている。それは「物質そのものではなく物的状態、すなわち、社会的に決められた用途から自由になった物と同様にありたいと願う人との出会い」であり、「意味づけられていない自由な音のために黙々と続けられる」実践なのである。大谷能生が14年前に提起した「新しさ」をも彷彿させるこうした定義は、当時見出された可能性を自らの身体と楽器を前にした音楽の現場において、さらに一層洗練させていく一傾向として捉えることもできるだろう。

歌女
盲声
blowbass (2014)
daysuke
こうした傾向を語るにあたって、昼間賢がそれを体現するアーティストとして挙げていたチューバ奏者の高岡大祐について触れないわけにはいかない。ステージでパフォーマンスをおこなうだけでなく、生きることそれ自体が即興演奏と地続きにあるような発言を残してきた「旅するチューバ吹き」の彼が、石原雄治と藤巻鉄郎というふたりの打楽器奏者とともに結成した「歌女」は、ブラスバンドからそのキャリアを出発させたという高岡の音楽的な原点に立ち返るかのように、ニューオリンズ・スタイルのリズム隊を彷彿させる編成となっている。だがその音楽はまったく異なるものであり、重音奏法を循環呼吸によって延々と続けるチューバの響きにふたつの打楽器が交差するリズムが絡み合う演奏や、細かいパルスの連続が大きなうねりを生み出していく演奏など、音楽的なサウンドを聴かせる一方で、何かを転がしたりファスナーを開け閉めする物音が連ねられていく「非音楽的」な音響も聴かせている。そうした音楽が収められた『盲声』は、アルバムの冒頭に野外からライヴ会場へと赴く足音が、末尾にはライヴ会場から去っていく様子が録音されていることを思うと、この作品全体が「歌女」というグループの音響を生け捕りにした、いわばフィールド・レコーディング作品とも言えるものとなっている。

徳永将豪
Alto Saxophone 2
hitorri (2015)
Amazon
楽器の求道者として自らに固有の音響を生み出してきたアルト・サックス奏者の徳永将豪もまた、「即響」とも言えよう特筆すべき試みをおこなっている。14年前の大谷能生の論考においてもっとも若い世代のひとりとして紹介され、当時多くの即興演奏家がエレクトロニクスを取り入れた演奏をおこなっていたのに対して、あくまでも「サックスというアコースティックな楽器の響きに取り組んでいる貴重な存在」(34)として挙げられていた徳永は、その後も自らの音楽を錬成していくことで誰にも到達できないような響きを獲得するに至った。運指をほぼ固定したまま息を吹き込むサックスからは、その呼吸の運動によって様々に反響し共鳴する驚くべきサウンドの豊かさを聴かせてくれる。それだけでなくときおり荒れ狂うように軋るノイジーな演奏もおこないながらも、気息によって形づくられる身体的なリズムが、特殊奏法を駆使したサックス演奏を、単なるノイズ生成ではなくより音楽的な流れとなっていくような構成的な展開をももたらしている。ファースト・ソロ・アルバムでは抑制された静謐さの揺らめきを探索していたその音楽は、5年半後の『Alto Saxophone 2』においてよりダイナミクス溢れる強靭な演奏に至り、そしていま現在も変化を続けている。彼の3枚めとなる新たなソロ・アルバムは近くリリースされる予定のようである。
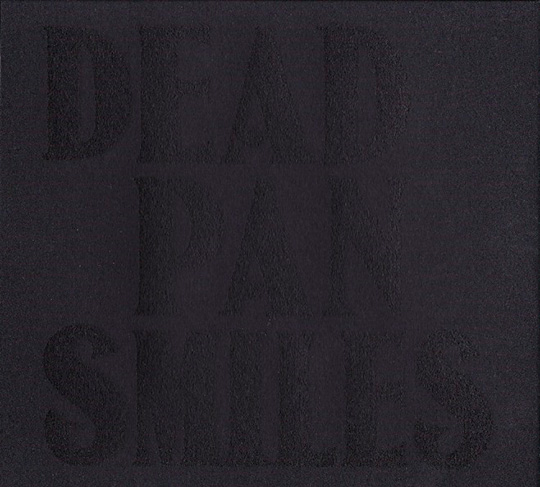
大上流一
Dead Pan Smiles
DPS Recordings (2015)
Tower
さらにもうひとり、ギタリストの大上流一の実践をこうした特徴から捉えることもできるだろう。すでにゼロ年代の前半には活動を始めていた大上を「新しい波」などと呼ぶわけにはいかないものの、80年代から続く中野のライヴ・スペース「Plan-B」において、彼が2004年から10年間にわたって毎月おこなってきたライヴにおけるソロ・インプロヴィゼーションが、5枚組のアルバムとして陽の目をみることによって、ようやくわたしたちは彼の試みに録音を介して出会うことができるようになった。10年間の記録から厳選された録音が収録されている『Dead Pan Smiles』には、デレク・ベイリーを思わせる点描的なハーモニクスとフレーズから逸脱する演奏や、後期高柳昌行のごときフィードバックを取り入れた轟音ノイズなどがありながらも、ベイリーとも高柳とも遠く離れたミニマルに反復していく独自の即興演奏までもが収められている。それはどこかジム・オルークのギター・ソロを彷彿させるところがあるかと思いきや、そこにとどまることもなく、豊富なアイデアと卓越した技術を駆使して新たな即興に挑んでいく様に立ち会うとき、こうした連想ゲームがことごとく無意味になるような気にさえなってくる。ひとつとして同じ演奏がなく、つねに変化を続けるその音楽は、当然のことながらジャンル化した「フリー・インプロヴィゼーション」の再生産などではなく、まさしく「意味づけられていない自由な音のために黙々と続けられる」実践の軌跡と言うことができるだろう。
*

Various Artists
Ftarri Third Anniversary Vol. 1 ~ Vol. 6
meenna (2015)
Ftarri / Meenna
もっとも懸念すべき事態は、こうした見取り図を描くことによって、その図式に収まりきらない魅力的な実践の数々が、わたしたちの前から見えなくなってしまうことにある。それを避けなければならないということは強調してもし足りない。そこで最後に、水道橋Ftarriが実店舗を構えて3周年を記念してリリースしたアルバムを紹介しておくことにしたい。Vol.1からVol.6まで計6枚出されたこれらのコンピレーション・アルバムには、これまで言及してきたミュージシャンたちのほとんどを含みながら、それだけでなく、総勢28名にも及ぶ多様な音楽が収録されている。そこには当然のことながらこれまで書き記してきた4つのテーマではまったく掬い取れないような特異な実践もあれば、そうしたテーマに当て嵌まるものの紹介し切れなかった試みもあるだろう。だがさらに言うならば、水道橋Ftarriを窓口として眺めることそれ自体が妥当なことなのかどうかということも、問われなければならないように思われる。そこに出演しているミュージシャンたちは言うまでもなく他のスペースでも活躍しており、たとえば六本木Super Deluxe、大崎l-e、桜台pool、東北沢OTOOTO、八丁堀七針、千駄木Bar Isshee、神保町試聴室など、他にも十分に窓口となり得るような音楽の現場が無数にあるのだ。さらにそれらの情報が掲載されたウェブサイトは、現在では「Improvised Music from Japan」だけでなく、それぞれのミュージシャンたちが容易にインターネット上に個人の拠点を作ることができるようになっているし、あるいはト調のように、都内のライヴ日程を価値判断を下す以前にひたすら収集し続ける驚異的なウェブサイトもあらわれてきている。本来であれば、そうした個別の現場とそこで活躍する単独者たちについて、ひとつひとつに丁寧に言説を付していくという作業が正しいことのようにも思う。しかしその個別の実践があまりにも膨大に広がっていることが、一般的なリスナーにとってどこから近づけばいいのかわからない難解さを生み出しており、さらにそうした多様性がむしろ興味を分散し触れてみる機会をも数少なくしてしまっているようにも思うのである。そうしたことを打ち破るきっかけとして、本稿のような踏み台の役割を果たす言説も必要なのではないか。無論、ここから先は、個別の読者が実際に現場へと足を運んでいくことが期待されている。ここで紹介した数々の実践は、それを目前にしてみるならば、音盤とはまったく異なる風景として立ちあらわれてくることだろう。そしてそれを未だなお「即興音楽」と呼び続けることが適切であるのかどうかは、今後あらためて議論されるべきことでもあるように思われる(35)。
註
(33)昼間賢「音響音楽論」(『ファーズ』第5号、首都大学東京大学院 人文科学研究科 表象文化論分野、2014年)。
(34)大谷能生「Improv's New Waves ―論考―」(『Improvised Music from Japan EXTRA 2003』IMJ、2003年)。
(35)たとえばそれを即興であるか否かという観点から捉えるのではなく、その「特殊性」(https://www.ele-king.net/columns/005311/)から捉えたほうがより広がりを持った考え方ができるようになるのではないか。






 〈workshop〉からのリリースによりブレイクしたライプツィヒが誇る若手プロデューサー、グナー・ヴェンデル aka カッセム・モッセは、いまドイツで最も熱い実力派アーティストのひとりである。オマー・S の〈FXHE〉、ドイツの〈Laid〉や〈Mikrodisko〉、UKの〈nonplus+〉などからもアヴァンギャルドながら、ファンキーな魅力も併せ持つエレクトロ~ディープ・ハウス~テクノの傑作トラックを多数発表、カルト的人気を得ているアンダーグラウンド・ヒーローだ。同郷の盟友 Mix Mup とのユニット、MM/KM として〈The Trilogy Tapes〉からのリリースも評判になっており、自身のレーベル〈Ominira〉からも多様なスタイルの作品を発表、昨年は名門〈Honest Jon’s〉から実験的なアルバムを出し話題になるなど、非常に精力的ながら独自のスタンスで活動を続けているユニークな存在。また、パフォーマンスにおいても一点に留まることがない。つねにセッティングや内容を変え、2回と同じことはしない、まさに「ライヴ」感満点なセットだ。特に Kassem Mosse 名義ではヒップホップにも通じるラフなビート感、自然と身体が動いてしまうグルーヴを備え、何度見ても新しさを発見させてくれる。
〈workshop〉からのリリースによりブレイクしたライプツィヒが誇る若手プロデューサー、グナー・ヴェンデル aka カッセム・モッセは、いまドイツで最も熱い実力派アーティストのひとりである。オマー・S の〈FXHE〉、ドイツの〈Laid〉や〈Mikrodisko〉、UKの〈nonplus+〉などからもアヴァンギャルドながら、ファンキーな魅力も併せ持つエレクトロ~ディープ・ハウス~テクノの傑作トラックを多数発表、カルト的人気を得ているアンダーグラウンド・ヒーローだ。同郷の盟友 Mix Mup とのユニット、MM/KM として〈The Trilogy Tapes〉からのリリースも評判になっており、自身のレーベル〈Ominira〉からも多様なスタイルの作品を発表、昨年は名門〈Honest Jon’s〉から実験的なアルバムを出し話題になるなど、非常に精力的ながら独自のスタンスで活動を続けているユニークな存在。また、パフォーマンスにおいても一点に留まることがない。つねにセッティングや内容を変え、2回と同じことはしない、まさに「ライヴ」感満点なセットだ。特に Kassem Mosse 名義ではヒップホップにも通じるラフなビート感、自然と身体が動いてしまうグルーヴを備え、何度見ても新しさを発見させてくれる。 この1~2年で急に頭角を現してきたように見える(かもしれない) Resom (レゾム)は、ベルリンではよく知られた存在だ。反ナショナリズム、反差別主義を掲げる、ベルリンの中でも特にリベラルなスタンスのクラブ、〈:// about bank〉のレジデントDJを長年務め、ライプツィヒでの学生時代からの友人であるカッセム・モッセや Mix Mup (ミックス・マップ)らを陰で支えるブッキング・エージェントとしての顔も持ち、それ以外にもつねに様々なイベントのオーガナイズや、制作に関わってきた。音楽業界における女性の地位向上のためにも行動する、フェミニストでありアクティヴィストでもある。そのDJスタイルは一言では形容しがたい、非常に独特なもので、ジャンルで言えばアンビエントからエレクトロ、歌物からミニマルまで非常に幅広く縦横無尽にミックスしていくのだが、ただ色々かけているというのではなく、彼女の中で明確なイメージやテーマがあり、それをもっともオブスキュアでレフトフィールドな選曲によって紡ぎ出していくような、まったく予測不可能ながら、いつも彼女らしいちょっぴりストレンジな高揚感に到達させてくれるのである。Ben UFO や DJ NOBU も絶賛する彼女の個性を、ぜひ一度体験してみて欲しい。
この1~2年で急に頭角を現してきたように見える(かもしれない) Resom (レゾム)は、ベルリンではよく知られた存在だ。反ナショナリズム、反差別主義を掲げる、ベルリンの中でも特にリベラルなスタンスのクラブ、〈:// about bank〉のレジデントDJを長年務め、ライプツィヒでの学生時代からの友人であるカッセム・モッセや Mix Mup (ミックス・マップ)らを陰で支えるブッキング・エージェントとしての顔も持ち、それ以外にもつねに様々なイベントのオーガナイズや、制作に関わってきた。音楽業界における女性の地位向上のためにも行動する、フェミニストでありアクティヴィストでもある。そのDJスタイルは一言では形容しがたい、非常に独特なもので、ジャンルで言えばアンビエントからエレクトロ、歌物からミニマルまで非常に幅広く縦横無尽にミックスしていくのだが、ただ色々かけているというのではなく、彼女の中で明確なイメージやテーマがあり、それをもっともオブスキュアでレフトフィールドな選曲によって紡ぎ出していくような、まったく予測不可能ながら、いつも彼女らしいちょっぴりストレンジな高揚感に到達させてくれるのである。Ben UFO や DJ NOBU も絶賛する彼女の個性を、ぜひ一度体験してみて欲しい。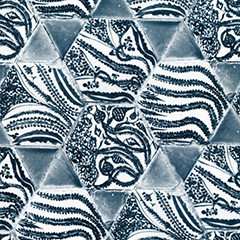
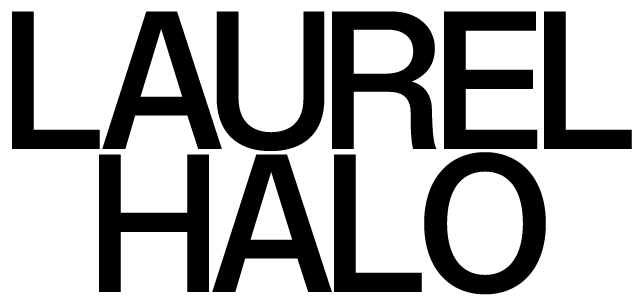
 label: HYPERDUB / BEAT RECORDS
label: HYPERDUB / BEAT RECORDS アーティスト: Jeff Parker / ジェフ・パーカー
アーティスト: Jeff Parker / ジェフ・パーカー アーティスト: Jamire Williams / ジャマイア・ウィリアムス
アーティスト: Jamire Williams / ジャマイア・ウィリアムス