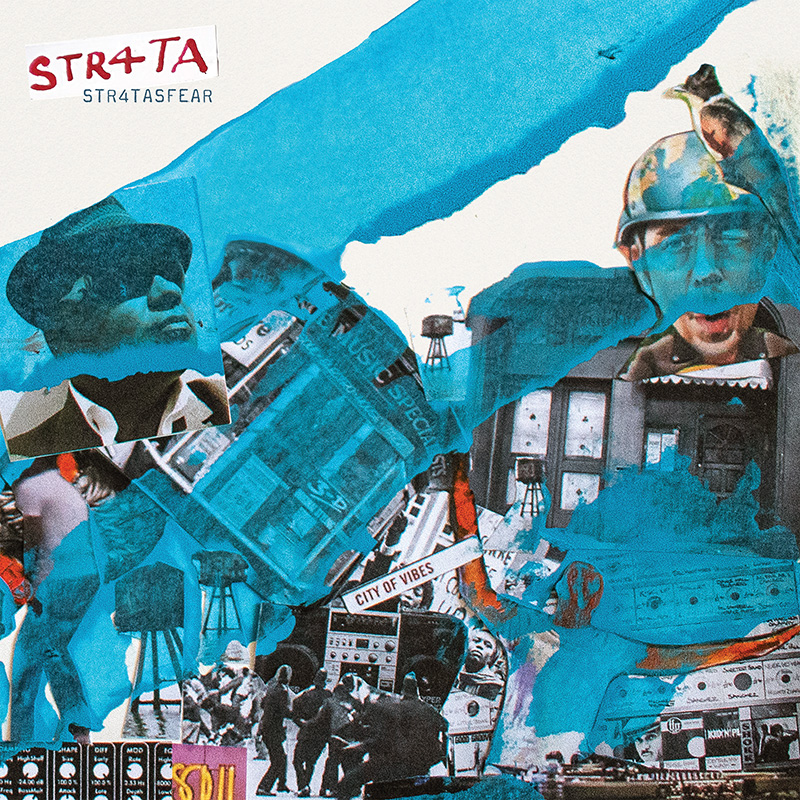日本語をいかにリリックとラップで操るか──その一点の革新性において、日本語ラップが大きな転換期を迎えた。これは、KOHH 以来となる大きな変化と言えるだろう。『ele-king vol.30』掲載、2022年ベスト・アルバムについてのテキスト(12月27日発売)で、私は次のように記した。「2022年は、Watson の年だった。雑多なサウンドがひしめくフェーズへとシーンが突入しているからこそ、圧倒的な強度のリリックとラップを矢継ぎ早にドロップし続けた彼が、シンプルに勝者である」と。先日、早くも今年2枚目となるアルバム『SPILL THE BEANS』を発表したばかりの Watson だが、そもそも春にリリースされた『FR FR』すらいまだ十分に語られていない。すでにヘッズの間では確固たるプロップスを築き上げているこのラッパーに対し、尽くされるべき言葉はあふれている。
以前から “18K” といった曲で垣間見えていた彼のクリエイティヴィティがいよいよ結実した『FR FR』は、次々に繰り出されるラップの集積が、カットを積み上げ延々とフィルムを回し続ける映写機のような技巧で生み出されている。この忙しなくオーヴァーラップし続ける映像的なラップこそが彼のオリジナリティだ。と同時に、映画のごとく移りゆくその描写には、日本語ラップに脈々と受け継がれてきたあらゆる断片も観察できる──RHYMESTER の鋭い一人称、キングギドラの体言止め技法、BUDDHA BRAND のナンセンスな言語感覚、 SEEDA のユーモア──それらすべてを。
1曲目の “あと” から、センスが猛威をふるっている。「金と/あと/知名度/あと/お化粧/加工/が上手い女の子」というリリックから「あと」をタイトルに抜き出す感覚が斬新だ。めくるめくラップを次々に発していくスタイルを、「あと」という一言でサクッと象徴させる軽やかさ。一方で、「踵踏まない大事に履く靴/靴 今トヨタ プップ/No new friends 今ので十分/あの子気になるおれのクリスマス/その日も見えない所skill磨く」というお得意のリズミカルなリリックによって「毎日磨くスニーカーとスキル」(Lamp Eye “証言”)といったクラシックへさり気なくオマージュを捧げることも忘れない。
映写機のごとく回り続ける技巧が最も機能したのは “BALLIN” である。言葉をころころ転がすような早口と叙情的なメロディが同時に奇襲するこの曲は、「辞めたタバコ好きだったナナコ/徳島サッカーのみな産む赤ん坊/ピカソじゃないパブロの真似/古着買ったTommy/そからballin黒髪でもballin/簡単に思い浮かぶ絵/最終は俺が勝つgame」というラインで、パラパラ漫画を彷彿とさせるシーンの転換が見事になされる。さらにはそのような場面展開が、ただことばの次元に留まるのではなく運動となってイメージを喚起する点が Watson の独自性であろう。たとえば、“DOROBO” の「夜書く汗と けつ叩く歌詞を/前行く為でしょ 人間足ついてる2本/関係ないパンパン膨らませるお下がりの財布も/プレ値がパンパンついた服着るおれ丁度いいサイズを」というライン。ここで「人間足ついてる2本」という映像的なリリックを差し込んでくる才能には、ひれ伏すしかない。この2本の足は “I’m Watson” で「金なくって乗れないタクシー都合いいよ俺には/歩きながら書いてるリリック1年前の俺21」というリリックに接続され、見事なモンタージュを見せる。“Living Bet” における、「持つペンが手首につける腕時計」や「枯れる事知らないタトゥーの薔薇」というラインも同様である。耳にするすると飛び込んでくる発音が「腕時計」や「薔薇」というイメージとして立ち上がり視覚へと昇華されるさまは、極めて立体的な視覚性に満ちている。
そもそも、ラップのスキルが桁違いではないだろうか。ハッキリとした活舌が基盤にあるのはもちろんだが、“DOROBO” での「ZARA menのジャケット」「PRADA」など、炸裂する巻き舌が楽曲を随所でドライヴさせる。音程を上げることで高揚感を効果的に演出する技も見事で、同じく “DOROBO” での「なけなしの金」や “I’m Watson” での「チョップ」「パーティ」など、メロディアスなラップのなかでもさらに強弱をつけることで各シーンを映し出すカメラが躍動し続ける。
群雄割拠のラップ・シーンにおいて、いま、高い技術を持ったラッパーは数多くいる。しかし、ここまでスキルフルで独創的でありながらも模倣を促すようなチープさを感じるラップは、それこそ KOHH 以来と言えるだろう。もちろん、その間に LEX や Tohji といった素晴らしい演者もいた。ただ、LEX のラップの新規性はフロウの多様さにあり、Tohji のラップの革新性はラップというフォーム自体の解体作業に宿っている。一方で Watson のラップは、「誰もが真似しやすくゲームに参入しやすい」民主性に則っており、その点で KOHH が『YELLOW T△PE』とともに現れた2012年以来、約10年ぶりにゲーム・チェンジャーとして抜本的にルールを変える力を秘めている。
私は『FR FR』を聴き、随所に用意されたユーモアへ宿る哀愁についてチャールズ・チャップリンを連想せずにはいられなかった。この徳島の若きラッパーが膨大なカットを積み上げ延々と回し続ける映写機によって映し出すのは、「裁判所で泣くママ治すZARA menのジャケット/先輩かばってももらえない約束のお金/これで稼いで贅沢させるマジ/友達にvvsあげたい」といった、哀しみに支えられたユーモアである。ここには、チャップリンの『街の灯』のような、普遍的なドラマ性を支える必死の運動がある。
Watson の時代が来た。日本語ラップの新たなスクリーンが幕を開けたのだ。



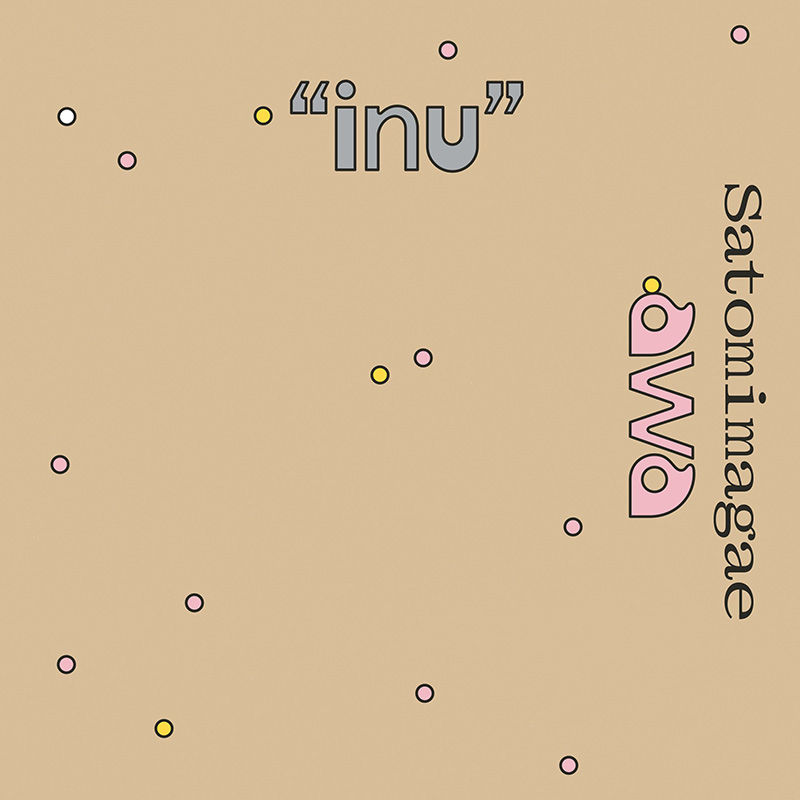


 by Ben Rayner
by Ben Rayner