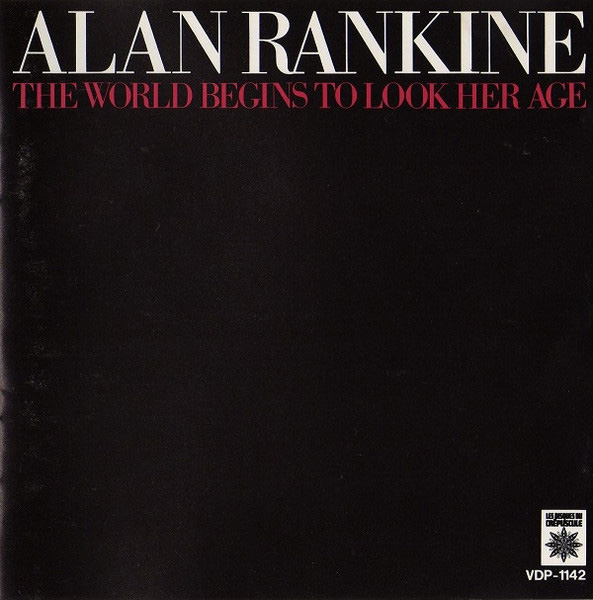モダン・ノイズのカリスマ、アーロン・ディロウェイが来日する。元ウルフ・アイズのメンバーにして、『Wire』誌にいわく「ノイズの扇動者」、そしてテープ・ミュージックの急進主義者、2021年にはルクレシア・ダルトとの素晴らしい共作『Lucy & Aaron』も記憶に新しいアーロン・ディロウェイが来日する。もちろんあの傑作『Modern Jester』(2012)や『The Gag File』(2017年)の作者です。
ディロウェイは2013年に初来日しているが、そのときのすさまじいライヴ・パフォーマンスはすでに伝説になっている。今回は10年ぶりの再来日。東京の〈Ochiai soup〉と大阪の〈Namba Bears〉の2公演のみ。すべてのノイズ・ファンをはじめ、変な電子音楽/実験音楽/アヴァンギャルド好きは必見。
■Rockatansky Records Presents
Aaron Dilloway Japan Tour 2023
2/11 Sat at Ochiai soup
Open 6 pm, Start 6:30 pm
Door 3,500 yen
w/ Incapacitants
Rudolf Eb.er
Burried Machine
ご予約 | reservation:
https://ochiaisoup.com/?event=2022-02-11-sat-rockatansky-records-presents-aaron-dilloway-japan-tour-2023
2/19 Sun at Namba Bears
Open 6 pm, Start 6:30 pm
w/
Solmania
Burried Machine
Info: https://rockatanskyrecords.bandcamp.com
なお、2月10日にはDOMMUNEにて、来日記念番組があり。アーロン・ディロウェイのほか、今回の競演者でもあるキング・オブ・ノイズこと美川俊治。初来日に続き今回の来日も主宰、Nate Youngの初来日も企画するなどWolf Eyes関連との交友を持つBurried Machineこと千田晋、そして編集部・野田も出ます。アーロン・ディロウェイってどんなアーティストなのかを知りたい方は、ぜひチェックしましょう!
Talk : Aaron Dilloway(Hanson Records)、美川俊治(Incapacitants)、千田晋(Rockatansky Records/Burried Machine)
ゲストMC:野田努(ele-king)
Live:The Nevari Butchers