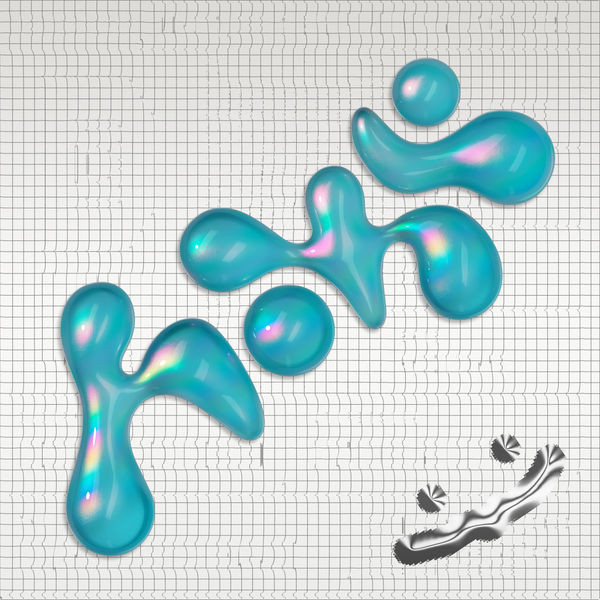昨年より大きな話題を集めていた新バンド、トム・ヨーク、ジョニー・グリーンウッド、トム・スキナーからなるザ・スマイルがついにアルバムをリリースする。告知にあわせ、新曲 “Free In The Knowledge (知のなかの自由)” のMVも公開された。
6月15日に発売される同名のアルバムには、これまで単発で発表されてきた5曲すべてが収録される。プロデューサーはおなじみのナイジェル・ゴドリッチ。フル・ブラス・セクションも参加しているという。どんな作品に仕上がっているのか、楽しみに待っていよう。
The Smile - Free In The Knowledge
THE SMILE
トム・ヨーク×ジョニー・グリーンウッド×トム・スキナー
ザ・スマイル待望のデビュー・アルバム
『A LIGHT FOR ATTRACTING ATTENTION』発売決定!!
レディオヘッドのトム・ヨークとジョニー・グリーンウッド、フローティング・ポインツやムラトゥ・アスタトゥケのバックを務め、現在はサンズ・オブ・ケメットで活躍する天才ドラマー、トム・スキナーによる新バンド、ザ・スマイルが待望のデビュー・アルバム『A Light For Attracting Attention』を〈XL Recordings〉よりリリース。新曲 “Free In The Knowledge” とレオ・リー監督による同曲のMVが公開された。
今回公開された “Free In The Knowledge” は2021年12月にロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで行われたイベント「Letters Live」の一環として、パンデミック以降初めてトム・ヨークが観客を前に演奏して話題を呼んでいた。ザ・スマイルはこれまでにシングル “You Will Never Work in Television Again”、“The Smoke”、“Skrting On The Surface” を連続リリースし、4月3日に発表された “Pana-vision” は英人気BBCドラマ「ピーキー・ブラインダーズ」の最終回に起用された。
アルバムは5つのシングルを含む全13曲を収録し、盟友ナイジェル・ゴドリッチがプロデュースとミキシングを務め、名匠ボブ・ラドウィッグがマスタリングを担当。収録曲にはロンドン・コンテンポラリー・オーケストラによるストリングスや、バイロン・ウォーレン、テオン&ナサニエル・クロス、チェルシー・カーマイケル、ロバート・スティルマン、ジェイソン・ヤードといった現代のUKジャズ奏者たちによるフル・ブラス・セクションが参加。5月13日(金)にデジタル配信され、日本盤CDは6月15日(水)、輸入盤CD/LPは6月17日(金)に発売。
本作の日本盤CDは高音質UHQCD仕様で解説および歌詞対訳が封入され、ボーナス・トラックを追加収録。輸入盤は通常盤CD/LPに加え、限定イエロー・ヴァイナルが同時リリース。本日より各店にて随時予約がスタートする。

label: BEAT RECORDS / XL RECORDINGS
artist: The Smile
title: Free In The Knowledge
release date: 2022/06/15 WED ON SALE

CD 国内盤
XL1196CDJP
(解説・歌詞対訳付/ボーナストラック追加収録/高音質UHQCD仕様)
2,600円+税
CD 輸入盤
XL1196CD(6/17発売予定)
1,850円+税

LP 限定盤
XL1196LPE(6/17発売予定/限定イエロー)
4,310円+税

LP 輸入盤
XL1196LP(6/17発売予定/通常盤)
2,600円+税
BEATINK.COM:
https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=12758