2016年はパンク40周年だったので、自分でもそれにちなんだ書籍を作りたかったのだけれど、今年はそんな余裕を持てず、いまその年も過ぎ去ろうとしている。パンクって何だった? 何だったのか? そんなこともう忘れちまったかのか? はっきりしているのは、13歳のとき、ラジオで初めてそれを聴いて、ぼくはそれ以前のぼくとは別の人間になっていたってことだ。パンクを聴いたからいまのぼくがあり、聴いてなかったら違うぼくになっていた、このことは疑いの余地がない。
The Quietusという音楽サイトにビル・ドラモンドの「PUNK`S NOT DEAD」というエッセー(というか、動画)が載っている。以下、その要約です。
「セックス・ピストルズとザ・クラッシュによって定義されたパンクとは、マルコム・マクラレンとバーニー・ローズに形づけられたものだ。いわばパンク版ティン・パン・アレーは、イーストエンドの服飾産業によって世界に提示された。そのショックと目新しさは、しかし、100年前のミュージック・ホールや軽演劇とたいして変わらない。ギー・ドゥボールを混ぜたラリー・パーソンズ(ロックンローラー)のようなものだ。彼らのパンクは死んだ。
しかし俺たちのパンクは死んでいない。それはこの島全域の公営住宅の狭い部屋のベッドルームのティーンエイジャーの想像によって生まれた。前の世代に何も期待しない10代のガキどもから。ベルファストからコヴェントリー、グラスゴーからブリストル、シェフィールドからマンチェスター、そしてリヴァプール。このパンクは、ピンクのモヘアセーターともチェックのボンデージパンツとも無関係だった。明らかにキングスロードとも服飾産業とも無関係だった。このパンクは、1977年2月29日マンチェスターのバズコックスによって出現した。それは止まらなかった、それは現在も起きている。
親父(マルコム・マクラレン)の持ち物を燃やすロンドンでボロ切れ商売をやっているヤツ(ジョセフ・コー)なんかと俺たちのパンクはまったく関係ない。俺たち全員は親父と問題が絶えなかった」
「俺たちのパンクは死なない」と、60を越えたビル・ドラモンドは力強く喋っております。なぜならそれは、10代の貧しいベッドルームから生まれたものだからと。ぼく個人は、セックス・ピストルズとザ・クラッシュによって定義されたパンクも否定できないのですが、しかしドラモンドのこれがパンク40周年で、もっとも響いた言葉だった。ロンドンの高橋勇人とも話していたが、ストリートでもライヴハウスでもなく、ベッドルームで生まれたというのがいい。
※ビル・ドラモンドは、以前TVの録画撮りで意にそぐわない編集にあい、以来TV出演依頼を拒み、依頼に関してはこうして自分で動画を用意して対応しているようです。
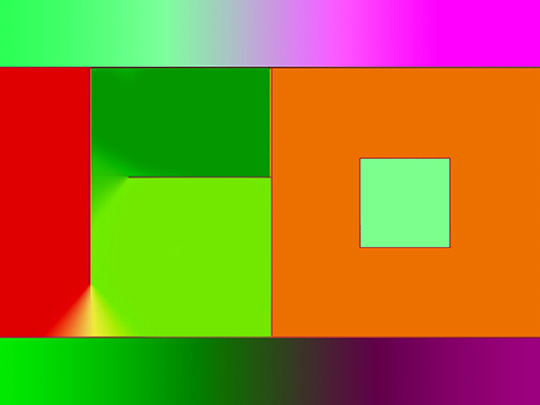







 戸川純 著
戸川純 著