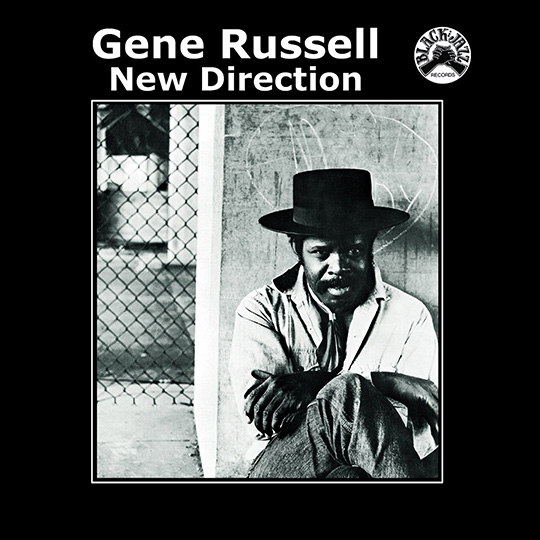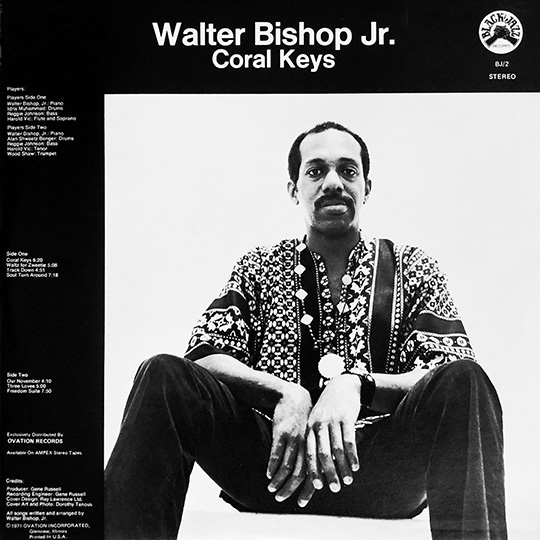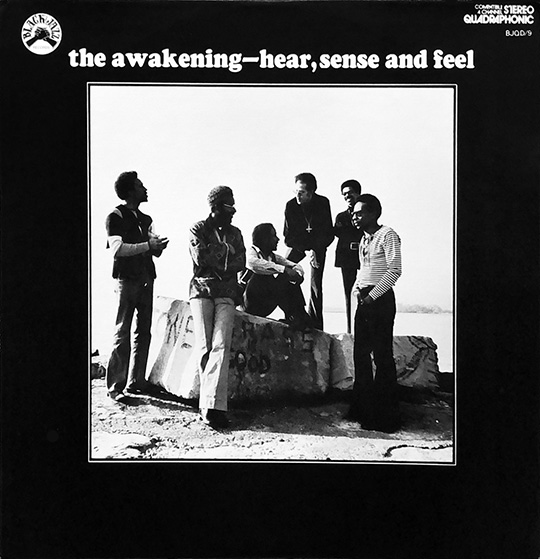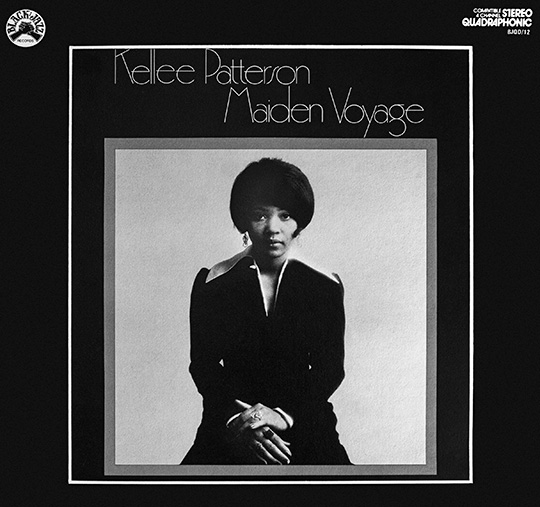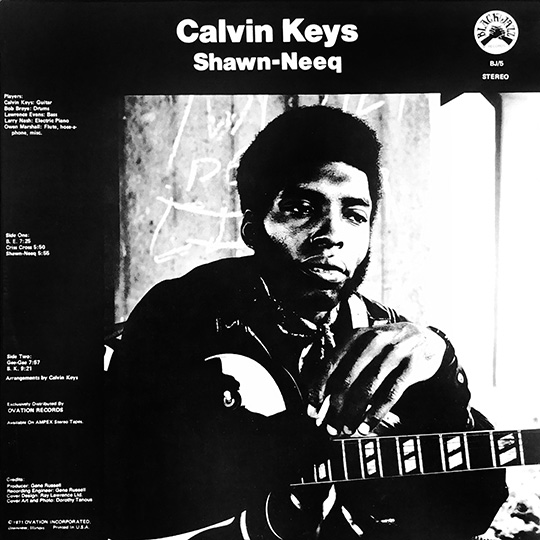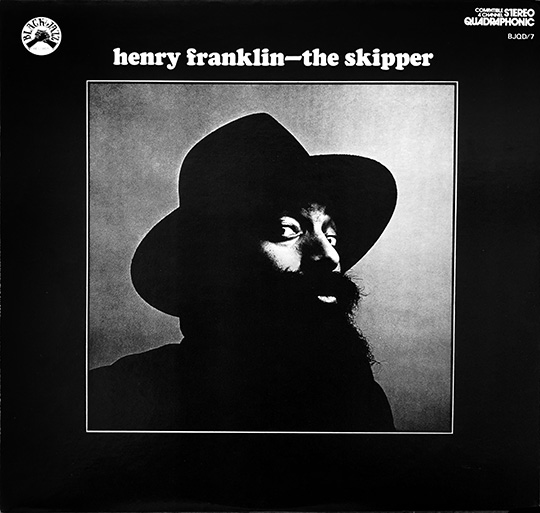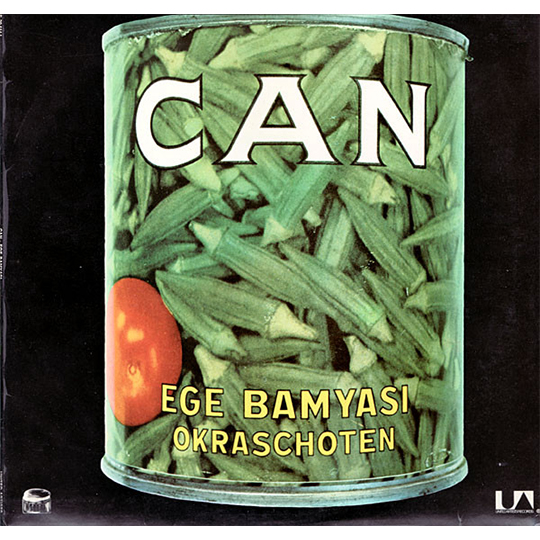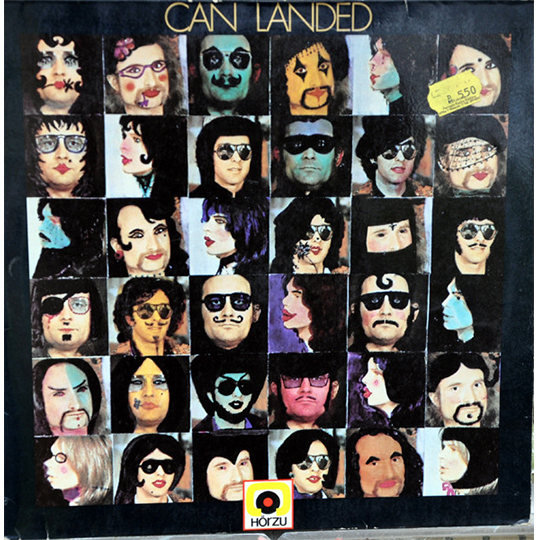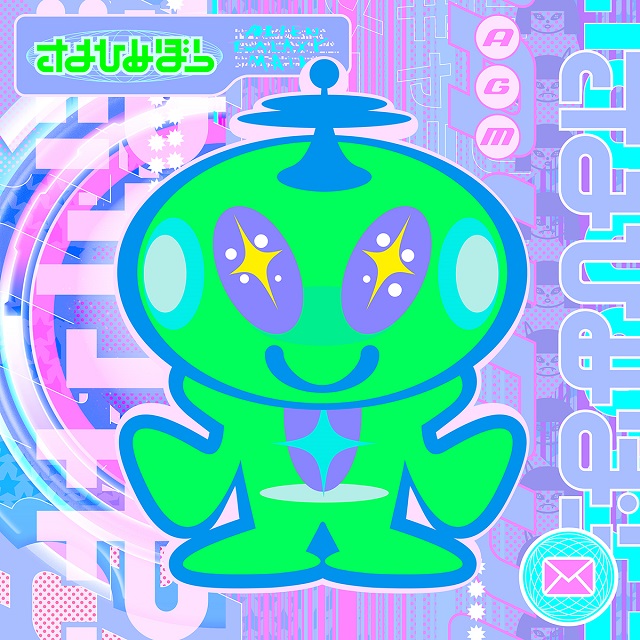生きる意味なら自分で作るわ
新装増補版・全曲加筆
「レーダーマン」「12才の旗」など4曲追加
比類なき情熱の作詞家・戸川純による半自伝的分析
【プロフィール】
戸川純(とがわ・じゅん)
1961年、新宿生まれ。歌手・女優。
子役経験を経て1980年にTVドラマデビュー。『刑事ヨロシク』(82)で初レギュラーを経、『あとは寝るだけ』(83)、『無邪気な関係』(84)、『花田春吉なんでもやります』(85)、『華やかな誤算』(85)、『太陽にほえろ! 第701話「ヒロイン」』(86)など。ヴァラエティ番組では『笑っていいとも!』を始め、『HELLO! MOVIES』や『ヒットスタジオR&N』では司会も。同じく映画では『家族ゲーム』(83)、『パラダイスビュー』(85)、『野蛮人のように』(85)、『釣りバカ日誌(1~7)』(88~94)、『男はつらいよ』(89)、『ウンタマギルー』(89)、『あふれる熱い涙』(92)、『愛について、東京』(93)、『ルビーフルーツ』(95)などに出演。またオムニバス形式の『いかしたベイビー』(91)では監督、脚本、主演をこなす。舞台にも立ち、『真夏の夜の夢』(89)、『三人姉妹』(92)、戸川純一人芝居『マリィヴォロン』(97)、『羅生門』(99)、戸川純二人芝居『ラスト・デイト』(00)、『グッド・デス・バイブレーション考』(18)など。
ミュージシャンとしてはゲルニカの一員としてデビューし、『改造への躍動』(82)、『新世紀への運河』(88)、『電離層からの眼指し』(89)を。ソロ名義で『玉姫様』(84)、『好き好き大好き』(86)、『昭和享年』(89)。戸川純とヤプーズ名義『裏玉姫』(84)。戸川純ユニット名義『極東慰安唱歌』(85)。ヤプーズの一員として『ヤプーズ計画』(87)、『大天使のように』(88)、『ダイヤルYを廻せ!』(91)、『Dadadaism』(92)、『HYS』(95)。ほかに戸川純バンド『Togawa Fiction』(04)、非常階段×戸川純『戸川階段』『戸川階段LIVE!』(16)、戸川純 with Vampillia『わたしが鳴こうホトトギス』(16)、戸川純 avec おおくぼけい『戸川純 avec おおくぼけい』(18)、『ヤプーズの不審な行動 令和元年』(19)をリリース。ほかに映像作品も多数。TOTOウォシュレットのCM出演も評判を呼んだ。
著作類に『戸川純の気持ち』(84)、『樹液すする、私は虫の女』(84)、『戸川純のユートピア』(87)、『JUN TOGAWA AS A PIECE OF FRESH』(88)、『戸川純全歌詞解説集 疾風怒濤ときどき晴れ』(16)、『ピーポー&メー』(18)、『戸川純写真集 ジャンヌ・ダルクのような人』(20)。
【オンラインにてお買い求めいただける店舗一覧】
◆amazon
◆TSUTAYAオンライン
◆Rakuten ブックス
◆7net(セブンネットショッピング)
◆ヨドバシ・ドット・コム
◆HMV
◆TOWER RECORDS
◆disk union
◆紀伊國屋書店
◆honto
◆e-hon
◆Honya Club
◆mibon本の通販(未来屋書店)
【全国実店舗の在庫状況】
 Jam City
Jam City