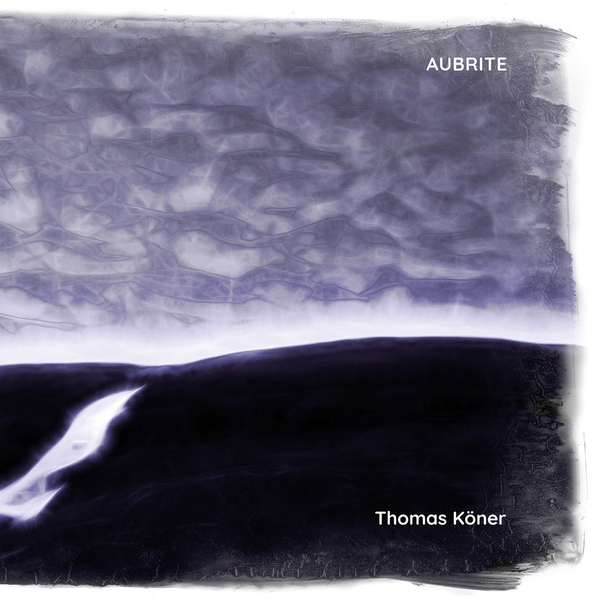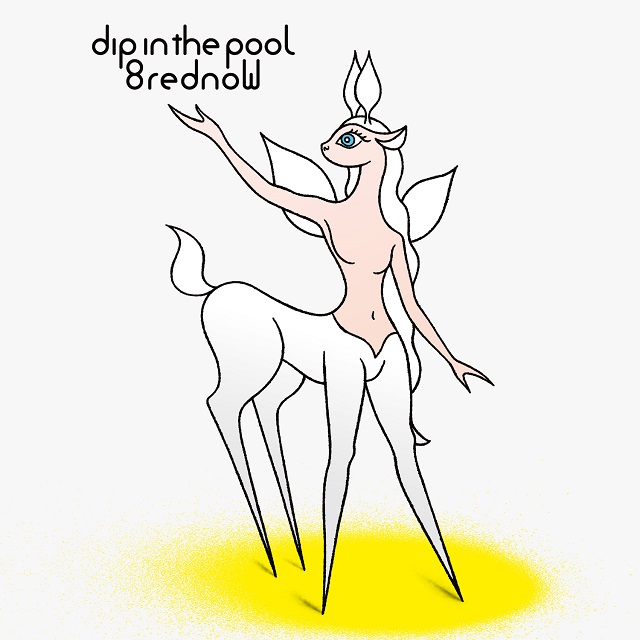ノイズを無視するとかえって邪魔になる。耳を澄ますと、その魅力がわかる。
——ジョン・ケージ『サイレンス』(柿沼敏江 訳)
アーロン・ディロウェイなるアーティストは、今日日のノイズ好きにとってはほとんどカリスマのひとりなのだが、ふだんはノイズを聴かないリスナーのなかにもファンは多くいる。昔から過剰に多作なノイズ界において、ディロウェイのアルバムはたびたび広く注目され、海外のメディアでも積極的に紹介されている。『モダンな道化師(Modern Jester)』(2012)や『ダジャレ名簿(The Gag File)』(2017)といった代表作の題名からも匂うように、そこには「狂気」とともに「笑い」が含まれていることがその理由のひとつであろうと、ぼくはにらんでいる。『ダジャレ名簿』のアルバム・スリーヴは腹話術で使う人形のバストショットだったが、見方によってはある種気味の悪さがあり、別の見方によっては滑稽でもあり、さらにまた別の見方では可愛くもある。こうしたアンビヴァレンスは、ディロウェイ作品の魅力であり、彼のノイズの本質を代弁していると言えるだろう。
ミシガン州デトロイト郊外の町ブライトンで生まれ育ったディロウェイにとってのもっとも初期の影響は、少年時代に出会ったバットホール・サーファーズだ。子供だったこともありバンド名からしてゲラゲラ笑ったそうだが(but holeにはケツの穴、いやな奴などといった意味がある)、これがパンクってもんだと教えられた彼にとって、あとから聴いたセックス・ピストルズは、ただただ凡庸なロックにしか聴こえなかった。
ディロウェイの影響でもうひとつ大きかったのは、キャバレー・ヴォルテールの『ザ・ヴォイス・オブ・アメリカ』だ。テープ・コラージュ(高尚に言えばミュジーク・コンクレート)という、彼の創作におけるもっとも主軸となる手法を彼はこのアルバムによって知った。で、それをもって、1998年にミシガン州デトロイト郊外の町アナーバー(デストロイ・オール・モンスターズの故郷)にて、インダストリアル・ノイズ・バンド、ウルフ・アイズを結成、ディロウェイ自身のレーベル〈Hanson〉からデビューする。とは言うものの、ディロウェイは、ウルフ・アイズがゼロ年代半ばに大手インディの〈サブ・ポップ〉からアルバムを出すくらいにまでになってしまうと、プロモーションなどが面倒でバンドを去る。以来彼は、コラボ作こそ多くあれど、基本的にはソロ・アーティストとして活動を続けている。
ディロウェイはかつて、イギリスのFACTマグの依頼でDJミックスを作成したことがある。選曲はすべてビートルズやらストーンズやらボウイやらといった超有名どころの、ただしコピー・バンドの演奏を集め、エディットし、そこに不快で奇妙なノイズをミックスしたものだった。安倍晋三ではないが自分たちサークルの正統性を振りかざし、その外部を批判ばかりしている人たちを舐めきっているかのようなノイズ、いかにもディロウェイらしいキッチュなものへの愛情、いかがわしさへの関心は、有名ロック・バンドのライヴ映像の海賊版VHSへの偏愛にも言える。いささかアイロニカルとはいえ、ディロウェイの創作にはメタな視点があり、彼の諧謔性はキャプテン・ビーフハートやザ・レジデンツにも通じている。奇怪なその音響、サウンドプロダクションに関して言えば、AFXの牧歌的ではない側面が(も)好きなリスナーにも推薦したい。
コミカルで、よく見ると不気味なスリーヴアートをあしらったディロウェイの新作は、〈Rvng Intl.〉からの作品で知られる、現在はベルリン在住の電子音楽家、ルクレシア・ダルトとの共作『ルーシー&アーロン』、これがじつに良かった。考えてみれば、男女のデュオという点では前回レヴューしたマリサ&ウィリアムと同じで、ふたりの個性が合流することでマジックが生まれているという点もまた同じ、音楽性は著しく違っているけれどね。なにしろこちらはディロウェイのバカバカしいテープ・ループ、不快なミニマリズム、ダルトの妖しい声と幻想的なシンセサイザーによるシュールで魅惑的なガラクタというか呪文というか。しかもユーモアと恐怖が交錯する『ルーシー&アーロン』には、曲によってはグルーヴもあり、所々ぼくにはファンキーに聴こえたりもする。ひとつの感情に凝り固まらない、安易にディストピアでもない、こうした毒の入った笑える音楽は、自分の正気を保つためにもいま必要なのだ。
現在はオハイオ州オバーリンで暮らしているディロウェイは、ダルトとは数年前のツアー中に知り合っている。お互いを賞賛し合っているふたりはアルバムを作ることを決め、その多くはNYで録音されている。残りの作業はそれぞれの自宅、ベルリンとオバーリンで終えたそうだ。なお、ディロウェイはこの10月末、ジョン・ケージの作品を蒐集し、整理し、広める非営利団体「ジョン・ケージ・トラスト」からの招待を受けてケージの12台のレコーダーを使用したテープ音楽作品「Rozart mix」をディロウェイなりの解釈で演奏することになっている。また、キム・ゴードンとビル・ネイスによるプロジェクト、Body/Headにディロウェイが参加した作品『Body/ Dilloway/Head』も直にリリースされる。