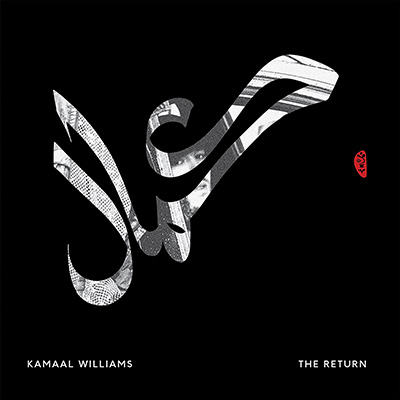TT LoveLaws LoveLeaks / ホステス |
かのハリー・スタイルズが、昨年~今年のワールド・ツアーでオープニング・アクトに指名したのは、ケイシー・マスグレイヴスとリオン・ブリッジズ、それからウォーペイントだった。ガーディアン誌は以前、この1Dのメンバーによるプリンスと同名異曲のヒット曲“Sign of the Times”を紹介する際に、NYを代表する燻し銀のインディー・バンド、ザ・ウォークメンの名前を挙げていたものだが、彼が選んだ3組――現代カントリーの花形と、レトロ・ソウルの新星、独立独歩のLAガールズ・アート・バンドという並びには、英国の白人ポップ・スターから見た「いまのアメリカ」が反映されていた気がしてならない。
ウォーペイントのヴォーカル/ギター、テレサ・ウェイマンによる初のソロ・アルバム『ラヴローズ』の制作は、バンドが2016年に発表したサード『ヘッズ・アップ』よりも早くからスタートしていた。彼女はみずから歌い、ギターを弾くばかりか、ベースやシンセ、ビートのプログラミングまで一手に担当。ポップで開放的だった『ヘッズ・アップ』に対し、『ラヴローズ』は繭に包み込まれるように、内向きでパーソナルな音像を描いている。シューゲイザーやトリップホップの要素も見え隠れするが、実際にはこのあとのインタヴューでも語られているように、ヒップホップの影響がとにかく大きかったらしい。
共同プロデューサーとして、ケイシー・マスグレイヴスにも携わった実兄のイヴァン・ウェイマンと、ウォーペイント人脈とも縁の深いダン・キャリー(フランツ・フェルディナンドの3作目『トゥナイト』など)がクレジットされており、バンド仲間のジェニー・リーとステラ・モズガワ、古参リスナーには驚きのマニー・マークなど多彩なゲスト陣にも目を惹かれる。しかし一方で、密室的な『ラヴローズ』は「ひとり」を強く感じさせるアルバムだ。そんな本作のテーマは「愛」。他の記事によると、かつて交際していたジェイムス・ブレイクとの破局も(あくまでポジティヴな形で)反映されているそうだが、ウォーペイントとしてデビューしてから14年が経ち、37歳の母親となった彼女は、月が夜を照らし、孤独がやさしさをもたらすように、一面的ではない「愛」のかたちを歌っている。

自分がキュレーターだとしたら、楽曲はアートギャラリーね。私はギャラリーにさまざまな絵画を並べることで、一編のストーリーを作り上げていくの。
■そもそも、どういう動機でソロ・アルバムを作ろうと思ったのでしょう?
テレサ・ウェイマン(Theresa Wayman、以下TW):自分自身をもっと探求してみたかったの。それに曲を書いたり、いろんな楽器を弾いたりすることで、いちミュージシャンとしても成長したかった。そう考えて取り組んでいくうちに、100%自分の音楽をやることの必然性を感じるようになったのよ。
■昔からバンド活動と並行して、そういう個人としてのレコーディングもおこなっていたんですか?
TW:ええ。昔からPCを使って少し作ってたんだけど、2009年に入ってから本格的に制作するようになって。その頃はLogicのUltrabeatという安っぽいのを使ってたんだけど、2年後にGeistというソフトウェアと出会ったことで、曲作りの仕方が一変したの。LogicとGeistを組み合わせながらの制作は自分のワークフローとすごく合っていて、アイデアもどんどん湧くようになった。
■今回のアルバム収録曲とは別に、まだ世に出ていないデモもたくさんありそうですね。
TW:何百とあるわ(笑)。
■そういう自分の曲って、どういうモチベーションで作っているんですか?
TW:普段から音楽をよく聴いていて、そこから自分でも曲を作りたくなるの。それで、真っ白なキャンパスのうえにいろいろ描いていくうちに、最初に想定していたのと違う方向にどんどん進んでいったりして。そういうのが楽しくて仕方がないのよね。
■へぇ。
TW:例えば、アルバムに“Mykki”という曲があるでしょ。これはミッキー・ブランコの“Wavvy”を聴いていたときに生まれた曲で、ワーキング・タイトルをそのまま採用したの。とはいっても、彼の音楽とはまったく雰囲気の違う曲になったんだけど、サビの部分で「make it feel」と歌ってるくだりが、なんとなく「Mykki」って聴こえる気もするのよね。
■じゃあ、6曲目の“Dram”はラッパーのDRAMから?
TW:違う(笑)。これは「ドラマティック」からきているの。
■話を伺いながら納得するところも多いですが、ギタリストによるソロ・アルバムだからといって、ギターを弾きまくる類の作品ではないですよね。音作りについてはどんなテーマを設けていたのでしょう?
TW:ただ感じるがままに、それぞれの曲に相応しいものを作っていった感じかな。出だしのパートにギターを入れるのがベストだと思ったら弾くし、他のサウンドを入れるべきだと思ったらた迷わずそうする。自分がキュレーターだとしたら、楽曲はアートギャラリーね。私はギャラリーにさまざまな絵画を並べることで、一編のストーリーを作り上げていくの。そもそも、私自身いろんなパーソナリティをもっていて、ギタリストであることがすべてではない。「この楽器じゃなきゃいけない」というこだわりは特にないのよね。
■ウォーペイントの一員という立場を一旦離れて、ソロになったからできたことってなんだと思いますか?
TW:ベースが弾けることかな(笑)。あと、ドラムビートを自分で作ったりね。音楽を作るのは、自分がどういった人間であるのかを理解する手段でもあると思うの。今回は私自身のためにアルバムを制作したから、いつもより自分のなかに深く潜り込むことができたと思う。きっと私は、そういう探究心が強い人間なんでしょうね。
■このアルバムは、エレクトロニック・ビートも聴きどころだと思います。ヒップホップやファンクの要素も感じましたが、どんなことを意識しながら打ち込んだのでしょう?
TW:うまく言えないけど、Geistを通じて自分好みのサウンドを見つけたり、それらをPro Toolsで組み立てながら、ピッチを下げたり、フィルターをかけてファジーで温かみのある音にしていく感じかな。そうやってループを作ったら、そのバリエーションを構築していく。個人的には、ストレートなものよりもランダムな要素を入れていくほうが好き。
■なるほど。
TW:私がヒップホップを好きな理由のひとつは、完璧なループさえ用意できたら、あとはそれを永遠に鳴らしているだけで曲が成立するところ。それって物凄くパワフルだと思う。あとはそうね……私の場合は、必要に応じて生ドラムも入れるようにしている。100%エレクトロニックではないかな。
■いまの話にもあったように、BPMが全体的に緩やかですよね。
TW:そうね。ムードのある音楽が作りたかったし、聴き手に押し迫るようなものではない、ダウンテンポなアルバムにしたかった。でもグルーヴはあるはずだし、スロウだけど踊ることのできる音楽になっていると思う。だからこれは、夜向きのアルバムじゃないかな。
■あと、歌声の使い方も興味深かったです。ウォーペイントにはあなたも含めて複数のヴォーカリストがいますけど、ここではコーラスで自分の声を重ねたり、普段と違うアプローチに取り組んでいますよね。
TW:それはハーモニーが大好きだから(笑)。ただ、声を重ねすぎるのもそんなに好きではないの。だから、(音を重ねない)一本のヴォーカルをよりよく聴かせようというのは意識したわ。そうすることで、サビで声を重ねたり、曲が進むにつれて和音を増やしたり――チョコレートケーキのように豊潤なハーモニーも活きると思うから。あと、ハーモニーのなかに低音が結構入っているはずだけど、そういう声の使い方がもたらすフィーリングも好きなの。
■収録曲でいうと、“Love Leaks”のハーモニーはいいですよね。ゴスペルっぽさもあったりして。
TW:たしかに。5曲めの“Tutorial”にも、ゴスペルっぽい分厚いハーモニーが入っていると思う。
愛についてだったら、いくらでも曲が書けると思う。『ラヴローズ2』や『ラヴローズ3』だって作れるくらい(笑)。
■ハーモニーという観点で、誰か好きなアーティストはいますか?
TW:いい質問ね。ヴィンス・ステイプルズの“Dopeman”かな。歌っている女の子の名前が思い出せないけど(筆者注:キロ・キッシュのこと)、ハーモニーの重ね方が素晴らしくて、あの曲には大いにインスパイアされたわ。あとはリアーナも……うーん、どうだろう(少し考え込む)。とにかく、ヒップホップのコーラスで好きなものはたくさんあるわ。
■アルバムのゲストや制作陣のなかで、個人的にはマニー・マークの参加が気になったんですが、彼とはどのように知り合ったのでしょう?
TW:一緒にコラボしている友人を通じて知り合ったの。アルバムが完成目前のところでマークを紹介してくれて、2日間くらい一緒に音を出したりしているうちに意気投合してね。それで、彼の意見も知りたかったから、アルバムの音源を聴いてもらったら、「こうしたらどう?」って適切なアドバイスをしてくれたの。
■前情報のせいもありますが、マークが参加している“Love Leaks”と“Tutorial”のメロウネスは、彼が鍵盤を弾いているビースティ・ボーイズのインスト曲とも重なる雰囲気がある気がします。
TW:どうだろう。さっき話したように、曲自体はほとんどでき上がっていて、彼はそこに少し音を加えてくれた感じだから。
■一昨年、ウォーペイントの“New Song”をマイク・Dがリミックスしていたじゃないですか。だから、あなたがビースティの大ファンだとか、密接なコネクションがあったのかと予想していたんですが……。
TW:ううん、そうじゃないの(苦笑)。
■そのあたりはさておき、ウォーペイントの『ヘッズ・アップ』では90年代のスタイルを意識していたそうですが、今回のアルバムもトリップホップなど、当時のある種の音楽と同じようなフィーリングを感じました。
TW:そこは全然意識してなかったつもりだけど、「トリップホップっぽい雰囲気だね」って感想にも納得できるの。ダークな曲調でビートがあるけど、かといってヒップホップではないし、やっぱり白人が作った音楽だなって。それに、もともとトリップホップの醸し出すムードは好きだったし、自分が若い頃にミュージシャンを志すきっかけをくれたのも、トリップホップのアーティストが多かったから。ようやくここにきて、自分でもそういう音楽が作れるようになったのかもね。
■最初に「自分を掘り下げたかった」という話がありましたが、歌詞の面ではどういったことを伝えたかったのでしょう?
TW:テーマになっているのは、大きな意味での愛。実体験に基づくものもあれば、ファンタジーもあるし、束の間のロマンスや、失恋についても歌っている。ほかにも友情とか、自分を愛すること――いろんな種類の愛を歌っているけど、どの曲もすべて自分の人生経験から生まれている。私自身、母親でありながら、世界中をツアーで廻る生活をしていることに思うところもあってね。どこにも還る場所がないと感じることもあったけど、音楽こそが自分の居場所なんだなって、このアルバムを作りながら強く感じたの。
■そうですよね。男女のロマンスのみに留まらない、広くて深い視点は歌詞からも伝わってきます。
TW:愛についてだったら、いくらでも曲が書けると思う。『ラヴローズ2』や『ラヴローズ3』だって作れるくらい(笑)。
■愛(love)に法則(Law)があるとすれば、それはなんだと思いますか?
TW:人間関係における根本的な部分、もっとも根底にある法則こそが愛なんだと思う。お互いをリスペクトしたり、愛し合う気持ちがあってはじめて社会が成り立つわけで。でも、いまの時代は憎しみの感情が氾濫していて、バランスが取れなくなっている。
■ええ。
TW:それに恋愛も含めて、人との付き合い方にはいろんな関係性があるわよね。ロマンチックなものに、友情とか家族との繋がりだってそう。それに、必ずしも上手くいく関係だけではないわけで。人との繋がりがうまく機能しなかったり、自分自身を大事にすることができなかったり、いろいろな事情で苦しむこともある。そういった話も含めて、私たちが生きていくうえで、愛はものすごく重要で大きな位置を占めている。それぐらい普遍的なテーマだと思うな。