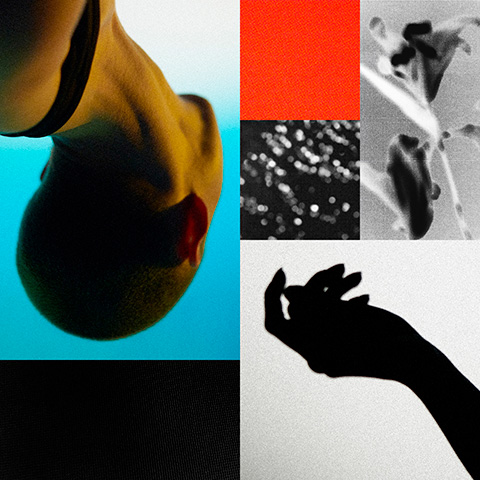Eccy復活のニュースが意外なところからやって来ました。2ndアルバム『Blood The Wave』以来7年ぶりのフルアルバム『NARRATIVE SOUND APPROACH』をリリースするようです。しかも元銀杏BOYZの安孫子真哉が主宰する〈KiliKiliVilla〉から。Eccyは以前から銀杏BOYZのリミックスやプロデュースをしていたから違和感こそないものの、このニュースには驚きましたね。〈KiliKiliVilla〉やるなあ。確実にこの2017年、目が離せないレーベルの一つです。
今回のニューアルバムにはShing02、そして超久しぶりのあるぱちかぶといったメンツから、泉まくらやどついたるねんといった少し変化球な人たちも参加していて、特にどついたるねんが参加している「Sickness Unto Death」は、いい意味で「今これをやるか!」といったオールド・スクール・チューンで思わずニヤリとしてしまいますよ。
アルバムのリリースに先駆けて、「Lonely Planet feat. あるぱちかぶと」の7インチもリリースされているようです。アルバム収録曲のMVが数曲公開されているので、お見逃しなく。
Eccy - Lonely Planet feat.あるぱちかぶと
アーティスト:Eccy
タイトル:『Narrative Sound Approach』
レーベル:KiliKiliVilla
発売日:2月22日
品番:KKV-039
価格:2,160円(税込)
TRACK LIST :
01. Splendor Solis
02. 天蓋のオリフィス feat. Shing02
03. After Midnight
04. Sickness Unto Death feat. どついたるねん
05. Modular Arithmetic
06. The Fool (Upright) feat. Candle,Meiso
07. Odd Eye
08. Blood feat. 泉まくら
09. Open Face Spread
10. Lonely Planet feat. あるぱちかぶと
11. あのころ僕らは
[ご予約はこちら]
AMAZON:https://www.amazon.co.jp/NARRATIVE-SOUND-APPROACH-ECCY/dp/B01MSYB1HF
Eccy/エクシー
1985年生まれ、東京育ち。2007年10月、Shing02をフィーチャーしたデビューシングル『Ultimate High』でHip Hopシーンに新しい感性で切り込み、デビューアルバム『Floating Like Incense』が新人としては異例のセールスをあげシーンにその地位を確立。その後、環ROYとのコラボレーションアルバム『more?』、toe柏倉やACOなどをフィーチャーした実験作『Narcotic Perfumer』、2ndアルバム『Blood The Wave』などをリリース。P-Vineから発売された『Loovia Mythos』収録曲はRas GのBTS radio mixでも使用された。Low End Theory Podcastでも曲が取り上げられるなど、活躍の場を世界に広げている。2011年にはSam Tiba & Myd(Club Cheval),Subeena(Planet Mu)をリミキサーに迎えた『Flavor Of Vice EP』を発売。Produceワーク多数。RemixワークもShing02から銀杏BOYZまで多岐に及ぶ。Fuji Rock Fes ’07,’08,’09,’12、Sonar Sound Tokyo’12、Outlook Fes Japan Launch Partyなどに出演。2014年にIRMA Recordsよりリリースされた「Into The Light / Dark Fruits Cake」はZomby(XL Recordings)などのアーティストから幅広い支持を得る。NIKEのランニング用アプリ「NIKE RUN TRACK」、Panasonic「Neymar Jr. Chant」に楽曲提供。米COMPLEX MAGによるThe Best Of Japanese Hip-Hop 25 Artistsに選出。2015年、銀杏BOYZ「Too Much Pain(The Blue Heartsカバー)」トラックプロデュース。2016年、銀杏BOYZ公式ライブ映像作品「愛地獄」OP、ED曲を楽曲提供。