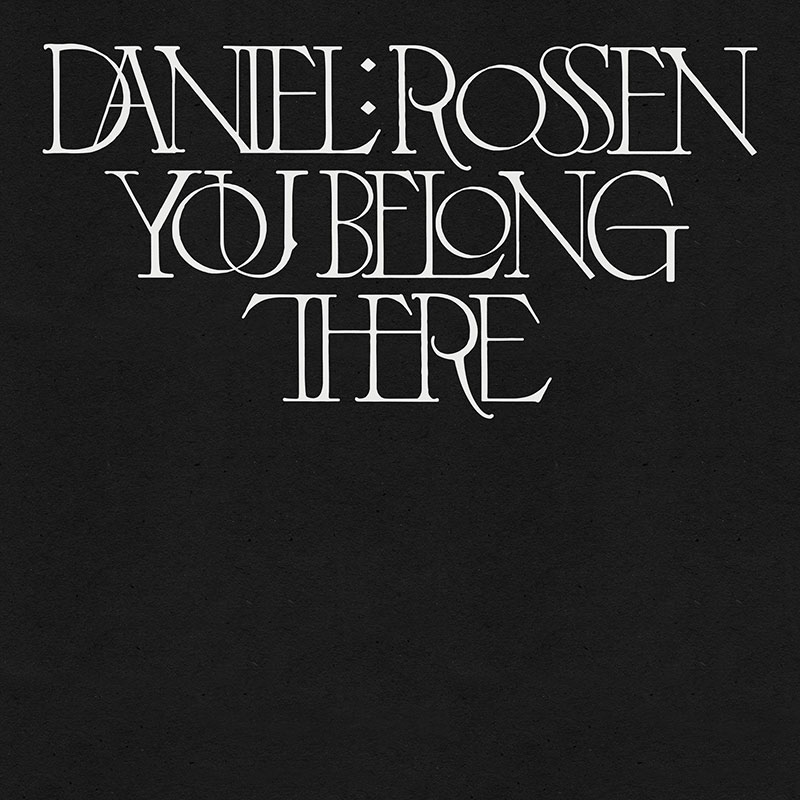PiLのマスターピース『Metal Box』(79)に収録された“Radio 4”はキース・レヴィンがひとりで多重録音したもので、2016年のデラックス・ヴァージョンに収録されたレコーディング・テイクを聞くと、当初はカウボーイ・インターナショルのケン・ロッキーがドラムを叩いていたことも明らかになった(尺も倍近い→https://www.youtube.com/watch?v=se-Z6EO5pfA)。ベースもわざわざジャー・ウォッブルをマネて弾いたものだとレヴィンは述懐していて、広いスタジオでポツンと作業していた「冷たさ」が曲のムードに反映されているという。そして、最終的にドラムを抜いて短くエディットしたものが『Metal Box』のラストに収められ、それはまるでビートルズ“Good Night”と同じくチル・アウト効果をもたらすことになる。『Metal Box』という複雑怪奇な迷宮に鮮やかな出口を用意してくれたというか。“Radio 4”はビニール袋のようなものが膨らんだり縮んだりするようなイメージを繰り返す。それはオーケストラが短いコードしか弾かないとどうなるかというアイディアから出発した結果だそうで、ドラムを抜くことでその効果は最大限まで引き上げられた。『Metal Box』はどの曲も印象深く、いまだに得体の知れない感じがあり、とりわけ“Radio 4”はミステリアス度が高い。
チリからフアン・マッジョーロ(Juan Maggiolo)とドイツ系らしきヴェルナー・ハインツ(Werner Heinz)によるデビュー作を聴いた時、それはまるで“Radio 4”が8つのヴァリエーションに増幅されて蘇ってきたという印象を僕は持った。かすかにジャー・ウォッブルのようなベース・ラインが聞き取れる曲もある。スピーディーなアンビエント・ドローンを基本にポップな味付けが多種多様に施されたカラフルな展開。マイ・ブラッディ・ヴァレンタインが“Radio 4”をカヴァーしたり、リミックスしたり、様々な手法を用いてカスタマイズしたような……。ドローンといっても大して持続せず、細切れになっているせいでそう感じるだけかも知れない。とはいえ、キース・レヴィンのいう「冷たさ」も似通っているし、頻繁に転調するのも一因をなしている。何度も聴き込んでいるうちにやはり違うとは思うものの、初期イメージから脱却したくない気分も手伝って、いまのところ『Abraxas』は僕にとっては43年後の“Radio 4”である。アブラクサスとはちなみにグノーシス思想における偽神で、選ばれし者を天国に連れていくというニューエイジのフェイクのような存在。その姿はヒトの体にライオンの頭と下半身は蛇。
南米のアンビエント・ミュージックはどうも得体が知れない。フアン・ブランコであれ、トマス・テロであれ、アカデミックな手法を使ってもその様式美に呑み込まれないという共通点があり、アブラクサスの2人がアカデミックなキャリアを持っているかどうかも想像がつかない。ついでにいえばアロンドラ・デ・ラ・パーラのようなクラシックの人でさえ、指揮をしながら踊りだしたり、パリの観客が手拍子を始めるなどアカデミックの枠組みは崩壊している。アブラクサスの背景にはなんとなくクラブ・カルチャーが横たわっているような気もするけれど、ヴィラロボスやアトム・ハートが撒いてきた種が花開いたにしてはタイミングが遅いし、そもそもドイツ資本とつながりがあるのかないのかよくもわからない。ここにあるのはイメージ豊かな曲の数々と曲の雰囲気には悪い予感のかけらもないこと。チリは一時期はコロナによって危機的状況を呈したものの、現在では南半球でもっともコロナの危険から遠い国という評価を受け(新自由主義に基づく税制に改められたことで連日のようにデモが起こったコロンビアとは対照的)、フランツ・エデルマン賞まで受賞している。そういった国の気分が感じられる作品でもある。つーか、『アンビエント・ディフィニティヴ 増補改訂版』を校了した10日後にリリースされやがった。く~。