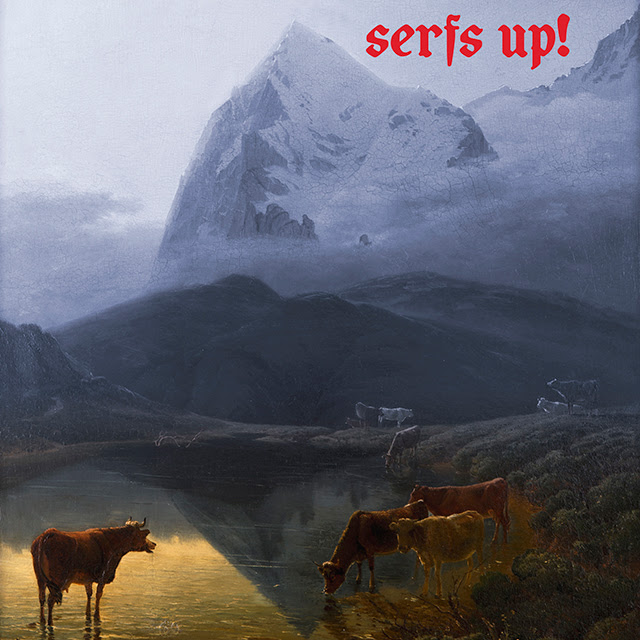ベルリンの壁が崩壊した時にはまだ7歳だったというトーマス・ステューバー監督がドイツ統一直後のライプツィヒ(旧東ドイツ)を舞台に描く『希望の灯り』。フランツ・ロゴフスキ演じる主人公のクリスティアンは研修先のスーパーマーケットでタトゥーを客に見せてはいけないと最初に釘を刺される。永遠に繰り返されるかと思うほど反復される開店の準備や毎日の労働の場面で、何度も何度もタトゥーを隠そうと袖を引っ張るクリスティアンの仕草はそれだけで順応の儀式であり、統一後のドイツに組み込まれようとする覚悟として彼の意志を伝えるものになっている。東ドイツ時代に彼はどうやらヤクザまがいの生活をしていたようなのだけれど、それについて多くは語られない。ショーペンハウアー風にいえば、どこから来たのかはわからないけれど、どこに行くかだけはわかっている。統一後のドイツとはつまり資本主義社会ということである。日本ではいま水道事業が民営化されるだけでオタオタしていたりするのに、東ドイツは統一後に国がまるごと民営化したわけで、『社会契約論』が吹き飛び「万人の万人における闘争」状態に引き戻されたような精神状態に陥ったに違いない。クリスティアンはとにかく仕事を覚えなければいけない。『希望の灯り』の前半はただひたすら夜間労働の場面が繰り返されるだけで、それだけで最後まで押し切ってしまうアート作品にならないことを祈るばかりであった。

クリスティアンは極端に口数が少ない。何を考えているのかわからない。最初は周囲の人たちと心を通い合わせる気配もなく、彼の視点を通して得られる視界の狭さだけが印象付けられる。この映画の原題は『In den Gängen (In the Aisles)=通路にて』で、それは彼の人生がスーパーマーケットの一部に集約されていることを意味している。彼は商品を積み下ろすためにフォークリフトの操作を覚え、乱暴に運転するぐらいしか楽しみを見出せない。倉庫に置かれた水槽から魚が飛び出そうとするけれど、結局、飛び出せないシーンは彼の心象風景そのままであり、映画で使用されている音楽がスーパーマーケットで流されがちなクラシックとシュラッガー、そして労働の象徴としてのブルースだけというのも世界の狭さを畳み掛けてくる。駐車場の向こうにはアウトバーンがちらちらと映り込む。クリスティアンに仕事を教えてくれるブルーノ(ペーター・クルト)は東ドイツ時代にはトラックの運転手をしていたといい、その言い方には東ドイツ時代には移動の自由があったけれど、資本主義になった現在、彼にはそれに類する自由がないと言わんばかりの含みがある。(以下、ネタバレ)そしてクリスティアンに仕事を教え終えたブルーノは自殺してしまう。考えてみればアウトバーンも「通路」である。「通路」というのはどこかに通じているから「通路」なのに、クリスティアンたちは「通路」にいることが仕事であり、一生出られないかもしれない場所なのである。

商品棚の向こう側には同じ店で働くマリオン(サンドラ・ヒュラー)がいる。単調な労働の日々が続くなか、彼は彼女に興味を持ち始める。「通路」に閉じ込められている同士が、そして「休憩室」で一緒にコーヒーを飲む。それだけが邦題にある「希望の灯り」となる。しかし、既婚者であり、夫から暴力を受けていると聞いたマリオンが続けて休みを取ると、クリスティアンは「通路」を飛び出して彼女の家へ向かう。この映画では唯一に近いといえるほどスーパーマーケット以外の場所がスクリーンに映し出され、ただの住宅地は別世界のように見える。そして、クリスティアンはコントロールを失ってしまうものの、その時だけが生き生きとしていたことも確かである。「東ドイツは確かにシュタージがいましたが、独裁者がいた国ではありません。いいところもあった、むしろ今よりも女性は解放されていました」とステューバー監督は語る(パンフレットより)。いま、この映画をつくる意味はノスタルジーだけではないだろう。資本主義がかつてなく肥大し、クリスティアンたちが働くスーパーマーケットがこの世界をすべて覆ってしまったとしたら、それとは違う社会システムの下で暮らしていた人たちの思い出はそれだけで現代に対する批判の要素を持つ可能性がある。邦訳はされていないようだけれど、『通路にて』を著し、ここでは脚本も手がけているクレメンス・マイヤーには『おれたちが夢見た頃』という長編小説があり、東独版『トレインスポッティング』と評されているらしい。ブレクジットやイエローヴェストで急速に可視化されつつあるヨーロッパの下層階級を小説という形でマイヤーはすでに先取りしていたのだろう。

グローバリゼイションの時代に移動の自由を享受できない人々はもはや奴隷と変わらない。一か八かに賭ける難民たちはどっちの範疇に収めればいいのかよくわからないけれど、『希望の灯り』で描かれる人物たちはスーパーマーケットの全景さえ映されることなく、常に「通路」とセットでしか表現されない。クリスティアンとマリオンは最後にフォークリフトを操作しながら油圧装置から漏れる空気の音が「波の音」に聴こえるという。自殺したブルーノが教えてくれた秘技である。アウトバーンというのは都会から一瞬にして自然の中に戻れるようにとヒトラーが建設した高速道路であり、ドイツ人にとって本物の自然と触れ合うことは過剰なまでの意味を持っている。しかし、クリスティアンとマリオンは本物の自然ではなく、フォークリフトに海の音を聴くだけである。『希望の灯り』という邦題は少し残酷すぎるのではないだろうか。
映画『希望の灯り』予告編







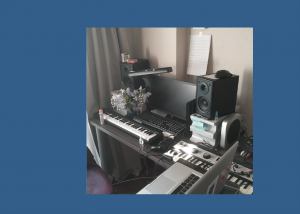


 この時期発掘したCDで、従来の批評的価値の向こう側からやってきた究極の盤は、上述のTBS『アトロク』でも紹介し反響があった、100円ショップダイソーが(おそらく2002年前後)にオリジナルで作成して自社店頭で販売していた〈100円アンビエント〉のCD『アンビエント・リラクゼーション VOL.2』です。当時ダイソーは(今でも一部店舗で展開していますが)、クラシック名曲や落語などを手軽に編んだCDを大量にリリースしていたのですが、その一環として、なんとオリジナルのアンビエント・ミュージックも制作していました。(同シリーズではこのvol.2を含め計2枚リリースされていたよう。好事家によると、vol.1の方はアンビエント的にはたいしたことないらしいけれど…)。
この時期発掘したCDで、従来の批評的価値の向こう側からやってきた究極の盤は、上述のTBS『アトロク』でも紹介し反響があった、100円ショップダイソーが(おそらく2002年前後)にオリジナルで作成して自社店頭で販売していた〈100円アンビエント〉のCD『アンビエント・リラクゼーション VOL.2』です。当時ダイソーは(今でも一部店舗で展開していますが)、クラシック名曲や落語などを手軽に編んだCDを大量にリリースしていたのですが、その一環として、なんとオリジナルのアンビエント・ミュージックも制作していました。(同シリーズではこのvol.2を含め計2枚リリースされていたよう。好事家によると、vol.1の方はアンビエント的にはたいしたことないらしいけれど…)。