だいぶ前の話になるが、映画『アトミック・ブロンド』を観た。来年公開予定の『デッドプール2』の監督も務めるデヴィッド・リーチが作りあげたこのスパイ映画は、壁が崩壊する前夜のベルリン、年代で言えば1980年代末を舞台にしている。物語は、世界情勢に深く関わる極秘リストを奪還するため、MI6によってベルリンに送り込まれたロレーン(シャーリーズ・セロン)を中心に進んでいく。厳しいトレーニングを積んだうえで臨んだというシャーリーズ・セロンのアクションなど、見どころが多い内容だ。なかでも圧巻だったのは、スパイグラス(エディ・マーサン)を逃がすときにロレーンが披露する体技。ビルの階段を移動しながらおこなわれるそれは7分以上の長回しで撮られており、華麗に立ちまわるロレーンの姿がとても美しかった。
アクションでよくある、ご都合主義的な綺麗さが見られないことも特筆したい。華麗に敵をなぎ倒していく様は映画的でも、戦うごとに体のアザは増え、それを手当てするシーンも随所で挟まれたりと、生々しい描写が際立つ。そうして傷だらけになるロレーンだが、被虐的な様子はまったく見られない。むしろ、スパイとしての凛々しい姿とプロ意識を観客に見せつける。その姿を観て筆者は、“カッコいい……”という平凡極まりない感想を呟いてしまった。
『アトミック・ブロンド』は、劇中で流れる音楽も魅力的だ。ニュー・オーダー“Blue Monday 1988”、デペッシュ・モード“Behind The Wheel”、パブリック・エネミー“Fight The Power”といった、80年代を彩ったポップ・ソングが取りあげられている。しかも、ただ流すだけじゃない。MI6のガスコイン(サム・ハーグレイブ)が殺されるシーンでは、イアン・カーティスの死について歌われた“Blue Monday 1988”を流すなど、曲の背景と劇中のシーンを重ねるような使い方なのだ。ここに筆者は、デヴィッド・リーチのこだわりを見た。
そのこだわりをより深く理解するため、映画のサントラである『Atomic Blonde (Original Motion Picture Soundtrack)』を手にいれた。本作は先に挙げた曲群を収録しておらず、そこは非常に残念だが、それでもデヴィッド・ボウイ“Cat People (Putting out Fire)”、スージー・アンド・ザ・バンシーズ“Cities In Dust”、ネーナ“99 Luftballons”など、劇中で使われた曲はだいたい収められている。
とりわり目を引くのは、ボウイとの繋がりが強い曲を数多く起用していることだ。ボウイは1976年から1978年まで西ベルリンに住み、そこで得たインスピレーションを元に『Low』『Heroes』『Lodger』というベルリン三部作が作られたのは有名な話だが、このことをふまえて映画ではボウイが象徴的な存在になっている。
面白いのは、それを少々ひねりが効いた方法で示すところだ。その代表例が、ニュー・ロマンティック期のエレ・ポップど真ん中なサウンドを特徴とする、アフター・ザ・ファイアー“Der Kommissar”。もともとこの曲は、オーストリアのファルコというシンガーソングライターが1981年に発表したシングル。重要なのは、このシングルのB面に収められた曲だ。“Helden Von Heute”というそれは、ボウイの代表曲“Heroes”へ賛辞を送るために作られた曲で、メロディーは“Heroes”をまんま引用している。こういう婉曲的な仕掛けを通して、ボウイの偉大なる影を匂わせるのだ。
その影は、ピーター・シリング“Major Tom (völlig losgelöst)”でもちらつく。タイトルからもわかるようにこの曲は、ボウイが1969年に発表したアルバム『Space Oddity』へのアンサー・ソングだ。もともとの歌詞はロケット発射の様子を描いたもので、深い意味はない。だが、『アトミック・ブロンド』の中では冷戦時代の一側面を表す曲になっている。1980年代末のベルリンは冷戦まっただ中であり、そんな時代に米ソ間でおこなわれた熾烈な宇宙開発競争を連想させるからだ。こうした既存の曲に新たな意味をあたえるセンスは、退屈な懐古主義に陥らない同時代性を漂わせる。
この同時代性は、映画のために作られたいくつかのカヴァー曲にも繋がっている。特に秀逸なのは、映画のスコアを担ったタイラー・ベイツがマリリン・マンソンと共作したミニストリー“Stigmata”のカヴァー。殺伐としたドライな音質が耳に残る激しいインダストリアル・ロックで、マリリン・マンソンの金切り声を味わえる。もちろん、このカヴァーも映画と深い繋がりがある。オリジナル版“Stigmata”のMVにはスキンヘッドのネオナチが登場するが、そこに映画の核であるベルリンという要素との共振を見いだすのは容易い。
そうした綿密な選曲において、ひとつだけ気になる点がある。ザ・クラッシュ“London Calling”を選んでいることだ。この曲は1979年にリリースされたもので、80年代でもなければ現在の曲でもない。しかしそこには、他の曲以上に重要な意味を見いだせる。
“London Calling”は、ザ・クラッシュから見た当時の社会について歌った曲だ。1981年のブリクストン暴動、セラフィールド、フォークランド紛争といった、80年代のイギリスで起こることを予見するような言葉が歌詞に並んでいる。
そんな予見的な曲が、映画ではベルリンの壁崩壊後の終盤で流れる。決着を迎えてめでたしのはずが、〈すぐさま戦争が布告され 戦いがやってくる(Now war is declared and battle come down)〉と歌われるのだから、なんとも興味深い。ここまで書いてきた映画と曲の深い繋がりから考えても、かなり意味深だ。ロレーンの次なる戦いが始まるから……とも解釈できるが、過去の要素に同時代性を見いだし表現する『アトミック・ブロンド』の特性をふまえると、この映画はあなたたちの現状であるという暗喩を込めた選曲ではないか。そう考えると、冷戦時代のベルリンが舞台であるにもかかわらず、それにまつわる物語じゃないと否定するグラフィティーが映画の冒頭で挟まれるのも納得だ。“London Calling”が流れた途端、西ドイツと東ドイツの間にあった経済格差や、壁によってもたらされた抑圧といった映画の時代背景には、新冷戦(New Cold War)なる言葉も飛び交うようになった現在を表象する機能が付与される。
ここまで大胆な音楽の使い方を前にすれば、客寄せパンダ的にヒット・ソングを使ったという揶揄も跪くしかない。



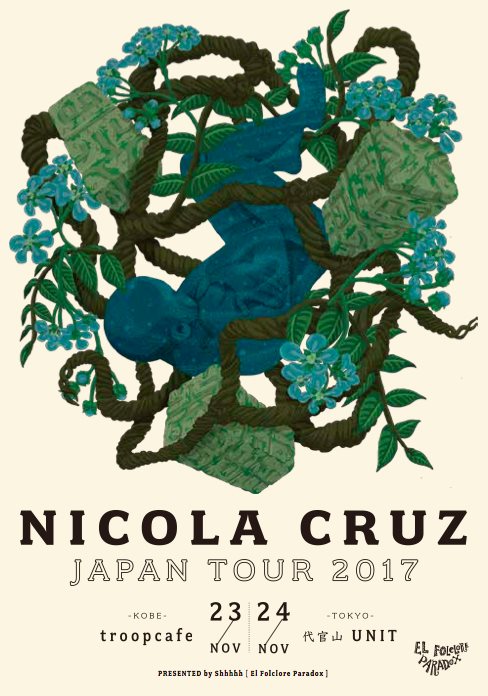
 アーティスト: Nils Frahm (ニルス・フラーム)
アーティスト: Nils Frahm (ニルス・フラーム)




