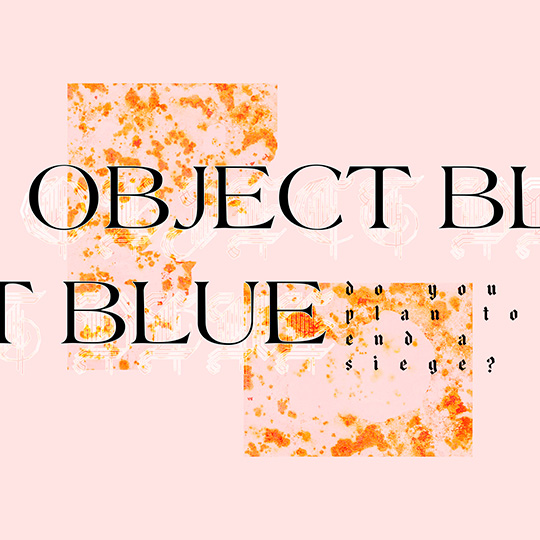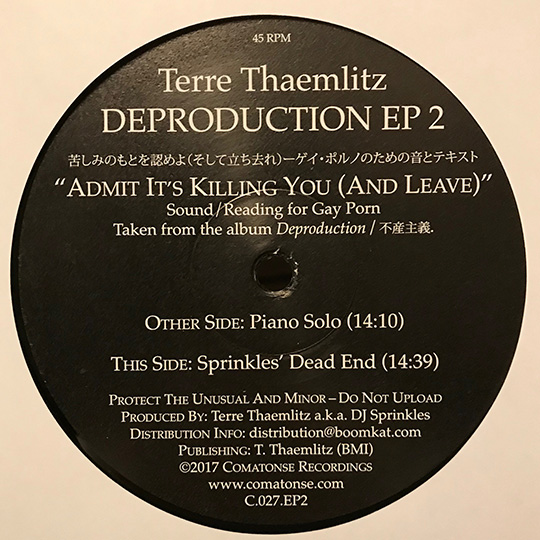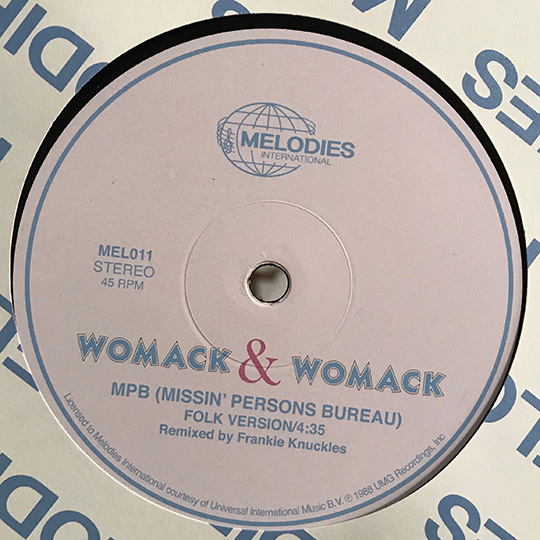ロンドンに「Keep Hush」という YouTube のライヴ配信チャンネルがある。UKガラージやグライムからハウス、テクノ、ディスコまで幅広いDJ、トラックメイカーがプレイする不定期番組で、Boiler Room や Dommune といった番組を思い浮かべてもらえればいいと思う。そういったライヴ配信チャンネルと異なるのは、彼らが「ロンドンの若手アーティスト」に焦点を当てている点と、毎回開催場所を変えて、秘密のロケーションでおこなわれる点だ。場所は開催直前に登録制のメールマガジンに配信される仕組みで、小さめの会場でおこなわれることもあいまってアットホームな空気が伝わってくる。また、配信時のザラついた質感は90年代のレイヴを意識しているのでは、と邪推したりした。
そんな Keep Hush にて、〈Coyote Records〉が主催する夜には新鮮さと勢いを感じた。下の動画でプレイしているのは気鋭の若手アーティスト Drone だ。
Drone DJ Set | Keep Hush London: Coyote Records Presents
Drone は自主作品のUSBに続き、2018年は〈Sector 7 Records〉から「Sapphire」をリリース、続いて〈Coyote Records〉から「Light Speed」をリリースした。
Drone - Light Speed
https://bit.ly/2P6ZlKx
Keep Hush のプレイでもリワインドされた Drone の“East Coast”はサンプリングの声ネタ・金物が印象的で、組み合わせられるUKドリルを感じさせる、うねるようなキック・ベースにハイブリッドなセンスを感じる。
さらに紹介したいのは、上にあげた Drone が何曲かプレイしている Bengal Sound。2018年にコンセプト作品『Culture Clash』をカセットでリリースしている。
Bengal Sound - Culture Clash
全ての曲でボリウッド映画のサウンドトラックからサンプリングしており、ハイエナジーなベースラインにサンプリングされたローファイなホーンやパーカッションがとても自然にマッチしている。手法に関して言えば、Mala が『Mala in Cuba』でキューバ音楽を用いたのと比べることもできるが、こちらはよりローファイなカットアップ、ループ感はインストのヒップホップを思わせる。
サンプリングという観点で最後に紹介したいのは、ラッパーでありトラックメイカーである Rocks FOE。ラッパーとしてもアルバムをリリースする傍ら、日本でも人気を集めるレーベル〈Black Acre〉から 140 bpm のインストゥルメンタル作品もリリースする。多くの作品でサンプリングを用いており(寡聞にしてそれぞれのサンプリング・ネタがわからないのだが……)、ホーンやディストーションされたシンバル、そして低く震えるラップは独自の怪しげな世界観を築いている。
2018年6月にリリースされた Rocks FOE のアルバム『Legion Lacuna』
https://rocksfoe.bandcamp.com/album/legion-lacuna
こうしたザラザラとしたサンプリングをおこなったダブステップについては、2016年の Kahn, Gantz, Commodo による名盤『Vol.1』が思い起こされるが、その後のシーンについてはどうだろうか。〈Sector 7 Records〉を主催する Boofy はインタヴューでこのように述べている。「ダブステップには、(シーンを語る上で)欠かせない歴史もあるけど、いまお気に入りのアーティストはもうそういう「レイヴ・バンガーの公式」の教科書は気にしないでやりたいようにやっているよ」(Mixmag, Jan, 2019)
近年のダブステップはサンプリングのセンス、音の組み合わせ方が新鮮さに満ちていて、常にインスピレーションを与えてくれる。