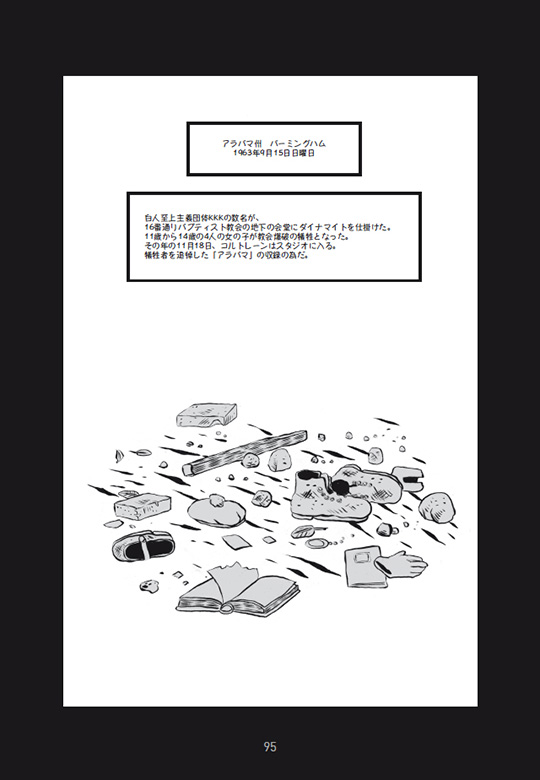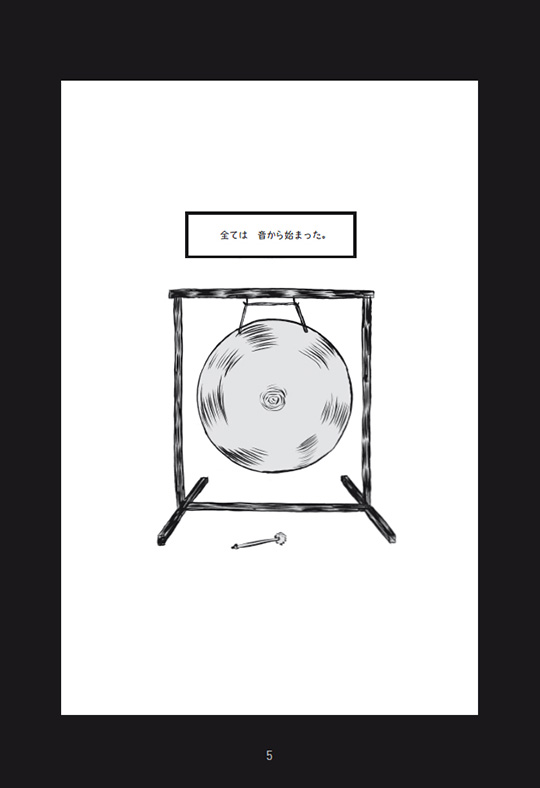フローティング・ポインツとUKグライムとの溝を埋めることができるのは、ディーゴだ。ジャングル/ドラムンベースの創世記におけるキーパーソンとして知られるディーゴは、まずUKハードコアをデトロイト・テクノと結びつけ、そして数年後にはUKハードコアをクラブ・ジャズとも結びつけた。ベース・ミュージックが成熟と洗練とに向かっている現在、この偉人が再評価されるのはなんら不思議ではない。
今回は東京CONTACT、大阪CIRCUS、京都METROの3都市をツアー、各地Degoのニッポン・サポーターとの共演です!
Dego & The 2000Black Family - It Don't Get No Better
https://soundcloud.com/2000black
Dego / 2000Black Japan Tour 2016
"Dego meets Nippon Friends!"
クラブ・ジャズ・シーンにおいて常にトップに君臨する重鎮ユニット4 HEROのメンバーにして、ロンドンに音楽シーンの礎を築いた先鋭的アーティストとして長年UKのクラブ/ソウル・ ミュージック・シーンを牽引し続けるディーゴ。
USのセオ・パリッシュと共に第一人者としてUKシーンの雄として君臨する。
昨年リリースしたアルバム『The More Things Stay the Same』は、ドラムンベース、ブロークンビーツから出発し、アフロ、ヒップホップ、ジャズ、ソウル、ディスコと様々な音楽を飲み込み壮大なミュージック・ジャーニーを経て、ムーヴメントのパイオニアとして絶大な支持を獲得きたディーゴの面目躍如たる傑作、飽くなきビートの追求とスピリチュアルな音楽への拘り、音楽への深い愛情がそのまま反映された21世紀のハイブリッド・ソウル・ミュージックとして喝采を浴びた事は記憶に新しい。
ルーツに深く根差しながらも、未来のビートへの飽くなき探求を続けるリアルアーティストDEGOのジャパン・ツアーが決定!
東京、大阪、京都のdegoサポーターらが競演する"Dego meets Nippon Friends!"開催!
ツアー日程:
【東京】 08.12 (FRI) TOKYO at CONTACT https://www.contacttokyo.com/
【大阪】 08.13 (SAT) OSAKA at CIRCUS https://circus-osaka.com/
【京都】 08.20 (SAT) KYOTO at Club METRO https://www.metro.ne.jp
========================================
DEGO (2000Black | 4hero | from UK)
ロンドンに生まれたDEGOはサウンドシステムや海賊放送でのDJ活動を経て90年にReinforced Recordsの設立に参加、4HEROの一員として実験的なハードコア/ブレイクビーツ・トラックのリリースを開始。やがて4HEROはDEGOとMARC MACの双頭ユニットとなり、タイムストレッチング等、画期的な手法を編み出し、ドラム&ベースのパイオニアとなる。傑作『PARALLEL UNIVERSE』(94年)、『TWO PAGES』(98年)以降、4HEROはD&Bのフォーマットを捨て、『CREATING PATTERNS』(01年)、『PLAY WITH THE CHANGES』(07年)で豊潤なクロスオーヴァーサウンドを打ち出す。DEGOはTEK9名義でダウンテンポを追求する等、オープンマインドかつ実験的な制作活動は多岐に及び、98年に自己のレーベル、2000Blackを始動し、革新的な音楽共同体としてのネットワークを拡張、ブロークンビーツ/ニュージャズの潮流を生む。KAIDI TATHAMらBUGZ IN THE ATTIC周辺と密に交流し、DKD、SILHOUETTE BROWN、2000BLACK名義のアルバムを制作。11年には満を持してDEGO名義の初アルバム『A WHA' HIM DEH PON?』を発表、ジャズ、ファンク、ソウルetcへの深い愛情を反映した傑作となる。その後も精力的な活動を続け、12年に『TATHAM,MENSAH,LORD & RANKS』を発表。14~15年には盟友KAIDIとの共作をFaltyDLのBlueberry、FLOATING POINTSのEglo、THEO PARRISHのSound Signature等から立て続けにリリースし、ニューソウル/ニュー ジャズ・ムーヴメントを牽引している。そして15年5月、DEGO名義の待望の2ndアルバム『THE MORE THINGS STAY THE SAME』を2000Blackから発表(8/5 BBQより日本盤のみCDリリース)、昇華するDEGOソウルを鏤めている。
https://www.2000black.com/
https://soundcloud.com/2000black
https://mrgoodgood.com/
https://www.facebook.com/2000blackrecords
https://twitter.com/2000black_dego
========================================
【東京】
2016年8月12日(金)@CONTACT
Studio:
DEGO (2000 BLACK | from UK)
Yoshihiro Okino (Kyoto Jazz Massive)
77 KARAT GOLD (grooveman Spot & sauce81)
DJ IZM. (Jazzy Sport | Stax Groove)
and more.
Dance:
Jazzy Sport Dancers
Contact:
Yukari BB
Sayuri (Destination)
Midori Aoyama
and more.
Open: 10PM
¥3500 Admission
¥3000 W/F
¥2500 GH S Members
¥2000 Under 23
¥1000 Before 11PM
========================================
【大阪】
2016年8月13日(土)@CIRCUS
DEGO (2000Black/4hero,from UK)
Yoshihiro Okino (Especial Records / Kyoto Jazz Massive)
DJ::
CM Smooth(PLANT RECORDS / STORE One)
NAO-K(PLANT RECORDS)
DANCE SHOWCASE:
HOMEBOY
よっち(プリンケツプリンケツ/くしゃみ屋)
O'malley
FOOD:
THAT’S PIZZA
OPEN 23:00
ADV2000YEN DOOR2500yen
========================================
【京都】
2016年8月20日(土)@京都METRO
Special DJ:
DEGO ( 2000Black/4hero,from UK)
DJ:
Yukari BB (Especial Records Sessions)
Masaki Tamura (DoitJAZZ!)
SHINYA (BUTTER)
SOTA(pride&joy, Rokujian)
Torei(HUgE)
and More!!
FOOD :
Sunny
OPEN 23:00
ADV 2500YEN DOOR 3000yen
PIA (P-code: 304-027) 、Lowson (L-code: 51453)
e+ (https://eplus.jp/)