先日デヴィッド・バーンとコラボしていることが明らかになったばかりのOPNが、新曲(の一部)を公開しました。今度のお相手はなんとイギー・ポップです。次々と意外な相手と組んでいくOPNもすごいですが、アルヴァ・ノトやソンゴイ・ブルースなど、他ジャンルの精鋭たちと積極的にコラボしていく現在のイギー・ポップにもシビれます。詳細は下記をチェック。
ONEOHTRIX POINT NEVER
ワンオートリックス・ポイント・ネヴァーが音楽製作を手がける
映画『Good Time』のトレーラー映像が公開!
イギー・ポップ参加の新曲の一部が解禁!
各国の映画祭で賛否両論の嵐を巻き起こし、2014年の東京国際映画祭にてグランプリと最優秀監督賞の2冠に輝いた映画『神様なんかくそくらえ』を手がけたジョシュア&ベニー・サフディ監督の新作で、『トワイライト』シリーズで知られるロバート・パティンソン主演の新作映画『Good Time』のトレーラー映像が公開され、ワンオートリックス・ポイント・ネヴァーことダニエル・ロパティンとイギー・ポップがコラボレートした新曲“The Pure And The Damned”の一部が解禁されるとともに、同映画の音楽製作をワンオートリックス・ポイント・ネヴァーが手がけていることが明らかとなった。また同映画は、第70回を迎えるカンヌ国際映画祭2017のコンペティション部門での上映が決定しており、英BBC は、パルムドール有力候補のひとつにも挙げている。
Good Time | Official Trailer HD | A24
https://youtu.be/AVyGCxHZ_Ko
公式HP: https://goodtime.movie/
DIRECTOR: Ben Safdie, Joshua Safdie
CAST: Robert Pattinson, Jennifer Jason Leigh, Barkhad Abdi
ORIGINAL SCORE: Oneohtrix Point Never
MUSIC: "Hospital Escape" by Oneohtrix Point Never, "The Pure And The Damned" by Oneohtrix Point Never ft. Iggy Pop. https://pointnever.com



 『Mellow Waves』
『Mellow Waves』


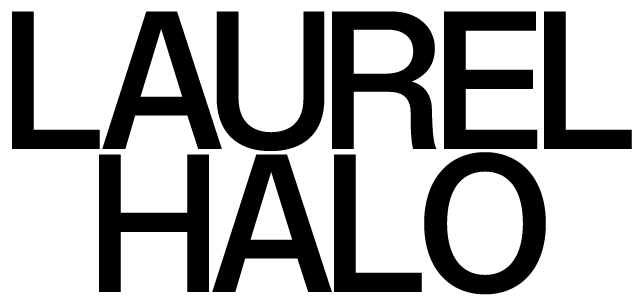
 label: HYPERDUB / BEAT RECORDS
label: HYPERDUB / BEAT RECORDS
 アーティスト: Jeff Parker / ジェフ・パーカー
アーティスト: Jeff Parker / ジェフ・パーカー アーティスト: Jamire Williams / ジャマイア・ウィリアムス
アーティスト: Jamire Williams / ジャマイア・ウィリアムス