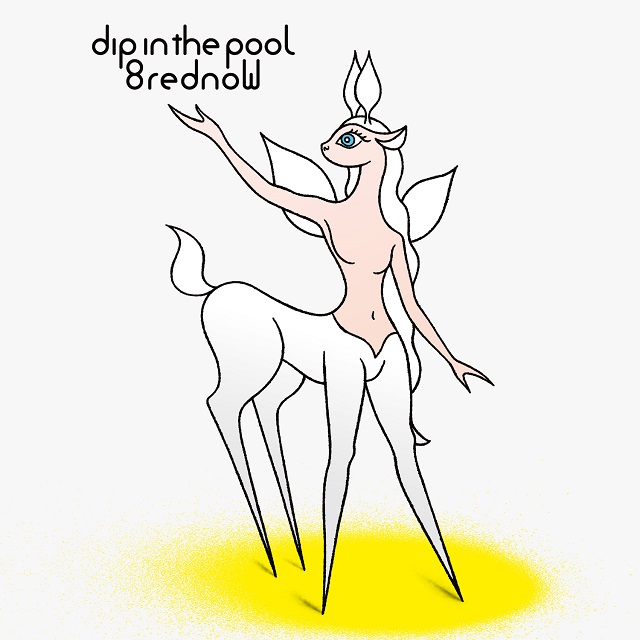ナカコーと duenn が主催するプロジェクト《Hardcore Ambience CH.》の最新映像作品に、ゲストとして岡田拓郎が登場している。先日の GONNO × MASUMURA のライヴでもギターで参加し華を添えていた岡田だが、ナカコーと duenn のサウンドにマルチプレイヤーの彼が加わることで、いったいどんな化学反応が生まれるのか? ぜひ動画を観て確認してみてください。
ナカコーとduenn主催のアンビエントに特化したプロジェクト『Hardcore Ambience CH.』
今回はKoji Nakamura+ duenn + 岡田拓郎によるライブパフォーマンスを公開。

『Hardcore Ambience』は、“ナカコー”(Koji Nakamura, Nyantora, LAMA, exスーパーカー)と、福岡を拠点とするコンポーザー “duenn” によるライブや映像作品を展開するプロジェクト。
第5回となる今回は、ライブゲストに孤高の天才音楽家“岡田拓郎”を迎え、ナカコー・duennと共演する。岡田拓郎はバンド「森は生きている」で活動したのち、現在ソロ活動の他にもギタリスト, プロデューサー, ミキシング・エンジニアとしても活躍している。今回のライブでは岡田のマルチプレイヤーならではの特質的な演奏に、ナカコーのギターと、duennのシンセが加わり、どこか温かみと優しさが感じられる音楽映像作品に仕上がっている。
Hardcore Ambience CH.
■HARDCORE AMBIENCE #5-2【LIVE】-Koji Nakamura + duenn + Okada Takuro