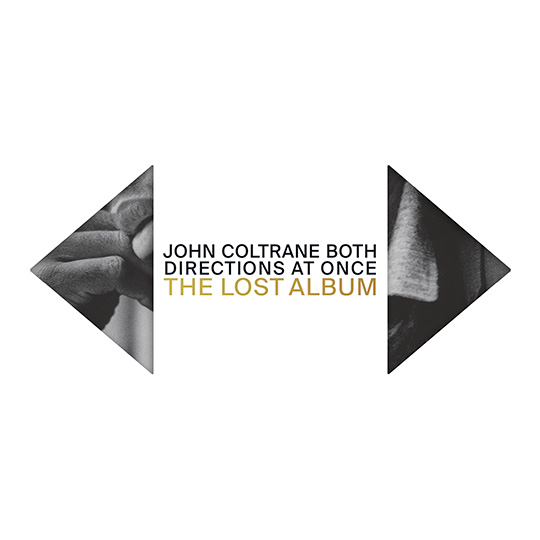なんと、アンダーワールドとイギー・ポップがコラボEPをリリースします。これはなんとも意外な組み合わせ……と一瞬思ってしまいましたが、いやいやいや、まったく意外ではありません。『トレインスポッティング』です。あの映画のオープニングを飾っていたのは“ラスト・フォー・ライフ”、そしてエンディングは“ボーン・スリッピー”でした。
その続編である『T2トレインスポッティング2』の音楽を担当していたリック・スミスは、制作中にイギー・ポップと会合を重ね、それが今回のコラボとして結実したそうです。このたび公開された“アイル・シー・ビッグ”のリリックは、オリジナルの『トレインスポッティング』と『T2』の背景からインスパイアされているのだとか。
発売は7月27日。22年ぶりの共演に、胸を躍らせましょう。
UNDERWORLD & IGGY POP
Teatime Dub Encounters
ロック界のレジェンド、イギー・ポップと
世界屈指のダンス・アクト、アンダーワールドが満を持して
コラボEP「ティータイム・ダブ・エンカウンターズ」のリリースを発表!
昨年満を持して公開された映画『T2トレインスポッティング2』。その映画音楽を担当したアンダーワールドのリック・スミスは、制作中、ともにオリジナルの『トレインスポッティング』に楽曲を提供したイギー・ポップとロンドンでミーティングを行ない、新作映画のためのコラボレーションの可能性を話し合った。
イギーは快く「会って何か話そう」と応じてくれた。僕らはともにトレインスポッティングとダニー(・ボイル)に強い絆を抱いていたからね。この紳士を説得して一緒に仕事をする一度きりのチャンスだろうと思った。だからホテルの部屋を貸し切って、スタジオを用意して彼が現れるのを待ったんだ。 ――リック・スミス(アンダーワールド)
イギー・ポップの“ラスト・フォー・ライフ”で幕を開け、アンダーワールドの“ボーン・スリッピー(ナックス)”で幕を閉じる96年公開の『トレインスポッティング』。完璧なオープニングと完璧なエンディングを持った映画は、青春映画の最高傑作として本国イギリスを中心とするヨーロッパはもちろん、アメリカ、日本でも異例の大ヒットを記録。ユアン・マクレガーやロバート・カーライルといったスター俳優を生んだ一方、イギー・ポップ、ブライアン・イーノ、プライマル・スクリーム、 ニュー・オーダー、ブラー、ルー・リード、レフトフィールド、デーモン・アルバーン、そしてアンダーワールドといった当時の先鋭的ポップ・シーンを代表するアーティストが名を連ねたサウンドトラックも大きな話題となった。
それから実に22年。リック・スミスのもとに現れたイギー・ポップは、完璧にセッティングされたスタジオを目にし、すぐにでも制作に取り掛かろうという情熱に駆られた。
ホテルの部屋に完璧なスタジオを持った誰かと会って、Skypeにはアカデミー賞監督がいて、目の前にはマイクと30もの洗練された楽曲があったら、頷くだけでびびってられないだろ。一瞬で血が沸き立ったよ。 ――イギー・ポップ
今作『ティータイム・ダブ・エンカウンターズ』は、アンダーワールドが『バーバラ・バーバラ・ウィ・フェイス・ア・シャイニング・フューチャー』を、イギー・ポップが『ポスト・ポップ・ディプレッション』を2016年3月16日に同時にリリースした数週間後に、ホテルの部屋で秘密裏に行われた数回のセッションの末に誕生した。これは過去に対するトリビュート的なものではなく、今もなお第一線で活躍し、持っているすべてを目の前の作品に捧げ、ひらめきこそが創造を生むという信念を持ったアーティストたちが作り上げた、最高に刺激的で躍動に満ちた作品である。
先行曲である“ベルズ&サークルズ”は、BBC Music主催イベント《Biggest Weekend 2018》でアンダーワールドがヘッドライナーとしてパフォーマンスした際に初披露された。そしてEPリリースの発表と合わせて、新曲“アイル・シー・ビッグ”が解禁。“ベルズ&サークルズ”とはある意味真逆の魅力を持った楽曲で、壮大なアンビエント・トラックの上で、イギー・ポップは語りかける。その歌詞は、ダニー・ボイルとの会話の中で、『トレインスポッティング』と『T2トレインスポッティング2』の背景にインスパイアされて書かれたものだという。
今では俺も多少は年を食い、俺がいなくなった時に俺のことを思ってくれる友達について考え始めてる
1人か2人は笑顔を浮かべ、俺との楽しい思い出に浸ってくれるだろう奴がいる
I’ll See Big
Apple Music: https://apple.co/2Ie6vtk
Spotify: https://spoti.fi/2luH9OZ
Bells & Circles
https://youtu.be/KmJWD9jQvhc
アンダーワールドとイギー・ポップによるコラボレート作「ティータイム・ダブ・エンカウンターズ」は、7月27日(金)に世界同時リリース! 国内盤CDにはボーナストラック2曲が追加収録され、歌詞対訳と解説書が封入される。iTunes Storeでは「Mastered for iTunes」フォーマットでマスタリングされた高音質音源での配信となり、今アルバムを予約すると、公開された“Bells & Circles”と“I’ll See Big”の2曲がいち早くダウンロードできる。
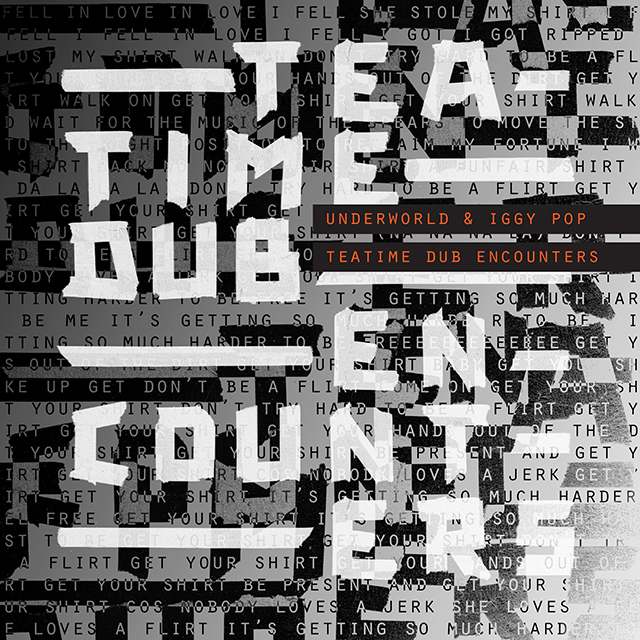
label: Beat Records
artist: Underworld & Iggy Pop
title: Teatime Dub Encounters
release date: 2018.07.27 FRI ON SALE
国内盤CD: BRC-576 ¥1,500+tax
リリース詳細はこちら:
https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=9742
Tracklist
01. Bells & Circles
02. Trapped
03. I See Big
04. Get Your Shirt
05. Bells & Circles (instrumental version) *Bonus Track for Japan
06. Get Your Shirt (instrumental version) *Bonus Track for Japan