命を賭して音楽に向き合っている人が好きだ。ここで言う命というのは、埃や小銭にまみれた決してきらびやかではない、暮らしそのものを指している。「命を懸ける」というのは刹那的に燃え尽きることではなく、ひたすら続く人生のすべてを費やすということで、人生を薪にくべて音楽を生み出すようなある種の狂気性に裏打ちされた行動をひたすら取り続けることだと僕は考えている。
そういったことを粛々と遂行し続けられるアーティストは、いつか歴史に対し垂直に立ち、記念碑的な作品をたびたび生みだす。2023年9月9日、7年ぶりのフル・アルバムとして満を持して世に放たれたworld’s end girlfriendの新作『Resistance & The Blessing』はその条件を満たしていると確信できる内容だった。たとえ YouTubeの有名音楽レヴュアーが本作に最低点の1点を与えようと、その素晴らしさは揺るがない。もちろん好みや時代の要請によって、本作をどう捉えるかは大きく変わってくるだろうけれど。
ショート・レングス全盛の、わかりやすさこそ正義とされる時代と相反する約144分、35曲入、LP4枚組/CD3枚組の大作というパッケージングもさることながら、(2020年代にまったく異なる形で復権を果たした)ブレイクコア、(こちらも姿化を変えて復活した)トランス、ボーカロイド、グラニュラー・シンセシスといったトレンドを包摂しつつも、それらとは相反するプログレッシヴ・ロックやシンフォニック・メタル、モダン・クラシカルといったような、現行のヴァイラル・チャートとは距離のあるジャンルが本作の美学を主柱として支えている。
そう、本作『Resistance & The Blessing』のサイズは、2020年代のインディ電子音楽の地平にとってあまりにも巨大である。とてもカジュアルには向き合えそうもない(だから、最低得点?)。けれど、『Resistance & The Blessing』にはworld’s end girlfriend=前田勝彦氏の命が込められているはずだから、作品が重さを帯びるのは当然のことだ。なにしろ、7年もの間ライヴ活動を休止し、ひたすら作り続けられたアルバムであり、本人をして “最高傑作” と断言する大作である。怪作と受け取る人が出現するのも無理はないだろう。本作は隙間なく敷き詰められたひとりの音楽家の美学と全身で向き合うことを余儀なくされるような作品なのだ。もちろん、そのような要素を抜きにしても、音像そのものを遺跡を見にいくような感覚で誰もが楽しめるはずなのだけど。
サウンドデザインの面に目を向けると、本作にはジャンル/美学を含む、広範にわたる要素が散りばめられている印象を受ける。それはまるでworld’s end girlfriendが辿ってきた足跡すべてを回想するように。とはいえ、僕の「WEG体験」は非常に断続的で、ずっと追い続けてきた人々のそれと比べて乏しいものだ。どちらかといえば、world’s end girlfriendそのものより、ひとりの愛好家のCD棚を見せてもらうような感覚で〈Virgin Babylon Records〉のリリース作をバラバラにダウンロードしていくうちに、たびたび現れるオーナー本人の作品、といったような距離感で接していた。最初に触れたのは、BandCampでName Your Price配信されている『dream's end come true』(2002)と『Hurtbreak Wonderland』(2007)あたりだったろうか。ブレイクコア~ポスト・ロック~アンビエントをシームレスに繋ぐようなそのサウンドスケープを、コロナ禍で沈みきっていた時期にたびたび求めた。
だから、「そういう人間がWEGのすべてが込められた『Resistance & The Blessing』を評してよいものか?」という葛藤があり、それが9月発売の本作をこうしていま取り上げている一因になっている。本作と向き合うことの難しさに大きなプレッシャーを覚え、心中の感想はどれも独立してまとまらない。それでも何度も振り返り、整理を続けていくと、「エピック・コラージュ」とされるジャンル群との結びつきが徐々に浮かび上がった。
「エピック・コラージュ」とは、デコンストラクテッド(脱構築)・クラブから派生した非クラブ・ミュージック的なサンプリング・ミュージックを指すジャンル定義であり、数多のサンプルを文脈から切り離し新たな文脈を創り出すような音楽性を持つ作品群に適用されるものだ。そこにはたとえばアンビエント、グリッチ、ノイズ、映画音楽、ニューエイジ、非音楽などさまざまな文脈を持つものが重層的に重なり合っており、そして「エピック」という語句が指すようにしばしば壮大なスケールを感じさせる。
また、近いものに「プランダーフォニックス」と呼ばれるジャンルがあり、こちらも成立こそ1980年代ごろまで遡るものの、2023年現在はサンプリングを主としたその技法(もしくは精神性)だけが取り残され、また新たな枠組みができあがりつつある(デスズ・ダイナミック・シュラウド.wmvやウラ、そして日本からは冥丁やMON/KUといったアーティストの作品が、音楽レヴュー・フォーラムのRate Your Musicにより分類されている)。こういった定義に本作『Resistance & The Blessing』を当てはめてみると、アプローチ的にはかなり近しいものを感じた。プランダーフォニックスはその名称に、Plunder(略奪)とPhonics(音声)という「剽窃的サンプリング」といった負のニュアンスを帯びているジャンルであり、もちろん『Resistance & The Blessing』にそのすべてが当てはまるというわけではない。けれど、2016年末のウェブ・インタヴューにて「world’s end girlfriendを変えた5枚の音楽アルバム」として、プランダーフォニックスの先達とされるDJ シャドウ『Endtroducing.....』が紹介されていたりと、(おそらく)WEGの音楽を構成する一要素として考えられるはずだ。
メタルやプログレッシヴ・ロック、エレクトロニカ、ブレイクコア、シューゲイザー、グリッチ、脱構築、そういった物事すべてを通過して向かった先がどこであったのかはいまだ結論が出ないというのが正直なところだ。けれども、本作が我々に与える音と奔流は、インスタントな喜怒哀楽を超えたなにかを心の奥底に焼き付けようとする。クラシカルなピアノの演奏に始まり轟音のスーパーソー(トランス・ミュージックの肝であるシンセサイザー・サウンド)に終わる “FEARLESS VIRUS” から “Dancing With me” のグリッチ・ベースとも呼ぶべき脱構築的サウンドに突き落とされる中盤の流れや、“Ave Maria” のラスト1分の痛いほど耳を刺す轟音のフィードバック・ノイズはもはや快楽というより苦悶に近い。しかしその先にはたしかな解放感が待っている。
なお、この作品の基本設定は
「人間がこれまで幾千幾万の物語で描いてきたふたつの魂、それらの物語が終わったその先の物語」
「ふたつの魂が何度も何度も輪廻転生し続ける物語」
とworld’s end girlfriend本人より説明されている。そして、
「これらの魂は男女、同性、親子、友人、敵、様々な姿で、様々な時代と土地を生き、出会いと別れ、生と死を繰り返し、物語は続きます。」
とも明言されている。だから1曲目は “unPrologue Birthday Resistance” で、35曲目は “unEpilogue JUBILEE” なのだろう。誕生を喜ぶことも、終わりを迎えて救済されることも両方拒んでいるアルバムというわけだ。人にも音楽にも、続きがあるということだろうか。苦悶に近い陶酔の果てに現実へと突き放されるような本作の視聴体験を、厳しさと捉えるか優しさと捉えるかでまた、聴いたあとに見えてくる景色や考える物事も変わるような気がする。僕はこの大作を前に、結局音の先に人を見出してしまった。エピックな大作でありながら、個々人の持つ美意識や感情=つまりは生に訴えかけるパーソナルなメッセージを独り発信するworld’s end girlfriendのことが、さらに好きになった。


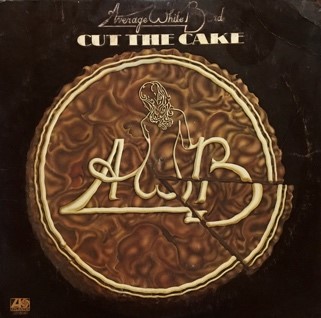
















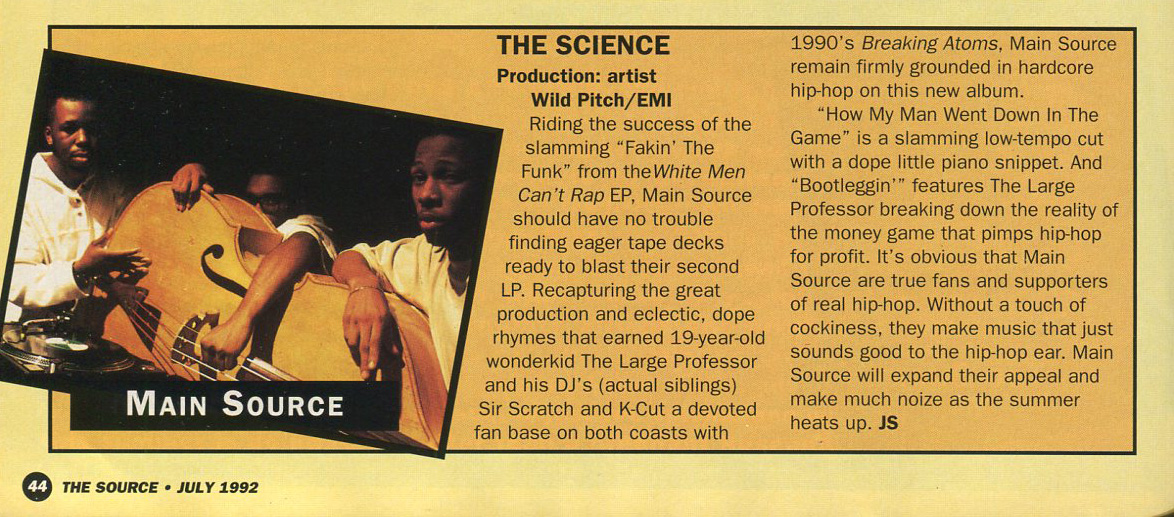













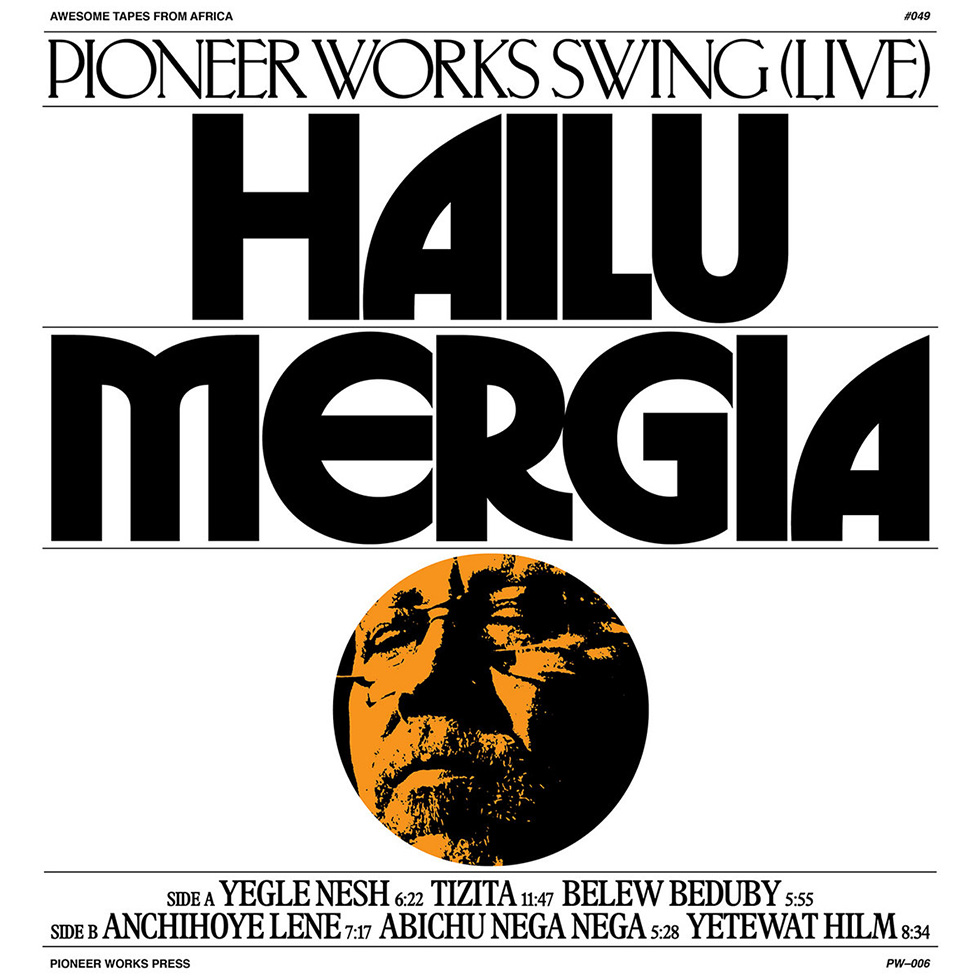

 ファースト・プレスプロモ盤
ファースト・プレスプロモ盤 ファースト・プレス市販盤
ファースト・プレス市販盤 セカンド・プレス FULLERSOUND盤
セカンド・プレス FULLERSOUND盤 セカンド・プレス・スローダウン盤
セカンド・プレス・スローダウン盤 ファースト・プレスプロモ盤
ファースト・プレスプロモ盤 ファースト・プレス市販盤
ファースト・プレス市販盤 セカンド・プレス FULLERSOUND盤
セカンド・プレス FULLERSOUND盤 セカンド・プレス・スローダウン盤
セカンド・プレス・スローダウン盤
