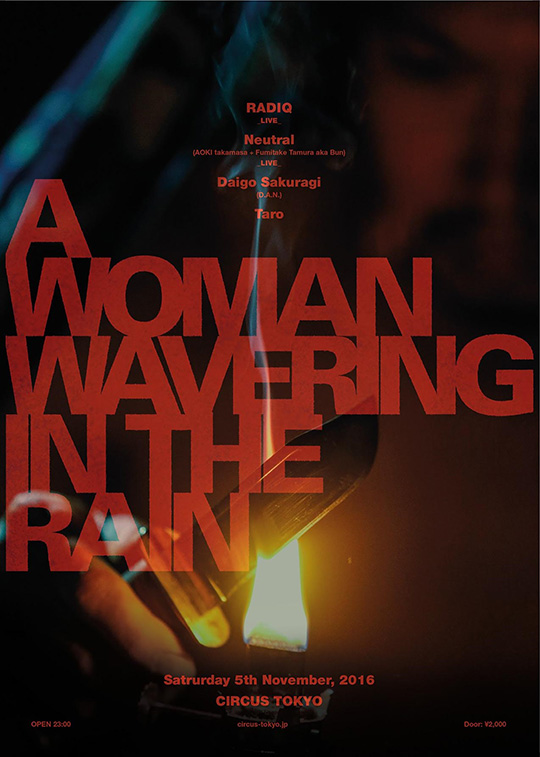ケンタッキー州はルイヴィル出身。ボニー・プリンス・ビリーの名称以外にパレス・ブラザーズ、パレス・ソングス、パレス、パレス・ミュージック、ひいては本名のウィル・オールダム名義で着々と出しつづけた音盤を、私なぞ日々くりかえしくりかえし聴きつづけてきたせいで干支がひとまわりするまでナマの彼を拝んでいなかったとはにわかに信じられないが来日公演は12年ぶりである。
米国インディの中堅どころでありフォークロアをたっぷり吸った歌心をもつ楽曲がどこか輪郭がひしゃげた聴き心地なのは、その風貌のせいもあるとの意見を否定するつもりはありませんが、それをしのぐ音楽のナゾめいたものがボニー・プリンス・ビリーの音楽には秘められている、それを確認するかっこうの機会だろう。さらに今回は新作『Epic Jammers and Fortunate Little Ditties』〈Drag City〉を共作したビッチン・バハスが帯同するという。トータスしかり〈オネスト・ジョンズ〉からのトレンブリング・ベルズとの共作しかり、コラボレーターとしても無類の柔軟性と順応性をみせるボニー・プリンス・ビリーが在シカゴのクラウトロック・バンドとどのようにわたりあうか、フリーフォーキーな弾き語りとハルモニア的な天上のドローンとが重なり合い、アシッドでありながらときにローリー・アンダーソン風のアヴァン・ポップ(おもに“You Are Not Superman”の印象です)を思わせる新作に耳を傾けつつ、首を長くして待ちたい。(松村正人)
Bonnie 'Prince' Billy & Bitchin Bajas Japan Tour 2016
ボニー・プリンス・ビリー&ビッチン・バハス ジャパン・ツアー2016
10月26日(水)京都 アバンギルド(075-212-1125)
京都府京都市中京区木屋町三条下ル ニュー京都ビル3階
出演:ボニー・プリンス・ビリー、ビッチン・バハス、風の又サニー
開場 6:30pm/開演 7:30pm
料金 4,500円(予約)/5,000円(当日)*ドリンク代別
10月27日(木)金沢 アートグミ(076-225-7780)
石川県金沢市青草町88 北國銀行武蔵ヶ辻支店3階
出演:ボニー・プリンス・ビリー&ビッチン・バハス、ASUNA quintet(ASUNA+宇津弘基+黒田誠二郎+ショーキー+加藤りま)
出店:喫茶ゆすらご
開場 7:00pm/開演 7:30pm
料金 3,500円(予約)/4,000円(当日)/2,500円(学割)
*学割:学生証など証明となるものをご持参ください。
10月28日(金)名古屋 KDハポン(052-251-1324)
愛知県名古屋市中区千代田5-12-7
出演:ボニー・プリンス・ビリー、ビッチン・バハス、Gofishトリオ(テライショウタ+黒田誠二郎+稲田誠)
開場 6:30pm/開演 7:00pm
料金 4,500円(予約)/5,000円(当日)/3,500円(学割)*ドリンク代別
*学割:学生証など証明となるものをご持参ください。
10月29日(土)東京 O-Nest(03-3462-4420)
東京都渋谷区円山町2-3 O-Westビル6階
出演:ボニー・プリンス・ビリー、ビッチン・バハス、井手健介と母船(墓場戯太郎+清岡秀哉+石坂智子+山本紗織+羽賀和貴+岸田佳也)
開場 6:30pm/開演 7:00pm
料金 5,000円(予約)/5,500円(当日)*ドリンク代別
10月30日(日)東京 7th FLOOR(03-3462-4466)
東京都渋谷区円山町2-3 O-Westビル7階
出演:ボニー・プリンス・ビリー&ビッチン・バハス with 馬頭將器(The Silence / ex: Ghost)、ダスティン・ウォング
開場 6:30pm/開演 7:00pm
料金 5,000円(予約)/5,500円(当日)*ドリンク代別
チケット:予定枚数が終了しましたので、予約受付を終了いたしました。当日券の有無につきましては、公演当日、会場に直接お問い合わせください。
企画・制作:スウィート・ドリームス・プレス
(詳細は以下をご参照ください)
https://www.sweetdreamspress.com/2016/08/bonnie-prince-billy-bitchin-bajas-japan.html