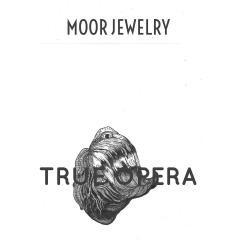いまから15年以上前のことだが、渋谷のとあるクラブで、DJ KRUSH にこう言われたことがある。「そのままでいてくれ」と。彼のサングラス越しの目線に、実際のところどんな真意が秘められていたかは分からない。だがそれは、自身のグループでの活動を始めて数年間、デモテープや12インチを祈るように彼に手渡していた筆者にとっては、とてつもない褒め言葉に聞こえた。「このままでいいのか!」「信じる道を突き進めばいいのか!」というわけだ。
だからいま、DJ KRUSH の新譜を前にして、自然と次の疑問が浮かんだ。果たして DJ KRUSH は、「そのままでいる」のだろうか。
結論から言えば、1994年のファースト・アルバム『KRUSH』から、2020年の本作まで、DJ KRUSH は、「そのまま」だ。とはいえ、懐古趣味に引き摺られ、今作の中にいつまでも『Strictly Turntablized』(1995)や『Meiso』(1995)のような初期サウンドの面影を探そうというわけではない。なにしろ、26年の歳月がもたらしたテクノロジーの変化に伴い、機材や制作方法、そしてなによりもそのアウトプットとしてのサウンドは、とてつもなく変化してきたのだ。
では何が変わらず、「そのままでいる」というのか。それは、DJ KRUSH がその興隆の一端を担った「アブストラクト」という方法論に対する「構え」のようなものだ。
とはいえ、サウンド面の変化は大きい。前々作『軌跡 -Kiseki-』(2017)はラップ・アルバムだったし、前作『Cosmic Yard』(2018)は近藤等則らの楽器奏者とのコラボレーションを含んでいたが、今作は全12曲、ノーゲスト、DJ KRUSH ひとりだけで向き合った作品だ。
初期作品から近作にかけての一番大きなサウンド面の変化は、AKAI のサンプラーを使ったレコードからのサンプリング・ミュージックから、Ableton Live 中心で制作されたDTMへの移行ということになるだろう。近作でもサンプリングCDや、あるいは楽器奏者や自分で演奏したフレーズからのサンプリングという手法は継続されている。だが、サンプリングという側面で考えれば、今作は、これまでにないほど、サンプリング感の少ないアルバムと言えるだろう。
その分、複雑な音色のモダンなシンセやノイズの打ち込み色が濃厚な今作は、あえてジャンルの名を挙げれば、インダストリアルやダブステップ、そしてLAビートと共鳴し合う、ビート・ミュージックだ。その執拗なまでに重ねられたレイヤー状のサウンドの塊の密度は、これまでないほどに、高い。そして4小節ごとに訪れる展開の慌ただしい豊かさ、キメの数々もかつてなく丁寧に構築されている。つまり縦(トラック数)にも横(経過時間)にも増えたり減ったりを繰り返し、変化し続ける楽曲群。今作にはひとりで制作に対峙する DJ KRUSH の意気込みが、いたるところに見え隠れしている。
どういうことか。今作の流れを追いながら、聞こえるものを言語化してみたい。
オープニングの “Incarnation” は、アブストラクトな件の場所への、不穏な案内状だ。甲高いスネアがノックする、普段とは別の聴覚のドア。今作の一曲一曲は、毎月一曲ずつ配信リリースするという試みのもと、制作されてきた音源だ。だがアルバム用にミックスが施された同曲は、キックとスネアが一気に前景に踊り出て、何よりも「DJ KRUSH の音楽を聞いているのだ!」と知らされる。不穏でも幽玄でもあるSEとキックが、4小節ごとに小爆発を繰り返す。裏拍の太鼓のような打楽器やサイドチェーンの効いた風の音色が教えてくれるのは、DJ KRUSH が背負ってきた「和」の鳴らし方。全体を通して鳴っている死者たちの高らかな笑い声のような音色は、タイトル通り「受肉したビート」を指し示しているようだ。
続く “Doomsayer” では、DJ KRUSH の音楽的な顔が覗く。3連ベースで刻むリズムが運ぶのは、和風でもありオリエンタルでもあるようなメインのホーンの旋律の力強さと、対照的なオルゴールのアルペジオの内省的な調べ。それが指し示す叙情は、どこか Boss The MC との名曲 “Candle Chant” のパッセージを想起させる。2小節毎の2種類の和音で聞かせてくれるループが、少ない音数で熱くなり過ぎないエモーションを捉える。ほぼ4小節ごとにいくつものサウンド群が入れ替わり立ち替わり現れて交響曲のように展開する本曲は、アルバム随一「物語」を感じさせる曲かもしれない。
3曲目 “Onomatop” では、細かく刻まれるサブベースとハイピッチのスネアがドライヴするバンガー。注目すべきは、順番に重ねられる、ハットの代わりにリズムを刻む3種類の音色たちだ。中央で鳴る吐息を加工したようなハットのようなサウンドは、人が息を吐く際の音色が口の形で変わるように、ハイハットのオープンとクローズを代弁している。中央と左右にパンされ絡み合う粘着性のスタブ音も、どこか生物の立てる音を想起させる。さらにはアトモスフェリックのSE然としたうねるノイズが中央の後ろを飾るが、これもまた人や獣の唸り声を加工したようなサウンドだ。「オノマトペ」というタイトル通り、これらは人の声を入力の一部に使っているような音色たちなのだ。今作では、このようなオノマトペ・サウンドが積極的に用いられ、有機的なサウンド作りに一役買っている。
4曲目 “Regeneration” で披露されるズバりフライング・ロータスを想起させるトライバルな打楽器とクラップから成るヨレたビートとコズミックなシンセのアルペジオは、DJ KRUSH・meets・LAビートと呼びたくなるようなサウンドだ。だが人間の歌声ベースのスピリチュアルな調べが、このビートが紛れもない DJ KRUSH 製であることを強調する。若き時分に DJ KRUSH を聞いてインストゥルメンタルのアルバム表現の可能性に気づいたフライング・ロータスとの、インスピレーションの往復運動。
後半に突入し、8曲目 “Infinite Fragment” で耳に飛び込んでくるのは、徹底的にドライなキックとスネアだ。そしてそれとは真逆の地底の奥底から響くような残響音を伴ったSEの数々。それらが表象するのは、地底から吹き付ける風やマグマの唸りであり、自然が本来持つ不穏さであり、冷たい雨であり、人為を焼き尽くそうとする炎である。隙間を縫うように聞こえるのは、縦横無尽に飛び回る微生物のような跳躍音。だがこのようにいくら言葉を尽くそうとも、ここには本来言葉で形容できそうなサウンドは何もない。だから、DJ KRUSH の音楽は「アブストラクト」と呼ばれる。彼のDJプレイで、フロアの真ん中で突然、いまいる場所を忘れ、人間や生物の生と死、自然や何か大きなものと対峙するような感覚に陥ったことがあるなら、それは「アブストラクト」であることが呼び水になっているからに違いない。オノマトペといい、自然の環境音を想起させるシンセ音といい、マシナリーとオーガニックのあわいを音で表現することこそ、DJ KRUSH が「そのまま」で探求を続けている試みのひとつだろう。
叩きつけるようなキックとスネアが駆動する “Cell Invasion” と “C-Rays” を経てたどり着く12曲目の “Signs of Recovery” は、BPMがスローダウンする一方で、32分ベースで刻まれるハットとシンセのスタブによって、逆にスピード感が強調される構造をしている。あえて言うなら、これは DJ KRUSH 流のトラップだ。後半にかけて徐々に盛り上がる展開がフロアの興奮を想像させるが、前半の残響の深い汽笛のような笛の音色がもたらす陶酔は、トラップの代名詞である酩酊感と符合する。
ビートメイカーにとって、最初はDJであることが前提条件でなくなって久しいが、DJ KRUSH は何よりもまず「DJ」であり続けている。例えば YouTube にアップされている2019年にバルセロナで開催されたSonarフェスティヴァルの彼のDJセットを聞けば、現在進行形のバキバキのブロステップなどクラブバンガーを矢継ぎ早に繰り出し、クラウドを湧かせている。だからそのDJプレイの中に自身の曲を入れたときに、最新モードの楽曲群にもマウントを取りにいける音圧とリズムが必要だ。どんなにビートの種類が変わっても、DJ KRUSH の音楽が、聴衆に眩暈を起こさせるダンス・ミュージックであることは、決して変わらない。
アルバムのラストを飾る “Bluezone” は、金属を打ち鳴らし、深さを競い合うようなインダストリアルなSEサウンドから始まる。今作で何度も存在感を誇示してきたサブベースとタッグを組むキック、そしてドライなスネアが、ゆっくりと感情を押し殺しながら醒めたビートを立ち上げる。するといくつものシンバルや打楽器の音色で狂ったように跳ね回る32分音符のリズムが、徐々に明滅し始める。シンセのリフが導く後半から、どこまでも音数を増やしながら重なりゆくリズムのシンフォニーは、やがて絶頂を迎え、弾けて消える。その残響音の余韻は、そのまま1曲目の “Incarnation” のイントロに輪廻するだろう。
かつて DJ KRUSH が、どのレコードのどの楽器のサウンドやフレーズを引っ張ってきたのか特定できない「抽象的な」音をサンプリングしたり、スクラッチして組み立てたビートは、「アブストラクト」という名にふさわしい発明だった。だが今作にいたって「アブストラクト」を提示する方法は、極めて大きな変化を遂げた。彼が辿り着いた方法は、うねりながら咆哮する無数のシンセやSEサウンドをレイヤー状に織り上げることによって、複雑に変化し続け、かつ全体の輪郭すら把握できないほど巨大なゆえに「アブストラクト」である音塊を産み落とすことだった。
しかし方法は変われど、DJ KRUSH が「アブストラクト」な音像を用いて接近しようとしている境地は変わらない。フロアの真ん中で身体を揺らす、あるいはヘッドフォンを装着して自室にこもる僕たちに、DJ KRUSH が見せてくれる景色=眩暈は、ずっと「そのまま」なのだ。