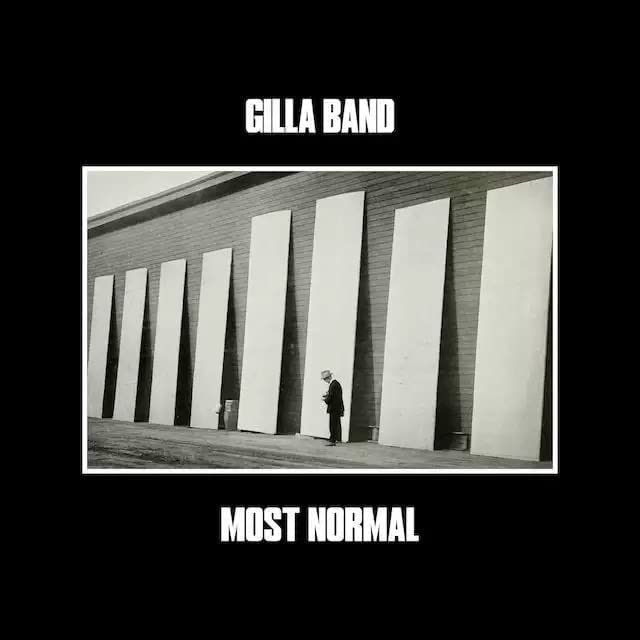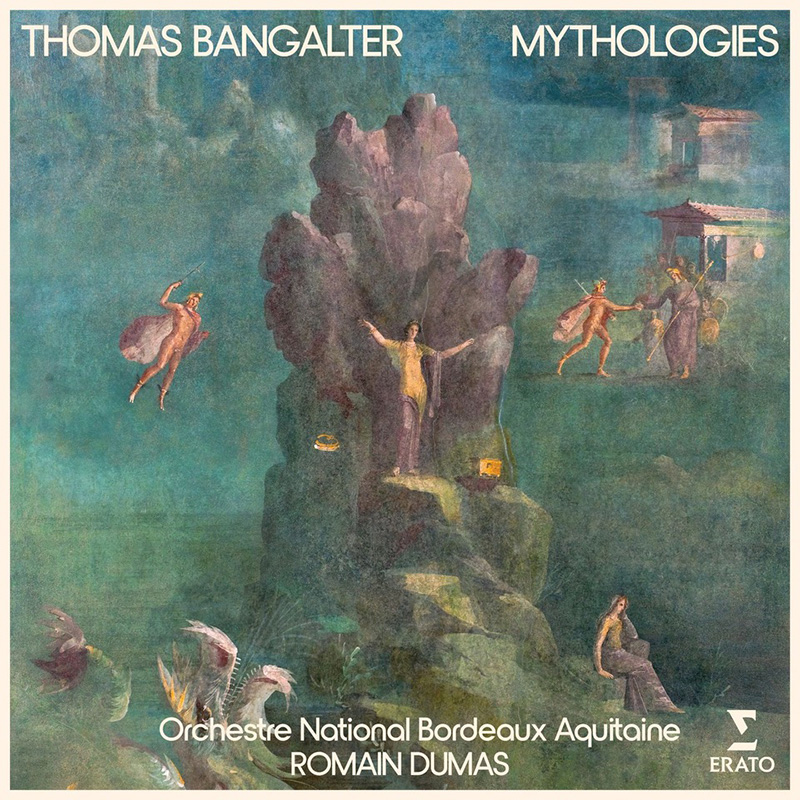ロックが培ってきた実験精神と、ゴスペルやR&Bといったブラック・ミュージックが育んできた大衆性、その最良の結合──エディンバラの3人組、全員がヴォーカルをとるヤング・ファーザーズの魅力といえばそれに尽きる。ソウルを愛する文化がアメリカ以上に深く根づいている、イギリスだからこそ出てくる音楽だろう。
2010年代前半、LAの〈Anticon〉から浮上しエクスペリメンタルなヒップホップ・サウンドを展開していた彼らは、ファースト『デッド』(2014)でマーキュリー・プライズを受賞するとヒップホップ色を薄め、徐々にポップな要素を増大させていった。クラウトロックの冒険心をとりいれたセカンド『白人も黒人だ』(2015)やその延長線上にあるサード『ココア・シュガー』(2018)も、実験的でありながら親しみやすいコーラスを持ちあわせた、広く門戸の開かれた作品だった。
はたして5年ぶり4枚めの新作『ヘヴィ・ヘヴィ』は、その重々しいタイトルとは裏腹に、かつてないキャッチーさを携えている。ノイズがだいぶ控えめになったことに驚くファンもいるかもしれない。出だしの “Rice” からして祝祭感満載で、ネオリベ社会を風刺したかのようなリリックの “I Saw” にそのアンサー “Drum” と、アルバムはどんどん疾走感を増していく。注目すべきはやはりゴスペル的な要素の前景化だろう。オルガンが教会を想起させる4曲目 “Tell Somebody” でその聖性は最初のピークを迎える。各曲で重ねられるコーラスはまるで、あなたがけしてひとりではないことを強調しているかのようだ。なぜ彼らは今回、ゴスペルやソウルの部分を最大限に押し広げたのだろうか。
セカンドのタイトル『白人も黒人だ』によくあらわれていたように、ヤング・ファーザーズは聴き手に「どういうこと?」と立ちどまって考える機会を与えることを忘れない。「賛成する意見もあれば反対な意見もある。そして、みんなこのタイトルについて考えていた。〔……〕そういう作用を引き起こしたかった」のだと、メンバーのグレアム・ヘイスティングスは同作について語っている(紙版『ele-king vol.16』、2015年)。もしヤング・ファーザーズの音楽が難解なだけの代物だったら、そんな現象は起こらなかっただろう。リスナーと身近な人びととの会話を刺戟することができるからこそ、彼らはポップであることにこだわるのだ。「5時半に仕事を終え、運転して帰宅途中の人たち」のために音楽をつくっているという彼らの瞳には、つねに生身の人間、生活する人間が映っている。
新作のテーマはずばりコミュニティだ。というとなにか志を同じくする集団のようなものを思い浮かべてしまうかもしれないけれど、難しく考える必要はない。ようは近しいだれかと一緒にいることである。アルバムには、ネイティヴ・アメリカンの戦士の名を掲げた曲がある。彼はコミュニティのために戦った勇者だった。今回取材に応じてくれたアロイシャス・マサコイは、そのじつにソウルフルな賛歌 “Geronimo” について「人間関係のなかで、自分ができること、自分の役割を全うしたい。ぼくはそのために生きているし、そのために生まれてきた」とまで言ってのける。
ひとはひとりで生きているわけではない。パンデミックを経てヤング・ファーザーズは、あらためてわれわれにその事実に目を向けさせようとしているのかもしれない。そもそも「ヤング・ファーザーズ」なる気どらないバンド名からして、メンバー全員が父とおなじ名前だからという理由でつけられたものだった。身近な人びととのつながりこそ、彼らの出発点だったのだ。
けして軽くはないテーマを忍ばせ、ときにはメランコリックなことばを紡ぎながらも、最終的には歓喜と祝祭に満ちたこのアルバムは、たとえば満員電車で無言でひとを押しのけたり舌打ちしたり、泣く赤子をあやす親にキレちらかしたりするのがあたりまえのここ日本においてこそ、もっとも聴かれるべき音楽ではないだろうか。
母親のためにスーパーに行って食材を買わなきゃいけないし、姪っ子や甥っ子の学校の送り迎えだってしなくちゃいけない。〔……〕自分のまわりのひとに尽くせないひとが、社会を変えられるはずがないと思うから。
■エディンバラはパンデミックのあいだどのようなムードだったのですか? やはり外出するひとがいない時期が長く続いたのでしょうか?
アロイシャス・マサコイ(Alloysious Massaquoi、以下AM):そうだね。街はかなり人出も少なくて静かな感じだったね。でも、報道されるような大袈裟な感じではなかったよ。実際には出歩いているひともいたし、仕事をしているひともいたし。テレビで観るような感じではなかったと思う。ぼくも外の空気を吸いに散歩に出かけたりしていたけど、出歩いているひとも結構いたね。
■いまは完全にもとどおりという感じですか?
AM:そうだね。もとどおりになってけっこう経っているかな。前と同じようにコミュニケーションがとれるようになったよ。
■前作から5年ぶりのアルバムですが、この5年でブレグジットやパンデミック、ウクライナの侵略などがあり世界は大きく変わりました。あなたたち自身はどこか変わりましたか?
AM:社会はつねに変化を続けているからね。それは世界という大きな枠ではなくても、個人個人の人生にとっても同じことだと思うんだ。自分とひととの関係性やリレーションシップも変化を重ねていくものだから。関係性がより強まったり、深まったり、ときには失ってしまったり、終わってしまったり。自分のなかで折り合いをつけて進んでいくしかないんだよ。若いときはその関係性のなかから自分が欲しいものを得ればいいし、歳を重ねるごとにひととの関係性に求めるものは変わってくると思う。家族にせよ友人にせよ、その関係性の上に築かれたものは強度や深度を増していくんだ。とにかくいろいろな変化を経験しながら進んでいく。それが人生だと思うから。
■社会的な問題などがあなたの考え方に影響をもたらすことはあるのでしょうか?
AM:それはあると思うね。もちろん、メディアで報道されていることについては自分の恋人や友人と議論することもあるし、会話のなかにも出てくるし。でも、たいせつなことは自分がいまいる場所、やるべきこと、やっていることに向き合うことだと思うんだ。社会でどんなことが起こっていても家賃は払わなくちゃいけないし、家のローンは払わなくちゃいけないし、光熱費だって払わなくちゃならない。母親のためにスーパーに行って食材を買わなきゃいけないし、姪っ子や甥っ子の学校の送り迎えだってしなくちゃいけない。自分がすべきことがあるから、まずはそれに責任を持たなくちゃ。社会の問題についてぼくたちができることは限られているし。もちろん抗議デモに参加して、自分の意思を表明することなんかはできるから、自分にできる範囲でやればいいんだよ。コントロールできない問題だからと諦める必要もないけれど、自分のすべきことを放り出してまでやるのはちがうと思うな。まずは自分にできることからやるべきだよ。自分のまわりのひとに尽くせないひとが、社会を変えられるはずがないと思うから。それができて初めて、もっと大きなことに目を向けるべきなんじゃないのかな。先人たちもずっとそうやって乗り越えてきたはずだよ。今回のことが最後の戦争ではないし、これからも国同士の諍いや戦争は繰り返されて、終わりが来ることはけしてないんだから。自分にできることをやるだけさ。
■まずは自分のまわりのひとを幸せにしなければということですね。
AM:そのとおりだよ。

photo by Fiona Garden
全体をとおしてぼくたちが表現したかったことは、コミュニティの雰囲気や共同体の持つ様相といったものなんだ。みんながユニゾンで歌ったり、レイヤーを重ねていくところに、そうしたものの要素が込められていると思う。
■ところでこの5年間に、好きな音楽の種類に変化はありましたか?
AM:どうだろう。パンデミックの時期は、むかし聴いていた音楽をよく聴き直していたような気がするな。子どものころに聴いていた曲とか。自分にとって忘れられないような出来事があったころに聴いていた曲を思い出したりしていたよ。当時好きだった曲ということではなくて、けしてその曲が気に入っていたわけじゃなくても、自分にとって人生の転機になるようなころの思い出と、そのころ聴いていた曲が結びついているような感じなんだ。その出来事のBGMになっているというか。もちろん、強烈に覚えているのは出来事のほうなんだけど、その曲を聴くと、当時のシチュエーションが鮮明に思い出される感じだね。そういう曲をよく聴いていた気がするよ。
■たとえばどんな出来事と、それに結びつく曲を聴いていましたか。
AM:鮮明に覚えているのは、ぼくがほんとうに小さいころ、難民として母とふたりの姉妹と一緒にアフリカからスコットランドに移住したときのことだね。4歳か、4歳半くらいのころだけど。アフリカにいたころ……それこそ1歳かそれくらいだったと思うけど、母がよくマキシ・プリーストの “Wild World” をかけていて、そのメロディを覚えていたんだね。スコットランドに移ってから、地球の環境問題なんかがとりざたされるときにその曲が話題にのぼっていたりして、ふとこの曲がぼくの頭のなかに響いたんだ。もちろん、誰のなんという曲かは知らなかったよ。それで、7歳か8歳のころに、母に「こういうメロディの曲を覚えてるんだけど……」って歌って聴かせたんだよね。そうしたら母が「ああ、それはマキシ・プリーストよ」って教えてくれて。あの曲を聴くと、幼いころに嗅いだ匂いとか、スコットランドに移住してきたときのこととかを思い出すんだ。2015年に、祖父や叔母、いとこたちに会うために、ぼくは母を連れてガーナに里帰りしたんだ。ガーナの空港に降り立って空気の匂いを嗅いだとき、あの曲が頭のなかに流れてきた。母が大音量で聴いていたあの曲が、ぼくを当時の思い出のなかに連れ戻したんだ。
■すごくよくわかります。匂いと音楽は密接に記憶と結びついていますよね。ところで、5年前の『Cocoa Sugar』リリース後の話ですが、ドイツのフェスティヴァルがあなたたちの出演をとり消す事件がありましたよね。彼らはイスラエル大使館とパートナーシップを結んでいて、あなたたちが反イスラエルのボイコット運動「BDS」を支持していたことが理由でした。サーストン・ムーアやブライアン・イーノはそんなあなたたちを支持しました。以降もそれに似た、許せないことだったり、コミットできない出来事を経験することはありましたか?
AM:すごく単純にあそこでは演奏したくない、って思っただけなんだ(笑)。フェスティヴァル自体にはなにも思うところはなかったんだよ。彼らはアーティストを集めて、ぼくたちが演奏できる環境を最大限に整えてくれていただけだから。たんに演奏したくないという気持ちの問題だったんだけど、イーノやそういうひとたちがそれを支持してくれて。そのあとどんどん話が大きくなっちゃって、「あのフェスティヴァルのオーガナイザーはテロリスト・グループだ。テロを企てようとしている」という話にまで飛躍してしまったんだ。でもそれはおかしな話で、オーガナイザーのほとんどがユダヤ人だったんだから、そんなわけはないよね。「オーガナイザーの一部が、いろいろなアーティストとメールなどで密談を交わしていた」とかなんとか。それで数年後にドイツのマスコミが当時のことを訊いてきたとき、ちゃんと事情を説明したよ。出演をとりやめたのは、とても単純明快な話だということをね。それで、たったそれだけの話だった、ということをようやく理解してもらえたんだ。ぼくたちは人種もさまざまなグループだし、単純にコミュニティをサポートしたいと考えているから、特定の人種を攻撃するのではなく、互いに助け合うことを望んでいるんだ。逆にいえば、特定の人種だけを守って、他を排除するような活動については容認できないというスタンスをとっている。同意できない主張を掲げている団体とは関係を持ちたくないという、すごくシンプルな理由だよ、その前にも同じようなことがあって。
ぼくたちは2014年にマーキュリー・ミュージック・アウォードを受賞したんだけど。これはアニメーションなども含めたクリエイティヴな活動に贈られる、イギリスではとても権威のある賞なんだ。ぼくたちは受賞することができたけど、そのときに「ぼくたちのことは右寄りのメディアには書いてほしくない」って明言したんだよね。ぼくたちのことはとりあげてくれなくて結構、ってね。頭にくるのが、タブロイド紙とかそういうメディアにはぼくたちのことは書いてほしくないのに、書いてほしくないと言っていると書き立てるわけだよ(笑)。ぼくたちには、ぼくたちのことを書いてくれるメディアを選ぶ権利があるはずなのに、実際は嫌だと思うメディアのほうが、「嫌がっている」ということを格好の材料にして書くというね。いろいろな考え方を持つ、すべてのひとに満足してもらうことは不可能だから、結局はぼくたちが銃を鞘に収めるしかなかった。受けいれたわけではけしてないけど、彼らを喜ばせてやる義理もないしね。そういうことはこれからもあるんだろうなとは思うけど、それでも自分たちの主張を持つことや、自分たちの考えをちゃんと表明していくことには、ネガティヴな面よりポジティヴな面のほうがずっと多いと思うから。ある程度の状況は受けいれるしかないよね。理解してもらえなかったり、ぼくたちとの会話が対立の火種になってしまったりすることはある程度覚悟しておかないと。ぼくたちのこれまでの作品を聴いてもらえればわかるとは思うんだけど。
■そういうひとたちに限って、あなたたちの音楽を聴いていなかったりしますよね。あなたたちの音楽を聴けば、どんなことを考えていて、なにを否としているかは一目瞭然だと思うのですが。
AM:そのとおりだよ。そうなんだ。そこがいらつくけど、まあ、仕方ないね。
[[SplitPage]]たいせつなのは自分を取り巻く共同体と綿密な関係を築くことや、ひととつながることだと思う。そうしたもののたいせつさをぼくたちは繰り返し音楽をとおして伝えようとしているんだ。
■では、少し新作の話を聞かせてください。“I Saw” が公開されたとき、バンドの声明には「なにもかもがうまく行かないことをエスタブリッシュメントと移民のせいにするパンフレット」「長らく死んでいた帝国の悪臭」といった表現が用いられていました。この曲の主人公はなかなか怖いことを言っていますが、彼はなにを恐れているのでしょう?
AM:「チェンジ(変化)」だね。変化や力関係を自分でコントロールするには、自分とはちがう考えのひとたちとおなじ土俵で闘わなければならないからね。
■“I Saw” の主人公は「俺は勝ちたい」と歌っていますが、次の曲 “Drum” では「だれもが勝者になる必要はない」と歌われています。これはストーリーになっているのでしょうか?
AM:そうだね。勝ちたいと思う権利はあるけど、思うからといって実際に勝てるとは限らないから(笑)。世界のあり方にたいする理想は掲げていても、現実に直面して打ち砕かれてしまうこともある。そういう二面性を描いているんだ。なにを思おうが、なにを言おうがそれは自由だけど、♪You Can’t Always Get What You Want (※ザ・ローリング・ストーンズの曲)だよ(笑)。
■(笑)。続く “Geronimo” とは、あの有名なネイティヴ・アメリカンの戦士のことでしょうか?
AM:彼をベースにしているけど、彼自身というよりはむしろ彼のアティテュードについて歌っているんだ。敵と対峙する戦士の姿、銃口をつねに構えている姿勢、物事を判断し決断する力、アクションを起こす行動力といったものだね。飛び乗ったり飛び降りたり、自分の人生は自分でコントロールするというアティテュードそのもののことだよ。ネイティヴ・アメリカンの戦士として、植民地化や奴隷化の危機に晒された自分のコミュニティのために彼がしたことは小さなことかもしれないけど、すごいことだと思うから。自分たちもそうありたい、自分の居場所にとって、良き兄弟であり、父親であり、息子であり、伯父でありたい、何か決断を下さなければいけないときは、正しく行動したい。自分が愛する女性に喜びを与えられる存在になりたい。ともにいい時間を過ごしたい。人間関係のなかで、自分ができること、自分の役割を全うしたい。ぼくはそのために生きているし、そのために生まれてきたと思うから。そうした思いが地脈に流れている曲なんだ。
■ヤング・ファーザーズの音楽には実験的な要素とポップな要素が同居しています。今回は以前のクラウトロック的な試みとは異なり、ストレートなポップネスが大きく出ていて、全体的にコーラスなどがゴスペル的な雰囲気を演出しています。このサウンドには自然に行きついたのでしょうか?
AM:そう思う。全体をとおしてぼくたちが表現したかったことは、コミュニティの雰囲気や共同体の持つ様相といったものなんだ。みんながユニゾンで歌ったり、レイヤーを重ねていくところに、そうしたものの要素が込められていると思う。どんどん要素を重ねて重ねて、極限まで重ねていった感じだね。ポップ・ミュージックのフォーマットでは、通常は多くの要素を削ぎ落としていくものだけど、今回のぼくたちは重ねて重ねて、とても密度の高いレイヤーに仕上げていったんだ。そこには再評価すべきものやサブカルチャー的な要素も含まれていると思うんだけど、ぼくたちがこのアルバムで描きたかったことは、世界で起こっていることや環境問題について、個人としてできること、それと共同体としてできることだと言えるだろうね。それに、コミュニティの感覚……個人個人のちがいをすべて包みこむような共同体。すべてのひとが自分らしくあることのできる共同体を表現したかった。これを聴いたひとが、最終的にはヒューマニティについて考えてくれたら嬉しいね。人間のあり方や、互いを認め合う寛容性のようなものに行きついてくれたら嬉しいとぼく個人は思っているんだ。
■実際、ヤング・ファーザーズの音楽にはつねに喜びや祝祭性、楽しむことがあります。それを忘れないのはなぜですか?
AM:それはやっぱり、ぼくたちの音楽がヒューマニティ、人類のあり方や人間関係、ひとの情について歌っているからだろうね。ぼくたちは難しい局面や辛い経験もしていかなければいけない。でも、それは笑うことを忘れるという意味でも、人生をエンジョイできないという意味でも、人生の楽しみを知ることができないという意味でもないと思うんだ。さまざまな困難にぶち当たって、痛みやトラウマを感じてしまうかもしれないけど、それでも楽しむことはできるし、いい時間を過ごすこともできるんだ。人生のなかで、ときにはなにか乗り越えなければいけないこともあると思うけど、そんなときはひとと会話を交わしたり、どこかに出かけたり、散歩をして気分転換したりすることもできると思うしね。それが人生そのものだからさ。そうしたなかで、やっぱりたいせつなのは自分を取り巻く共同体と綿密な関係を築くことや、ひととつながることだと思う。そうしたもののたいせつさをぼくたちは繰り返し音楽をとおして伝えようとしているんだ。
■8曲目の “Sink Or Swim” は疾走感のある曲ですが、「現状に泣きわめいても仕方がない そんなに深刻になる必要はない」というフレーズがまさに現代だからこそ重要に思えますよね。
AM:そのとおりだよ。もちろん、このフレーズで歌われているような心境に至るまでは、多くのことを乗り越えなければならないと思うし、だからこそ一度沈んでみる必要もあると思うんだ。深淵まで深く深く潜っていくことで、ことの真相を垣間見ることができるかもしれないし、そこをうまく泳ぎ切ることができたら、反対側の光のある方向から抜け出すことができるかもしれないから。もちろん、あえて自分から深みにはまっていく必要はないのかもしれない。表面を上手に泳いでいけばしのげることもあるからね。でも、深い場所に行けば行くほど見えてくることもあるし。深みを知ることで心が軽くなることもあるだろう。この曲で言いたかったことは、その決断は自分で下せるということさ。自分の人生の主人は自分だし、舵取りも自分自身なんだからね。
■そのことばにすごく勇気づけられます。あなたたち自身はついつい暗く悲観的になってしまうことはありますか?
AM:もちろん、そういう悲観的な精神状態というのも、楽観的な考え方の一部を構成していると思うから。ある状況下において、自ら決断を下すということは、その決断に責任を持たなければならないということだからね。ぼくたちの決断は、これまでの人生で経験したことに基づいているけど、そのことに責任を持つ必要があるし、自分自身にたいしても責任を持つ必要があるから。それにもちろん、自分と関わるすべてのひとたちにたいする責任もあると思うしね。自分が選んだことや決めたこと、それに自分がやったことの責任をほかのだれかに押しつけるようなことはしたくない。よりいい人生を送って、より大きな成功を収めるためには、自分ですべてのことに責任を持つことがたいせつだし、そのためには自分自身を律することもたいせつだと思うんだ。ジムでからだを鍛えるのでもいいし、ランニングをするのでもいいし、歩くのでもいいし、サイクリングでもいいし、本を読むことでも、なにかを書くことでもいい。自分の精神状態を健康に保つことがとても大事なんじゃないかと思うな。それが自分らしくあるための、責任のひとつでもあると思うよ。
■あなた自身は、具体的にどうやって精神状態を保っているんですか?
AM:ぼく個人としてはジムでからだを鍛えるのが性に合っていると思うね。それと、家族と会話を交わすこと。理解してもらおう、賛成してもらおうと思って話をするわけじゃないけど、自分の考えをひとに話して意見を交わすことで、明確になることもたくさんあるからさ。散らかっていたものをまとめるのに役立つし、それもぼくらしくあるために責任を持つべきことのひとつだね。あとは、エクササイズをするのも好きだよ。頭がスッキリして物事を明確に考えられるようになるからね。とにかく、自分を心身ともに健康に保つことが大切だと思う。ライスをたくさん食べるでもいいし(笑)。
繊細であれ、ということさ。「傷つきやすさ」を弱点ととらえるひとも多いけど、ぼくは逆に強みになるんじゃないかと思っていて。傷つくということは、いろいろなことにたいしてオープンである、ということでもあると思うんだよね。
■わかりました。最後の曲 “Be Your Lady” には「俺はお前の女になりたいんだ 俺が男だということを忘れて」という一節があります。これは近年のジェンダーの議論やアイデンティティの問題を踏まえているのでしょうか?
AM:そうとらえることもできるよね。この曲で描きたかったたいせつなことは、「繊細でいること」なんだ。繊細であれ、ということさ。「傷つきやすさ」を弱点ととらえるひとも多いけど、ぼくは逆に強みになるんじゃないかと思っていて。傷つくということは、いろいろなことにたいしてオープンである、ということでもあると思うんだよね。傷ついたり、精神的に落ちこんだり、なんとかそれを乗り切ることで強くなっていけるんだから。胸の痛みや悲痛な思いを経験するということは、そのひとがあらゆるものにたいして繊細で、感受性が豊かだということだ。テレビを観ていたって、本を読んでいたってなにかを感じることのできる感情の豊かさというものは、さまざまなことにたいしてオープンで受け入れる姿勢ができているということ。世のなかには男性的、女性的という感覚が存在していて、男らしくあることと繊細でいることは対極にあるように捉えられがちだけど、そうじゃない。そういう既成概念を取り払うべきだという思いもそこにはあるのさ。
■たしかに、傷つきやすくて繊細、というのは弱点のように感じてしまいますが、その考え方は興味深いですね。
AM:そうなんだよ。けして弱点じゃないんだ。なににたいしても感受性豊かに、オープンな気持ちで受けいれられるということだし、行間を読む力も空間把握能力もあるというだと思うんだよね。そこにある空気やエネルギーの流れも読みとることができる。そういうことができるひとはとても繊細だし、それは大きな強みだと思うんだ。
■それが最後にカネの話で終わるのが印象に残りました。これは皮肉ですよね?
AM:そうかもしれないね(笑)。
■全体をとおして、サウンド的には祝祭感のあるアルバムだと思うのですが、タイトルに『Heavy Heavy』とつけたのはなぜですか?
AM:これは、ぼくたちがレコーディングに際して踏んだプロセスに関係しているんだ。今回のアルバム作りは、すべて自分たちで手掛けたから、他のどの作品よりも時間が掛かったんだけど。外部のプロデューサーに参加して貰うこともなかったし、全部自分たちだけで作ったんだ。だから、自分たちにとってすごく重みのあるものになった、という意味が込められているんだよ。それに、「Heavy」1語だけだと、重量感だけが際立ってしまうけど、2回繰り返すことで、どこか軽さも出ると思ったんだよね。そうすることで、クリエイティヴな部分や作ることの楽しさ、というものもプラスすることが出来たんじゃないかな。忍耐と喜びと、進化の過程と、そういうものがすべて相まってペースの速いサウンドになっていったのかもね。悲しみと喜び、ほろ苦さと甘さの調和を試みた作品になっていると思う。
■今回のアルバム制作はどのようなプロセスを踏みましたか? 最初に、これをやる、これはやらない、というような約束事やルールのようなものはあったのでしょうか? サウンド面でもリリック面でも良いのですが。
AM:そういうルールはまったくなかったね。むしろ、どんなことにたいしてもオープンであるように心掛けた感じだね。スタジオに集まって、セッティングして、とにかくやってみよう、という感じでレコーディングして一発で上手くいったものも多いし。たとえばぼくが書いた曲でも、他のメンバーがもっといいアイデアを持っていたら、こだわらずにどんどん受けいれて、結果的にずっとよくなった曲もあるし、その逆もある。その躍動感のようなものを大事にしたかったから、誰かが咳をしたり、誰かがミスをしたりしても、敢えてそれを残したんだ。普通はそういう部分を細かくカットしていくものだけど、それこそがぼくたちの作品そのものだと思ったからね。だから、ルールのようなものは一切なかったよ。もしあるとすれば、これまでに耳にしたことのないようなものをやろうっていうこと。もし何かやりたいことがあったら、どこかで聴いたことのないものになるよう心掛けたということかもしれないね。
■では、2月から3月までヨーロッパとUKでのツアーが控えていますが、その後やってみたいことはなんですか?
AM:ツアーが終わったら、一旦少し休んで、それからまた集まって夏のフェスティヴァルに備えることになるだろうね。年内には、どこかに休暇に出掛けたいと思ってるけど。友だちに会いにどこかに行くのでもいいし。普通の暮らしがしたいね。友だちに会ったりとかさ。
■では最後に、もしこのアルバムのリミックス盤をつくるとしたら、依頼してみたいアーティストを教えてください。
AM:いい質問だね。そうだな……家族を招いてバッキング・ヴォーカルを録音してみたいかな(笑)。それをリミックス・ヴァージョンとして発表してみたいね(笑)。
■それは楽しそうですね(笑)。ゴスペルっぽい感じですかね。
AM:そうそう。そんな感じだよ。