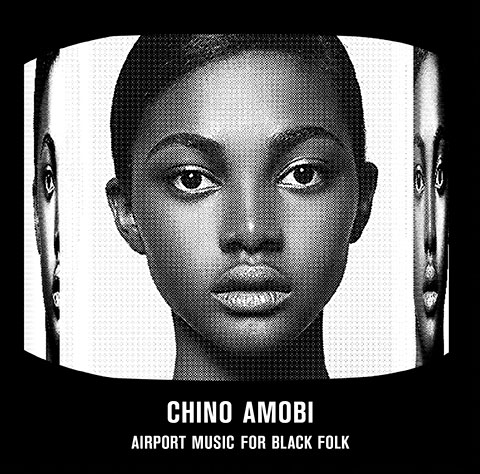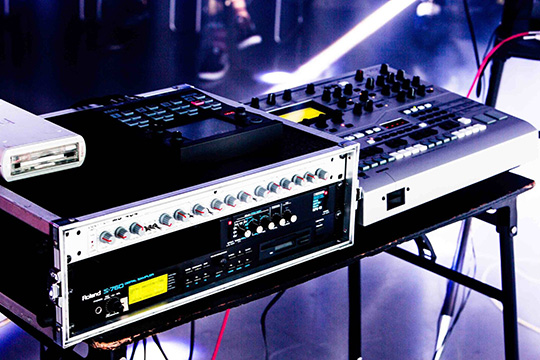人間の吐く息がダイレクトに空気の振動となり、音となる――という、管楽器の身体性が、昨年のボン・イヴェールの傑作『22、ア・ミリオン』に必要であったことは象徴的なことに思える。同作はテーマの抽象性や内省にも関わらずそこに多くの人間がいることが重要であったが――ある種の音楽的コミュニティがそこでは築かれている――、サウンド面ではとりわけ管楽器が多彩な表情をつけることに一役買っていた。そこからは様々な人間の吐く息が聞こえる。そしてそれは、ときに歪められたり加工されたりすることによって、まったく個性的な「声」としてそこで共存している……。
ボン・イヴェールやアーケイド・ファイア、アニマル・コレクティヴら北米インディ・バンドへの参加で知られるサックス奏者、コリン・ステットソンのソロ作『オール・ディス・アイ・ドゥ・フォー・グローリー』は、一言でいえばバリトン・サックスによるIDMということになるだろう。ステットソンはEX EYEというポスト・メタル、ジャズ・メタル(と、とりあえずはいまのところ呼ばれている。カテゴライズが難しい非常に実験的なメタルということ)・ユニットでも現在活動しているが、いまや北米のエクスペリメンタル・シーンをつなぐ重要人物のひとりである。これまでのソロ作や、同じくアーケイド・ファイアのライヴ・メンバーであったヴァイオリニストであるサラ・ニューフェルドとの共作『ネヴァー・ワー・ザ・ウェイ・シー・ワズ』ではそのミニマルな作風からスティーヴ・ライヒやマイケル・ナイマンと比較されることが多かったが、『オール・ディス~』では本人が明言しているとおり方法論的に雛型となっているのはエイフェックス・ツインであり、IDMである。つまり、複雑に変幻していくリズム感覚と緻密なエディットが大きな聴きどころとなっている。サックスの演奏を多重録音し、そこに少しばかりのリズム、声を加えていく作風はこれまでと同様だ。ただ、ヘンリク・グレツキの交響曲第3番を独自に解釈し、オーケストラと声楽を大きく導入した前作『ソロウ』がある種の過剰さに貫かれていたのとは対照的に、本作では音のレイヤーをぐっと減らし、少ない音を的確に配置していくことによってストイックに耳を興奮させる。
単一の楽器によるループとその多重録音を骨格とするという点では、たとえばマーク・マクガイアの手法と近いと言えるかもしれないが、マクガイアのギターが醸すリリカルさやスピリチュアリティに比べると、サックスという楽器の特性ゆえかステットソンの吐き出す音はもっと粗暴で生々しく、フィジカルだ。“Like Wolves On The Fold”や“In The Clinches”ではキーをカチャカチャと素早く押さえる音がそのままリズムとなり、ミストーンのノイズや音の乱れもそのまま録音されている。何よりもバリトン・サックスの低音の迫力――ゴッドスピード・ユー!ブラック・エンペラーのような重々しさを内包したまま、速弾きの躍動感でドライヴする離れ業がステットソンの魅力だ。本作のオフィシャル・ヴィデオではサックスを狂おしく吹き続けるステットソンの姿とサックスのアップばかりが映されるが、人間の身体からいまその瞬間に放たれる息が音に変換しているというダイナミズムがそこでは運動する。とりわけ、終曲“The Lure Of The Mine”において、13分にわたってウネウネと姿を変えていくサックスの旋律はほとんど官能的ですらある。ミニマルなのに自在に上下するメロディと、荒々しいグルーヴ、聴き手を陶酔と覚醒で翻弄するかのような不敵な構成――スリリング極まりない。
もうひとり、ボン・イヴェールに参加したプレイヤーのソロ作を紹介したい。ジャスティン・ヴァーノンと同郷のウィスコンシンはオークレアのトランペット奏者、トレヴァー・ハーゲンによるノイズ・アルバム『ワンダータウン』は日本のカセットテープ・レーベルである〈kolo〉からリリースされているが、これがトランペットという楽器の知らなかったポテンシャルを発見するような驚きに満ちている。プリペアド・トランペットによる乾いた高音は悲鳴のように轟き、それは切り刻まれのたうち回る。まるで音それ自体がひとつの生き物のようなのだ。けっして耳触りのいいものではないが、管楽器が呼吸器と繋がっていることを如実に感じさせるような熱がこもっている。そしてそれは、静謐なドローンへとやがて姿を変えていくが、緊迫感に満ちた音楽体験がここにはある。
ステットソンにしてもハーゲンにしても、2000年代後半からのノイズ/ドローンと地続きのものではあるのだろう。昨年のボニー“プリンス”ビリーとビッチン・バハスのジョイント・ライヴを観たときにも感じたが、USインディ・シーンにおいてアメリカーナやフォーク・シーンとノイズやエクスペリメンタルがシームレスに繋がっていることは、そのサウンドの拡がりにおいて大きな強みとなっている。そこでは雑多な人間の実存を主張するかのように、多様な「声」が複雑にポリフォニックに折り重なっているのである。