デビューからちょうど30周年を迎えたスチャダラパーによる、13作目となるフル・アルバム『シン・スチャダラ大作戦』。このタイトルは、彼らのデビュー・アルバムである『スチャダラ大作戦』の現代版アップデートとも読み取れるわけでもあるが、30年間、いい意味で全く変わらないスタイルを貫いてきた彼らのスタンスそのものが反映された作品にもなっている。
本作の目玉のひとつとなっているのが、“スチャダラパーからのライムスター”名義にて先行でシングル・リリースもされたRHYMESTERとの初のコラボレーションによる“Forever Young”だ。年代的にもキャリアの長さ的にもほぼ同じこの二組であるが、両者の歩んできた道はまったく異なる。『スチャダラ大作戦』リリースの時点ですでにサブカル界のニュースターであったスチャダパラーと、スチャダラパーから約3年遅れでリリースされたデビュー・アルバムを今では(半ば冗談だが)自ら封印しているRHYMESTER。いずれも、当時の日本のヒップホップ・シーンを牽引していたインディ・レーベルである〈ファイル・レコード〉からのデビューというのも何とも不思議な縁を感じるが、以降、スチャダラパーはスチャダラパーであり続け、かたやRHYMESTERは常に試行錯誤を繰り返して切磋琢磨し、成長し続けていく。時を経て、いまでは日本のヒップホップ・シーンを代表するベテラン・アーティストとなった二組の待望の初共演曲。Illsict Tsuboiがプロデュースを手がけ、生楽器もフィーチャしたファンクネス溢れるトラックと4MCとのコンビネーションが生み出した“Forever Young”は、彼らがこれまで約30年にわたって表現してきたヒップホップのまさに王道中の王道。若手や中堅のアーティストは決して真似することのできない、味わい深い1曲に仕上がっている。こんな曲が、2020年のいま聴けるなんて、彼らと同世代である筆者にとっても、実に感慨深い。
なお、今回のアルバムのメイン・プロデューサーは当然、これまでの作品と同様にスチャダラパーのDJであるSHINCOが担当している。SHINCOの作るサウンドは現在進行形の最先端のヒップホップとも当然異なるが、しかし、その時代時代に合わせて常にアップデートが繰り返されきた。とくに1999年リリースの『FUN-KEY LP』辺りで、スチャダラパーのサウンド面での基本型というものが作り上げられたように思うのだが、その型をずっとキープしたまま、その軸となる部分は全くブレない。その上での着実なアップデートによって、スチャダラパーの変わらないスタイルというものが、常に新鮮なままキープされている。それは実はBOSEとANIという2人のラップに関しても同様なのかもしれないが、『スチャダラ大作戦』にも収録された“スチャダラパーのテーマ”を引用した“イントロダクシン”から“シン・スチャダラパーのテーマ”へ至るド頭の流れの時点で、格好良さから面白さ、全てを含んだ彼らの普遍的なアーティストしての魅力が溢れている。
日本に限らず、世界を見渡しても彼らのようなヒップホップ・グループはおそらく他に存在しないであろうし、今後もそう簡単には現れることはないだろう。30周年を超えてもなお輝き続ける彼らが、今後さらにどんな活動を繰り広げてくれるのか楽しみでならない。
「You meã€ã¨ä¸€è‡´ã™ã‚‹ã‚‚ã®
昨年ファーストEP「REASON」を発表し、今年2月に公開された “Selfish” で注目を集めたラッパーの Ralph、グライムなどからの影響を独自に咀嚼する彼が、さらなる新曲 “Back Seat” を本日リリースしている。プロデュースは引き続き Double Clapperz が担当! 不安を煽るストリングスがラップを呼び込む冒頭からしてもう最高にクールです。同曲を収録した最新EP「BLACK BANDANA」は6月10日に発売。
[6月12日追記]
ついにリリースされた Ralph のEP「BLACK BANDANA」より、表題曲のMVが公開されている。監督は Hideki Amemiya で、MURVSAKI プロデュースによるドリル・サウンドを引き立てるクールな映像に仕上がっている。チェック!
「JapanViral 50」に楽曲がランクインするなど、いま注目のラッパー Ralph が新作EPから先行シングル “Back Seat” をリリース。
ファーストEP「REASON」のリリースでその地位を確固たるものにし、2020年2月リリースのシングル “Selfish” は Spotify で「JapanViral 50」のプレイリストにランクインするなど、その勢いは衰えを知らない新鋭ラッパー、Ralph。本作は6月に発売が予定されている新作EP「BLACK BANDANA」からの先行シングル。
グライムやベースミュージックシーンにおいて、世界的に活躍するプロデューサー/DJユニットの Double Clapperz が手がけるタイトなビートに、Ralph の代名詞であるリアルなリリックと巧みなフローが展開されている。
6月10日にリリースが予定されているEPは “Selfish” “Back Seat” を含む5曲で構成されており、いまの Ralph を象徴する作品になること間違いない。2020年最も注目を集めている若手ラッパーの第二章が、このシングルから始まる。

リリース情報
アーティスト:Ralph
タイトル:Back Seat
リリース日:2020年5月27日
各種配信サービスにてリリース
https://linkco.re/TAauh36b

Ralph/ラッパー
2017年に SoundCloud で発表された “斜に構える” で注目を集めたことをきっかけに、アーティスト活動を開始。2018年には dBridge&Kabuki とのスプリットEP「Dark Hero」をレコード限定でリリースし、即完売。ファーストEP「REASON」のリリースでその地位を確固たるものにし、2020年2月リリースのシングル “Selfish” は Spotify で「JapanViral 50」のプレイリストにランクインするなど、その勢いは衰えを知らない。
卓越したラップスキルと自身のバックボーンから生まれるリアルなリリックが高く評価され、ヘッズの信頼も厚い Ralph。いま東京で2020年の活動が最も期待されている若手ラッパーの1人と言える。
Twitter:https://twitter.com/ralph_ganesh
Instagram:https://www.instagram.com/ralph_ganesh/
パンクが大衆の認識に与えた衝撃が完全に浸透するよりも前に、ワイアーはすでにパンクを弄び、嘲笑い、その限界を超越していた。新興のパンク世代が、より純粋であると思われる1950年代のロックンロールの価値観を称揚し、1970年代のプログレッシヴ・ロックの大仰さを軽蔑して根絶を望んでいたのをよそに、ワイアーは〈Harvest Records〉と契約を結んでピンク・フロイドと同じレーベルの所属となり、伝統的ロックンロールに残るブルース・ロックの影響を自分たちのサウンドから排除しようとした。パンク・ムーヴメントの中核に残された者たちは、パンクの限界をより深く突き詰めようとしたが、それがあまりにもあっさりと超えられたことに、ほとんど気づいてさえいなかった。
それから40年以上が経ったいま、ワイアーの音楽が反ロックの衝撃をもたらすことはなくとも、その栄誉の一部はワイアー自身に与えられるべきだろう。彼らが短期間で鮮烈にロックの形態を歪め、解体したことによる影響は長くくすぶり続け、ここ数十年に渡ってロックを再構築しようとする動きに力を与えており、状況は1970年代の終わりに彼らが目指した方針に近づいている。一方でワイアーが少なくとも2008年の『Object 47』以来切り開いてきた道は、ロックとの和解を目指しているかのようであり、ロックの構造に対する遠回しでぎこちない攻撃は健在ながら、自分たちの言葉で曲作りの方法論を探求することで、以前より遙かに心地よい状態に繋がっている。
また現在のワイアーは、過去の自分たちとの対話にますます没頭しているように見受けられる。ロックの既成概念を解剖するアイデアと、ほとばしるポップスの輝きを組み合わせるスタイルは当初から変わっておらず、バンドは過去の自分たちを折に触れて肯定することを厭わない。コリン・ニューマンが皮肉とともに“Cactused”の切迫感のあるサビに込めたメッセージは、バンドによる1979年の珠玉のポップ・ソング“Map Ref. 41 Degrees N 93 Degrees W(北緯41度西経93度)”と同じ無味乾燥なほのめかしを表している。それでもワイアーが現在のロックのあり方を受け入れるなかで辛辣さはわずかに鳴りを潜め、うまくいっているときに得られる純然たる喜びも多少は感じられるようになってきた。
そこには以前に比べて少しだけ緩さも生じているのかもしれない。1970年代のワイアーの楽曲は槍のように脳をきつく刺激するもので、リリース時点ですでに彼らのミニマリズムは完成されており、バンドはそこにさらなる活力を与えて展開させることは望んでいないように見受けられたが、現在、その音楽のなかに新たな活気が生まれる余地が徐々に認識できるようになっており、とくに『Mind Hive』ではその狙いが見事に開花している。“Unrepentant”や最後の“Humming”のような曲では、ブライアン・イーノ風と言ってもいいほどの広大なアンビエントの流れができており、一方“Hung”は、8分近くにおよぶ曲の中で核となるグルーヴを乗りこなせるという自信に満ちている。そうしたエネルギーは、新たに加入したギタリストのマシュー・シムスが持ち込んだ幻惑的な色合いにもたしかに受け継がれており、彼の存在感はますます高まっているが、それはまたバンドが少なくとも過去12年間で辿ってきた進化の道筋に欠かせないものでもある。
ワイアーが変わらず妥協のない挑戦的なワイアーらしさを保っていることは、歌詞に現れている。その歌詞は、現在のインディ・ロック・シーンで彼らの影響を受けているどの若手バンドと比べてもなお、鮮烈で鋭く、謎めいていると言っていいだろう。多くの楽曲では、オンライン空間のまとまりのない空虚な世界観が断片的な形で漂っており、“Humming”では謎めいたロシア人の存在に言及し、喪失感やうまくいかないものごとや頭をよぎる失われた自由について述べていて、“Hung”においては混乱のなかで制御を失われる感覚や「一瞬の疑念」から生まれた些細な混沌がひたすら描かれる。『Mind Hive』全体を貫いているのは、現在まさに動揺し崩壊しようとするこの世界に対する明白な意識だが、それぞれの歌が具体的な何かから引き出されたものだとしても、その直感の閃きを歌詞から辿ることはできない。歌詞に唯一残されているのは、断片的な糸口と脅迫めいた暗示であり、それは力強く感情を込めた、憂鬱と偏執からなる筆致で描かれている。これはおそらくロック・ミュージックに限らず、世界の全体が、ようやくワイアーに追いついたということなのかもしれない。
訳:尾形正弘(Lively Up)
Ian F. Martin
Before punk had even fully made an impact on the public imagination, Wire were already kicking it around, mocking it, transcending its limitations. As the emergent punk generation championed the supposedly purer values of 1950s rock’n’roll and sneered the pomposity of 1970s progressive rock into what they hoped was oblivion, Wire signed to Harvest Records as label mates to Pink Floyd and set about expelling the blues-rock influences of classic rock’n’roll from their sound, leaving the core of the punk movement digging deeper into its own limitations, mostly not even aware of how swiftly they’d been surpassed.
Now, more than 40 years on, Wire’s music doesn’t land the anti-rock impact, but part of the credit for that should probably go to Wire themselves. The slow-burning influence of their short, sharp distortions and deconstructions of rock forms has helped rock music over these past few decades to reassemble itself in a way that brings it closer to the path that Wire had begun charting in the late 1970s. Meanwhile, the path Wire have carved themselves, at least since 2008’s Object 47, feels like a sort of reconciliation with rock, retaining the band’s oblique and angular attacks on its structures but combining that with a greater comfort in exploring its songwriting conventions on their own terms.
The Wire of today also seem to be increasingly engaged in a dialogue with their own past selves. The combination of ideas that dissect rock conventions and bursts of glorious pop has been there since the beginning, and the band aren’t averse to the occasional nod to their past selves. Colin Newman’s irony-laced announcement of the impending chorus in Cactused directly references a similar dry aside in the band’s 1979 pop gem Map Ref. 41 Degrees N 93 Degrees W. Still, there’s a little less sarcasm in Wire’s nods to convention nowadays, a little more comfort in the simple joys of what works.
There’s perhaps a bit more looseness too. Where Wire’s songs in the 1970s were tightly-wound lances to the brain, already at such a point of minimalist completion by the time of release that the band seemed to feel no need to let them breathe and develop, there’s increasingly a sense of breathing space to their music now that is in particularly full bloom on Mind Hive. Songs like Unrepentant and the closing Humming have an expansive, almost Eno-esque ambient drift to them, while Hung has the confidence to ride its central groove for nearly eight minutes. Some of this must surely be down to the psychedelic tint brought by new guitarist Matthew Simms as he increasingly makes his mark, but it’s also part of an evolutionary course the band have been on for at least the past twelve years.
Where Wire are still uncompromisingly and defiantly Wire is in the lyrics, which are still fresher, sharper, more cryptic than nearly any of the younger bands that carry their influence in the contemporary indie scene. The disconnected, spectral presence of the online world haunts many of the songs in a fragmentary fashion; references to an ambiguous Russian presence, a sense of loss, of something gone wrong, of freedoms lost flicker through Humming; the sense of something spinning out of control, of mere chaos born out of a “moment of doubt” pounds its way through Hung. There’s a definite sense running through Mind Hive of our current shivering, crumbling world, but if the songs are drawn from anything specific, access to that spark of inspiration is closed off by lyrics that leave only fragmentary evocations and menacing hints, painted in powerfully emotional strokes of melancholic paranoia. Perhaps it’s not just rock music but the whole world that has only just caught up with Wire.
〈ラフトレード〉からのベスト盤『All That Glue』のヴァイナルは先週UKチャート1位です。
この3月に東京から大阪へと拠点を移したシンガーソングライターの豊田道倫が、急遽明日5月22日、新曲 “明るい夜” をリリースする。緊急事態宣言下にて、引っ越したばかりの大阪の部屋でふと湧き上がってきた曲だそうで、MVも公開されている。ファースト・アルバムから25年、50歳を迎えたばかりの豊田、その新たな船出を祝福しよう。
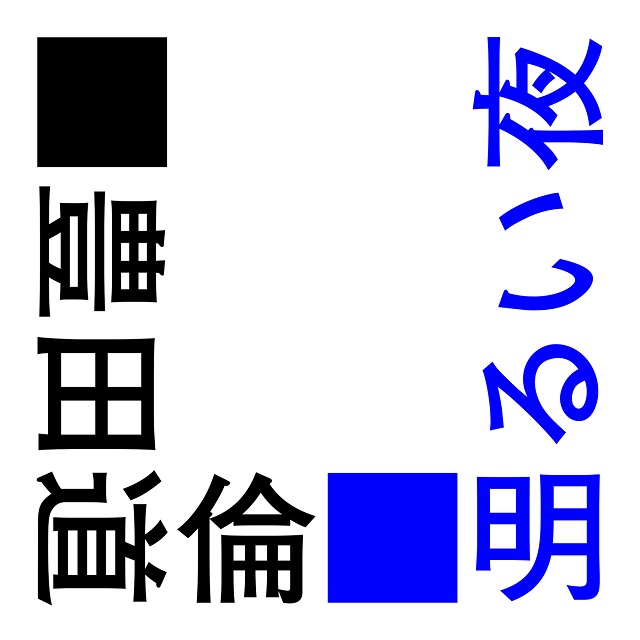
豊田道倫(Michinori Toyota)
タイトル:明るい夜(Bright Night)
企画番号:WEATHER 81 / HEADZ 246
発売日:2020年5月22日(金)
フォーマット:Digital
iTunes
https://music.apple.com/jp/album/%E6%98%8E%E3%82%8B%E3%81%84%E5%A4%9C-single/1512702591/
Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B088ZXYXZ7/
OTOTOY (ハイレゾWAV:24bit /48kHz)
https://ototoy.jp/_/default/p/546696
OTOTOY (ロスレスWAV:16bit / 44.1kHz)
https://ototoy.jp/_/default/p/546695
Apple Music
https://music.apple.com/jp/album/1512702591/
Spotify
https://open.spotify.com/album/3kLKfB6QcuwK0VdnxjeYty
Bandcamp
https://headzjp.bandcamp.com/album/-
Musicians
豊田道倫 : vocals & acoustic guitars
角矢胡桃 : drums & noise
みのようへい : bass, shaker & chorus
Tokiyo : electric guitar & chorus
Additional member
岡敬士 : synthesizer
Recorded & Mixed by 西川文章 at ICECREAM MUSIC on 30th, April 2020 & 4th, May 2020.
Mastered by 須田一平 at LM Studio on 5th, May 2020.
Produced by MT
Design:山田拓矢
https://www.faderbyheadz.com/release/headz246.html
豊田道倫「明るい夜」 [official music video]
監督:小池茅
出演:小川朋子, 小川大輝, 小川千晴
撮影:小川大輝, 小川朋子, 小池茅
https://www.youtube.com/watch?v=Jr6JqEOUPJg
緊急事態宣言発令の中、引っ越したばかりの大阪の部屋のキッチンで、この曲がふと出来た。
すぐに録音したくなった、バンドで。
ミュージシャンに声を掛け、リハを何とかやり、エンジニア、スタジオも確保して、録音した。
すべてが未知だったけど、ひたすら楽しかった。
何の迷いもなくやれた。
出来上がったMVを見て、デビュー25年、50歳。
でもおれは、本当に赤ん坊やと思った。
歌うこと以外、何をやってきたんだろう。
2020年の春のレコード(記録)として残せたことを、感謝します。
豊田道倫

撮影:倉科直弘
パラダイス・ガラージ名義で1995年5月25日に発表された1stアルバム『ROCK'N'ROLL 1500』から25年。
来たる2020年5月22日(金)に、シンガーソングライター豊田道倫が丁度1年振りとなるオフィシャル音源を発表します。
今年2月に50歳を迎え、3月に25年を過ごした東京を離れ、大阪に拠点を移してからの豊田の第一弾リリースとなる作品は、配信のみでリリースされる新曲 “明るい夜”。
このご時世でのリリースもあり、豊田の宅録作品と思いきや、関西在住のメンバーと共にレコーディング・スタジオにて制作され、近年の mtvBAND とのバンド・サウンドとも違う、新たなグルーヴを生み出した7分半を超える大作が完成しました。
(バンド編成でのレコーディング作品のリリースは2015年の『SHINE ALL ROUND』以来となります)
豊田道倫の新章のスタートを飾るに相応しい、世相を織り込みながらも普遍で、懐かしくも新鮮な、MT(Michinori Tokyota)のソングライティング、アレンジ、プロデュースの才能を存分に満喫できる作品となっています。
レコーディング・メンバーは、ノイジシャン、デュオ・ユニットの HYPER GAL としても活躍する角矢胡桃がドラムとノイズで、「みのようへいと明明後日」名義の全国流通作『ピクニックへ行こう』(SSR-01)で注目されたシンガーソングライターのみのようへいがベースやコーラスで、And Summer Club のメンバーでソロでも活動する Tokiyo が エレキ・ギターとコーラスで参加しており、〈Kebab Records〉を主宰する岡敬士(昨年は新バンド「自由主義」で豊田とバンドメイトだった)がシンセで彩りを加えています。
録音とミックスは ICECREAM MUSIC にて、(スタジオの主宰の一人でもある)西川文章が担当しています。
マスタリングは豊田の近作でも辣腕振りを発揮する関西のベテラン・エンジニア、須田一平(LM Studio)が手掛けています。
Music Video は、本日休演、ラッキーオールドサン 、加納エミリ、佐藤優介の映像を手掛けている小池茅が監督を務めています。
「明るい夜」のリリースに合わせ、昨年(2019年)の5月22日にパラダイス・ガラージ名義でカセットテープのみでリリースされた『SAN FRANSOKYO AIRPORT』(UNKNOWNMIX 49 / HEADZ 237)の配信リリース(サブスクも解禁)されることになりました。
カセットテープはレーベル在庫が無くなりましたので、この機会に新曲共々、是非お聴き頂ければと思います。
パラダイス・ガラージ(PARADISE GARAGE)『SAN FRANSOKYO AIRPORT』(UNKNOWNMIX 49 / HEADZ 237)
https://www.faderbyheadz.com/release/headz237.html
iTunes
https://music.apple.com/jp/album/san-fransokyo-airport/1511119090/
Spotify
https://open.spotify.com/album/53phrFAhth9SxyBlvwfi7r
明るい夜
昨日の新聞 そのままで キッチンテーブル 朝の影
彼女はひとり 出て行った 帰って来るとは 言わないまま
ふたり一緒に見ていたものは もう 夢みたい
くちびるの歌も 風の中 答えは誰も 教えてくれない
煙草の味は変わらない キスの味は変わらない
この街で いつか また
世界の色が変わっても ひとの心変わっても
僕は待つ 君を ずっと 明るい夜に
泣いてる踊り子 どこへ行く 劇場のあかり 消えたまま
花束はもう 枯れたけど 瞳の光は そのまま
僕らがずっと 見ていたものは もう 夢みたい
抱きしめた恋も 風の中 答えは本当は わかっている
煙草の味はしなくなった キスの味もしなくなった
あの街も 行けなくなった
世界の地図が変わっても ひとの言葉変わっても
僕は待つ 誰も 来ない夜も
煙草の味は変わらない キスの味は変わらない
この街で いつか また
世界の色が変わっても ひとの心変わっても
僕は待つ 君を ずっと 明るい夜に
作詞・作曲:豊田道倫
やはり〈Stones Throw〉は鼻がきくというか……またもLAから新たな才能の登場だ。カルロス・ニーニョのアルバムやカマシ・ワシントンの大作『Heaven And Earth』への参加経験もあるピアニスト、叙情的なムードから実験的なセッションまで柔軟に対応するジャメル・ディーン。昨年〈Stones Throw〉からリリースされたアルバム『Black Space Tapes』が、最新EP「Oblivion」の楽曲などを加えた形で日本盤化される(しかも、ハイレゾ対応のMQA-CD)。家聴きにもぴったりな、深いサウンドです。
JAMAEL DEAN (ジャメル・ディーン)
Black Space Tapes / Oblivion
Thundercat や Kamasi Washington とも共演し、名門〈Stones Throw〉から弱冠20歳でデビューした天才ピアニスト、プロデューサー Jamael Dean。
デビュー作『Black Space Tapes』と最新EP「Oblivion」に加え、2019年作「Eledumare」の全10曲を、ハイレゾCD「MQA-CD」仕様にてリリース!!
この若きピアニストをいち早くバンドに引き入れたカマシ・ワシントン、才能に惚れ込み共同プロデューサーを務めたカルロス・ニーニョ、二人から興奮気味にその名前を聞いた。
彼が弾くピアノは、ジャズ・ヴォーカルにしっとりと寄り添ったかと思えば、スピリチュアルでポリリズミックなジャム・セッションにも、ヒップホップとネオソウルの狹間にもディープに浸透していく。LAのコミュニティで発見され、現在はNYのニュースクールでジャズを学ぶ俊英の、驚くべきデビュー作だ。
(原 雅明 rings プロデューサー)
Official Release HP:
https://www.ringstokyo.com/jamaeldean

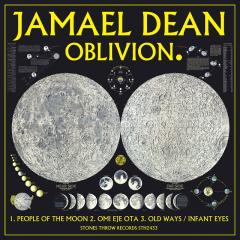
アーティスト : JAMAEL DEAN (ジャメル・ディーン)
タイトル : Black Space Tapes / Oblivion
発売日 : 2020/7/22
価格 : 2,800円+税
レーベル/品番 : rings / STONES THROW (RINC65)
フォーマット : MQACD (日本企画限定盤)
※MQA-CDとは?
通常のプレーヤーで再生できるCDでありながら、MQAフォーマット対応機器で再生することにより、元となっているマスター・クオリティのハイレゾ音源をお楽しみいただけるCDです。
Tracklist :
01. Akamara
02. Adawa
03. Kronos
04. Akamara Remix
05. Olokun
06. Emi
07. Eledumare
08. People of the Moon
09. Omi Eje Ota feat. Sharada Shashidhar
10. Old Ways / Infant Eyes feat. Sharada Shashidhar
いま岡田拓郎がすごい! え、以前からすごかったって? そうなんですけど……、まず驚いたのは最近彼がBandcampで発表しているアンビエント作品。今年の1月から4月まで、4か月連続で、『Passing』~『みずうみ』~『Between』、そして『Like A Water, Like A Song』と。この4作品すべてがわずか数秒で聴き入ってしまうほどの魔力を秘めたドローン/アンビエントなのだ。すべてが極めてシンプル(ミニマル=極少)で、なかには録音自体が5年以上前にものだったりする音源もあるのだが、STAY HOMEにくたびれた精神に心地良い芳香を吹き込んでくれる。なかでも増村和彦が参加している『Like A Water, Like A Song』は、あたかもクラスター&イーノの領域にまで届きそうな、いわば夜明け前のひんやりとした広がりを見せている。素晴らしいです。この4作品、フィジカルでも出して欲しいなぁ。
それから5月20日には、Okada Takuro + duenn によるアルバム『都市計画(Urban Planning)』がデジタル・リリースされている。こちらはジム・オルークのアンビエント作品『Sleep Like It's Winter』やAna Da Silva & Phewの何気に過激な『Island』を出している〈Newhere Music〉から。近々レヴューを掲載予定です。
そして岡田拓郎の待望のポップ・アルバム『Morning Sun』。歌モノとしては『ノスタルジア』以来の3年ぶりの2枚目。すでに配信リリースされているこのポップ・アルバムに彼の実験的なアンビエントが無関係であるはずがなく、自らのサウンドで押し広げた静寂のなかで彼のあらたなメランコリック・スタイルは築かれている。それは人影まばらないまの街にじつによく響いている。そう、まさに岡田にはじまり岡田に終わる──いくつもの岡田作品、ぜひ聴いて欲しい。
僕たちの野心は慎ましいと言えるものではなかった──なにしろそれは、パリを叩き起こすことなのだ。
ロラン・ガルニエ『エレクトロショック』
パリのレーベル〈F Communications〉、通称Fコミ。テクノDJのロラン・ガルニエ、レーベル・マネージャーのエリック・モーランの2人によって、1995年からはじまっている。つまり今年で25年。
ロラン・ガルニエは、たとえばデリック・メイやウェストバムのように、シーンのないところにシーンを切り拓いたフランスにおけるテクノの開拓者で、情熱がそのまま歩いているような人物である。なにしろこの男ときたら、1998年パリの路上のテクノ・パレードにおいてマイクを握り「テクノはバスティーユを奪った」と高々と宣言したほどなのだ。
そう、たしかに革命は果たされ、〈F Communications〉は多くの名盤をリリースしていった。彼の自伝『エレクトロショック』はフランスではベストセラーとなり、映画化されることになっている。テクノに関しても、パリで大がかりな展覧会が開催されるほど文化としての評価を固めている。
いま世界はコロナウイルスによって甚大なダメージを受け、変化を強いられている。「DJの仕事とは、場所がどこであろうと、ギャラがいくらであろうと、客を踊らせること」、『エレクトロショック』においてこう記したロラン・ガルニエをはじめ、世界中のDJたちはオーディエンスを前にブースに立つことはできないでいる。つい数か月前まであったクラブ・カルチャーがいつ戻ってくるのかいまの時点では見えていない。5月21日の時点でのフランスでの死者数は2万8千人、イギリスとイタリアに次いで多いことになる。
以下は、そんな渦中でのインタヴューである。

僕にとってもっとも重要なことは、人びとを踊らせるためにタンテーブルの後ろに立つことだ。それが僕の使命だ。
■私たちはいま、歴史のただならぬ雲行きの渦中にいるわけですが、この状況をどのように捉えていますか?
エリック:まずはその質問に対して、いま私はじっさいどのように答えられるのだろうか? つまりこの瞬間は、そしてその次の瞬間には、さらに多くの質問を引き起こしているのだから。より一般的に言えば、この地球上のすべての人間と他の生命体がどのようにして、私たちが変化とともに、たしかな進化とともに生きなければならないかということだろう。
もうひとつ言えるのは、西洋の文化は人生、変化、未知のサイクルとのつながりを失っていると私は見ている。18世紀の「啓蒙運動」以来、フランスではより(それまで恐れていた)科学を推奨し、むしろ精神や神聖さを排除しようとしてきた。「科学的」な時代においてはすべてを明晰に説明し、すべてを制御し、すべてを計画できるという盲信がある。しかし、高度に組織化された現代の社会は、その適応能力を失っている。生命はつねに適応する方法を知っていると私は深く感じているが、おそらく現在の社会のシステムではそれができないのだろう。未知なるものに対応する私たちの能力とは、つまりそれらを制御するのではないはずだ。これらの変化において踊ること。人生の一部であるものをコントロールできると盲信するのではなく、生、死、病気とともに生きること。そういうことについていまは考えるべきではないだろうか。
■なるほど。それは興味深い話です。ところで、パリはどんな感じなのでしょうか?
ロラン:状況は非常に複雑で、とても大きな不安を引き起こしている。政府からの支援もあったけれど、多くの人びとはロックダウン以来収入がないからね。特定の商業分野──たとえば旅行、ホテル、ケータリング、エンターテインメント、映画館、バー、ナイトライフ──は、この夏またはこの秋までに再開することができないかもしれない。すべてのフェスティヴァルとスポーツ・イベントはキャンセルされているし、さらに多くの失業者が出る可能性がある。経済的に見れば状況は壊滅的であり、ロックダウンの延長は僕たちの多くにとってさらに事態を複雑にするだろう。特定の都市での門限、ロックダウンを強制するための警察のパトロール、スーパーマーケットでの特定の食料品──卵、パスタ、小麦粉など──の欠如などがあって、まったく、僕たちは「戦争の時代」を生きているようでもあるんだ。
が、その一方フランスでは現在、並外れた連帯が生まれてもいるんだよ。介護者、ホームレス、高齢者、経済的に不安定な人々ための連帯──地域社会は、もっとも弱い立場の人たちを助けるために組織している。毎晩のことフランス全土が窓やバルコニーに集まり、仲間の市民の世話をするために毎日命を危険にさらしている医師や介護者、そして働き続けているすべての人びとを称賛しているんだ。
いまのフランスは、介護者、レジで働いている人たち、ごみ収集人、配達人、宅配便業者、ホームヘルパーが僕たちの国を回していることに気づいている。銀行員ではなくね。マクロン大統領も、それ以前にくらべてはるかに謙虚さを示しているようだけど、フランス人は本当にこの危機を契機に、より良い世界を構築すんだろうか? それはまだわからない。
■ロックダウンされた状況下で、人びとはどんな風に過ごしているんでしょうか?
ロラン:できる人は在宅勤務している。多くの人はかなりの時間を掛けて子供たちが何とかうまく授業を受けらるように手伝っている。人びとは本を読んだり、音楽を聴いたり、料理したり、スポーツをしたり、ドラマ・シリーズを次々と見たりしているね。
僕たちは皆、電話で多くの時間を過ごしたり、愛する人、友人、家族からのニュースを受け取っている。Skypeで友人と食前酒を飲んだりね! 片付けをしたり、ガーデニングをしたり、初めて絵を描くことをしたり……
僕は、家で息子とたくさん話しているよ。ロックダウンによって僕たちは考えたり、話し合ったり、たくさんのことを共有したり、たくさんの音楽を聴いたり、クラシック映画を見たり、ボードゲームをしたり……。実際、僕たちはこの休憩時間を利用して、家族で一緒に良い時間を過ごすようにしているんだ。
■そういうポジティヴな側面もあると。しかし、それにしてもFコミ25周年の年にこんなことが起きるなんて……。
エリック:現在(4月末)のロックダウンにより、フランスでは窒息について話す人もいるね。自由の欠如。音楽で逃れる人もいる。そして、それは私がフランスに住んでいる80年代の終わりに感じた感覚を直接思い出させるんだ。あの頃も音楽シーン、クラブ、レコード業界が本当に行き詰まっていた。イギリスまたはベルギーに行くとすぐに私は新しいエネルギーとすべてのダイナミックを見た。当時の私にはイギリスやオランダに住むという誘惑はあった。でも、私はフランスに残って物事を起こしたいと思った。それがロラン・ガルニエと私がパリで立ち上げたパーティ〈Wake Up〉なんだよ。そしてこれが、フランスのエレクトロニック・ミュージック・レーベルを設立する契機を与えてもくれたと。周りの人に「目を覚ませ」と伝えるというね。そのコンセプトはこうだ。つまり「別の人生は可能である!」と。「あなたには踊るし、あなたには夢を見る権利がある!」と。もしロックダウンの終わりに、物事を変えるのと同じエネルギーがあれば、ふたたびマジックが起きるかもしれない!
■Fコミは25年ですが、〈Fnac〉時代から数えるともっと年数はいくんじゃないですか? 「A Bout De Souffle EP」が1993年ですし。
エリック:今年はFコミの25年だけれど、それ以前の歴史もある。たしかに1991年11月にロラン・ガルニエの最初の12"のリリースが〈Fnac Music Dance Divisio〉であった。しかし、その〈Fnac Music Dance Division〉は1994年2月に終了した。
(※Fnacとは当時のフランスにおけるもっとも大きなレコード・チェーン店で、当初はその店の事業部がダンス・ミュージックの12インチをリリースした)
■これまでの25年のあいだの、とくに思い出深い出来事はなんでしょうか?
エリック:その質問に答えることができるとしたら、パリのクラブ〈La Locomotive〉で、月曜日の夜にクリシー大通りの交通を遮断して開催されたレーベルの1周年パーティになるんだろうな。でも、私個人にとっては、1995年のベオグラードでのFコミのパーティが一番の思い出だよ。

ちょうどのそのときは、ユーゴスラビアでの戦争が数か月前に終わってはいたものの、ユーゴスラビアはまだ封鎖されていた。で、1人のプロモーターがFコミのパーティをベオグラードで開催したいと、そのために我々を彼の地に連れていきたいと言ってきてね、彼はその数ヶ月前は戦地で戦っていた。
ロランはエレクトロニック・ミュージックが存在しなかったり、そのジャンルに対して決して好意的とは思えない国でプレイすることが大好きなDJなんだ。だから、私たちはこのクレイジーなプロジェクトに乗り出した。フランスからの直行便はないので、ブダペストに着陸し、ミニバスで移動したんだけど、軍隊がいる国境を越える瞬間が思い出深い。ロラン、Shazz、Scan X、私、プロモーター、ドライバーとライヴセット用の機材で満たされたミニバスをじっと見つめる機関銃と不吉な顔をした税関職員の顔を想像してみて欲しい。やっとの思いで通過して、ベオグラードに到着した。市長との式典に招待されて、 そのあとすぐに古いベオグラード空港でのパーティーがはじまった。戦後初のパーティでね、2000から3000人の興奮された人びとがやって来た。とても素敵な人たちだった。まさに私たちが好むクレイジーな冒険であり、素晴らしい思い出だ!

なにもライヴ体験に取って代わることでは決してない。音楽は「その場で」体験できること、それはDJの本質でもある。瞬間を理解し、捉え、人びとと交流すること。
■あなたのなかのFコミのベストな5枚は? 選ぶのはたいへんでしょうけど、ぜひ!
エリック:はい、レーベルの280枚のリファレンスから選択するのは非常に困難だ! これだけ異なる音楽ジャンルから選択するとなるとなおさらね!
この多様性のなかで、私は常にA Reminsicent Driveのアルバム『Mercy Street』に大きな愛情を持っている。Ludovic Navarre(St Germain / Deepside)の「French」、もちろんLaurent Garnierの「Crispy Bacon」、アルバム『Unreasonable behaviour』の「Communications from the lab」、Aqua Bassinoの「Milano Bossa」、またはAvrilの「Velvet Blues」、Del Dongoの「Samiscience」の完全にサイケデリックなハイパー・グルーヴ、いまでは廃盤になったけれど、1996に再発したDJ Kudoの「Tiny Loop」もある……あ、5タイトルを大幅に超えたね(笑)!

■コロナによって、音楽ファンの嗜好は変化すると思いますか?
ロラン:人びとの好みが変わるかどうかはわからないけど、ロンクダウンしている現在、人びとはより多くの音楽を聴いている可能性があるだろうね。多くの人びとが音楽を聴いている。音楽はより強く、よりそのひと個人の味方となって、内面や恩恵になるだろう。「私たちを慰めるためにそこにいる親友」のようにね。外界との接触の欠如により、おそらく現在の一部の人びとの人生のなかには音楽は別の意味を示しているかもしれないね。
僕の場合、それは指数関数的で、いまは以前よりも多くの音楽を聴いている。もちろん以前もたくさん聴いていたけれどね。しかし奇妙なことに、新しいもの、新譜を聴くのはとても難しい。目の前を見るのに苦労しているような感じだね。
ロックダウン以来、僕は自分のレコード・コレクションを再発見しているんだよ。完全に忘れていたアルバムを何時間も聴いている。自分はノスタルジックな人間ではないんだけれど、でもいまは、自分を形成してきた音楽を評価をする必要があるような気がする。これはおそらく、今後数週間で実際に何が起こるかについての情報がないことに関連しているのだろうけれど。
もうひとつ少し奇妙な発見があって、それは僕はいま(ハード)テクノを絶対に聴くことができないということ。僕にとって、この時期この手の音楽を聴くことにはまったく向いてない。テクノは僕にとっての心臓の一部のはずなのに、いまはまったく無理なんだよ!
■そうですよね。5年前の『La Home Box 』はテクノ、ハウスに向き合ったあなたの原点回帰とも言える内容でしたもんね。ところで、あれからアルバムをリリースしていませんよね。ご自身の制作はいまどうなっているんでしょうか?
ロラン:僕にとって、いま音楽を作ることは楽しみではあるけれど、絶対ではない。僕は自分をホンモノのミュージシャンだと思ったことはないからね。アーティストとして僕にとってもっとも重要なことは、人びとを踊らせるためにタンテーブルの後ろに立つことだ。それが僕の使命だ。
それに……音楽を作るには時間がかかる。緊急時に作曲するのも悪いことではないだろうけどね。ただ、僕のDJツアー+毎日新譜を聴く時間+ラジオ番組の制作+僕がギャビン・リヴォワールと4年間取り組んできたドキュメンタリー・プロジェクトの制作+家族生活とすべて……以上の他に皆さんがあまり知らない小さなプロジェクトを数えると、制作に割ける時間は決して多くないんだよ。
■なるほど。
ロラン:『La Home Box』以降でいえば、〈Kompakt〉のEP「Tribute EP」とRekidsのEP「Feelin' Good」があったね。Madbenと共作した「MG’s Groove」、〈Skryptom records〉のアニヴァーサリー・コンピ用に1曲提供したし、Roneもリミックスしたよ。ロック系ではフランスのバンドThe Liminanasをリミックスしたし、Steeple Removeのリミックスもやったよ。
それから、フランスのドラマ長編映画「Paris est a Nous」のサウンドトラックの50%を作曲したし、フランスのテレビ局のドキュメンタリー番組の音楽も担当したね。僕のドキュメンタリーでは、一部のKickstarter参加者のために超限定アナログ盤企画用に新しい12分のダンスフロア・トラックも作曲したな。そして、この夏はツアーができないので、フランスのロック・バンド、The Liminanasと一緒にアルバムを共作するプロジェクトが予定されてるよ。
■いろいろやることがあるわけですね?
ロラン:その他、僕が住んでいる村で毎年ポップ/ロック・フェスティヴァル(YEAHフェスティヴァル)を共催している。フェスティヴァルの傍で、僕たちはより多くの社交的な目的──刑務所、家、障害者の家、学校、大学など──のために、年間を通してたくさんのミニイベントを企画しているんだ。
執筆にも多くの時間を費やしているよ。僕は自伝『エレクトロショック』の映画化企画に10年以上取り組んできているし。こんな感じで、あまり自分の音楽に時間をかけることができないんだけど、ずっと忙しいんだよ。ちなみに来週引っ越しをするので、新しい場所、新しいスタジオに引っ越すことで、また音楽を作る気になるかもしれないね!
■いま言ったドキュメンタリー映画プロジェクト#LGOTR Laurent Garnier: off the recordについて教えてください?
ロラン:ギャビン・リヴォワール監督は4年以上も僕をフォローしている。ドキュメンタリーのアイデアは、テクノについて少し語りながら、僕のキャリアのある局面、瞬間をさかのぼってかなり親密な肖像画を作ること。実際、僕たちが興味深いと考える特定の主題、場所、瞬間に立ち止まりながら、僕が歩んで来た道をフォローしている。ドキュメンタリーの目的は、この音楽(テクノ)の全体像を伝えたいと思って教訓を示すことではない。もしそれをやるなら、25時間のドキュメンタリーを実行する必要があるだろうし。ここではむしろ、この音楽(テクノ)の歴史にとって僕にとって重要であった場所、人びと、または瞬間によって区切られた一種の個人的な歩行としての体験が強調されているんだ。だからすべては主観的だね。

長年ナイトライフの世界が維持してきた経済モデルを劇的に変化させなければならないだろうし、それが論理的に重要に思える。少しの謙虚さと親切さが僕たちに最大の益をもたらすんじゃないだろうか。
■いまこういう状況のなかフランスの音楽シーンで、なにか新しい取り組みなどありますか?
ロラン:現時点では、Covid-19の影響で、今後数か月の間に何が起こるかについて明確なヴィジョンを持つことは不可能だよ。すべてのクラブは閉鎖されていて、フェスティヴァルは禁止されている。僕たちは国境を越えて隣国に行くことさえできない、現状は非常に深刻だよ。ロックダウンの開始以来、誰にも何の収入が入っていない──0セントもね! この危機が長続きすると、僕たちの多くは間違えなく職を失う。DJ、クラブ、コンサートホール、フェスティヴァルなどなど。
リニューアルについて考える前に、このシーンが今後に単純に生き残ることができるかどうかについてまず知る必要があるんじゃないのかな。もし生き残れるのであれば、どのように、誰が? たしかなことのひとつは、フランスのテクノ・シーン──他のすべての国のシーンと同様──がこの前例のない危機から多大な影響を受けることだ。残念なことに多くの人が姿を消すことを僕たちは認識しなければならない。何が起こるかがわかるまで、しばらく待たなければならないだろうな。
僕たちみんながいままでの職業を守り続けるためには、長年ナイトライフの世界が維持してきた経済モデルを劇的に変化させなければならないだろうし、それが論理的に重要に思える。少しの謙虚さと親切さが僕たちに最大の益をもたらすんじゃないだろうか。
あるいは、この危機が音楽よりもお金が好きな連中、日和見主義者的DJ、無能なマネージャー、変態ツアーマネジャー、不正なプロモーターを排除することができたら、それはそれで僕たちにとってとても良いことだろうけれど。
■コロナ渦においてはストリーミングはひとつの手段だけど、ほかにどんなことが考えられると思いますか?
ロラン:人びとは現在、僕たちが以前知っていたのとは非常に異なる状況で音楽を聴いている。たぶんストリーミングでのDJセットで特定の経済が発展するだろうね。
でも音楽がそこにあっても、同じダンスフロアで一緒にいるとき、DJセットやコンサートを一緒に楽しむ体験に勝るものはないよ。いまはストリーミングも良いと思うよ。ストリーミングは人と人との間に何らかのつながりを保つから。しかし、ライヴ体験に取って代わることでは決してない。音楽は「その場で」体験できること、それはDJの本質でもある。瞬間を理解し、捉え、人びとと交流すること。
■とにかく、お互い無事生き延びて、いつかダンスフロアでお会いしましょうね。
ロラン:僕も心からそう願っている。僕たちみんなが愛する音楽は、それが同じダンスフロアで一緒に聴けて、体験できるときにだけ本当の価値があるんだ。そしてそれが日本のダンスフロアでもあるとすると……僕にとってそれは本当に世界でもっとも美しいものなんだよ。
■最後に、25周年ということで特別に企画していることがあれば教えて下さい。
エリック:最近になってFコミを発見し、そしてフランスの音楽の歴史において私たちがどのような役割を果たして来たかを理解したいと思ってる20〜25才くらいの若いオーディエンスから多くの要望があった。こうしたインターネットでの連絡があって、私はこの25年間を祝いたいと思ったんだよ。今日では、1991年以前にフランスのハウス/テクノまたはエレクトロニック・ミュージックのアーティストについて誰も知らなかったことを想像することは難しい。しかしじっさいは、フランスのインディペンド・レーベルがフランス国外でレコードを販売することすらなかった。Gypsy Kings(ジプシー・キングス)やMory Kante(モリー・カンテ)などのワールド・ミュージックのアーティストを除いて、フランスのアーティストはフランス国外でコンサートを行うことはほとんどなかった。
FnacとFコミでひとつのドアを開くことができたと思っている。だからこそ、すべてのレコードを復活させる必要があると思っているんだ。25年の祝いとして、元のDATマスターから完全にリマスターされた25枚の名盤、そしてあまり知られてない作品まで25枚の12"を選択した。アナログ盤とデジタルで5回に渡って5枚づつリリースするよ。今年の終わりには、アナログ盤2枚でMegasoft Officeの特別ヴァージョンもリリースする。また、デジタルで利用可能なタイトル数も増やそうと思う。デジタルで利用できなかったタイトル、宝物がまだたくさんあるからね。
──────
個人的なよき思い出としては、2006年に『エレクトロショック』の日本語版を出せたことと、ゴダールの映画『勝手にしやがれ』でジャン・ポール・ベルモンドが最後にぶっ倒れる道路を明け方よれよれに酔っぱらいながらいっしょに歩いたことだ。その『勝手にしやがれ』のフランス語の原題「A Bout De Souffle」が、彼の最初の出世作だった。1993年のEPでその1曲目は『勝手にしやがれ』の英語タイトル“Breathless”。彼がエリック・モランとはじめたパリで最初のアシッド・ハウス/テクノのパーティの名前となった“Wake Up”も、その「A Bout De Souffle EP」に収録されている。
このEPはFコミからではなく〈Fnac〉からのリリースで、当時は〈Warp〉にもライセンスされている、時代を切り拓いた決定的なシングル。その筋で重要なもう1枚は、同じく1993年にデリック・メイの〈Fragile〉と〈Fnac〉からリリースされたChoice(ロランとサンジェルマン=ルドヴィック・ナヴァールによる)の「Paris EP」で、収録された“アシッド・エッフェル”は永遠のクラシックである。

■Alex from Tokyo Pratによる〈F Communications〉25枚
(年代順))
St Germain-en-Laye - Mezzotinto EP
D.S. – Jack On The Groove
Shazz – A view of Manhattan EP
Nuages – Blanc EP
Juantrip – Switch out the sun
Nova Nova – Nova Nova EP
St Germain – Boulevard LP
Laurent Garnier – Club Traxx EP
Various – Musiques pour les plantes vertes CD
Nova Nova – Tones
Scan X – Earthquake
DJ K.U.D.O – Tiny Loop
Laurent Garnier – Crispy Bacon
Aqua Bassino – Deeper EP
Various- Megasoft Office 97 CD
A Reminiscent Drive – Mercy Street LP
Jii Hoo – Let me love you
Frederic Galliano – Espaces Baroques LP
Jori Hulkonen – You don’t belong here
Various – Live & Rare 3LP
Mr.Oizo – Flat Beat
Laurent Garnier – The Man with the Red Face
Frédéric Galliano with Hadja Kouyaté - Alla Cassi Magni
Avril – French Kiss
Laurent Garnier - Retrospective LP
【元F Communications日本大使としての思い出】
文:ALEX FROM TOKYO PRAT
1991年9月、大学のために東京から出身地のパリへ。ダンス・ミュージックに関しては東京での高校時代にからすでに心酔、フランスに来てからパリのアンダーグランド音楽とクラブ・シーンを発見しました。
まずは毎週木曜日、伝説のRex ClubでLaurent GarnierとDj DeepがレジデントDJを務めていたフランス初のアンダーグランド・テクノ・ハウス・パーティ〈Wake Up〉に通う。そして、Gregory(グレゴリ−)とDj Deepと親しくなって、Dj Deep通して〈Fnac Music Dance Division〉のレーベル・マネージャー、Eric MorandとFnacのアーティストSt Germain(サンジェルマン)やShazz(シャズ)等と知り合いました。
1993年にDj DeepとDJ Gregoryと共にDJユニット「A Deep Groove」を結成します。伝説的なRadio FG 98.2fmのランチタイムに放送された「リアル・アンダグランド・ダンス・ミュージック」ラジオ番組が、St. GermainやShazzなどの初期シーンのディープ・ハウス・アーティストに初めてスポットライトを当てます。
1995年、東京に帰還しました。テクノとエレクトロニック・ミュージックが日本で爆発してるなか、来日するフランスやヨーロッパのレーベル、DJやアーティストたちの橋渡し役として活動。そのなかで、パリで仲良くなったLaurent GarnierとEric Morandのレーベル〈F Communications〉の日本大使役を1996年から2002年まで務めることになりました。
1995年の秋、King Recordとのレーベル契約に合わせて新宿Liquid Roomで〈F Communications〉のパーティが開催されました。Fumiya TanakaがオープニングDJでしたが、そのときのLaurent Garnier, Scan X, Lady Bらが出演したパーティはいまでも鳥肌が立つほど感動的でした。
1996年には西麻布のクラブ〈Yellow〉でレギュラー・パーティをはじめました。日本のエレクトロニック・ミュージックDJの立役者のひとり、DJ Kudoが〈F Communications〉から12”「Tiny Loop」をリリースします。日仏関係がさらに結ばれるようで、嬉しかった!
1996年にはP-VineからSt Germainのデビュー傑作アルバム『Boulevard(ブルヴァード)』が日本盤でリリースされます。普段限られた状況だけでしかDJプレイしないSt.Germain本名Ludovic Navarre(ルドヴィック・ナヴァール)がわざわざ来日し、Yellowで2公演を披露しました。そして、美しいディープ・ハウスをプロデュースするスコットランドのAqua Bassinoとの出会いと東京と大阪での日本ツアーがありました。Scan Xが1997年に「攻殻機動隊-Ghost In The Shell」のゲーム・サウンドトラックに参加したことも忘れられません。
1998年からは、Toys Factoryとのレーベル契約から数々の素晴らしい日本特別企画アーティスト・アルバムを発表&ツアー。2000年のLaurent Garnierのアルバム『Unreasonable Behavior』のリリースに合わせて『ele-king』ではパリの現地取材をしましたが、これはとても思い出深いです。
1998年から2002年頃までに掛けては、Frederic Galliano(フレデリック・ガリアーノ)のジャズ&アフリカ音楽の企画が日本でも注目されました。Fredericが〈F Communications〉を通して担当していた、マリ音楽の再発/リミックス特別企画レーベル〈Frikyiwa〉では、井上薫ことChari Chariが参加しましたが、自分もTokyo 246 Ave. Project名義でAbdoulaye Diabateのリミックスを手掛けました。青山CAYでFredericがフル・バンドと女性ヴォーカリストAfrican Divas(アフリカン・ディヴァーズ)と来日ライヴを披露したときは本当に感動しました!
それから、70年代から活動している作詞/作曲家と写真家であるJay Alanskiのエレクトロニカ/アンビエント・プロジェクト、A Reminiscent Drive(ア・レミ二セント・ドライヴ)の美しい桜の写真のアルバム『Mercy Street』も日本でとても人気がありましたよね。また、北海道、札幌のTha Blue HerbがライヴでNova Novaのピアノ傑作“Tones(トンズ)”をバックトラックに良く使っていたことを初めて聞いた時はビックリしました。
最後に、2006年にはロラン・ガルニエの自伝『エレクトロショック』を日本語に訳して、野田努さん監修のもと河出書房から出版しました。自分が学生の頃に通っていた東京の日仏学院でロラン、野田さんと三田さんとトークショーをやって、その後日仏学院をクラブ・パーティにしたことはとくに自分の人生のなかでは重要な素晴らしい出来事でした。その後、ロランとは一緒に、日本の数々の素晴らしいパーティ&ツアーでプレイしてます。〈F Communications Japan〉では日本のミュージック・ラヴァーと感動的で楽しい思い出深い時間を共有することができた。実に素晴らしい体験でした。
いままでサポートをしてくれた日本の音楽&クラブ業界のパートナーの皆さんや日本のファンには本当に感謝してます!
この25周年を祝って、日本の新世代にもここで〈F Communications〉レーベルの魅力を知ってもらいたいです。
Tres bon 25eme anniversaire F Communications!

「『What Kinda Music』はサウス・ロンドン・ジャズ・シーンの集大成なのか?」
昨今の音楽シーンを語る上でいまや欠かせない存在となったトム・ミッシュとユセフ・デイズ。今年の2月頃にふたりのコラボ・リリースのアナウンスがされたときはもちろん衝撃的だったが、トムが18年にリリースしたソロ・アルバム『Geography』のツアーの合間にインスタグラムでユセフとのスタジオ・セッションの動画をアップしたときに「いよいよこのときが来るのか!?」と興奮したのを鮮明に覚えている。それからあっという間に2年の歳月が経ち、ジャズ名門レーベルの〈Blue Note〉からこうして陽の目を浴びることになった。
いまさらここの読者にふたりの経歴について語るのも野暮かもしれないので、クラブ畑で育った僕がふたりを知ったキッカケを少し綴りたい。どちらも4~5年前のこと、ユセフ・デイズに触れたのはカマール・ウィリアムスとのコラボ・ユニット、ユセフ・カマールの『Black Focus』が最初。カマール・ウィリアムスの別名義、ヘンリー・ウーの存在がすでにハウス界隈で騒がれていたし、このアルバムが所謂「UKジャズ・シーン」というコトバに火をつけたキッカケになっているのは間違いない。17年に Billboard Live Tokyo で来日した際はカマール・ウィリアムスがまさかのドタキャンで驚かせてくれたが、残念半分で観たライヴで「あのヤバイドラマーは誰なんだ!?」とそれを超える驚きを見せてくれたのはいい思い出だ。
対するトム・ミッシュは16年にリリースしたシングル「Watch Me Dance」がハウス・プロデューサーのクラカザットにリミックスされた辺りから。翌年に発表した「South Of The River」はオランダのディープ・ハウス・デュオ、デトロイト・スウィンドルにもリミックスされるなど、ハウス/ディスコ界隈でその名を目にしていた記憶がある。その後リリースした『Geography』からは言うまでもないだろう。サマーソニックやフジロックにもその名を連ねるなど、その勢いは止まることを知らない。
つまり多少距離はあったにせよ、どちらも「界隈」にいたわけで、今回のコラボはお互いの活動の延長線上、起こるべくして起こった化学反応なのは間違いない。どちらもサウス・ロンドンを拠点に活動し、世代も近く、アレサ・フランクリン、マーヴィン・ゲイ、ニーナ・シモンらアメリカのジャズやソウルの教科書的アーティストもしっかりと通過し、ジャンルに縛られることなく自由に横断する「フュージョン感」はアルバムの中にも随所に散りばめられている。
What Kinda Music - Documentary
『Geography』のファンであればアルバムの冒頭から随分とダークな内容に仕上がっていると感じるだろう。この部分は実験的なサウンドを好むユセフ・デイズのカラーが前に出ている。アルバム・ドキュメンタリーで「大半はジャムをしながら作っていった」と語っているように、日頃からのライヴで培ったユセフのスキル溢れるドラムにトムがギターで重ねてセッションしていくというのが主な制作の流れだったんだろう。アルバムすべてにおいて、まさにドラムがメイン・パートになっており、彼の十八番でもある高速ドラミングから4曲目の “Tidal Wave” のようにスローだがグルーヴの感じるトラックまで様々だ。
多くの曲のクレジットに「Produced by Tom Misch」と書かれているのにも注目して欲しい。ベッドルーム・スタジオでのビートメイク上がりのトム・ミッシュが自身のアルバムを通して、レコーディングのスキルをより充実させより理論的にサウンドをプロデュースしていく部分も非常に興味深い。「ジャムで作った」と簡単に言いながらも、音楽に対する間違いのない技術と豊富な経験値や知識がなければこのレヴェルの高い作品はできるはずがない。
ドキュメンタリーの後半では「15年前くらいにユセフが学校のイベントでドラムを叩いてるのを観たことがある」、「お互いの親父がアルバムを通していまでは自分たちより仲良くなってる」と語るように、親の世代でも距離が近く、世代や人種、ジャンルを超えてコラボレーションが盛んなロンドンのミュージック・シーンならではのコンセプトがこのアルバムのなかに強烈に落とし込まれている。何度もアルバムを聴き返し、彼らの言葉にも耳を傾けると、ある種2015年ごろから火がついた「UKジャズ・シーン」と呼ばれる一種のムーヴメントの集大成的アルバムの位置付けのような気もしてくる。トム・ミッシュしか知らなかった人はユセフ・デイズや彼の関連作品を、逆もまた然り。このアルバムをキッカケにまた色々な作品を掘り下げていけばジャンルを超えた新たな音楽体験が待っているのかもしれない。
パレットの片方には真っ黒な絵の具、もう片方には真っ白な絵の具をたっぷり出して、それらをゆっくりと混ぜていく。できるだけゆっくり、ゆっくり、もう少しゆっくりと……。そうやって出来上がった「グレー」は単色ではなく、無限のグラデーションを生み出している。
モーゼス・サムニーのセカンド・アルバム『GRÆ』は黒と白が混ざった色としての「グレー」を巡るコンセプト作だが、それはちょうど彼自身の存在への問いでもある。ガーナ系アメリカ人としてのアイデンティティを持ち、ニーナ・シモンとよく比較される「フェミニンな」ハイ・トーン・ヴォイスで、ソウルとインディ・ロックとチェンバー・ポップが入り混じった音楽のなか、ロマンスとエロスの境界が溶けた地点の情動を歌う……。それは彼のなかにある多層性や複雑さをさらに撹拌する作業であり、ブラックの男性であることから世間に貼られるレッテルを丁寧に鮮やかに剥がすことでもある。個々のアイデンティティが強く問われたことで2010年代なかばに生み出された傑作がケンドリック・ラマーの『To Pimp A Butterfly』のような「黒い」アルバムだったとすれば、黒人男性のアイデンティティの揺らぎを音楽に白い絵の具を混ぜることで繊細に封じこめたフランク・オーシャンの『Blonde』を通過し、2017年にデビュー・アルバム『Aromanticism』をリリースしたモーゼス・サムニーはさらにその先を模索しようとしている。
ごく初期にグリズリー・ベアのクリス・テイラーのレーベル〈Terrible Records〉から7インチを出していたり、スフィアン・スティーヴンスと共演したりしていることが象徴的だが、インディ・フォーク/ロック界隈との繋がり、なかでもオーケストラル・ポップや室内楽の要素がその音楽に入っていることがモーゼス・サムニーの個性であり強みだ。それらは一般的に「白い」とされているものなのかもしれないが、あらかじめ彼のソウル・ミュージックと溶け合っていた。そもそもがとてもマージナルな存在で、たとえば音楽性は異なれど、ンナムディと並べてみると現代的なムードが感じられるのではないだろうか。
『GRÆ』はそんなモーゼス・サムニーの抽象的な折衷性の奥ゆきを深めたアルバムで、前作からもっとも洗練されたのが「ゆっくり」という感覚、そのスローなタイム感であるように思う。ダブル・アルバムとなった本作は、室内楽フォークやソウル/ゴスペルの要素が基盤になっているのはこれまでと同様だが、ジャズ、エレクトロニカ・ポップ、オーケストラル・ポップ、さらにはノイズ・ロックを取りこみ、それらを余裕のある間合いで扱うことによってスムースに聴かせる。アルバムのオープニングにおいて、荘厳なストリングスとスポークン・ワードとスペーシーなシンセ・サウンドが重なる “Insula” から “Cut Me” へとイントロダクションがまず見事で、けっして性急なテンポにならない “Cut Me” はフレーズの細やかなクレッシェンドやコーラスとアンサンブルの重なりの妙味で魅せるチェンバー・ソウルである。ジャンルを折衷するために異なる要素を無理にぶつけず、丁寧に並べてしなやかな歌声で繋いでいく。メロウかつ甘美にドリーミーな “In Bloom” を挟んでシングル “Virile” に至るころには、インディ・シーンの要人ロブ・ムースが手がけたストリングスとパワフルなバンド・アンサンブルによってダイナミックなサウンドの広がりを聴かせるが、あくまで余裕のあるスピード感でじっくりとエモーションを高めている。2枚組といえど通して1時間少しとじつはそんなに長いアルバムではないのだが、1枚聴き通すころには壮大な音楽トリップをしたような充実感を味わえるのは、この、ゆったりとした展開によるところが大きい。
その “Virile” では「男らしさを誇張しろ/お前は間違った考えを持っている、息子よ」とある種反語的に繰り返されるが、典型的な男性性の抑圧のモチーフがアルバムには散見できる。黒人男性にかかる男らしさのプレッシャーはアメリカにおいてとりわけ強く、それは白人目線からの性的な期待を内面化したものであることが昨今指摘されているが、モーゼズ・サムニーは黒人男性である自分の男性性と女性性の「グレー」なゾーンを探求しているようだ。アメリカで生まれた彼は幼少期に一度ガーナに家族とともに移住し、しかしそこでのコミュニティに馴染めなかった経験があるというが、したがって彼のなかにあるアンビヴァレントな感覚はルーツと現在という点にも及んでいるだろう。『GRÆ』にはダニエル・ロパティン(ほんとにどこでも名前を発見できますね)をはじめジェイムス・ブレイク、サンダーキャット、ジル・スコット、FKJ などなど30名以上のゲストが参加しており、それが本作の音楽性の拡張に貢献していることは間違いないのだが、それでも中心として表現したかったのはモーゼス・サムニーそのひとのなかの複雑さだったように思う。(サムニーも参加した)レーベル・メイトのボン・イヴェールによる『i, i』がやったような異なるアイデンティティ(人間)の共存と融和ではなく、個人のなかに潜っていくことでひとりの人間のなかに宿っているはずの多様性を発見するというあり方だ。だから、とろけるようにジャジーなソウル・ナンバー “Colouour” も、それこそグリズリー・ベア的にフォークとクラシックが熱狂的に交わる “Neither/Nor” も、淡いコーラスがひたすら心地いい室内楽フォーク “Polly” も……すべて、サムニーのなかにあるグレーのグラデーションなのである。
2枚目にあたる “Two Dogs” 以降はとりわけフルートやハープの調べによって天上的な響きを増していき、その陶酔感を高めている。そこではサムニーの存在を通してルーツと現在、男性性と女性性、アヴァンとポップ、肉体と精神、黒と白……の境目がなくなっていく。そしてその「なくなっていく」ことが聴く者の快楽になるのである。「二面性」などというものはないと言わんばかりに。弾き語りフォークの小品 “Keeps Me Alive” やジェイムス・ブレイク参加の “Lucky Me” のミニマルなアンサンブルを通過したあとにやってくる、“Bless Me” のクライマックスはただただ圧倒的だ。
ブレス・ミー、わたしを祝福せよ。『GRÆ』のまばゆい美しさと甘美な陶酔は、単純に切り分けることのできない人間の内面の複雑さや、そのグラデーションのなかを変容していくことを祝福していることによって生まれている。
