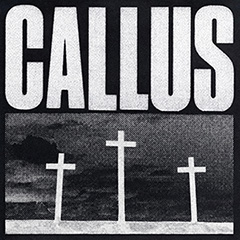日本のインディ・シーンが好きなアナタ、こんな魅力的なフェスを見逃してませんか?
群馬県は足利を拠点に活動するバンド、スエットの岡田圭史が主宰するマチカドフェス2016が、小平の里キャンプ場(群馬県)にて9月10日、11日の2日間にわたって開催される。
出演予定のアーティストは、地元出身のCAR10、スエットをはじめ、ネバー・ヤング・ビーチ、DYGL、ジャッパーズ、ノット・ウォンク、ホームカミングス、テンパレイ、柴田聡子などなどインディ・シーンの名だたる若手たちが揃い踏みだ。こんなメンツを2日間に渡って、しかも野外で見れるイベントって意外とないんじゃなかろうか。
マチカドフェスは、群馬県桐生の有志たちが作りあげるDIYなフェス。ロケーションも最高だし、東京からも案外気軽に行けちゃうし、リラックスした雰囲気のなか聴ける音楽も最高となれば、群馬まで繰り出すしかないでしょう!

日程:2016年9月10日、11日
会場:小平の里キャンプ場 群馬県みどり市大間々町小平甲445
OPEN/START:10:45/11:30
END:19:40
出演 :
・1日目
CAR10
Homecomings
Not Wonk
Special Favorite Music
Tempalay
TENDOUJI
フジロッ久(仮)
上州八木節保存会
DJ星原喜一郎
DJ遠藤孝行
DJ田中亮太
・2日目
DYGL
JAPPERS
never young beach
Suueat.
踊ってばかりの国
柴田聡子
すばらしか
上州八木節保存会
DJ星原喜一郎
DJ遠藤孝行
DJ田中亮太
チケット料金:
一日 ¥3800
通し ¥7000
e+ https://sort.eplus.jp/sys/T1U14P0010843P006001P002195534P0030001
・高校生以下
通し ¥500
メール予約のみ machifes.kiryu@gmail.com
・桐生店頭割引(枚数限定)
一日 ¥3000
・八木節祭割引(枚数限定)
一日 ¥3000(缶バッジ付き)
HP:https://machikadofes.com/
Twitter:https://twitter.com/machifes_kiryu
Facebook:https://www.facebook.com/MACHIKADOFES/