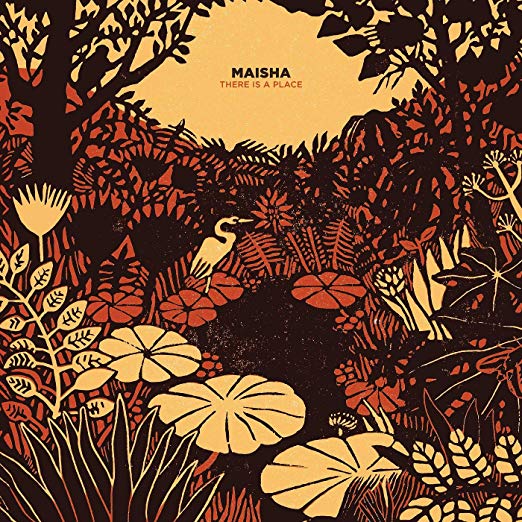ロリ・スカッコの音楽を聴くと、いつも「波紋」のようなサウンドだと感じる。水滴と波紋。その水面での折り重なり。いわば「丸と円」のレイヤーのような音楽。もしくは「輪」のような音のアンサンブル。それはカタチや現象の問題だけではなくて、どこか人と人との関係性、つまり「縁」を表しているのではないか。
じっさい2004年にスコット・ヘレン(プレフューズ73)が運営し、あのサヴァス・アンド・サヴァラスのアルバムなどもリリースしていたレーベル〈Eastern Developments〉から発表された彼女のソロ・ファースト・アルバムも『Circles』というアルバム名だった。このアルバムを制作する前、ロリ・スカッコはバンド、シーリー(Seely)の解散を経験していたわけだし、それなりに人間関係の大きな変化の只中にいたのだろう。
ちなみにシーリーは、1996年にトータスのジョン・マッケンタイア・プロデュースのファースト・アルバム『Julie Only』を〈Too Pure〉からリリースしたバンドである。シューゲイザーからステレオラブまでのエッセンスを持ちながらミニマル/ドリーミーなポップを展開し、熱心なリスナーも多かったと記憶している。ロリはこのシーリーのピアニスト/ギタリストだった。シーリーは2000年にアルバム『Winter Birds』をスコット・ヘレンとの共同プロデュースでリリースし、そして解散してしまったが、その解散から4年の月日をかけて彼女はソロ・アルバム『Circles』をリリースしたわけだ。
そしてその音楽性はバンド時代から大きく変わった。ギターやピアノ、弦楽器などにエレクトロニクスが控えめにレイヤーされた「アコースティック・エレクトロニカ」とでも形容したい作品に仕上がっていたのだ。日曜の朝とか晴れた日の夕暮れ時を思わせる穏やかで美しいクラシカルなアルバムである。永遠に耳を澄ましていたいような心地良さがあった。もちろん聴き込んでいくと、音と音の重なりは和声感も含めて、実に繊細に織り上げられていることに気が付く。まさに「サークル」の名に相応しい作品である。このアルバムは熱心な聴き手に深く愛され、リリースから10年後に日本盤CDが〈PLANCHA〉からリイシューされ、新しいリスナーからも歓迎された。
『Circles』リリース以降のロリ・スカッコは、ダンス、映画、ビデオ・アートの音楽制作を行いつつ、サヴァス・アンド・サヴァラスのメンバーのスペインのアーティスト Eva Puyuelo Muns とのストームス(Storms)としても活動し、2010年にはアルバム『Lay Your Sea Coat Aside』をリリースした。そして2014年にはデジタル・リリースのソロ・シングル「Colores (Para Lole Pt.2)」を発表。加えて先にも書いたように〈PLANCHA〉から『Circles』がリイシューされた(ボーナス・トラックを追加収録)。
新作『Desire Loop』は、14年ぶりのセカンド・ソロ・アルバムである。リリースは、ニューヨーク・ブルックリンを拠点とするアンビエント・レーベル〈Mysteries Of The Deep〉から。〈Mysteries Of The Deep〉は、ニューヨーク・ブルックリンのエクスペリメンタル・バンド、バーズ・オブ・プリティのメンバー、グラント・アーロンによって運営されており、Certain Creatures、William Selman などの作品をリリースしている。
本作も生楽器主体の『Circles』から一転し、シンセサイザーをメインに据えたアンビエント/トライバルな電子音楽に仕上がっていた。この変化には一聴して驚いてしまったが、しかし何度も聴き込んでいくと、どんどん耳に馴染んでくる。『Circles』と同じように波紋のような音がレイヤーされていく構造になっているからか、聴くほどに耳と身体に浸透するような音楽なのだ。音と音が泡のように生成しては変化し、持続やリズムをカタチづくっていく。あの見事なコンポジションは、形式を変えても健在であった。いや、深化というべきかもしれない。
シンセ中心のサウンドのムードは、どこか現行のアンビエントやニューエイジ・シーンともリンクできる音楽性だが、浮遊感に満ちた和声感覚と音のレイヤー感覚などから、やはりロリ・スカッコという「作曲家」の個性が強く出ている電子音楽にも思えた。
とはいえ、あざとい作為は感じられない。ごく自然にミニマルな音とミニマルな音が重なり、そこにコードやリズムが必然性を持って生まれていた。1曲め“Coloring Book”には、本作の特徴が良く出ている。やや硬めの電子音の持続から音が分岐するようにいくつかのループが生まれ、やがて糸がほぐれるように変化したかと思えば、それらはループを形成し、トライバルなビートが鳴り始めもする。持続と反復。その中断と非連続性の美しさ。まるで確かに水の波紋のように、一種の自然現象のように、電子音たちが踊っている。続く2曲め“Strange Cities”はニューエイジなムードのシーケンスから幕を開け、それらが電子音の層へと溶けるように変化を遂げていく。この最初の2曲に象徴的なのだが、ロリ・スカッコの作曲は音の反復を持続の中に「溶かす」。電子音という生成変化が可能な音響だからこそ実現する反復と非反復の融解とでもいうべきか。
アルバム中、重要な曲は5曲め“Back To Electric”ではないか。トライバルなリズムが鳴らされていくのだが、もう1階層、別のリズム/ビートがレイヤーされており、そこに規則的な電子音と民族音楽がグリッチしたような旋律が鳴る。聴いていくと時空間が「ゆがんで」いくようなサイケデリック感覚を味わうことができた。続く6曲め“Tiger Song”は細やかなノイズと、どこか日本的な旋律に反復的なビートが重なる印象的な曲だ。7曲め“Red Then Blue”もノイズのレイヤーからミニマルな反復が生成し、ゆるやかに聴き手の知覚を変化させるような見事なトラックである。アルバム・ラストの8曲め“Other Flowers”では、それまでサイケデリックに歪む時空間が、次第に知覚の中で整えられていく。まさに「花」のような端正な電子音楽である。
こうして14年ぶりとなるロリ・スカッコの新作アルバムを聴いてみると、やはりこの歳月は必要だったのだと痛感する。反復と非反復の往復。知覚の遠近法を変えてしまう音のゆがみ。それらを曲として成立させること。作曲と即興のあいだにある音と音の自然な生成の追求。そのための時間。何より音楽それじたいが聴き手に対しても長い時間をかけて浸透するような時を内包しているのだ。それは自分の音楽を作り続けた人だからこそ獲得することができる「時の流れ」の結晶ではないか。そんな感覚を『Desire Loop』の隅々から聴き取ることができた。
かつてはアトランタで建築を学ぶ学生であった彼女だが現在はニューヨーク在住という。いまのアメリカの政治や社会状況には憤りを感じているというが、音楽にそのような感情は直接には反映されていないように思えた。しかし、彼女の音楽に耳を澄ましていると見えてくるのは、脆さや弱さ、そして美や強さに向かい合いつつ、極めて誠実に音楽=世界と向かい合っている音楽家/作曲家の姿だ。この酷い世界を音楽によって肯定すること。音と人の関係性を、その弱さを脆さと共に感じ取ること。そんな意志が音の粒子に舞っているのだ。
本作は繰り返し聴取することで、どんどんその魅力が増してくるようなアルバムだ。ぜひとも「電子音楽家としてのロリ・スカッコ」が鳴らす音の波に耽溺してほしい。世界の事象が溶け合っていくような見事な作品である。