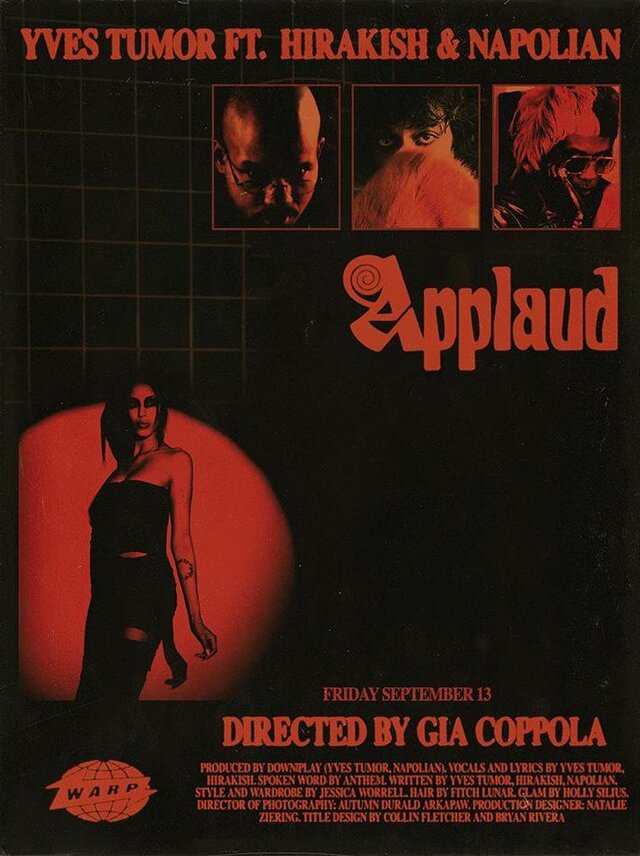Noah 『Thirty』は、いくつもの色彩が反射するダイアモンドのようなエレクトロニカ・ポップであり、ひとりの音楽の感性の中に瞬いた「光と旅と都市を巡る音楽」でもある。
Noah は日本の電子音楽家だ。2009年より音楽活動を本格化させ、ピアノやクラシック音楽をベースにしつつ、繊細で緻密なエレクトロニカ/ポップな作品をリリースしてきた才人である。代表作をひとつ挙げるとするならば東京の音響レーベルの老舗〈Flau〉から2015年にリリースされ、英国『ガーディアン』誌で絶賛されたという『Sivutie』だろうか。
「白昼夢」の世界を描いたという『Sivutie』から4年を経て発表された作品が、新作『Thirty』である。本作品において Noah は「自分が自分でないような」感覚をカラフルな現実として表現していく。「東京」という都市が現実と虚構の狭間で色彩豊かに生成するような感覚とでもいうべきか。じじつこの4年のあいだに Noah は故郷の北海道を離れて東京を活動拠点とするようになったという。『Thirty』には未知の都市に対する繊細な感性が横溢している。
そう、エレクトロニカにおいて私たちはいつもひとりの音楽家の感性と感覚と認識と感情を知ることになる。エレクトロニカはとてもパーソナルな音楽なのだ。Noah の音楽も都市が放つ粒子の只中で、自身の「声」を生成する。「声」とはいわゆる人の声だけではない。音楽の、音響の、和声、旋律の中に息づいている音楽家の「声」だ。
私たちはすぐれた音楽を聴くと、たとえインストの楽曲であっても作曲した音楽家の「声」を感じることがある。例えば坂本龍一のピアノ曲。彼のハーモニーは、その音楽の「声」だ。近年ではフローティング・ポインツのトラックに彼の「声」を聴き取ることができた。Noah の楽曲も同様である。彼女の音楽には、彼女にしかない響きがあった。たとえばそのハーモニーに、そのメロディに、そのノイズに。
本作『Thirty』は Noah の新しい代表作に思えた。『Thirty』は前作『Sivutie』以上にポップなトラックを収録している。電子音響のカーテンのように幕開けを告げる“intro”、ダンサブルなエレクトロニカ・ディスコ“像自己”、ピアノと電子音とヴォイスが交錯するオリエンタルな“夢幻泡影”、エキゾチック・エレクトロニカ・ミニマル・ミュージックとでも形容したい“18カラット”、80年代香港ポップをエレクトロニカ経由で粒子化したような“メルティン・ブルー”、硬質なムードに満ちたラグジュアリーでインダストリアルな“愛天使占”、シンプルなメロディとミニマルな電子の交錯が心地よい“シンキロウ”、エレピの響きとハイハットの刻みの中心に空間的な静寂のなか中華的なメロディと微かな電子音が交錯する“風在吹”、アップテンポの4つ打ちビートとディスコ的なベースラインと麗しい音響処理による“像自己 alternative ver.”。
全曲 Noah という音楽家の作曲家としての力量とサウンドメイカーとしての繊細さと緻密さが交錯しており、現時点での彼女の最高傑作といっても過言ではないだろう。2018年にリリースされた Teams と Noah と Repeat Pattern による『KWAIDAN』での制作が、『Thirty』にも大きな影響を与えているのでないかと想像してしまった。
『Thirty』を聴くこと。それは見知らぬ都市を訪れたときに感じる未知の「光」を感じる経験に似ている。都市の放つ光に目が眩む感覚。この作品には、どこかそのような旅行者の意識を感じた。その場のすべてを吸収するように移動を重ね、意識と感覚を飛躍させる未知なる都市の旅人たちと同じように、本作の楽曲たちは、どこか「次」へと向かおうとする意志を放っていたのである。
ここではないどこかへ。仮想と現実の彼方へ。エレクトロニカ、ポップ、オリエンタル、クラシック、ヴェイパーウェイヴ、アジアン・ポップなど軽やかにステップしつつ、まるでダイアモンドのように華麗な光を放つ本作を聴きながら、私はすでに Noah の次回作がいまから楽しみになっている。

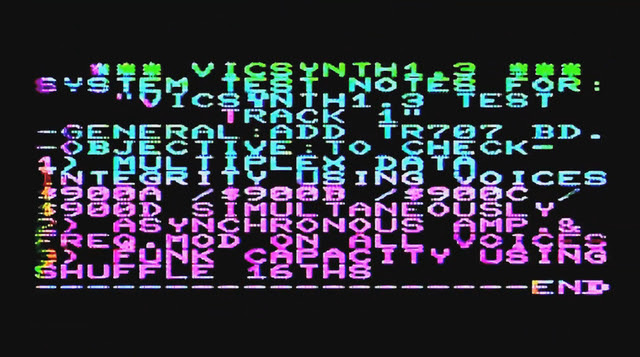
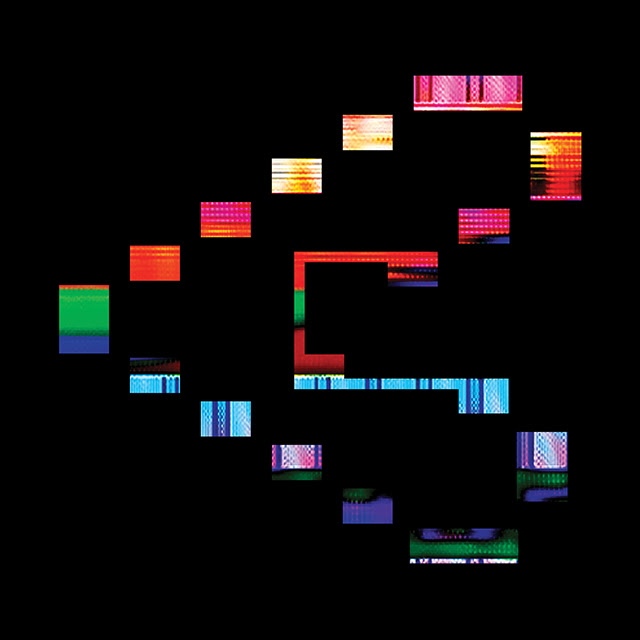


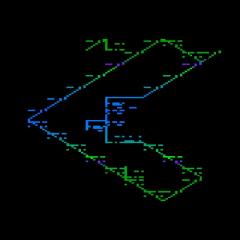
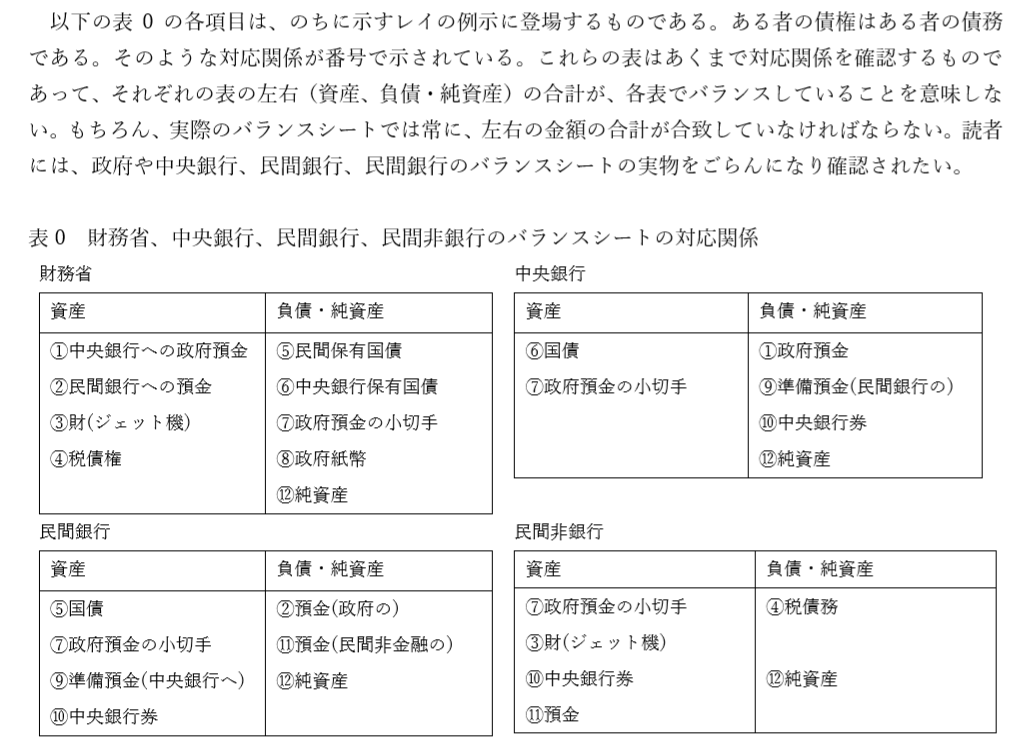
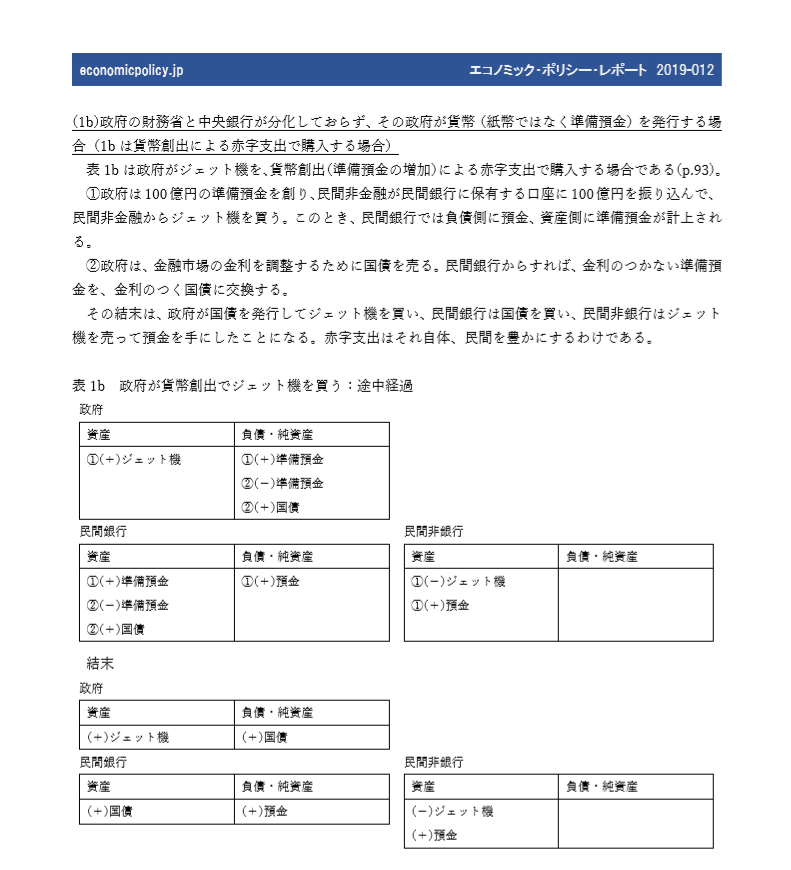 出典:
出典: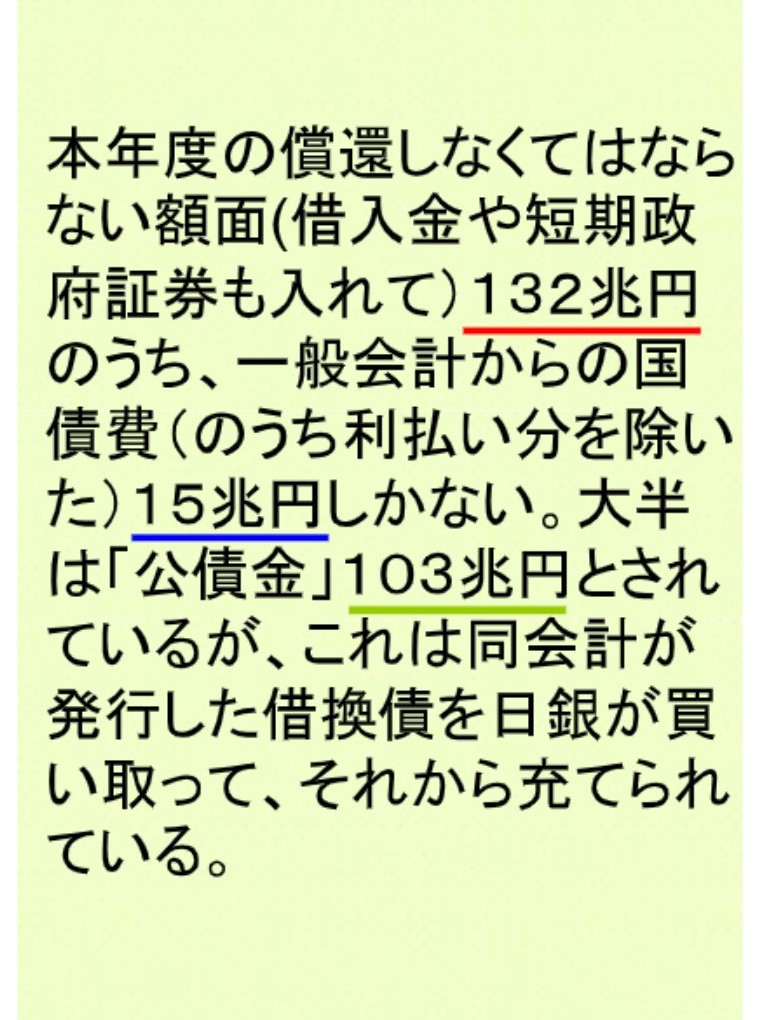
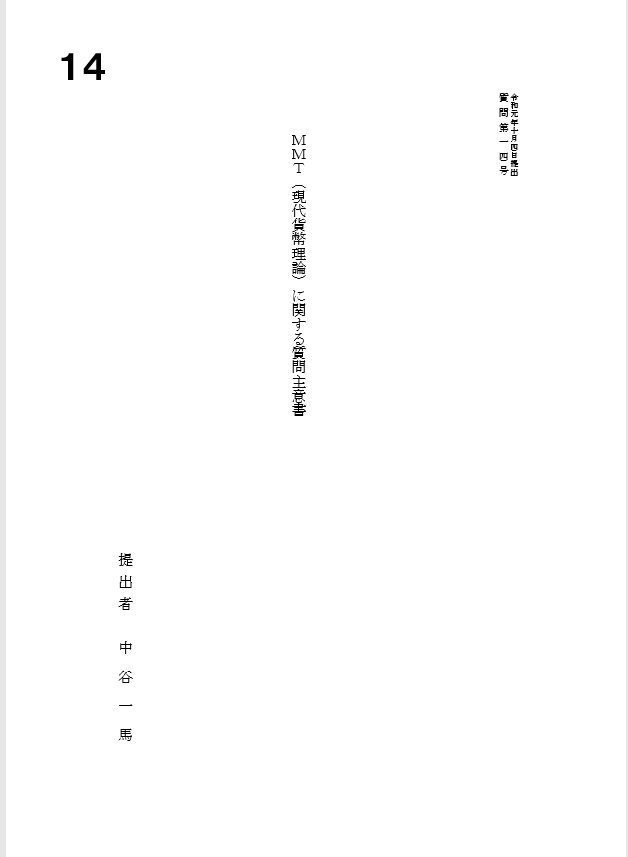
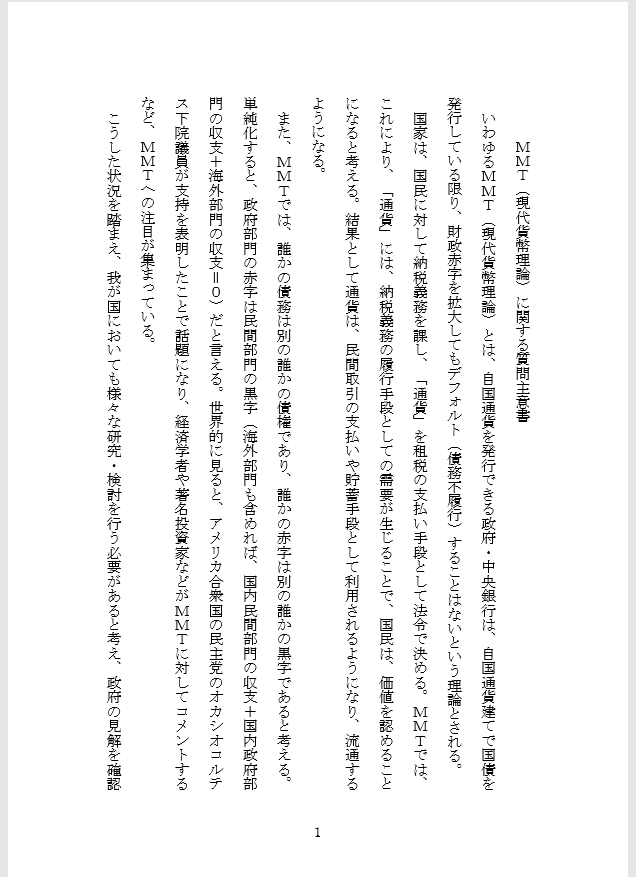 出典:
出典: