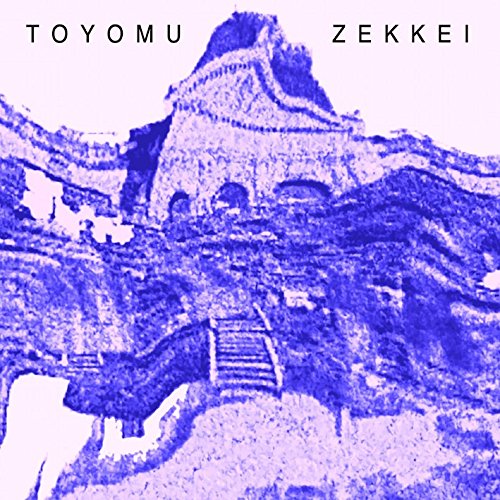コモンの新譜情報を漁っていて見つけた『ローリング・ストーン』の記事には「先行シングル『Black America Again』のアウトロでスティーヴィー・ワンダーは歌う:『山のような問題を解決するひとつの手段として、人を自分にとって大切な誰かであるかのように思うこと(以下略)』」などと書かれていたので、あれ、これはジェームズ・ブラウンのMC音源のサンプリング部分のことでは、てか『ローリング・ストーン』誌ともあろうものがこんな間違いをするだろうか、とコメント欄を開くと「スティーヴィーじゃない、JBだよ」というどこかの誰かの呆れたような短い一文がぽつんと書かれているだけで別に訂正もされていないところを見ると、ひょっとすると誰もこの曲について大した関心は持たなかったのではないか、と思えてくる。
しかし、いくら何でもJBとスティーヴィーを取り違えたままでいいものだろうか。
シカゴ出身のラッパー、コモンの11作目となるアルバム『Black America Again』がアメリカでリリースされたのは11月4日、米大統領選投票日の4日前である。「(ま、いろいろ突っ込みどころはあるけど)どうせヒラリーじゃね?(盛り上がんねぇなぁ)」といった物見遊山なムードだけを感じつつぼんやり日本から眺めていた自分は日本時間の11月9日頃にはやべえ、やばいけど落ち着け、などと極めて凡庸にうろたえておりました。そんな中でふと、本当に偶々コモンの『Black America Again』を耳にして、ああアメリカにはこの人がいた、とようやく自然な呼吸ができるように思えたのでした。
選挙後、同じくシカゴ出身のカニエ・ウエストが、あたかも面白ポップにひねり過ぎて自分自身を捩じ切ってしまったかのような先月の惨状とは際立って対照的に、かつてカニエと組んで『Be』(2005)/『Finding Forever』(2007)などのヒット作を飛ばしたコモンが見せる姿勢は今作もほとんど揺るがない。相変わらず重層的にメロディアスであることも、生真面目に「一枚目」を務めることなど躊躇わない様子も、先人の遺産への深い敬意と愛着を失わないことも全て含め、何はともあれキャッチーに売れなくては、といった発想ではないのが清々しい。件のシングル「Black America Again」の20分を越すロング・ヴァージョンPVなどはさながら実験映画のようでもあるし。
アルバムとしては自伝的なリリックにTasha Cobbsのヴォーカルで締めくくられる14曲目“Little Chicago Boy”でシミジミと終わる、というのが無難に常道なやり方であるはずなところにボーナス・トラックのごとく足された(奴隷制廃止から現在に至る150年間の連続性を扱ったAva DuVernay監督のドキュメンタリー長編『13th』(2016)で使用された曲とのこと)15曲目“Letter To The Free”が、そんなリラックス・ムードで聴いている人間に軽く平手打ちを喰らわすかのように鳴り響いてくる。
「俺らが吊るされた南部の木、その葉」という、ビリー・ホリデイの“奇妙な果実”を本歌取りした一節から始まるこの曲は畳み掛けるように「The same hate they say will make America great again」とトランプの選挙戦キャッチフレーズを折り込み、「Freedom, Freedom come, Hold on, Won't be long」というチャントで終わる。そんなラスト曲を繰り返し聴いていると、元々は『Little Chicago Boy』にする予定だったらしいアルバム・タイトルを『Black America Again』に改めた彼の確かな危機感も伝わってくる。そう言えば、ずっとクリントンを応援していたアメリカの友人(黒人ではないがゲイの映像作家)のことが心配になり、でも事情を何も知らないジャパニーズがいまさら何と声を掛ければ良いもんやら、と途方に暮れながらも投票日から数日後に短いメールを送ったところ速攻で「今や皆がアクティヴィストになっている。確かに解き放たれた感はあるがしかし、この恐怖はリアルなものだ」とこれまた短い返信があった。
実は冒頭に触れた『Black America Again』について書かれた記事で「アウトロでスティーヴィー・ワンダーが歌う」という記述は間違いではないのであるが、致命的なことにラインが違う。ジェームス・ブラウンの語りに続いてスティーヴィーが10回以上繰り返し実際に「歌う」のは「We are rewriting the black American story(ブラック・アメリカンの物語を書き直すのだ)」というワンフレーズである。果たして歴史なり現実なりが「物語」に回収されていいものだろうか? とは思うものの、何かが危機に瀕しているらしい時に人びとをユナイトさせるのは良かれ悪しかれある種の「物語」である、というのもまた事実である。
真面目な正論っていつだって何だか息苦しい(よね)、という時代が妙に長すぎたせいか、最早ポップなものは多かれ少なかれふざけたアティテュードをまぶさないと拡がらない、といった情勢は末期的ではありつつもまだ今のところ隆盛だ。が、コレ面白いから見て見て見て(聞いて聞いて聞いて)と氾濫する情報に窒息しそうな自身に気付いた時、ド直球にまともな作品に触れることでこれだけ楽に息ができるのだ、という現実はどう考えても未だ経験したことのない感覚である。