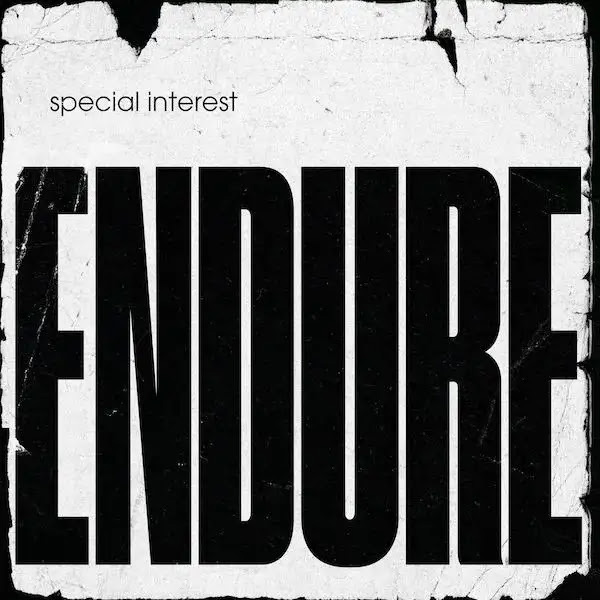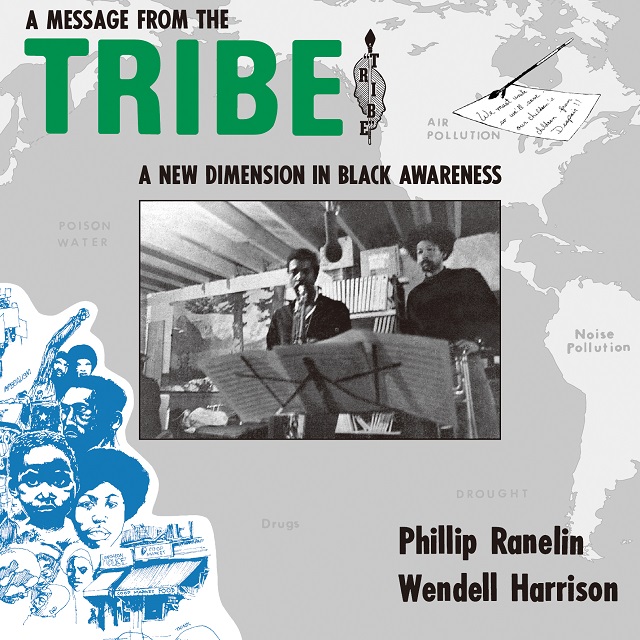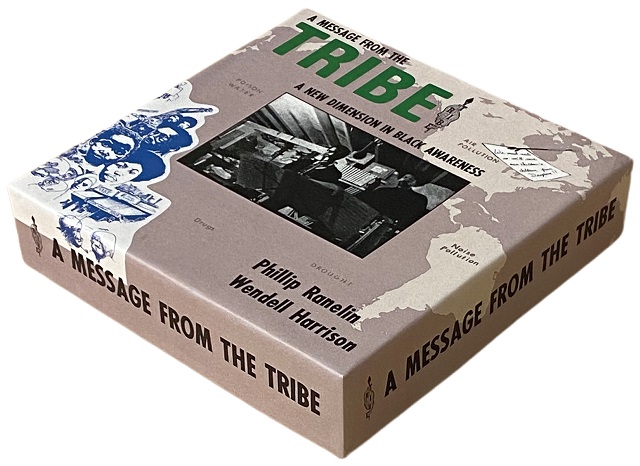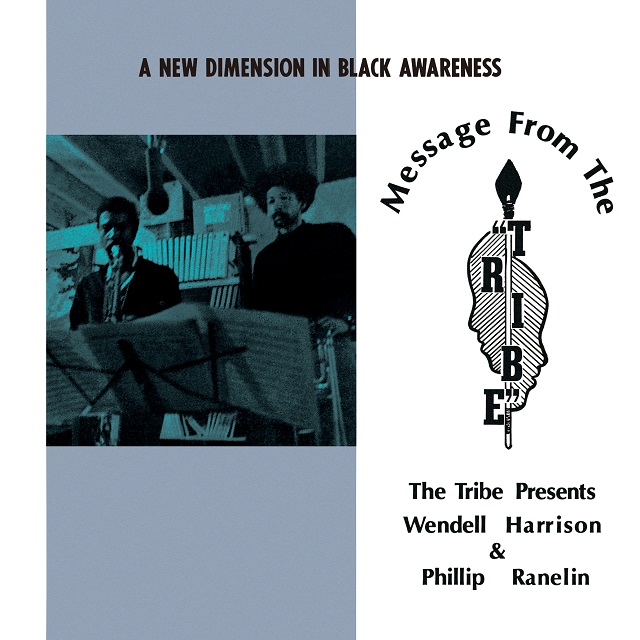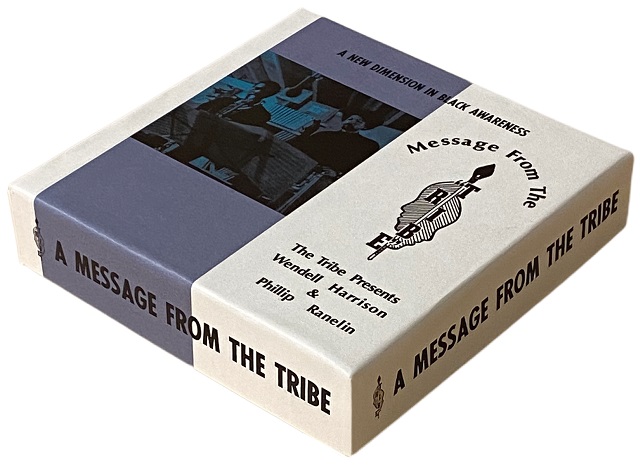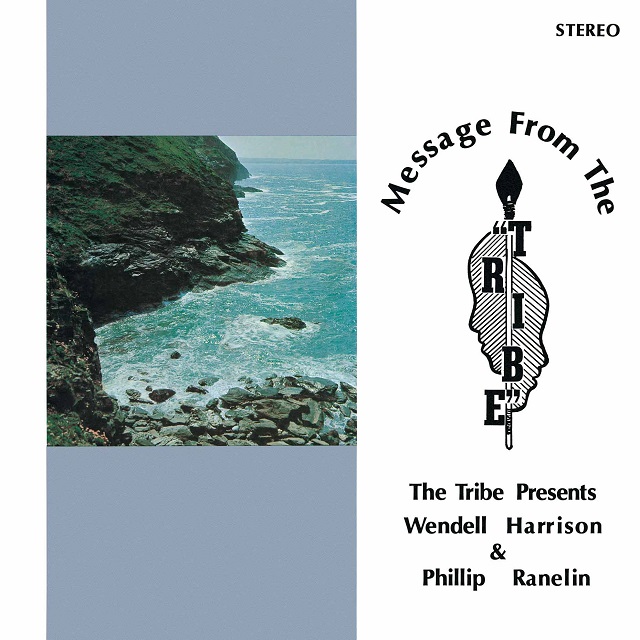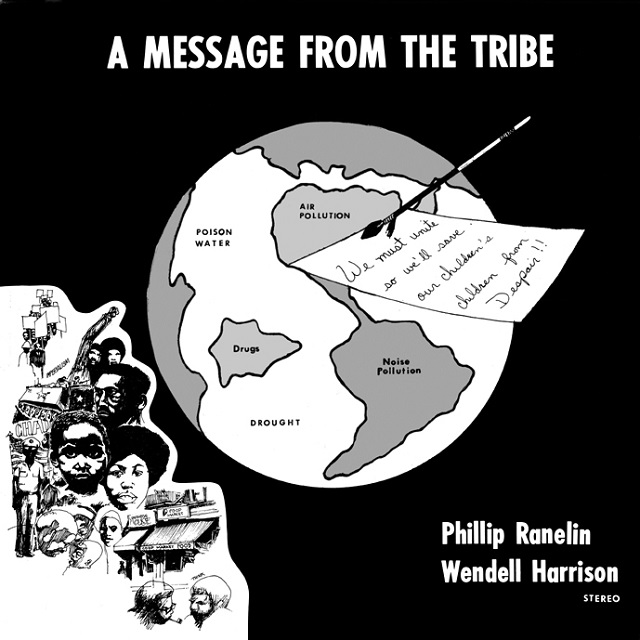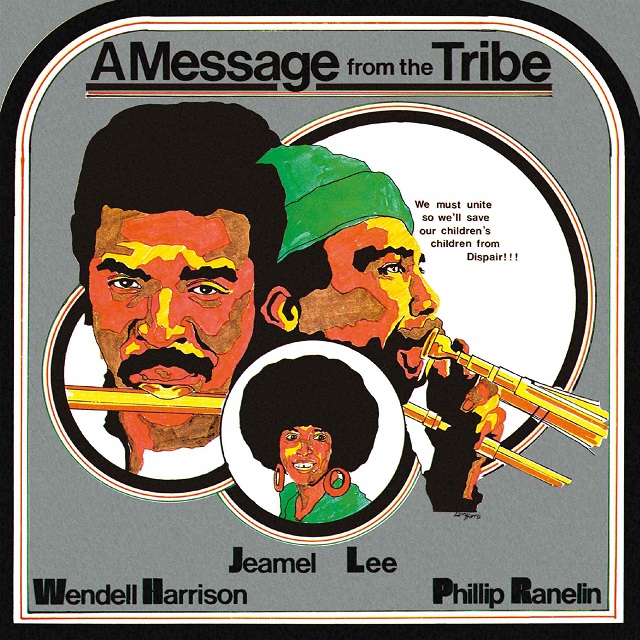これまで〈Mexican Summer〉などからリリースを重ねてきたニューヨークのプロデューサー、フォテー。9歳の若さでエイフェックス・ツインの音楽と出会いながら、その後ギニアへの旅を経てアフリカン・パーカッションとフィールド・レコーディングに目覚めたという、興味深い経歴を持つプロデューサーだが、その彼がLAのキーパーソン、カルロス・ニーニョをフィーチャーした2作、『An Offering』と『More Offering』が特別仕様のCDとしてリリースされることになった。環境音に電子音、サックスやハープなどが交錯する美しいサウンドスケープに注目したい。
Photay with Carlos Niño
『An Offering & More Offering Special Edition』
2022.12.14(水) 2CD Release
天才ビートメイカーとも評されるフォテーと、現代スピリチュアル伝道師カルロス・ニーニョによる共演作『An Offering』と『More Offering』が、2枚組のスペシャル・エディションとしてCDリリース!! 水に反射する様々な色彩や風景から、レイヤーや奥行きを感じさせる視覚的な体験をサウンドスケープとして聴かせる。豪華ミュージシャンも多数参加した、強力なコラボレーション作品の完成!!
西アフリカのギニアへの旅を経て、サンプリングとフィールド・レコーディングの可能性を拡げる実験へと乗り出した早熟のプロデューサー、フォテーが、カルロス・ニーニョやミカエラ・デイヴィスらを招いて作ったサウンドスケープを、どう表現してよいかまだ言葉が見つからないでいる。だが、そのことがとても心地よく思えるほど、何度でも繰り返して流しておきたい音楽がここにある。(原 雅明 ringsプロデューサー)
参加ミュージシャン:Photay - Synth、Mikaela Davis - Harp、Randal Fisher - Tenor Saxophone、Mia Doi Todd - Voice、Carlos Niño - Percussion、Natt Ranson - Trombone、Aaron Shaw - Tenor Saxophone、Diego Gaeta - Keyboards、Nate Mercereau - Guitar Synth、Iasos - Voice

【リリース情報】
アーティスト名:Photay with Carlos Nino(フォテー・ウィズ・カルロス・ニーニョ)
アルバム名:An Offering & More Offering Special Edition(アン・オフアーリング・アンド・モア・オフアーリング・スペシャル・エディション)
リリース日:2022年12月14日(水)
フォーマット:2CD(一部店舗にて、Tシャツ付き限定バンドルあり)
レーベル:rings / International Anthem
解説:原 雅明
品番:RINC97
価格:3,000円+税
【トラックリスト】
《 An Offering 》
1. PRELUDE
2. CURRENT
3. CHANGE
4. EXIST
5. PUPIL
6. MOSAIC
7. HONOR
8. ORBIT
9. EXISTENCE (feat.Iasos)
《 More Offering 》
1. ECHOLOCATION (featuring Randal Fisher)
2. PUPIL (Photay's Tributary Mix)
3. EXISTENCE (Photay's Infinite Mix)
4. EXISTENCE (Photay's Infinite Mix)(Club Diego Version)
5. FLOATING TRIO PART 3 (Photay Carlos Niño and Randal Fisher)
6. QUARTET IMPROVISATION 053021 (Carlos Niño & Friends)
7. FEELING NOW
8. NOW FEELING
9. PHASES (Solstice Mix)
販売リンク:https://photay.lnk.to/Ob68Z6Kx
オフィシャルURL:https://bit.ly/3WD9KSx