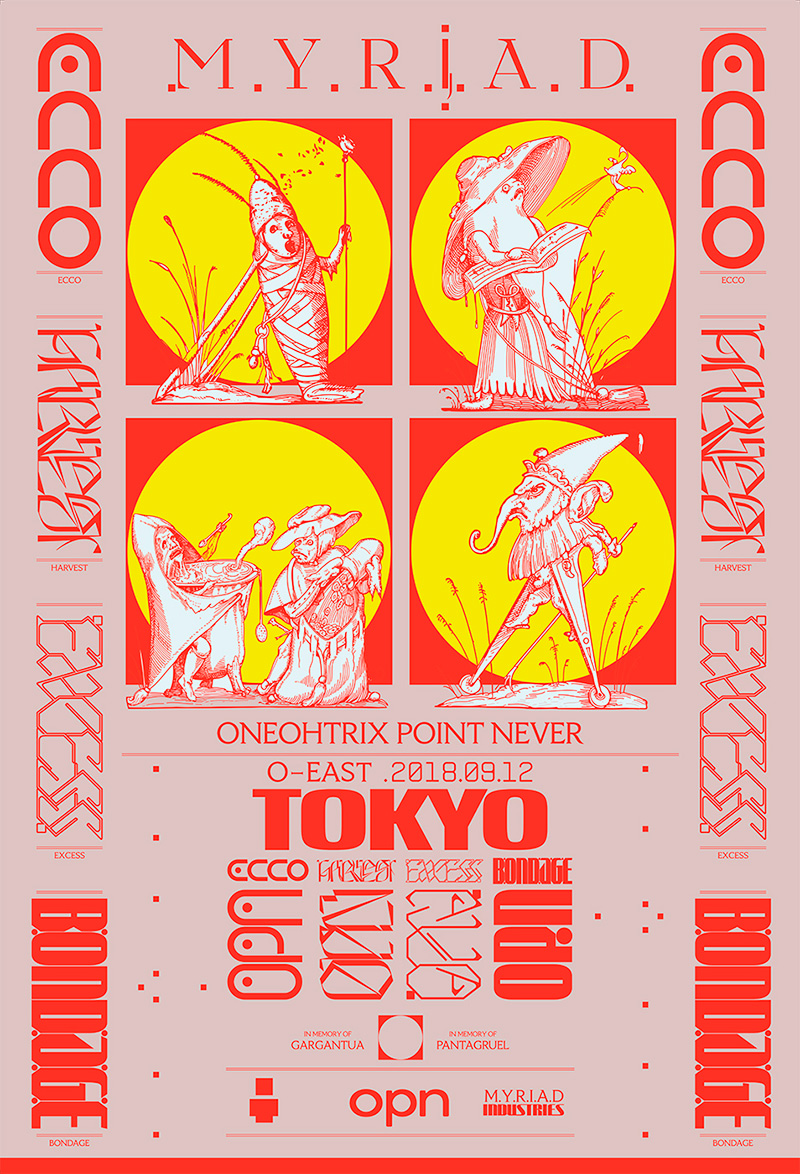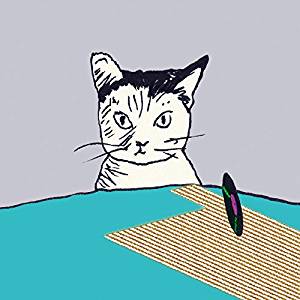70年代中期から末期、ポスト工業化していく社会にむけて「インダストリアル・ミュージック」を提唱したスロッビング・グリッスル。その創設メンバーであり、電子音楽家/電子音響サイエンティスト/サウンド・デザイナーでもあるクリス・カーターのソロ・アルバムが老舗〈ミュート〉からリリースされた。前作『Small Moon』以来、実に18年ぶりのソロ新作である。
これまでリリースされた彼の純粋なソロ作品自体は4作品のみだが、寡作という印象はまったくない。近年も再始動したスロッビング・グリッスル(ジェネシス脱退でX-TGに)、クリス&コージー、カーター/トゥッティ/ヴォイドなどのアルバムやEPを継続的に活動・発表をしていたから常に現役という印象である。
逆にいえばソロとコラボレーションの違いをあまり気にしていない職人気質の人ともいえる。なるほど、こういう人だからこそスロッビング・グリッスルという過剰な(人たちの)存在をまとめることができたのだろう(スロッビング・グリッスルは、その過剰・過激・批評的なコンセプトやパフォーマンス、センセーショナルなアートワークのむこうで音楽性自体はどこか端正な側面もあったと思う)。
本アルバムは、インタビューでも語っていたようにクリス・カーターがさまざまなプロジェクトを同時進行していくという多忙な活動の中で、一種の息抜きのように制作されたトラックをまとめたアルバムのようだ(コージー・ファニ・トゥッティは参加していない)。そのせいか過去のソロ・アルバム以上にリラクシンなムードの電子音楽集となっていた。
“Blissters”、“Nineteen 7”、“Modularity”などは彼のルーツであるクラフトワークを思わせるシーケンシャルなモダン・テクノ・ポップといった趣である。同時に“Field Depth”、“Moon Two”などのアンビエントなトラックは、どこか50年代、60年代の電子音楽、たとえばディック・ラージメイカーズを思わせもした。じっさい、クリス・カーターはこんなことを言っている。「特にこのアルバムに関して影響を受けたものがあるとすれば、それは間違いなく60年代の電子音楽だね」(国内盤をリリースする〈トラフィック〉のサイトより引用)
加えて“Durlin”、“Corvus”、“Rehndim”などのX-TGの『Desertshore / The Final Report』を想起させるモダンな音響感覚が強調される曲も収録されているが、何より“Post Industrial”、“Ars Vetus”などは完全に現代的インダストリアルで痺れるほかない。
どのトラックも時間が2分から3分ほどの小品であり、どこかクリス・カーターのハードディスクにあるマテリアルを聴いているような興味深さもあった(もしかすると、ありえたかもしれないX-TGとして?)のだが、しかし、どの曲もミックスのバランスは完璧だ。素朴であると同時に、無駄がなく聴きやすいのである。
さらに聴き込んでいくと、その奇妙な音響処理にも不意を突かれる。特に“Cernubicua”をはじめとする「声」処理の独特さにも注目したい。本作における「声」は、「存在しながらも不在を強く意識させる幽霊的な音響」を実現しているように思えた。じじつ、彼は、こうも語る。
「スリージー(スロッビング・グリッスルの創設メンバーで2010年に逝去したピーター・“スリージー”・クリストファーソン)と僕はかつてソフトウェア、ハードウェア双方を使って人工的な歌声を作っていく作業を共同で担当してたんだ。今回はそれを僕だけで、さらに進んだことをやろうと思ってね。自分の声もしくはかつてスリージーと一緒に作った音声コレクションを引っ張り出して、それらを思いっきり切り刻んで歌詞を作っていったんだけど相当ヘンテコな感じになったね」(国内盤をリリースする〈トラフィック〉のサイトより引用)
そう、この「声」は、ある意味、ピーター・クリストファーソンとのコラボレーションの延長線上にあるともいえるのだ(それが本作にX-TGらしさを感じる所以かもしれない)。
そして何より25曲というボリュームにまず驚く。だからといって壮大な「コンセプト・アルバム」ではない。むしろEPを聴いているような軽さがある。もしくはミックス音源のような流れも感じた。天才のメモやスケッチを観る(聴く)感覚に近いアルバムともいえるし、架空のエレクトロニック・バンドの「グレイテスト・ヒッツ」を聴いているような感覚もあった。要するにクリス・カーターという電子音楽家・音響デザイナーのエッセンスが、最良のかたちでアルバムに収められている、という印象である。
ではそれはどういったエッセンスなのか。おそらく、カーター自身が使っているモジュラーシンセなどの電子楽器における最良のメロディとトーンを追及するという姿勢・実践に思える。オールドスクールな曲調は、むしろ楽器と音色にとって最良の選択なのだろう。
そのような彼の技術志向は「生真面目さ」などではなく、マシンと音の「必然」性を及しつつ、そこに、これまでにない「逸脱」をどう組み込むのかに肝があるはずで、むしろ技術者の心性に近いのではないか。私見だが「逸脱」に関しては、カーター/トゥッティ/ヴォイドのトラックのほうで実現され、「必然」がこのアルバムに結晶されたようにも思える。
むろん、この場合、「必然」とはあくまで電子音楽/電子楽器の必然であり、何か社会的主題のようなそれほど意味はない(と思う)。そこがスロッビング・グリッスルとの大きな差異であり、クリス・カーターのソロたる所以でもあるのだろう。彼は「匿名性」を希求している。本作を聴きながらそんな印象を持った。
電子音/音楽への研究と耽溺を経て、そのむこうに「匿名的な音楽」を見出すこと。スロッビング・グリッスルというあまりに巨大な署名を背負っているクリス・カーターだが、意外と彼が希求する音楽/音響は、匿名の果てにあるマシニックな機能性の美なのではないかと思う。そしてそれこそが言葉の真の意味での「インダストルアル・ミュージック」ではないか、とも……。
いずれにせよこれこそがクリス・カーターの考える電子音楽である。それはわれわれの耳が求めてしまう魅力的な電子音楽作品でもあるのだ。