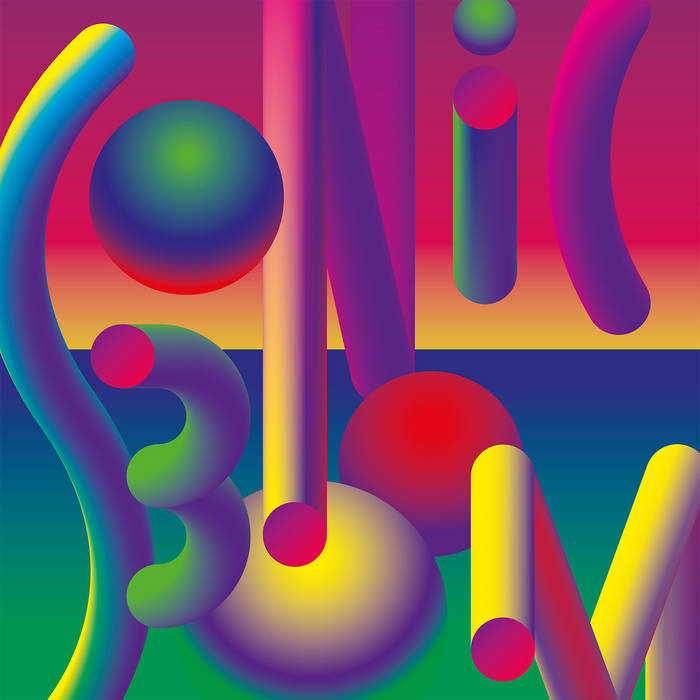5月25日にアメリカ合衆国のミネアポリスで白人警官によって黒人男性のジョージ・フロイド氏が殺害され、それに端を発する人種差別撤廃を掲げる抗議運動「Black Lives Matter(以下、BLM)」が、現在世界各地で行われている。先週末の日曜日、6月7日にイギリスのロンドンで開催された抗議集会に僕は参加してきた。この記事では、そこで自分が見たものを記していきたいと思う。
ロンドン市内での大規模な抗議は5月31日から合計4回開催されており、この日のデモの開始地点は、ロンドン中心地のテムズ川の南に位置するエリア、ヴォクソールにあるアメリカ大使館(『007』シリーズに出てくるMI6本部の建物もここにある)。現在のコロナ禍に対応するため、抗議運動の主催者からは、マクスの着用が求められていた。抗議には多くの年齢層が参加していたが、20代から30代の若者が多かった印象を受けた。人種は黒人系を中心に、白人層やその他のバックグラウンドを持つ者も大勢集まっていた。政府の発表によれば、この一週間のロンドンの抗議運動には、合計137500人が参加し、警察からは35人の怪我人を出し、逮捕者は135人に登ったというが(The Guardian, 2020) 、僕の周りでは終始、平和的に抗議が行われていた。
今回のデモには多くのアフロ/カリブにルーツを持つミュージシャンや俳優などの文化人も参加している。先週はディズニー版『スター・ウォーズ』三部作にフィン役で出演していたジョン・ボイエガがハイド・パークの集会でスピーチをし、他にはグライムMCのストームジーやUKラップのデイヴ、サックス奏者のヌビヤ・ガルシアなど、多くの人物が抗議に参加した。サウンド・カーで音楽を披露するわけではなく、文化の現在を形成する者たちはイギリスを生きる黒人として、一般人と同じ立場から、彼らはその声を届けにきていた。
この日の天候は決して良くはなかった。そして、徐々に規制が緩和されているとはいえ、イギリスはまだコロナ禍によるロックダウン(都市封鎖)の最中である。都心部から電車でだいたい40分ほど離れた場所に位置する、サウスイースト・ロンドンのルイシャム地区、ブロックリーに住む僕は、自転車で目的地まで向かう必要性を感じていた。いくつかの駅は閉鎖され、運行本数は減らされているものの、電車やバスは動いているし、「不要不急」の使用を避けるように要請されているだけで、実際は使用することはできる。しかし、出来る限り感染のリスクを下げるため、お互いの「ソーシャル・ディスタンシング」を保ちながら、近所に住む友人たちと雨に降られながら、僕は自転車で集合場所へ向こうことにした。
現場に到着する10分ほど前から、歩道と自転車道は抗議への参加者でいっぱいだった。バスターミナルがあるものの、普段はそれほど混むことはないヴォクスホールだが、駅周辺に自転車を駐めるのは困難なほどの人混みだったため、そこから少し離れた公園の柵に自転車をくくり付け、アメリカ大使館へと向かった。この時点で携帯がネットになかなか繋がらない。ロンドンでは、大勢が密集する地域ではよく起こることだ。僕は以前、三日間で100万人以上が集まるノッティングヒル・カーニヴァルで同じ現象を経験したことがある。電波が悪くなるのに十分な人数がこの時点でもう集まっていた。
集合時間の2時から30分ほど遅れ現場に到着した。集合エリアでは、脱中心的にいたるところでシュプレヒコールが巻き起こっていた。すでに道路は閉鎖され、集合地点であるアメリカ大使館へは到達できないほどの群集ができあがっている。「Black Lives Matter」、「No Justice! No Piece!(正義がなければ平和もない)」、「I can't breathe (息ができない)」、「Fuck Donald Trump!」「What's his name? George Floyd!」など、25日以降、世界中で叫ばれている言葉が群集から飛び出してくる。参加者たちがヒートアップするなか、大使館前にいるグループからの掛け声で、集合エリアの参加者は跪き、拳やプラカードを掲げ、1分ほど沈黙によって抗議の意を示した。

(抗議マーチの起点となったアメリカ大使館近くのヴォクソール橋)
その後、参加者たちは列を作り、徐々に移動を開始する。ヴォクスホールの再開発によって奇妙な形のタワマンが立ち並ぶエリアから橋を渡り、川の北川の伝統的でポッシュな建物が立ち並ぶエリアをぬけ、一般的市民が住めるレベルの建物がやって見えてくる。周知の通り、ロンドン中心地の家賃は恐ろしいほど高騰しているが、そんなエリアでも公営住宅は存在している。窓からは「Black Lives Matter」のプラカードを掲げた家族や子供たちが、シュプレヒコールを路上に向けて叫んでいる。
この周辺には、ロンドンで最も混雑する駅のひとつ、ヴィクトリア駅があり、普段は多くの車が行き交っているのだが、この日はその道路も抗議マーチによって封鎖された。立ち往生し、不満が募っている周囲のドライバーたち……、と思いきや、その多くからは抗議への賛同を示すクラクションが聞こえてきた。なかには、わざわざマーチが進行する道路に車を駐車して、車中から音楽を流し、窓から上半身を乗り出してプラカードを掲げる者もいた。

(マーチが通る場所に位置するバス停や電話ボックスには、「Black Lives Matter」や「George Floyd」、「ACAB(All Cops Are Bastards:すべての警察はクソ野郎)」などの文字が書かれていた)
ヴィクトリア駅周辺のビル街を抜けると、国会議事堂があるウェストミンスター地区がある。いわゆる「ビッグベン」で知られる、現在は修復中の時計台が見下ろす議会広場を中心に、このエリアもすでに抗議の参加者たちで溢れていた。この広場にはデビッド・ロイド・ジョージやウィンストン・チャーチルといったイギリスの歴代政治家とともに、マハトマ・ガンジーやネルソン・マンデラといった国外の政治指導者たちの銅像も並んでいる。その周辺では有志の若者たちがマスクと手の消毒液を無料で配っていた。広場でしばらく休憩したのち、僕は抗議の終着地点に向かった。首相官邸がある、ダウニング・ストリートである。

(議会広場のネルソン・マンデラ像)
混雑する通りを進むと、ゲートが閉まったダウンニング・ストリートの入り口では、群集がザ・ホワイト・ストライプスの “Seven Nation Army” の替え歌を大合唱していた。この歌は、前回の総選挙時にはジェレミー・コービン支持者らが「オー、ジェレミー・コービン!」の替え歌で合唱したことでも有名だが、今回の歌詞は「Boris Johnson is a racist!(ボリス・ジョンソンは人種主義者)」である。政府機関が入る周囲の建物には抗議者がよじ登り、壁には「Black Lives Matter」の文字が殴り書かれていた。この場所では先日6日の抗議では抗議者と機動隊が衝突した場所でもある。けれども、この日は建物や信号によじ登る者はいたものの、警察の介入はなく、暴力的な場面に遭遇することもなかった。通りには過去の大戦での戦没者を追悼する記念碑もあり、そこに座ろうとする者を注意する抗議参加者たちもいて、秩序立ったなかで抗議は進行していった。そこでしばらくシュプレヒコールをし、僕たちは南へと帰ることにした。時刻は5時近く。国会周辺からは一向に人が減る気配はなかった。

(ダウニング・ストリート周辺の抗議)
この原稿の目的はあくまで抗議の様子を紹介することなので、イギリスにおけるBLMの考察などには踏み込まないが、最後にひとつだけ触れておきたいことがある。先ほどの「彼の名前は?」のシュプレヒコールで、ジョージ・フロイドに加えて、組織的な人種差別の犠牲者となった者たちの者たちの名前が叫ばれていた。そのなかのひとりに「Stephen Lawrence(スティーブン・ローレンス)」がいる。
1993年4月23日、サウスイースト・ロンドンのエルタムのバス停で、友人ともに外出していた18歳の黒人青年、スティーブン・ローレンスが、16〜17歳の5人組の白人の少年たちによって刺殺されるという凄惨な事件が起きた。殺害は彼が黒人だったからという、あまりにも稚拙で愚劣な人種主義的動機によるものだった。
このような残忍な犯行であったにもかかわらず、逮捕された5人は証拠不十分で不起訴となる。このような不当な事態を受け、被害者の母親であるドーリーン・ローレンスは警察側に正当な捜索をするように抗議運動を開始する。この遺族が中心となった活動により、警察内部での組織的な人種的偏見から、捜査そのものが適切に行われていなかったことが判明した。これを機に、イギリス国内における、この事件や人種政策に対する関心は大きな高まりを見せる。容疑者のうちゲーリー・ドブソンとデービッド・ノリスに有罪判決が出たのは、2012年。それぞれ禁固15年2月以上と14年3月以上の判決が言い渡された。事件発生からあまりにも長すぎる時間が流れ、刑の内容も十分とは思われないものの、関係者の努力により形で事件は大きな進展を見せた。
多文化主義が謳われるロンドンだが、権力レベルで人種差別が行われている制度的人種主義とそれが引き起こす問題が広く認知されるようになったのは、27年前の事件を境にしたことにすぎない。スティーブン・ローレンスの命日は、今日も人種差別撤廃を意識づける日として、毎年多くの者に追悼されている。ドーリーン・ローレンスは人種差別撤廃の活動を今日も続けており、2020年に入ってから、キア・スターマーを新たに党首に選出した最大野党の労働党によって、ローレンスは党の人種関連アドバイザーに任命されたばかりだ。
文化面に与えた影響も大きい。ロンドンを拠点に活動するサックス奏者、シャバカ・ハッチングスは積極的にイギリスのブラック・ムーヴメントにコメントをしてきた人物のひとりだ。彼が率いるバンド、サンズ・オブ・ケメトの2018年作『Your Queen Is A Reptile』は、歴史上に名を残す黒人女性たちの名前を曲名に関したアルバムで、終曲の名前は “My Queen Is Doreen Lawrence” であり、今作には彼女への大きな敬意が込められている。ハッチングスとも繋がりがある、グライムを産んだ音楽家であるワイリーもSNSで、この事件に関する投稿をローレンスの命日とBLMプロテストの日にしていた。イギリスのギラついた音楽は、人種主義へのカウンターとして、今日も鳴り響いている。
2011年、ロンドンで警官が黒人男性を射殺したことを発端に、イギリス全土で大規模な暴動が発生した。それから9年後、海を渡ったアメリカで起きたジョージ・フロイドの事件がトリガーとなり、今回のロンドンでの大規模なBLMの抗議運動へと繋がっている。イギリスは政治的にも、デモグラフィー的にもアメリカとは決して同じではない。しかし、警察や権力による日常的な人種主義的偏に対する怒りという意味では、この運動には国境は存在しない。そこには分断を超えていくようなエネルギーが満ち溢れている。帰り際、発煙筒からピンク色の煙が上がるチャーチル像の近くでスティーブン・ローレンスとジョージ・フロイドの名前を耳にしたとき、僕はそんなことを考えていた。

(議会広場のチャーチル像。この銅像には、このあと、「チャーチルは人種主義者(racist)だった」の落書きがされる。)
[参考資料]
•The Guardian (2020), “Bid to defuse tensions as Black Lives Matter protests escalate”
•AFP (2012), “18年前の黒人少年刺殺事件、白人被告2人に禁錮刑 英国”
•スティーブン・ローレンス事件と制度的人種主義の関連は、イギリス人ジャーナリスト、Richard Power Sayeedが著書『1997: The Future that Never Happened』(Zed Books, 2017)で、現在の英国の人種政治と絡めて詳しく書いている。