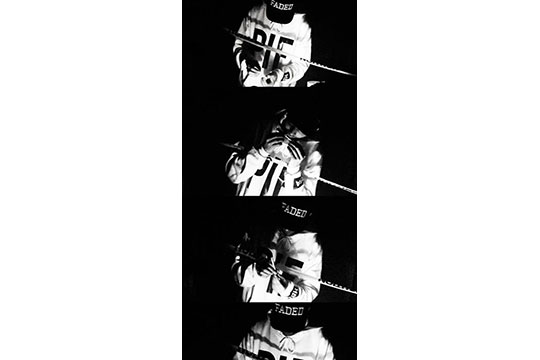もう何回も言ってることだけど、日曜は下北沢THREEで遊ぼうぜ!
先日告知したele-king本誌最新刊vol.10連動イベント「アンチ・ギーク・ヒーローズ」のことですよ。な、な、な、なぁぁぁんと、LowPass、カタコトに加え、ele-kingに欠かせないマン・オブ・タレント、踊ってばかりの国の下津光史(a.k.a The Acid House.)の出演が決定! イエー、ロックンロール~!
さらにはDJに、いまや売れっ子のライター二木信が登場。某ラップ・ユニットのミックステープではフリースタイルで客演するなど、垣根を超えた活動をするこの男が一体どんな曲をスピンするのか......見所と言えば、もしかしたらこれが一番の......いやいや、新人カタコトを見て欲しい!
というわけで、今週末、8月25日(日)、18時開場!
マジ、頼みます。みんな、下北沢THREEで遊ぼう!
ele-king presents "ANTI GEEK HEROES"
8.25 (sun) 下北沢 THREE
OPEN 18:00 / START 18:30
ADV / DOOR 2,000 yen (+ drink fee)
LIVE: LowPass / カタコト / 下津光史(踊ってばかりの国)
Opening ACT: バクバクドキン
DJ: 二木信
*公演の前売りチケット予約は希望公演前日までevent@ele-king.netで受け付けております。お名前・電話番号・希望枚数をお知らせください。当日、会場受付にてご精算/ご入場とさせていただきます。
INFO: THREE 03-5486-8804 www.toos.co.jp/3