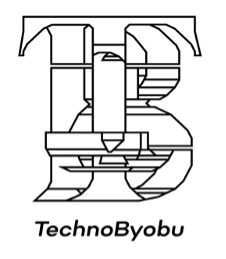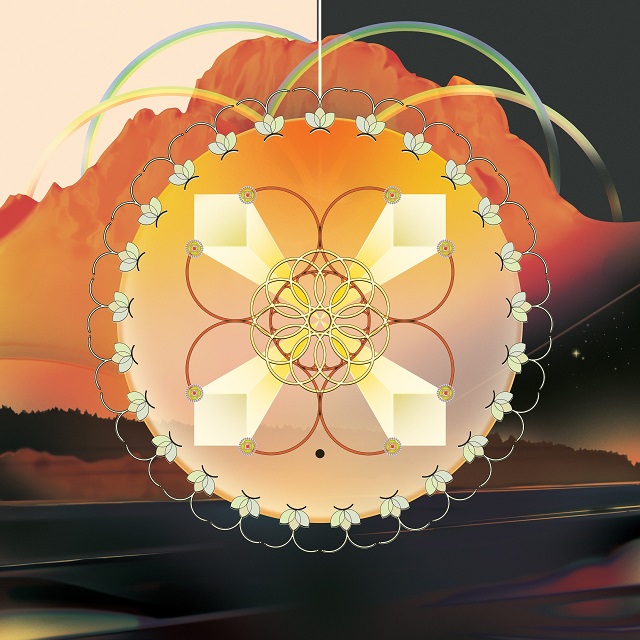3月に新作『UK GRIM』のリリースを控えたスリーフォード・モッズが、収録曲の “Force 10 From Navarone” のMVを公開した。これは、ドライ・クリーニングのフローレンス・ショウをフィーチャーした曲で、新作の目玉の1曲でもある。とにかくカッコいいので聴いてみて。
Sleaford Mods - Force 10 From Navarone
ジェイソンいわく。「俺たちはドライ・クリーニングの大ファンで、フローレンスがこの曲にぴったりだとわかっていた。彼女は本物で、そのたった一言で全体のストーリーを伝える方法で俺がウータン・クランから受けるようなインスピレーションを呼び起こす」
戦争から物価高、右翼に保守党、生活がめちゃくちゃにされた庶民の怒りを乗せたアルバムの発売は3月10日。なお、エレキングでは当然のことながらインタヴューを掲載します。こうご期待!