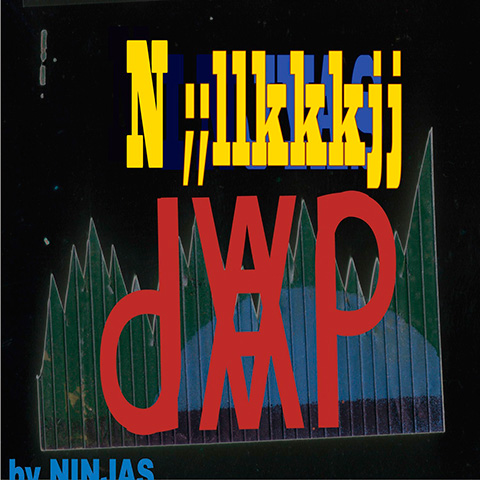2016年はテーブルの年だった。レナード・コーエンは「テーブルから離れる(「Leaving The Table」)」と歌ってその直後に他界し、ソランジュは「テーブルに黒人の席はあるか(『A Seat At The Table』)と問いかけてガーディアン紙から「ボブ・ディラン賞」を授与された(坂本麻里子さんに聞いたところではクラフトワークのライヴでソランジュたちが踊りまくっていたところ、後方の席にいた白人たちからモノを投げつけられた経験がこのタイトルにつながったらしい)。そして、グライムでとくに耳を引いたのはスペイシャル(Spatial)の「レインボー・テーブル(Rainbow Table)」であった。ダブステップではすでに10年近くキャリアを積んでいる才能のようで、しかし、ここ3作を聴く限り、少しずつグライムに舵を切りはじめ、どちらともいえなくなる作風に移行していった様子がよくわかる(https://www.youtube.com/watch?v=dL_lhFlUNP8)。「レインボー・テーブル」というのも(リー・バノン同様)数学用語である。
「テーブルの上に持ってくる(Bring to the Table)」という言い回しは英語では「明らかにする」という意味にもなる。ラシャド・ベッカーは何年か前に「シンセサイザーによって合成された音はその音を作り出した人の個性を暴き出す」とか「潜在力に満ちている」というようなことを語っていたことがあり、さらにはそのような力が持っているフィクションの優位について強調していたことがある。そして、彼自身がここへ来て完成させた『存在すると信じられている種族のための伝統的音楽Vol. II(Traditional Music of Notional Species Vol. II )』は彼自身の言葉をそのまま裏付けるような音楽になっていた。前作よりもフィクション性は高まり、簡単にいえば童話でも読んでいるような別世界感覚に富んでいるのである。
「Notional Species」というのは、まるで人類ではないかのような含みを持つ表現で、それがまた異様な音楽性に投影されているともいえるけれど、彼が過去に語っていたことから察するに、それはどうやらアジアやアフリカ、さらには南米の音楽家のことを指していると考えられる。要するにワールド・ミュージックのことで、それにどれだけフィクション性を喚起できるか、それが前作から続く彼のテーマだったのだろう。そして、『Vol. II』におけるフィクション性の増大は完璧なまでにワールド・ミュージックの痕跡をテーブルの下に隠し切った。ワールド・ミュージックの影響をわかりやすく表に出すことが「トレンド」だとしたら、ラシャド・ベッカーはそれとは正反対のことをやっているのである。これは恐るべき知性である
こうした試みは、しかし、ドイツでは初めてではない。共に故人となってしまったメビウス&プランクによる『ラスタクラウト・パスタ』(79)がすでに金字塔として存在している。クラウトロックにレゲエを取り入れ(だから「ラスタクラウト」)、カリブ・ミュージックのムードは微塵も感じさせずにドイツとジャマイカのサイケデリアだけを共振させた音楽をコニー・プランクとディーター・メビウスは40年近くも前に作りあげている。ラシャド・ベッカーは『ラスタクラウト・パスタ』を過去の遺物として葬り去らなければならない。そうでなければ何かをクリエイトしたとは言えない。いまのところはまだ、それに近いことはやったかもしれないとと思うばかりである。そして、ラシャド・ベッカーは今日もテーブルに機材を並べ、ライヴ・パフォーマンスを続けている。
それにしてもピート・スワンソンにジェイムズ・プロトキンと、マスタリング・エンジニアから知名度を挙げていく才能が多いのはなにかの偶然?