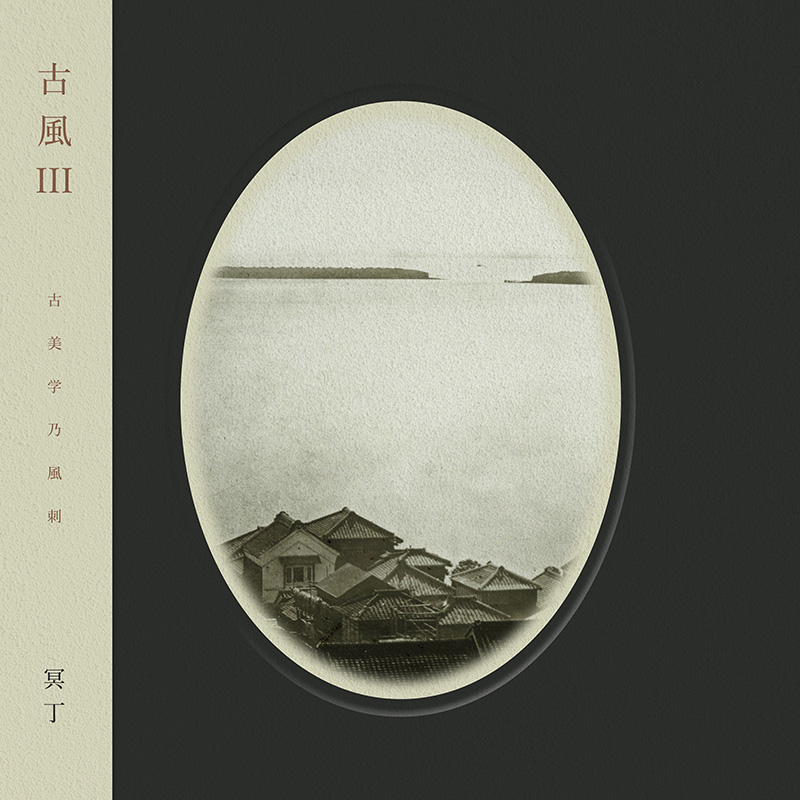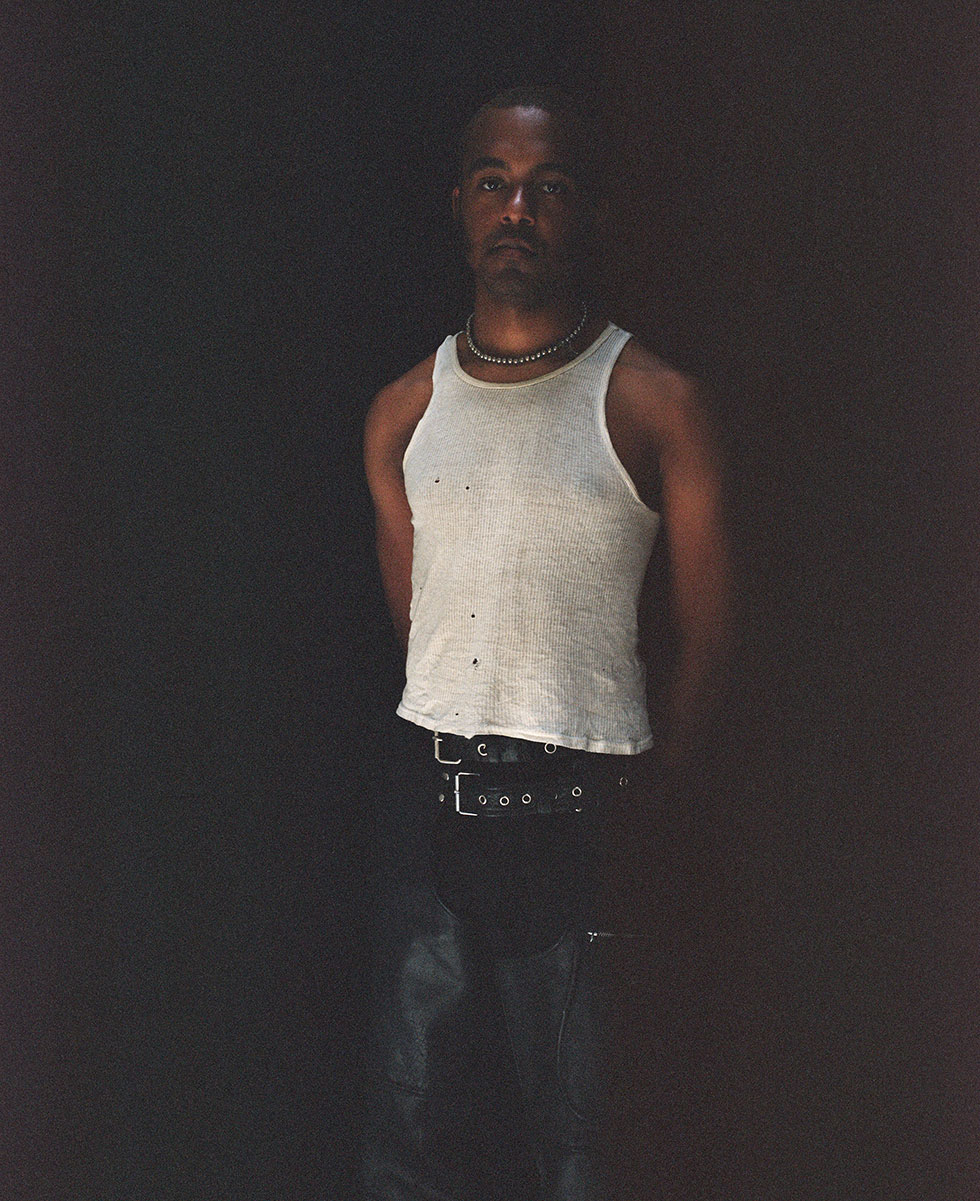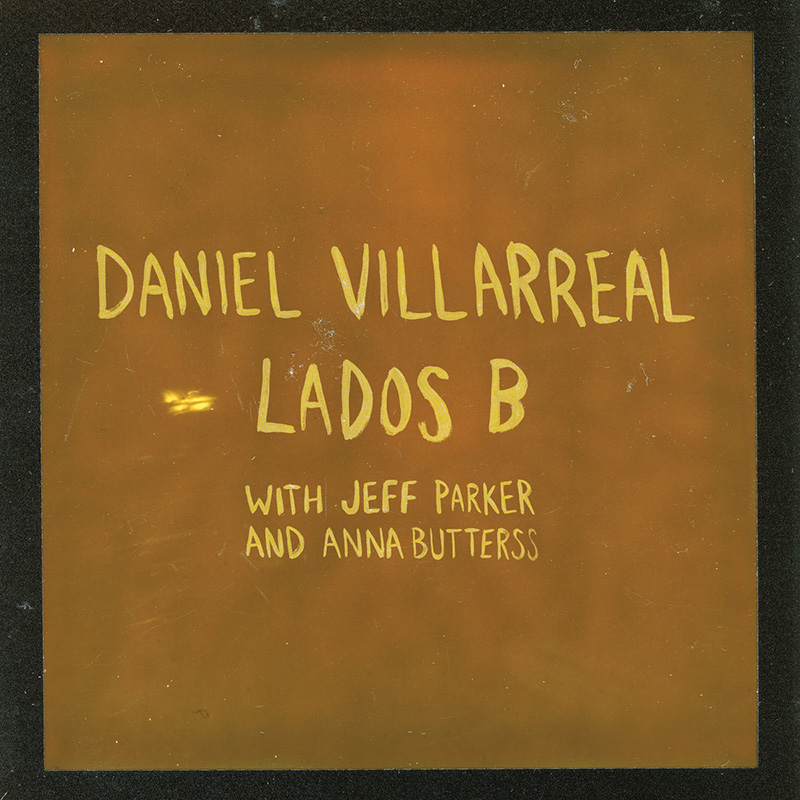少し落ち着いてきた。3日前にフィッシュマンズのツアー〝LONG SEASON 2023〟を観に行き、かなりコーフンして、人格などが変わり、しゃべり散らかしたあげく家に帰るまでがフィッシュマンズのライヴだと思っていたのに6時間寝て起きてもまだ同じで、昨日は取材の準備をしなければいけなかったのに何も頭に入らず、気がつくとフィッシュマンズを聴いているし、先ほど取材先から帰ってきてようやく地に足が着いてきた。おお、地面よ、そこにあったのか(『空中キャンプ』かよ)。あれから3日も経っているなんて信じられない。時の流れはほんともウソもつきすぎる。
フィッシュマンズのライヴはルーティンにならない。佐藤伸治がいないライヴに行くか行かないかでいちいち悩むので、好きなバンドのライヴだから機械的に足を運ぶという感じにはならないから。ただ、「いちいち悩む」こともルーティン化してきたきらいはあるので、悩むことも込みでライヴに行っているとも言えるし、それはそれで機械的と言われれば反論はできない。悩む。あれこれ考える。一から考え直す。結論はない。毎年のように発見があり、どんどん上書きされていく。とはいえ、前回は忙しくて行かれなかったので、それほど考えずに今年はすぐに結論が出た。
会場は超満員。男の方が多いだろうか。ぎっしりと人が詰めかけたZepp DiverCityを見て昔の野音にはポツポツと空席があったことを思い出す。金がないウッドマンがどうしても観たいというので事務所に頼み込んでムーグさんと3人でザ・KLFの話をしながら観ていたことがある。僕らの周囲には少し空席があり、こんなにすごいライヴなのにもったいないなーと思っていた。フィッシュマンズの出す音が空席にぶち当たってどこかに跳ね返っていく。ウッドマンは僕とムーグさんのよもやま話には加わらず、無言でフィッシュマンズを受けとめていた。7年前に彼が急死したという知らせを聞いて、巨漢の彼には野音の席が少し小さかったことを思い出した。
この日のフィッシュマンズは茂木欣一、柏原譲、HAKASE-SUNの〝オリジナル・スリー(佐野ディレクターの命名)〟と、ダーツ関口、木暮晋也に加えて原田郁子も正式メンバーとしてクレジットされている。この6人が実にだらだらと登場してくる。どこにも緊張感が漂っていない。これだけ大きな会場なのになんの演出もなく、低いテンションでスタートするというのは明らかに自信の表れである。そして、その通り、“A Piece Of Future”であっという間に彼らの世界へオーディエンスを連れ去ってしまう。瞬時にしてやられてしまった感じ。そして、木暮晋也がヘンな節と声にエフェクトをつけて順にメンバーを紹介していく。いつものようでいつものようではない。煽られまくって僕も叫んでいる。
ブレイクが入って次の曲に変わったのかと思ったら、まだ“A Piece Of Future”が続いている。このまま30分ぐらい演奏し続けて“LONG SEASON”と2曲で終わったらまた伝説じゃんと思ったけれど、さすがにそれはなかった。続けて“MAGIC LOVE”。急にテンポが上がったせいか、なんとなく勢いをつけ損ねたように感じるもすぐに立て直し、そつなく終わらせて“BABY BLUE”へ。これもまだエンジンがかかりきらず、演奏は及第点。この曲はもう少し疲れた頃に聴きたかった。やはりフィッシュマンズには陶酔させきって欲しいし、“MAGIC LOVE”の余韻にはちょっと合わない感じもあった。とはいえ、会場全体の揺れは早くもハンパない。客席が波のように揺れていた新宿リキッドルームの眺めが蘇る。踊りに没頭して周りが見えなくなればなるほど“BABY BLUE”の歌詞は突き刺さる。「今日が終わっても 明日がきて」というのは毎日が同じことの繰り返しで先に進む感覚がなく、その虚しさから生きることにはなにひとつ「意味なんかない」と思うほど自分自身の存在に価値が見出せない。そして「長くはかなく 日々は続く」と、「いま・ここ」に没頭(=実存主義)できないことに「泣きそう」になっている状態だと受け取れる。この感覚は“すばらしくてNICE CHOICE”の「そっと運命に出会い 運命に笑う」という現実の肯定と対になっていて、“幸せ者”の「みんなが夢中になって 暮らしていれば」感じられる気持ちだと作者はわかっているから“ナイトクルージング”で他者との出会いが実存的不安を解消してくれることを期待して「窓はあけておくんだ」と準備していることと結びつく。無に等しいと感じる個人が世界とかかわろうとすることをサルトルはアンガージュマンと呼び、60年代の若者はこれを政治参加の合言葉としたけれど、「60年代に生まれたかった」と話していた佐藤伸治はあくまでも主体的に「目的は何もしないでいること」とアンガージュマンを社会と切り離す方向で動機づけ、90年代に特有のアティチュードを模索した。いってみれば社会を前提としないアンガージュマンであり、「無に等しいと感じる個人」にとって、その価値は時間が流れる限り肯定と否定の感覚を繰り返さざるを得ない堂々巡りのようなものになる。泣いて笑って、泣いて笑って。何度も何度も何度も。遺伝子の乗り物ではなく、人間であるということはそういうことだから「止まっちまいたい」と思うのは自然な感情である。大脳を発達させ、感情豊かになったことの代償だと思うしかない。今日もきっとSNSは感情の不発弾であふれている。
続いて“バックビートにのっかって”。バックビートというのは日本人にはほとんど演奏できないとされている洋楽の演奏技術。業界には「バックビートおじさん」というのがあちこちにいて「日本人には無理だ、日本人には無理だ」と連呼する習慣があり、バックビートを演奏できるなどと公言しようものならあちこちから「出来てない!」というヤジが飛んでくるにもかかわらず、それに「のっかって」と歌ってしまうのだからフィッシュマンズも挑戦的である。そして、佐藤伸治がフィッシュマンズのリズム隊にどれだけ信頼を置いていたかということがよくわかる曲名ともいえる。バックビートは4拍目から入って2拍目と4拍目を強調する「4入りの2・4」が基本とされ、これを茂木欣一はレコーディング・ヴァージョンでは3拍目にスネアを入れ、ライヴでは逆に3拍目を抜いたり、1拍目と3拍目では手数を増やすという叩き方だったのが、この日はシンプルに3拍目しか叩いていなかった(←最後が面白い)。また、“バックビートにのっかって”の♪あ~~~あ~あ~あ~~、という生暖かいスキャットが僕は大好きで、これとL・L・クール・J“Mama Said Knock You Out”の冷めきった♪あ~あ~あ~あ、と、戸川純“蛹化の女”の追いつめられた♪あ~あ、あ~あ、が僕の3大「あ~」です。次点でピンク・レディとT・レックス。きゃりーぱみゅぱみゅは入りません。
続く“Smilin’Days Summer Holiday”でもドライヴ感は持続している。ベースがぐいぐいと渦を巻いて文句なしの流れをつくり出す。これも茂木欣一のドラムは『若いながらも歴史あり』では1拍目と3拍目で手数を増やし、『男達の別れ』では2拍目と4拍目を強調して重く沈み込ませるという叩き方だったのが、この日は“バックビートにのっかって”と同じく3拍目だけを強調していたと記憶。「あの外人みたいな髪型できっと同じことを考えてるぜ~」は何回聴いても笑うなー。佐藤伸治のいたフィッシュマンズにあって現在のフィッシュマンズにないのは、あの突拍子もない言語センスを駆使したMCなんだよな。急に雑誌名を連呼したり、「安いク○リ、やってんじゃないの?」とか。あればかりはもう無理なんだよな。続いて“いかれたBaby”へ。J~ポップからメタルまで幅広くカヴァーされた曲を本家の演奏で聴くという、かつてはなかった興奮を感じるも、韓国のアジアン・グロウによるシューゲイザー風のカヴァーが耳慣れてしまい、本家にしてはちょっと物足りなく感じてしまった。この曲と“SUNNY BLUE”は典型的なマンチェスター・ビートで、フリッパーズ・ギターと共に日本のロックが「聴くロック」から「踊れるロック」に変わった瞬間を刻印していることはとても重要なこと。ele-kingも最初はそこに反応したのに、なんでテクノと結びつけたように言われるのかわけわからん。ちなみに中国では“BABY BLUE”の方が人気で、Vログなどで無数にフィーチャーされ、フレックルズが2コーラス目を中国語で歌っているのがとても可愛い。
MCを挟んで客電が落ちると暗闇からアカペラで“頼りない天使”が聞こえてくる。ゲスト・ヴォーカルのUAがいつの間にかステージに立っていた。細い声の佐藤に寄せるより、思いっきり太い声で歌うUAはまったく違う魅力を感じさせる。いつも1人に向かって語りかけてくる佐藤に対して「不思議」という言葉が届く範囲が広がったように感じられ、単純に声量があるというだけで存在の儚さよりもこの曲が持つ慈愛の面が引き出されるということかもしれない。茂木のドラムがこの曲だけ2拍目にスネアを入れていたと聞こえたんだけど、僕の聞き違いだろうか。続いて“すばらしくてNICE CHOICE”。これは09年の「FISHMANS:UA」でもやっていたけれど、歌詞がUAには合わないというか、茂木のMCでもUAは生命力にあふれているとかなんとか話していた通り(手術して5日後にフェスでドラムを叩いていた茂木には言われたくないという気もしたけれど)、パワーがありすぎて、ぜんぜん「やられそう」じゃないのがどうもひっかかる。タナトスからエロスに引き返してくるところが“すばらしくてNICE CHOICE”の感動的なところなので、UAの歌い方だと強すぎて境界線上をさまよう立体感に乏しくなってしまうのである。これならいっそフォーク調で聴かせるUAの“甘い運命”を柏原譲のねっとりとしたベース・サウンドで聴いてみたかった。UAはしかし、絶好調だったのでしょう。曲が終わるとギャグが止まらず、お台場のガンダムをネタにしたり、モンキーダンス(?)を踊り始めたりと、いわゆるひとつの「大阪のおばちゃん」状態が止まらない。昨年末に細野晴臣のラジオ番組に出て、母の旧姓が平だから「タイラー・スウィフトです」と言って笑い転げていたそのまんまが続いていて。
この流れにさりげなくハナレグミも加わり……いや、ほんとにさりげなく加わって“WALKING IN THE RHYTHM”へ。それまでの雰囲気とあまりに落差がありすぎて、かえってストンと曲に落ちることができた。スライとピンク・フロイドを合体させているにもかかわらず決然とした曲調を崩さず、フリーク・アウトの予感だけで持たせてしまうというのか、この曲が最も90年代と変わらない印象を残したかも。90年代のライヴ・アレンジは破茶滅茶過ぎて、この日はまだ遊びきれてない感じもあったりと、いや、つくづく佐藤伸治はお化けでしたよね。生きていたらリー・ペリーみたいになっていたのかな。UAがヒゲダンスを踊りながらステージから消え、ハナレグミがメイン・ヴォーカルの“夜の想い”へ。前の日になんとなく1曲だけ聴いたのがこの曲だったので、アイスクリームのあたりが出た気分。ZAKさんが「あれが『空中キャンプ』の始まりだった」というだけあって何かが始まろうとしている感じがじわじわと伝わり、“WALKING IN THE RHYTHM”の「歌うように歩きたい」から「I WALK」へとテーマが続いたのもよかった。フィッシュマンズは前期に昼間の景色を歌った曲が多く(“土曜の夜”は小嶋謙介作)、後期は夜の景色が増えるので、ここがひとつの分水嶺だったといえる。そして、次の曲が実際に「『空中キャンプ』の始まり」となる“ナイトクルージング”。“夜の想い”の「誰もが調子のいい夢」が“幸せ者”に受け継がれ、「いいことあるかい?」が“ナイトクルージング”の「いい声聞こえそうさ」につながっていく。ハナレグミの鼻声は甘えのようなニュアンスもありつつ、内面に踏み込ませないという拒絶の感触も微妙に混じっていて、「窓はあけておくんだよ」のところでもうひとつ切実なニュアンスを伴わない気がしてしまう。佐藤伸治も歌い方を変えたというのだから“ナイトクルージング”を歌う人はもっと努力しナイト。この曲はそんなに簡単な曲ではないと思う。
“ナイトクルージング”の余韻もなく、すぐにプププーとベースが高音で鳴り、“LONG SEASON”が始まる。ツアー名で謳っているのだからやることはわかっているのに、なんか不意打ちだった。自分がいた場所のせいなのか、この日はHAKASE-SUNのキーボードが全部半音ズレているように聞こえ、“LONG SEASON”も最初はキーボードもベースもズレているように感じる。一緒に見ていた映画監督の朝倉加葉子はわざとやっていると言ってるんだけど、ほんとかなー。フィッシュマンズならやりかねないと彼女は言うんだけど、ズレて聞こえていたのが僕だけではなかったことは確か。ヴォーカルが入ったところで全部がピタッと合い、曲調が一気に加速する。ZAKさんによれば“LONG SEASON”をミックスしていた時にイメージしていたのはカン“Future Days”だったそうで、ヴォーカル・パートから演奏パートに移るあたりはなるほどなあと思えた。『空中キャンプ』のレコーディングを始める前、佐藤伸治はよくムーグさんの家でクラウトロックを聴いていたそうで(だからジャケットに「NEU」の文字)、もしかすると「UP & DOWN」という歌詞もハルモニアに由来するのかなとか。そして、茂木欣一のドラム・ソロがとんでもなかった。照明のせいもあって、なんだか幻影師アイゼンハイムみたいに見え、ピアノのループが鳴り続けているので実際には時々ブレイクを挟んでいるのだけれど、延々と続くドラム・ソロが様々な景色を描き出し、ドラムだけを聴いているという印象ではなかった。しかも、そのままメンバーが戻ってきて一気にピッチを上げたスピードコアに変容。一度だけペイヴメントとの対バンで聞いたパンク・ヴァージョンかと思ったけれど、ライヴが終わってから確認できたのは、あれはモール・グラブへのアンサーだったということ。昨年12月にメルボルンで行われたモール・グラブのDJでオープニングに“LONG SEASON”が使われたのはいいんだけれど、それは彼らがエディットしたヴァージョンで、とんでもなく回転数を早めたものになっていたのである。これを聞いたマネージャーの植田さんが最初に言った言葉が忘れられなくて、彼女の反応は「この手があったか!」というもの。「なんてことするんだ」とか「これじゃ曲が台無し」ではなく、現在のフィッシュマンズを現在進行形で捉えていなければ、とっさにこの表現は出てこなかっただろう。これに関してはアンサーを返そうとするフィッシュマンズもすごいけれど、植田マネージャーも大したものです。おかげで過去最高に長い〝LONG SEASON〟を聴くことができました。ここまでヒット曲大会だったステージは記憶の片隅に眠っていた“FUTURE”でエンディングを迎える。〝A Piece Of Future〟で始めたから〝FUTURE〟なのかなとは思うけれど、大騒ぎの締めくくりに、何もかもが夢だったかのような感触を運んでくる“FUTURE”というのはあまりにも絶妙。2年前にドミューンで川辺ヒロシが“LONG SEASON”の後に“むらさきの空から”をかけたのもグッときたけれど、今回の流れもとてもよかった。
そして、アンコール。メンバーが出てくるまで手拍子が途切れなかった。こういうことは昔はなかった気がするけれど、自分でも手拍子がやめられないし、フィッシュマンズがかつてのフィッシュマンズとは違うなら自分だってすっかり変わってしまったのだなと自覚する。フィッシュマンズを聴いてこんなに楽しく騒いでいる自分になるとは想像もしなかったし、そう思うと現在のフィッシュマンズを否定し続ける佐藤伸治至上主義者には絶対にいなくならないで欲しいと思う。皮肉でいっているのではなく、「止まっちまいたい」という感情に強く共感したことは確かだし、自分のなかにもそれが少しでも残っていると思いたいから。
再び客電が落ちて真っ暗になり、誰かが“POKKA POKKA”を歌い出す。「心の揺れを静めるために静かな顔をするんだ」~と、その日初めて聞く声。ライトがつくとGEZANのマヒトゥ・ザ・ピーポーだった。神宮外苑前で樹木伐採に反対する人たちがミニ・フェスをやった時(PAはZAK)と同じく全身真っ赤な衣装で、カズレーザーみたいだと思っていると、どんどんマヒトゥのヴォーカルに引き込まれる。人の曲を歌って「自分のものにする」という言い方があるけれど、歌詞はまったく同じなのに佐藤とは異なるマヒトゥなりの苦悩があるように聞こえたというか。「だれかにだけやさしけりゃいい」というのは佐藤伸治が当時、観ていたTVドラマ『ロングバケーション』で木村拓哉が言うセリフで、マヒトゥが歌うと佐藤とは人との距離感がまったく違うように感じられ、そもそも佐藤伸治はどうしてこの曲をつくろうと思ったのかと考え始めてしまう。続いて“Weather Report”。そろそろ疲れて終わりが近いという時にこの曲というのはオーディエンスには酷な気がする。ここから、さあ、踊るぜというモードになって、次で終わりというのは何か間違ってるだろー。茂木欣一も「じゃあ、朝までやるか!」と自分で言ってたじゃないか。そんな気分になる曲だし、この曲はもっと早い方が全体に勢いがついていいと思うんだけど。心のなかでそう叫んでもUAやハナレグミもまた出てきて、いかにも大団円といった雰囲気になり、あとはよく覚えていない。朝までやるといったのに「最後です」と前言をひるがえして、あと一曲やるというので“ひこうき”だろうと思ったら、“ひこうき”だった。一度でいいから“シーフードレストラン”で終わって欲しい(ウソ)。
3時間半のステージが終了し、快く疲れて弛緩していると視界にグレッグ・オールマンが入ってきた。よく見ると髪を伸ばしまくった佐野ディレクターである。「今日の譲はすごかった」と佐野さんは柏原譲のテクニックが『若いながらも歴史あり』の頃に戻ったとコーフンしている。そうかもしれない。ベース・ソロがなかったことが不思議なくらい柏原譲は柏原譲だった。予想通り、会場には外国人の数も増えていて、ベースが技を見せると「ファンタスティック!」という声が飛んでいた。佐野ディレクターはそして、今回のツアーTシャツ「FISH IS WATCHING YOU」を着ていた。またしても「A」がない。そして、そのことについて話をしていて僕は「I’M FISH」は「I’M A FISH」の間違いだとずっと思っていたのだけれど、これはムーグさんがわざとやったのだということを初めて知った。「魚」ではなく一種の抽象概念(=something fishy)だと。ちなみに「FISH」はスラングで「ムショ帰り」とか「キリスト」という意味もあったりするのであんまり外国では着ない方がいいかもしれません。「抽象概念としての魚があなたを見ている」というのは、しかし、ちょっと怖くないですか。「魔物が落ちてくる」よりはいいのかな。