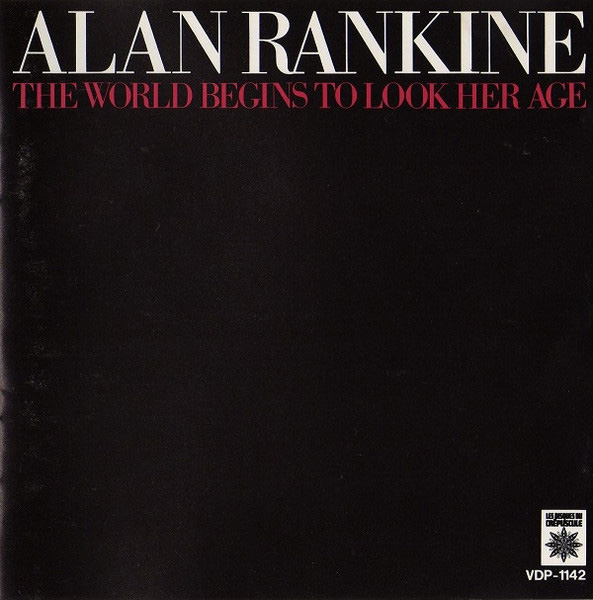トレイシー・ソーンとベン・ワットによるエヴィリシング・バット・ザ・ガール(EBTG)が新しいアルバム『Fuse 』を4月21日にリリースする。これは1999年の『Temperamental』以来の新作で、EBTGにとっての通算11枚目のアルバムとなる。
先行で発表されたシングル曲“Nothing Left To Lose”は、ハウス・ミュージックの影響下にあった90年代のEBTGの延長にあり、アルバムの内容も、エレクトロニックであり、ソウルであるという。
以下、レーベルの資料からの抜粋です。
2021年の春から夏にかけてベン・ワットとトレイシー・ソーンによって書かれ、制作された『Fuse』は、バンドが90年代半ばに初めて開拓した艶やかなエレクトロニック・ソウルを現代的にアレンジしたものとなっている。
サブ・ベース、シャープなビート、ハーフライトのシンセ、空虚な空間からなるワットのきらめくサウンドスケープの中で、ソーンの印象的で豊かな質感の声が再び前面に出ており、これまで同様、現代的、同時代的なサウンドでありながらエイジレスなバンドのサウンドに仕上がっている。
バンドの再出発とニュー・アルバムについて、トレイシーはこう語っている
「皮肉なことに、2021年3月にレコーディングをスタートしたとき、このニュー・アルバムの完成されたサウンドについて、あまり関心事がなかったの。もちろん“待望のカムバック”といったプレッシャーは承知していたから、その代わりにあらかじめ方向性を決めないで、思いつきを受け入れる、オープンマインドな遊び心の精神で始めようとしたのね」
2人は自宅とバース郊外の小さな川沿いのスタジオで、友人でエンジニアのブルーノ・エリンガムと密かにレコーディングを行った。
希望と絶望、そして鮮明なフラッシュバックが交互に現れるこのアルバムの歌詞は、時にとらえどころがなく、時に詳細に描写され、再出発することの意味をとらえている。
ベンは次のように語っている。
「エキサイティングだったね。自然なダイナミズムが生まれたんだ。私たちは短い言葉で話し、少し顔を見合わせ、本能的に共同作曲をした。それは、私たち2人の自己の総和以上のものになった。それだけでEverything But The Girlになったんだ」
二人のスタジオでの新たなパートナーシップは、新しいアルバム・タイトルにもつながった。
「プロとして長い間離れていた後、スタジオでは摩擦と自然な火花の両方があった」とトレイシーは言う。「私たちがどんなに控えめにしていても、それは導火線に火がついたようなものだった。そして、それは一種の合体、感情の融合で終わった。とてもリアルで生きている感じがしたわ」

Everything But The Girl
Fuse
Virgin Music
2023年4月21日、配信・輸入盤CD/LPにて発売予定
https://virginmusic.lnk.to/EBTG_NLTL

■バイオグラフィー
エヴリシング・バット・ザ・ガールは、トレイシー・ソーン、ベン・ワットの2人により、1982年にコール・ポーターの「ナイト・アンド・デイ」の荒々しいジャズ・フォーク・カバーで登場した。その後、80年代を通じて英国でゴールド・アルバムを次々と発表。1992年にワットが難病の自己免疫疾患で死に瀕した後、1994年に彼らの最大のヒット曲である「Missing」が含まれ、ミリオンセラーとなった熱烈なフォークトロニカ『Amplified Heart』で復活を遂げる。その後90年代を通じて多くのヒットを生み出し、96年リリースの『Walking Wounded』がバンド初のプラチナ・セールスを記録するなど、多くのヒット曲を生み出すが、1999年のアルバム『Temperamental』のリリースを最後に2000年に活動を停止する。
2000代はトレイシー、ベンそれぞれソロ活動を展開。ソロ・アルバムやノン・フィクションの出版、また自身のレーベル、Buzzin’ Flyの成功など、その才能を遺憾無く発揮してきた。
そして2023年、EVERYTHING BUT THE GIRLとして24年ぶりとなる新作アルバム『FUSE』を4月21日にリリースする。
■ アーティスト日本公式サイト
https://www.virginmusic.jp/everything-but-the-girl/