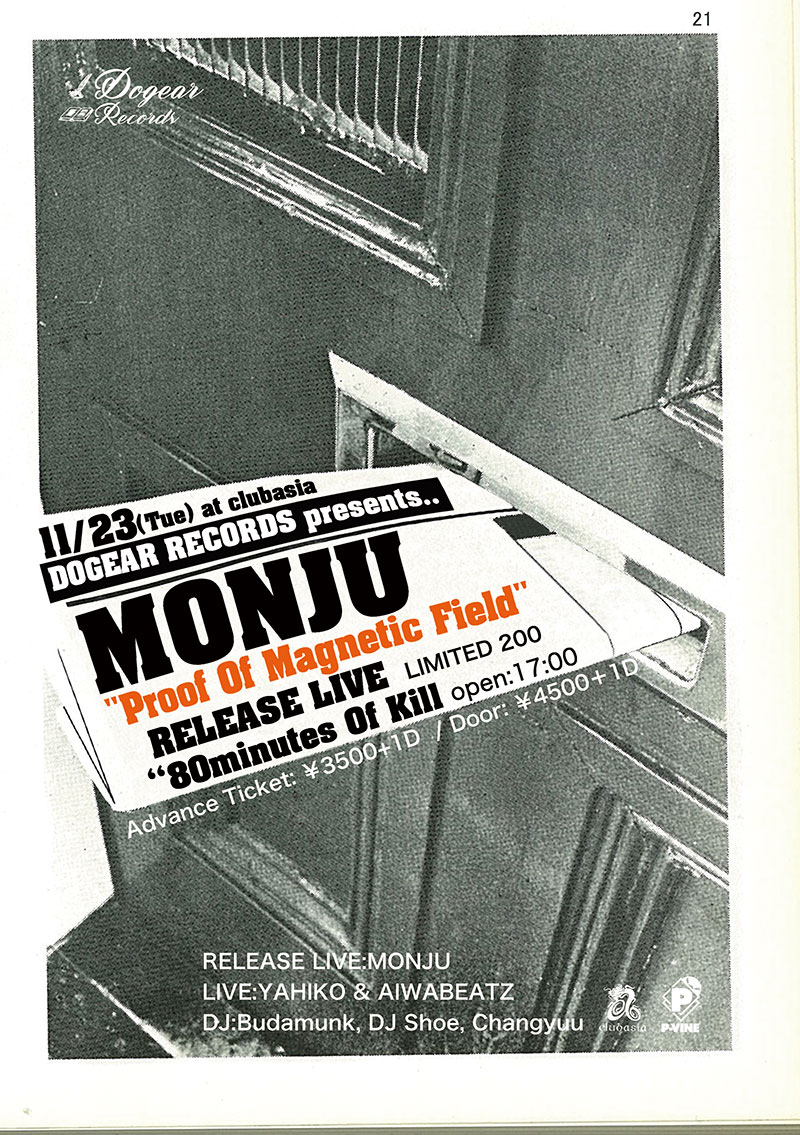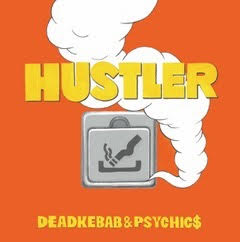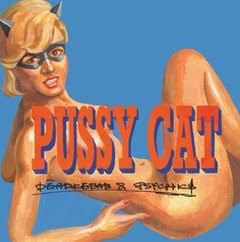いまやヒップホップに限らず、フィーチャリングやコラボレーションという手法はクリエイティヴィティの幅やファン層を広げるための常套手段となっているが、そうやって共演からはじまったアーティスト同士の関係がその後、グループ、あるいはユニットへと発展していくケースも少なくない。ZEN-LA-ROCK、G.RINA、鎮座DOPENESS からなるユニット、FNCY(ファンシー)も元々はソロ・アーティストして活動していた彼らが、お互いの作品で共演したことをきっかけに結成されたわけだが、3人のスタイルやバックグラウンドは全く異なる。強い個性を放つ3人が結びついたことによる高い総合力とそれぞれの絶妙なバランス感は、通常のヒップホップ・グループが容易には到達することはできない域にいる。
2019年にリリースされた FNCY の1st 『FNCY』から約2年ぶりのリリースとなる 2nd アルバム『FNCY BY FNCY』。昨年リリースされた「TOKYO LUV EP」の楽曲も本作には収録されているが、ヒップホップを下地にしながらブギー/ファンク、ニュージャック・スウィングといった前作の流れを踏襲しつつ、さらに音楽的な広がりを描いている。例えば “THE NIGHT IS YOUNG” でのダンスホール・レゲエ、“COSMO” でのベース・ミュージック、“REP ME” でのヒップハウスといった音楽的要素は個々のメンバーの過去の流れとも見事にマッチしているし、そこに3人の声が乗ることでその魅力は倍増している。本作にプロデューサーとしてトラックを提供しているのはメンバーの中では G.RINA だけであるが(他には grooveman Spot、BTB特効、オランダの Jengi がプロデューサーとして参加)、実は3人ともがDJとしても活躍しており、これだけ幅広いスタイルを打ち出しながらも、FNCYとして見事にひとつにまとまっているのは、DJとしての彼らの柔軟かつ優れたセンスに寄る部分も大きいだろう。
リリックに関しては、やはりこの時期に作られたということもあり、“FU-TSU-U(NEW NORMAL)” のようにコロナ禍だからこそのメッセージを強く感じる箇所は多い。しかし、そこは決して悲観的にならずに、前を向いてパーティを続けていくという彼らの強い意志が感じられ、コロナが落ち着いてきたいまの状況にも実にしっくりと響いてくる。そして、ヴォーカリストという観点でいうと、本作の肝(きも)は鎮座DOPENESS の歌と G.RINA のラップだ。もちろん前作でも披露されていた要素であるが、ラッパーである鎮座DOPENESS はより自由にメロディを奏で、シンガーである G.RINA は自身が元来ラッパーではないことをプラスに置き換えながら彼女ならではのフロウを聞かせる。ラップと歌の融合なんていまどき珍しいことではないが、個人的な好みで言わせてもらえば FNCY はそのトップレベルにあると思う。
ちなみに本作収録の “COSMO” にゆるふわギャング、“あなたになりたい” に YOU THE ROCK★をそれぞれフィーチャした「COSMOになりたいRemix EP」も素晴らしい内容なので、こちらも合わせてぜひ!