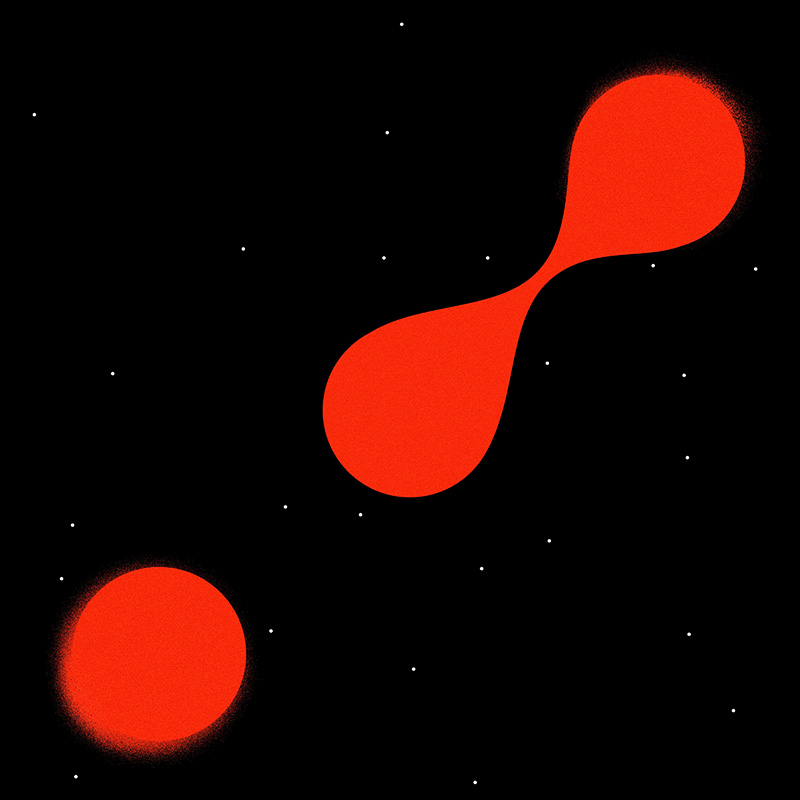シンガー・ラッパー、そしてプロデューサーとしても知られるUKのアーティスト「169」(ワン・シックス・ナイン)が、キャリア2枚目となるミックステープ「SYNC」をリリースした。UKの有名プロデューサー「169」の力強いメロディセンスに唸らされる一枚だ。
昨年は 169 にとって、プロデューサーとして大躍進の1年だった。マーキュリー賞を受賞したアルバム Dave 『Psychodrama』の楽曲プロデュース、Headie One のキャリアを大きく変えた大ヒット曲 “18 HUNNA feat. Dave” の制作、Netflix で公開されている「TOP BOY」のサウンドトラックを担当するなど、UKラップのメインストリームな楽曲を多く制作している。彼の過去作を紐解いていくと、アトモスフェリックなシンセ、隙間の多いミニマルなトラック構成、芯のあるピアノのメロディといった個性に気づく。グライム・UKラップがメインストリーム化する中で、彼の作家性はシーンのトレンドに大きな影響を与えているということ改めて感じる。
169のプロデュースワーク
Headie One - 18 HUNNA feat. Dave
ソフトなタッチのピアノから始まる 1. “Slide for Me” は、Dave の “Screwface Capital” を彷彿とさせるビターな雰囲気を醸しながら、169の甘く優しい歌声が映える。2. “No Fears” では、グライム初期からラッパー兼プロデューサーとして活躍する Wretch 32 をフィーチャーし、アフロビーツを昇華したミニマムなビートとピアノに乗せる。
3. “Cocoabutter” ではサックスや女性ヴォーカルのサンプルを織り交ぜたトラックが素晴らしく、169 との歌声との重ね方に聞き入ってしまう。アルバムの中盤の、UKソウルのシンガー「ジャズ・カリス」を迎えた 4. “Crazy” や、ラッパー「Jaiah」を迎えた 5. “Millies” といったコラボレーションでは、むしろ 169 は一歩下がって客演の存在感が一層映える楽曲になっている。
アルバムの後半では、6. “Respect” は暖かなトラックの上で女性に対するジェントルな一面を見せると、その後2回転調し不穏なビートに変わっていく。アトモスフェリックなシーケンスは、The Weeknd や Drake 周辺のR&Bを彷彿とさせる。ラッパー「KNGWD」を迎えた 7. “Over Me”、ベースラインの重ね方が美しい 8. “The Way” で、24分のミックステープは幕を閉じる。
作品全体ではラヴソングがほとんどで、トラックの作り込みのうまさに耳を惹かれる曲が多い。曲自体は短いものの展開はきちんと作り込まれており、聞き応えがある曲が多かった。また、客演している若手アーティストの個性も存分に映えている。今後は 169 のプロデュース・スキルを存分に発揮したフルスケールのアルバムにも期待したいところだ。