「民主主義を踏みにじるな」という言い方は誤解を招きやすい。民主主義を達成した社会など地球上には存在しないのだから。ないものは踏みにじれない。少数がすべてを決める社会ではなく、全員にのしかかってくる問題は全員で決めるというのが民主主義で、スイスのように全員でやるのは効率が悪いから代議士に話し合いの役目を託す制度があり、議会制というのはそうした方法のひとつではあるものの、唯一の手段であり続けるかどうかはわからないし、ほかにいい方法があるのならそれを採用すればいいとも思うけれど、どんなシステムを採用するにせよ、くじ引き制にでもならない限り、全員が話し合って意思決定を行うという土台は残るはず。「コミュニケーションは大切だ」という言い方も誤解を招きやすく、コミュニケーションはせざるを得ないものだし、自分が殺されることになっても「意見がない」という人はさすがにいないだろう。黙っていれば不利になると思う人ほどSNSで声を上げているのも、だから、当然の成り行きではある。アメリカで初めて男女平等が議論された最高裁の模様を描いた『ビリーブ』は社会の場におけるコミュニケーションの必要性を痛感させられる作品であった。通常、法廷ドラマというのは、複雑に入り組んだ犯人の動機を解明したり、相手の理屈を突き崩していく過程をスリリングに楽しむものだとは思うけれど、『ビリーブ』で焦点が当てられていたのは憲法解釈で、同じ文章を前にしながら、それがどれだけ解釈に可能性を与え、この場合でいえば男女平等という理念を導き出すツールとなっていたか。フランク・ダラボン『マジェスティック』でもラリー・チャールズ『ディクテーター』でも憲法を読み上げれば事態は収拾していく……というようなプリミティヴなレヴェルとはまるで違った。最高裁という場所が思想の生まれるところであり、知性の結晶として機能していることを実感し、権威として君臨できるのも当然だというか。

現代アメリカを代表する女性といえばRBGとAOC、そしてオプラ・ウィンフリーとビヨンセになるだろうか(個人的にはティナ・フェイも!)。RBGことルース・べイダー・ギンズバーグは70年代に男女平等を訴えた最高裁の弁論で広く知られるところとなり、ビル・クリントンによってアメリカの最高裁判事では二人目の女性に選ばれた弁護士である。『ビリーブ』は彼女がどれだけ優秀な成績で大学の法科を卒業しようとも女性(で、しかもユダヤ人)が弁護士になれる時代ではなかったために、最初は大学で教授職にしか就くことができず、女性の社会進出に当時としては珍しく多大な理解を持っていた夫に助けられて最高裁に立つことができ、数々の有名な弁論の中でも「ワインバーガー対ワイゼンフェルド」訴訟を取り上げた作品となっている。面白いのは反抗期を迎えた娘が不良化して親の言うことを聞かなくなったのはいいとして、彼女が出かけていく先はロックやドラッグの世界ではなく、グロリア・スタイネムの集会だったということ。実話なのか適当につくったエピソードなのかは知らないけれど、そのようにして親に反抗してフェミニズムの集会に行っていた娘がある時、路上でヒューヒューと男たちに卑猥な言葉を浴びせられると、RBGは「無視しなさい」と忠告するも、そんな時代ではないと娘は男たちにはっきりと言い返す。これでRBGの心に火がつく。そこから最高裁まではまっしぐらである。『ビリーブ』ではそのようにして彼女の家族関係も物語の大きなファクターをなしている。それはさらに追って公開されるRBGのドキュメンタリー『RBG 最強の85才』でさらに詳細に描かれている。『ビリーブ』も『RBG』も単独で充分に面白い作品だけれど、『プラダを着た悪魔』に続いてヴォーグの編集長アナ・ウィンターの素顔を追った『ファッションが教えてくれたこと』を観るのと同じような相乗効果があり、続けて観れば愛も勇気も100倍増しで感じられることは請け合い。

『ビリーブ』では若い時に夫がガンで入院し、看病を続けながら法律の勉強を続けるRBGに焦点が当てられ、『RBG』ではその夫が他界する場面に多くの時間が費やされている。『ビリーブ』では「ワインバーガー対ワイゼンフェルド」訴訟を起こすまでの長い手続きを詳細に追うことで、裁判を起こす意義やその難しさなどが同時に語られていく。『RBG』では彼女が扱った他の有名な訴訟も次から次へとダイジェストで解説され、彼女が最高裁判事になってからも、ジョージ・ブッシュによって保守派の判事が2名も任命され、中道に近かった彼女の存在感が一気にリベラルへと横滑りし、そこからはむしろ彼女の思う通りに判決が下せず、RBGはむしろ最高裁判決に対して「反対意見」を述べる立場になっていく。そのことがしかし、彼女の人気を若い人たちの間で決定づけ、ネット上に「#ノトーリアスR.B.G.」というハッシュタグが立つとTシャツやマグカップまでつくられ、作品中で言われているように「ロックスター並みの」の人気者となり、ポップ・カルチャーの新たな象徴とまで言われることに。ノトーリアス(悪名高い)というネーミングはどう思うかと聞かれたRBGは「似たようなもんだわよ」と言ってノトーリアスB.I.G.とは「同じブルックリン生まれだし」と言って笑う。ほとんどTVを観たことがないというRBGに「サタデー・ナイト・ライヴ」でケイト・マッキノンが彼女のモノマネをやっているところを観せてもRBGは笑い転げていて、これはおそらくドナルド・トランプが大統領戦に出馬した際に批判的な発言をして判事の行動としては軽率だったと批判されて謝罪したという経緯があり、そのドナルド・トランプがやはり「サタデー・ナイト・ライヴ」でアレック・ボールドウィンに自分のモノマネをされて怒り心頭のツイートを連発していたことと対比させて見せる意図があるのだろう。RBGはこれに限らず、どんな場面でもとにかくお茶目だし、人間として可愛らしい。黒柳徹子や樹木希林が芸能人ではなく政治家や法律家だったら、こんな風に見えるのかなというか。


日本で『ビリーブ』と『RBG』が公開される頃、RBGは86才になる(最高裁判事に定年はない)。トランプ時代になってから彼女が転倒して骨折した時はリベラルの火が消えてしまうと大騒ぎにもなった。また、両作を観ていると日本の女性たちはまだアメリカの60年代にいるとしか思えなくなってくるし、上に書いた以外にもとにかくエピソードが目白押しで、日本と照らし合わせて考えさせられることはとにかく多い。アメリカは個人主義だから組織的な圧力から個人を守るために過剰なほど正義が求められ、組織優先の日本では同じように正義を求める感覚はないのかもしれない(あるとしてもそれはネオ・リベラルがもたらすという皮肉でもある)。ツイッター上で振りかざされる正義感が座り心地のいい着地点を見出せないこともそのせいかなとは思うけれど、とはいえ、個人があってそれが組織に押しつぶされるという図式がまったくないわけではないし、「コミュニケーションせざるを得ない」のは圧倒的に個人の立場にいる人たちだとすれば、RBGに学べることは無限といっていいほど多いことは確か。
『ビリーブ 未来への大逆転』予告編
『RBG 最強の85才』予告編
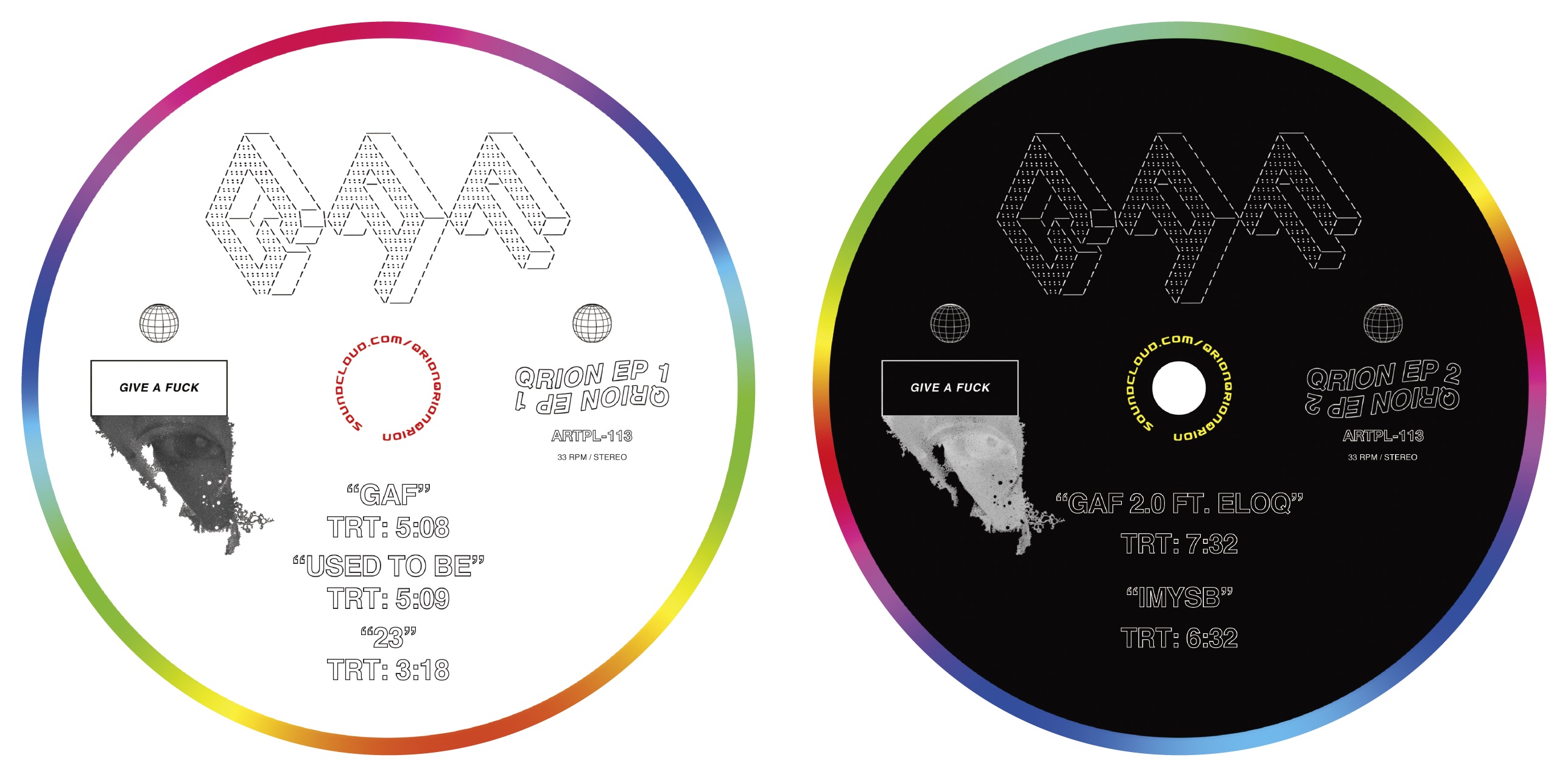

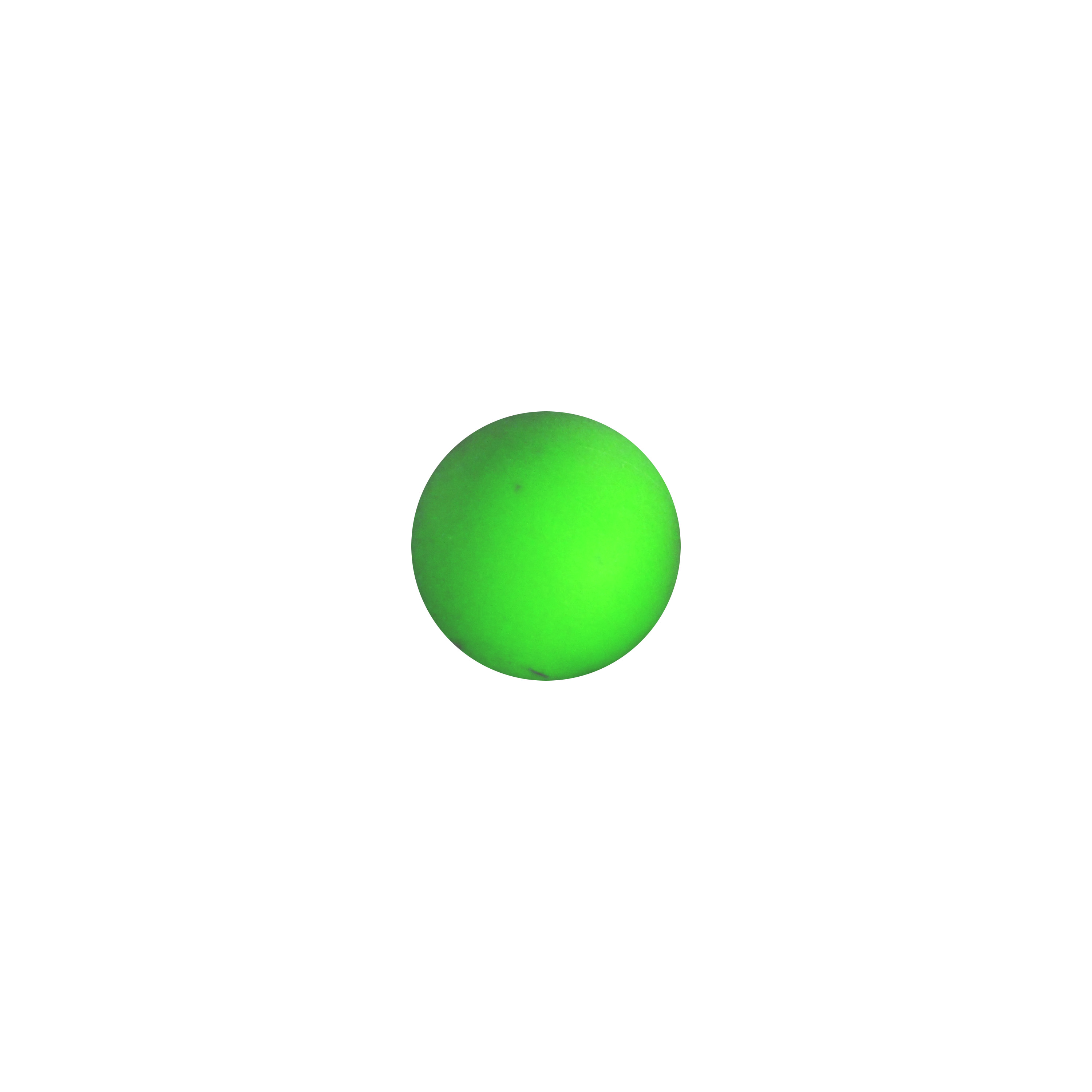









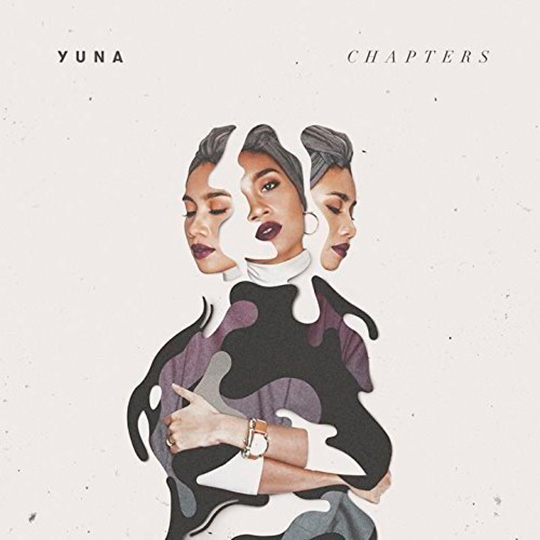








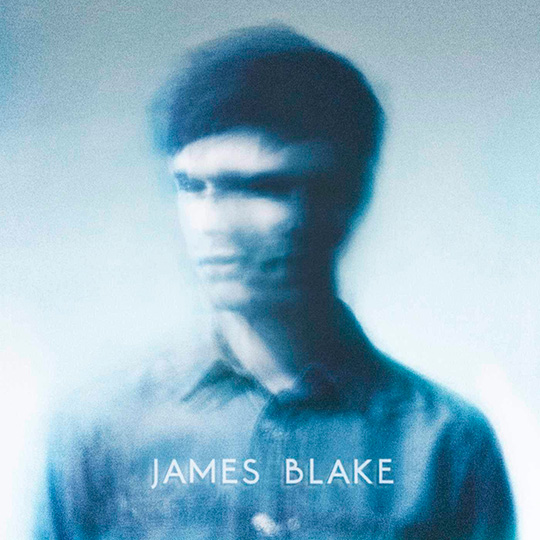




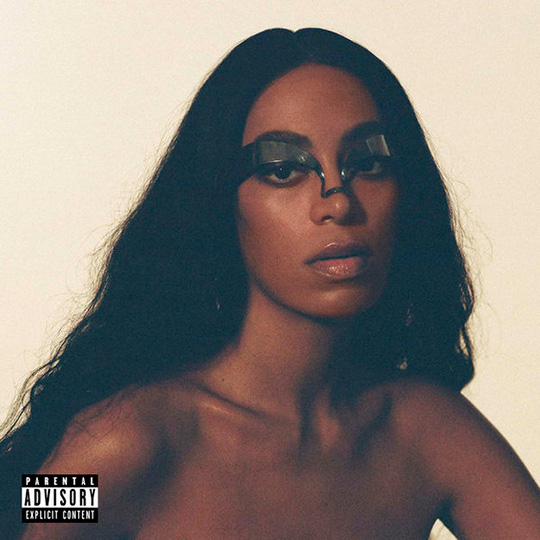
 FFK-007VL
FFK-007VL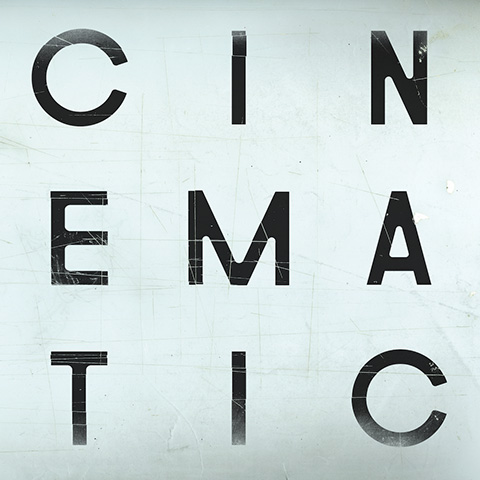


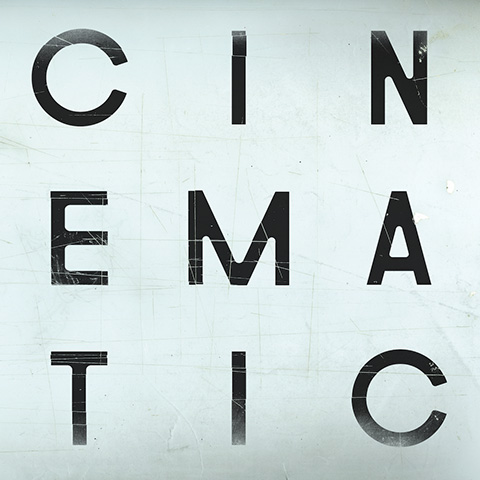 ザ・シネマティック・オーケストラの12年振りの最新アルバム『TO BELIEVE』が3月15日に発売決定。
ザ・シネマティック・オーケストラの12年振りの最新アルバム『TO BELIEVE』が3月15日に発売決定。