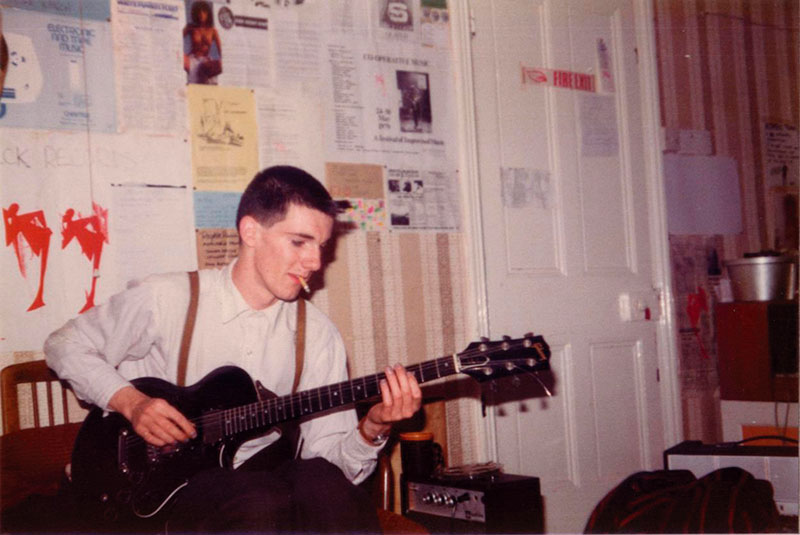電子音楽プロデューサーのサム・シャックルトンがベルリンを拠点に率いるグループ、チューンズ・オブ・ニゲーション(Tunes of Negation, 以下TON)の前作、『Reach the Endless Sea』は13世紀のペルシャの神秘主義詩人、ジャラール・ウッディーン・ルーミーから着想を受けている、ということを担当した自分のライナーの結びに書いた。それが全てではないにしろ、シャックルトンが、パーカッショニスト/作曲家タクミ・モトカワ、ヴィブラフォニストのラファエル・マイナートとともに新たなサウンドの地平を目指すプロジェクトが、TOGである。2020年、その2作目となる『Like the Stars Forever and Ever』が一年という短期間で我々のもとに届いた。
まずは〈Skull Disco〉時代のシャックルトンの円循環的リズムのごとく、自分のライナーから反復させてもうが、イスラム神秘主義、つまりスーフィズムにおいて、無限的な存在である神への消滅を目指すことが主眼におかれている。それを実行する上で非常に重要な役割を果たすのが、高校の世界史の授業でも登場する、自我忘却へと向かうあの旋回するダンスである。音楽を通し、スーフィーたちは無限へと回転する。
シャックルトンがやってきたダブステップとそれ以降のエレクトロニック・ダンス・シーンを見渡せば、このような非西洋由来の音楽の影響は散見される。シャックルトンとは共作で『Pinch & Shackleton』(2011)という名盤を残しているブリストルのピンチによる “Qawwali”(2006)(カッワーリーはスーフィズムの宗教童謡である。著者が住むロンドンでは、ムスリム系の住民たちは地域の大学や公民館などにあつまってその演奏会などを定期的に開いており、コミュニティの壁がないわけではないが、イギリスでは一般市民たちがその文化に触れる機会は決してゼロではない)、西欧の外側からやってきたトライバル・リズムと重低音のミクスチャーのある種の完成形を見せたクラップ!クラップ!の『Tayi Bebba』(2014)などは大きな例である。
それらはダンスフロアにおいて、リズムを経由し非日常的な空間を出現させたわけだが、TONはよりコンセプチュアルな方向へと向かい、サウンドの持つ思弁性や崇高なアレンジメントを駆使し、各楽曲のタイトルが持つイメージを聴き手に想起させる。 それはアルバムに先立ち公開された “Your Message Is Peace” のビデオが、VRゴーグルを装着しているような一人称の視点から、ジャケットに描かれているサイケデリックの世界を探索していくように、「外側」の「内側」へと埋没させていく感覚に近いかもしれない(「矛盾」もTONのテーマであると今作のプレスリリースにはある)。
これまでのシャックルトンのソロ作のように、敷き詰められたビートがあるわけではなく、太鼓がゆっくりと聞き手の意識を揺れ動かしながら空間を分割し、星のようにこぼれる旋律が、ソファにうずくまる身体を飲み込んでいく。埋没するVR的美学の採用という点や、彼と同世代のティム・ヘッカーが濃霧という自然現象が持つ超越性をアンビエントのフォーマットで表現していることを考慮すると、ここにはある種の同時多発的現代性も認めることができるだろう。
フロアでの昇天というよりは、神秘的な感覚へと向かうTONだが、シャックルトンがこれまでに我々の身体を震わせてきた重低音も、今作では基調的に機能している。前作に引き続きゲストとして参加している、演奏家/ヴォーカリストのヘザー・リーが冒頭部分を飾る “Naked Shall I Return” では、多層化されたコーラスと入れ替わるように登場するサブベースが主導権を握り、ダブが発生させる磁場によって他パートの演奏にグルーヴを生んでいる。
平均して一曲9分という長尺で構成されている今作は、一曲中だけでもドラマチックな展開がなされているが、アルバムの構成という点においても、異なるナラティヴが登場する。“You Touched Us With Light” では、それまでに生まれたリズムの磁場が消失し、視界の奥で微かになるヴィブラフォンと宙を舞う蝶のようなスネアが弾くポリリズムが、オルガンの旋律とともに奇妙なテクスチャーを生成している。光を経由して我々に接触してくる「You」という二人称は、おそらくは「神」のような超越存在を指しているのだろう。そのような抽象的存在と、触れることはかなわないが、確かに存在している光という「物体」の性質を表現するように、身体に響くという意味でのリズムの具象的な物質性がここでは後退していくかのようである。
『Like the Stars Forever and Ever』で最後に登場する概念は、終曲のタイトルにも現れているように “Impermanence / Rebirth”、つまり「無常」と「転生」である。前作からの共通概念として今作に引き継がれているのは「無限」だが、今作においてシャックルトンはその対概念ともいえるものに触れているのだ。アルバム最長の15分にも及ぶ再生時間のなかで、これまでとは対照的により静かに進行していく楽曲は、光り輝く前半部とは逆方向の隠を写している。異なる概念たちをそれ相応のサウンドで鳴らしてみせる描写力は、電子音楽作家としてシャックルトンのひとつの到達点だろう。
2020年はポーランドのマルチ楽器奏者ワクロー・ジンペル(Wacław Zimpel)との共作『Primal Forms』 を、今作と同様に〈Cosmo Rhythmatic〉からもシャックルトンはリリースしている。そちらはユニットであることに主眼が置かれ、より電子的なサウンドとリズムがサックスなどの楽器をシンプルに包握していく過程がスリリングな一枚だが、TONは四人のパフォーマンスにより、さらにアンサンブルな表現形態となっている。この流れでいくと、当然のことながら待たれるのは、この共作過程をへて「転生」したシャックルトンのソロ作品だろう。
TONにあえて的外れの粗探しをすれば、ここにないのは、これまで我々をフロアで汗だくにさせてきた強靭で最高に滑稽なシャックルトンのダンス・ビートである。前作から引き続き無限と対面することにより、新たなサウンドをそこから引き出し、変化を予期させるタイトルで終わる今作。輝く星々のように無限ではないものとは何か。それは他でもない人間である。2021年、一度粉々に砕け散った世界の再生が期待されるタームにおいて、無限に接近した孤高の作家がその有限な生で何を作るのか。我々はそれを心して待たなければならない。